モーツァルトの《ピアノ協奏曲第20番》
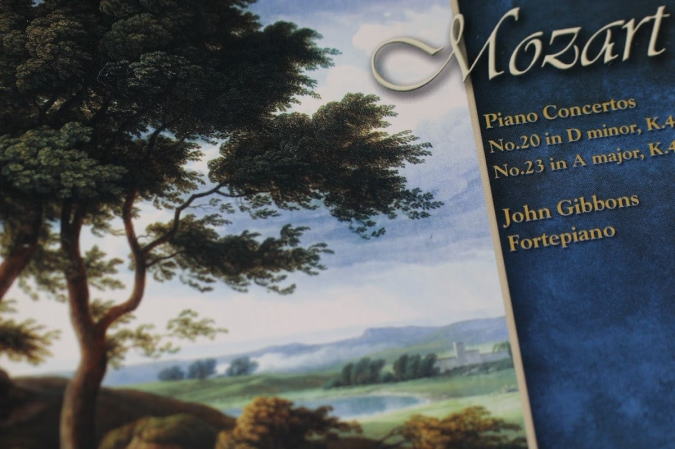
クラシック音楽ファンの皆さまは、どなたにも、最初にクラシック音楽に興味を持つきっかけとなった曲がおありだろうと思います。憚りながら私の場合は、モーツァルトの《ピアノ協奏曲第20番》がそれです。もう20年近く前になりますかね、iTunesでDL販売されている曲の冒頭部分が無料試聴できましたでしょ。あれをPCで片っ端から聴いていたんです。何をどう探したらよいか、まるっきり分からなかったですからね。そしたらたまたま耳に入ってきたのが、Apollo's Fireというアメリカのオーケストラが演奏する《第20番》でした(ピアノはジョン・ギボンズ)。
ただし試聴できる時間はごくわずかですから、長い前奏のあとピアノの音がちょこっと聴こえたところで再生は終わってしまいました。でも、たったそれだけでも琴線にビビビッと来ましたね。なんという情感あふれる音楽なんだ、と。早速ダウンロードして全部を聴きましたよ。CDもすぐに買いました。それが私がクラシック音楽にのめり込むことになったきっかけです。その後も暫くはモーツァルトばかり聴いていました。でも、2曲目に買った曲は何だったか忘れました。とにかく《第20番》の衝撃だけを今もよく覚えているんです。
その後もさまざまなアーティストの《第20番》を聴き比べました。でも、未だに私にとってApollo's Fireより好ましい演奏には出逢えていません。ハスキル、グルダ、アルゲリッチ、内田光子・・・・・・、あと覚えていないくらいたくさんの盤を聴きました。しかし、いずれもピアノ独奏は一流で素敵なものの、オーケストラの演奏とのマッチングというか、どうも全体としての雰囲気が好きになれなかった。いわゆるアレンジの問題です。ハスキルなんかのピアノだけ取り上げてみると、もう最高なんですけどね・・・。
Apollo's Fireによる《第20番》のどこが好きかって、言葉にすると「しめやかで落ち着きのある厳かな演奏」といったらいいでしょうか。モーツァルトが生きていた時代の楽器が使われていて、ピアノもフォルテピアノなので、現代のピアノのようには響きません。オーケストラも気品のある音型に終始し、何とも言えない情感が醸し出されています。それに比べると、他の盤は、どれもオーケストラが騒がしすぎると感じます。大好きな曲でありながら、全く聴く気にならない。ひょっとしてこういうの、「原始体験」があまりに鮮烈だったため、それ以外を全く受け容れなくなってしまう、初心者によくありがちな現象かもしれません。
とまれ、この《第20番》は、私ごときが気に入るまでもなく、既にモーツァルトのなかでもとても人気の高い曲なわけですが、かのベートーヴェンもえらくお気に入りだったようで、この曲のためにカデンツァ(独奏者がオーケストラの伴奏を伴わず自由に即興的な演奏をする部分)を書いていますものね。一つの曲の中でモーツァルトとベートーヴェンが聴けるなんて、考えてみればすごい贅沢なことです。
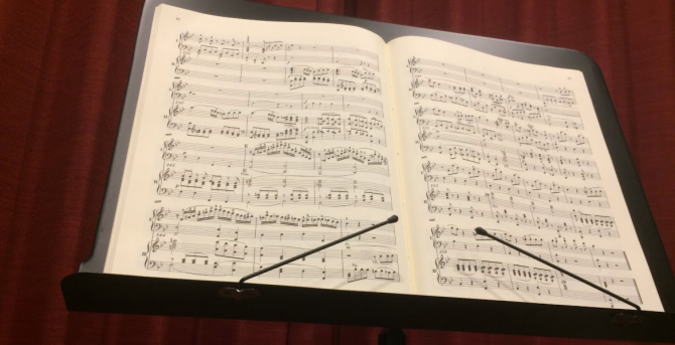
モーツァルトの《ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲》
第1楽章ではオーケストラによる長い導入部があり、これが実に色彩豊かで、とりわけシンコペーションの力強いリズムには心躍ります。初めて聴いたころ、この部分が大好きになって、何度も何度も繰り返し聴いていた時期があります。そして、急にどこからかスゥーっと現れたかのように、ヴァイオリンとヴィオラの両ソロ・パートの絡み合いが始まります。私には、あたかも二匹の蝶々が戯れて追いかけっこしているように、付いては離れ、付いては離れながら、広い野原を奔放に飛び回る風景が目に浮かびます(我ながらなかなかよい表現です)。
第2楽章は、穏やかながら深い憂いが込められたような緩徐楽章。第1楽章で見せたヴィオラの明るさは影をひそめ、すすり泣くような独奏ヴァイオリンのオクターブ下で同様のメロディーを静かに奏でています。まことに印象深い楽章です。
第3楽章は打って変わってアップテンポの晴れやかなフィナーレへと進行します。第2楽章までの流れが一変し、次々に登場する快活で平明な旋律にはかなり唐突な印象さえ受けます。熱烈なモーツァルト・ファンだったアインシュタインは、「常に予期しなかったことが起きる」と評したとか。何だか、もやもやっとした感じから急に解き放たれたかのような不思議な感覚になります。
なおこの曲でモーツァルトは、独奏ヴィオラの全ての弦の張力を強めて半音高くする「スコルダトゥーラ」という調弦法を指定しているんだそうです。独奏ヴィオラのパート譜はこの曲自体の変ホ長調の半音下のニ長調で書かれていて、この調弦によって華やかでよく通る響きとなり、地味な音色であるヴィオラがヴァイオリンと対等に渡り合う効果を狙ったといいます。素人にはちょっと分かりにくい話ですが、聴くと確かにヴィオラってこんなに艶やかな音が出るんだと感じさせられます。
私の愛聴盤は、エッシェンバッハ指揮、北ドイツ放送交響楽団と五嶋みどりさん(ヴァイオリン)、今井信子さん(ヴィオラ)による2000年の録音です。ややゆったりとした演奏は好悪が分かれるかもしれませんが、私はとても気に入っています。なお、ヴィオラの前述の調弦法による録音に際し、今井信子さんは「これまでとは次元の違う楽器になった」、また弦の張りが強くなったため「これまでよりずっと少ない労力で、それでいて今までよりもしっかりした音が出せるようになった」と語っていたそうです。
【PR】
モーツァルトの《クラリネット協奏曲》
クラリネットという楽器が面白いと思うのが、同じ木管楽器のオーボエは低音から高音にいたるまでほぼ同じ音色であるのに対し、クラリネットは、低・中・高それぞれの音域で音色が大きく変わります。知らない人が聴いたら全く別の楽器が鳴っているのかと思うほど(私も最初そう思っていました)。作曲当時はまだ登場して間もない新しい楽器だったそうですが、その特徴を駆使し、まことに表情豊かな曲に仕上げているのは、さすがモーツァルトですね。
ところで、この《クラリネット協奏曲》の旋律に接したとき、同じ年の1月に完成した《ピアノ協奏曲第27番》との共通性に気づかされます。《第27番》はモーツァルト最後のピアノ協奏曲となった曲ですが、どちらの旋律も、最晩年の作品にしてはあまりに平易であり清澄であることです。その理由について、当時のモーツァルトは高度な音楽教育を施された貴族たちの支持を得られなくなっていたため、素人の一般市民向けに平易な音楽を作らなければならなくなったからだとする見方もあります。
確かにそうした背に腹は代えられない苦しい事情はあったかもしれません。しかし、決してそれだけではないと思いたいです。35歳の若さとはいえ、幼いころからずっとまっしぐらに疾走し続けてきたモーツァルトです。ひょっとして私たち凡百の100年以上にも相当するような、濃く凝縮された人生だったかもしれません。だから、「達観」というと語弊があるかもしれませんが、これら2曲には、この年齢までおびただしい経験と実績を重ねてきたモーツァルトならではの真情が、素直に吐露されている印象を受けます。長きにわたる努力や苦労をふっと振り返り、「いろいろあったけど、がんばってきたなー」みたいな、充実した穏やかな気持ち。
つまり、ただ平易なだけの音楽では決してない、ってことです。また、それまでの膨大な数の作品のエッセンスをすべて足して、最大公約数的に表現するとあんなふうになる、つまりあの清澄なメロディーこそがモーツァルトの音楽の集大成に他ならないと思うんです。最後のほうですごい曲を作ってやろうなどというのではなく、ごく自然に彼の達観した魂から発せられたような音楽。さように、この2曲には格別な印象を受けるのですが、皆さまはいかが感じられますでしょうか。
最後に、モーツァルトが亡くなる3年前に書いた手紙に、自身のことを語った個所があるのでご紹介しておきます。
「ヨーロッパ中の宮廷を周遊していた小さな男の子だったころから、特別な才能の持ち主だと、同じことを言われ続けています。目隠しをされて演奏させられたこともありますし、ありとあらゆる試行をやらされました。これらは、長い時間をかけて練習すれば、簡単にできるようになります。僕が幸運に恵まれていることは認めますが、作曲はまるっきり別の問題です。長年にわたって、僕ほど作曲に長い時間と膨大な思考を注いできた人はほかには一人もいません。有名な巨匠の作品はすべて念入りに研究しました。作曲家であるということは、精力的な思考と何時間にも及ぶ努力を意味するのです」
【PR】
人生、ファイト
がんばれビジネスマン
【PR】
モーツァルトの略年譜
宮廷音楽家レオポルトの7番目の末っ子として、ザルツブルクに生まれる(1月27日)
1759年
3歳で、姉ナンネルのクラヴィーアを聴き、3度の和音を同時に弾く
1760年
父からクラヴィーアを習う
1761年
5歳で「アンダンテ・ハ長調」を作曲
1762年
ミュンヘン、ウィーンへ演奏旅行
マリア・テレジア御前演奏
1763年
ザルツブルクに戻り、再びパリ、ロンドン旅行へ
1764年
ヴォルフガングとナンネルが重症のチフスに罹患
初の交響曲「変ホ長調第1番」を作曲(9歳)
1766年
ザルツブルクに戻る
1767年
初の劇音楽「第一誠の責務」を作曲(11歳)
第2回ウィーン旅行
天然痘に罹患
1769年
第1回イタリア旅行
ローマ教皇から黄金拍車勲章を受ける
1771年
第2回イタリア旅行
1772年
ザルツブルク宮廷楽団のコンサートマスターに(16歳)
第3回イタリア旅行
1773年
第3回ウィーン旅行
マリア・テレジアに拝謁
1774年
ミュンヘン旅行
1775年
ザルツブルクに戻り、約2年半を過ごす
1777年
ザルツブルクの宮廷音楽家を休職
母とマンハイムへ求職のため旅行
1778年
マンハイムからパリへ
パリで母が死去
1779年
ザルツブルクに戻り、宮廷楽団に再就職
1781年
ザルツブルク大司教コロレドと決裂、ウィーンで活動
コンスタンツェと交際
1782年
コンスタンツェと結婚
翌年、長男が誕生するが2か月後に夭逝
1784年
次男のカール・トーマス誕生
フリーメーソンに加入
1786年
オペラ「フィガロの結婚」初演、プラハで大成功
三男が誕生するが死去
1787年
長女が誕生
父レオポルトが死去
1788年
3大交響曲を作曲(32歳)
長女が死去
1789年
家計が逼迫
ベルリン旅行
次女が誕生するが死去
1791年
四男フランツ・クサーヴァーが誕生
「レクイエム」未完のまま死去(35歳)

【PR】
→目次へ

