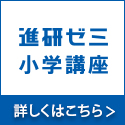がんばれ中学受験生!
ま行
(難しい熟語もふくまれています。中学受験生は青色文字の語を絶対に覚えましょう)
| 慢言放語 | まんげんほうご 言いたい放題言うこと。「放語漫言」ともいう。 |
| 曼殊沙華 | まんじゅしゃげ 仏教用語で、天界に咲く白い花。ヒガンバナの別名。 |
| 満場一致 | まんじょういっち その場の全員の意見が一つにまとまること。類:全会一致 |
| 満身創痍 | まんしんそうい 全身が傷(きず)だらけ。精神的にお手上げの状態。 |
| 三日坊主 | みっかぼうず 飽(あ)きやすく何をしても長続きしないこと。また、そのような人。 |
| 未来永劫 | みらいえいごう 未来にわたって永久に果てしないこと。類:未来永久 |
| 未練未酌 | みれんみしゃく 相手の気持ちがくみとれず心残りであること。 |
| 民族自決 | みんぞくじけつ 民族がそれぞれ政治的に独立し,みずからの政府をつくる権利。 |
| 無為自然 | むいしぜん 何もしないであるがままにまかせる。 |
| 無為徒食 | むいとしょく 何も仕事をしないで、ただぶらぶらと無駄(むだ)に暮らすこと。 |
| 無位無冠 | むいむかん 重要な地位についていないこと。類:無位無官 |
| 無為無策 | むいむさく 対抗策もなく何もせずにいること。類:拱手傍観 |
| 無学文盲 | むがくもんもう 教養がなく、文字が読めないこと。類:一文不知 |
| 無我無心 | むがむしん 我欲や邪(よこしま)な念がないこと。 |
| 無我夢中 | むがむちゅう ものごとに熱中してわれを忘れること。類:一心不乱 |
| 無芸大食 | むげいたいしょく 人並み以上に食べるくせに芸も才能もないこと。 |
| 無間地獄 | むげんじごく 仏教における地獄の世界観である「八大地獄」の最下層にあって、最も大きく恐ろしい責め苦を受ける地獄のこと。 |
| 無色透明 | むしょくとうめい 透(す)き通ってにごりがない、汚(よご)れていないこと。 |
| 無知蒙昧 | むちもうまい 智恵(ちえ)がなく、おろかで道理に暗いこと。類:無知無能・無知無学 |
| 無茶苦茶 | むちゃくちゃ でたらめで筋道(すじみち)が通らないこと。類:滅茶苦茶 |
| 無二無三 | むにむさん わき目もふらず、ひたすらなこと。類:遮二無二 |
| 無念無想 | むねんむそう 無我(むが)の境地(きょうち)に入って、何も考えないこと。 |
| 無病息災 | むびょうそくさい 病気もしないで健康で暮らすこと。類:一病息災・無事息災 |
| 無味乾燥 | むみかんそう つまらない内容で味も素っ気もないこと。 |
| 無味無臭 | むみむしゅう 味もにおいもない、つまり全く面白みがないこと。 |
| 無欲恬淡 | むよくてんたん 無欲で、あっさりしていて、執着(しゅうちゃく)のないこと。 |
| 無理往生 | むりおうじょう 無理やりに従わせること。強制的に承知・服従させてしまうこと。 |
| 無理算段 | むりさんだん 無理してお金を工面(くめん)すること。 |
| 無理難題 | むりなんだい 道理にはずれた言いがかりや、解決しそうにもない難しい問題。類:無理無法 |
| 無理無体 | むりむたい 道理にかなっていないことを無理矢理に押し通すこと。 |
| 明鏡止水 | めいきょうしすい 邪念(じゃねん)がなく、静かに澄(す)んだ心境。静かで物事に動じない状態。類:虚心坦懐 |
| 名実一体 | めいじついったい 名称と実質、評判と実際とが一致していること。 |
| 明窓浄机 | めいそうじょうき きちんと整理された清潔(せいけつ)で明るい書斎(しょさい)のこと。 |
| 明哲保身 | めいてつほしん 賢い人は物事の道理に従って行動し、危険を避(さ)けて安全な道を選び身を守るということ。 |
| 名誉挽回 | めいよばんかい 失った信用や評価を取り戻すこと。類:名誉回復 |
| 明朗闊達 | めいろうかったつ 明るく朗(ほが)らか、物事にこだわらないこと。類:明朗快活 |
| 迷惑千万 | めいわくせんばん たいへん迷惑なこと。類:迷惑至極 |
| 目茶苦茶 | めちゃくちゃ ひどく混乱して普通でない状態のこと。「滅茶苦茶」とも。 |
| 滅私奉公 | めっしほうこう 私心を捨て国のため公のためにつくすこと。 |
| 免許皆伝 | めんきょかいでん 師から弟子(でし)に、その道の奥義(おうぎ)を残らずすべて伝えること。 |
| 面向不背 | めんこうふはい どの角度から見ても形が整い美しいこと。 |
| 面従後言 | めんじゅうこうげん その人の前では服従(ふくじゅう)するように見せているが、隠(かく)れてかれこれと悪口を言うこと。 |
| 面従腹背 | めんじゅうふくはい 表面では服従(ふくじゅう)するように見せかけ、内心では背(そむ)いていること。類:面従後言 |
| 面目一新 | めんぼくいっしん 今までとは違う高い評価を得ること。「面目」は「めんもく」とも読む。 |
| 面目躍如 | めんぼくやくじょ 評判通りの活躍(かつやく)、評価にふさわしい様子。「面目」は「めんもく」とも読む。 |
| 孟母三遷 | もうぼさんせん 孟子(もうし)の母は、孟子の教育のために良い環境を求めて、住居を三回移し替えたという教え。 |
| 物見遊山 | ものみゆさん あちこち見物し、遊びに出かけること。 |
| 門外不出 | もんがいふしゅつ 秘蔵品を大切に保管し、他の人に見せたり貸したりしないこと。 |
| 門戸開放 | もんこかいほう 出入りや任官の制限をやめること。国の海港や市場を、外国の経済活動のために開放すること。 |
| 門前雀羅 | もんぜんじゃくら さびれて人も訪(おとず)れないこと。 |
| 門前成市 | もんぜんせいし その家に出入りする人が多いようすを言う言葉。 |
| 問答無用 | もんどうむよう 話し合っても無駄(むだ)、議論も必要ないこと。 |
や行
| 夜郎自大 | やろうじだい 自分の力量もわきまえず、仲間の中でいばること。 |
| 唯一無二 | ゆいいつむに それ一つだけで他に二つとないこと。 |
| 唯我独尊 | ゆいがどくそん 自分がいちばん偉いとうぬぼれること。ひとりよがり。 |
| 勇往邁進 | ゆうおうまいしん 目標に向かって勇ましく前進すること。 |
| 有害無益 | ゆうがいむえき 害があって、利益はないこと。 |
| 勇気凛々 | ゆうきりんりん 勇気に満ちあふれて、いきいきとしたようす。 |
| 有形無形 | ゆうけいむけい 形のあるものと形のないもの。 |
| 有言実行 | ゆうげんじっこう 言ったことは必ず実行すること。 |
| 優柔不断 | ゆうじゅうふだん 決断がぐずぐずしてはっきりしないこと。 |
| 優勝劣敗 | ゆうしょうれっぱい 勝っている者が勝ち、劣(おと)る者は負けること。 |
| 有職故実 | ゆうそくこじつ 古来の朝廷や武家の儀式、官職、制度、服飾、法令などの先例やよりどころを研究すること。 |
| 融通無碍 | ゆうづうむげ 障害がなく物事がなめらかに運ぶこと。 |
| 有名無実 | ゆうめいむじつ 名前だけで実質が伴わないこと。評判と実際とが違っていること。 |
| 勇猛果敢 | ゆうもうかかん 勇気があり決断力に富むこと。 |
| 悠々自適 | ゆうゆうじてき 俗世間(ぞくせけん)のわずらわしさから離れ、ゆっくりと自分の思うままに生きること。 |
| 油断大敵 | ゆだんたいてき 注意を少しでも怠れば、思わぬ失敗を招くから、十分に気をつけるべきだという戒め。類:油断強敵 |
| 余韻嫋々 | よいんじょうじょう あとに残る響きや風情(ふぜい)がいつまでも続くこと。 |
| 用意周到 | よういしゅうとう 用意が十分にととのって手抜かりがないこと。 |
| 容姿端麗 | ようしたんれい 顔つきも姿かたちも整って美しいこと。 |
| 羊頭狗肉 | ようとうくにく ひつじの頭を看板に出して犬の肉を売るという意で、表面だけりっぱに見せて実質が伴わないこと。 |
| 容貌魁偉 | ようぼうかいい 立派な体格と頼もしい顔つきの男性。 |
| 余裕綽々 | よゆうしゃくしゃく ゆったりと落ち着いていて、ゆとりのあるようす。 |
ら行
| 落花狼藉 | らっかろうぜき ものが散らかっているようす。 |
| 乱離骨灰 | らりこっぱい 散々に離れ散ること。めちゃめちゃになること。 |
| 乱暴狼藉 | らんぼうろうぜき 荒々しい振る舞いや無法な行為をすること。 |
| 利害得失 | りがいとくしつ 利益と損失。得るものと失うものと。類:利害得喪 |
| 力戦奮闘 | りきせんふんとう 力の限り努力すること。「力戦」は「りょくせん」とも読む。 |
| 離合集散 | りごうしゅうさん 離れたり集まったりすること。 |
| 立身出世 | りっしんしゅっせ 社会的に認められて名をあげること。出世して有名になること。 |
| 理非曲直 | りひきょくちょく 物事の善悪、正不正のこと。類:是非善悪 |
| 流言飛語 | りゅうげんひご 根拠のない、てたらめな噂(うわさ)やデマの類。 |
| 竜頭蛇尾 | りゅうとうだび 始めは勢いがいいが最後は尻(しり)すぼみに終わること。 |
| 粒粒辛苦 | りゅうりゅうしんく こつこつと努力と苦労を積み重ねること。類:苦心惨憺 |
| 良妻賢母 | りょうさいけんぼ 夫にとっては良い妻であり、子供にとっては賢い母親である人。 |
| 良風美俗 | りょうふうびぞく 良く美しい風俗習慣。 |
| 理路整然 | りろせいぜん 論理の筋道(すじみち)がよく通り、整っていること。 |
| 臨機応変 | りんきおうへん その場の変化や状況に応じて適切に対処すること。類:随機応変 |
| 輪廻転生 | りんねてんしょう 仏教で、人の生きかわり死にかわりをしてとどまることのないこと。 |
| 冷汗三斗 | れいかんさんと 恐ろしさやはずかしさで冷や汗がどっと出ること。 |
| 霊魂不滅 | れいこんふめつ 肉体は滅びても、魂(たましい)はいつまでも滅びないこと。 |
| 老少不定 | ろうしょうふじょう 老人が必ず先に死ぬとは限らず、少年が長生きするとは決まっていない。 |
| 老若男女 | ろうにゃくなんにょ 老人と若者と男性と女性と。さまざまな人々。 |
| 論功行賞 | ろんこうこうしょう 功績の有無や大きさの程度を調べ、それに応じてふさわしい賞を与えること。 |
わ行
| 和気藹々 | わきあいあい なごやかで仲のいいこと。 |
| 和光同塵 | わこうどうじん 知徳のすぐれた輝(かがや)きが目立たないようにして、世俗の人々と一緒(いっしょ)にいること。 |
| 和魂漢才 | わこんかんさい 日本的精神と中国伝来の学問・知識の合体。「和魂」は「大和魂(やまとだましい)」のこと。 |
| 和魂洋才 | わこんようさい 日本的精神と西洋の学問・知識の合体。 |
| 和洋折衷 | わようせっちゅう 日本風と西洋風を適当に取り合わせること。 |
バナースペース
意味の似た四字熟語
とてもひどい行い
悪逆非道
悪逆無道
極悪非道
とても苦しい
青息吐息
気息奄々
悪口をならべて罵る
悪口雑言
罵詈雑言
考えがまとまらない
暗中模索
五里霧中
元気いっぱい
意気軒高
意気衝天
意気揚々
多くの人が同じことを言う
異口同音
異口同声
異口同辞
一つのことに集中する
一意専心
一心不乱
専心一意
ほんのわずかの言葉
一言半句
一言一句
一言隻句
一人のように同じ
一心同体
異体同心
一度で二つ得る
一石二鳥
一挙両得
分かりやすくはっきりしている
一目瞭然
単純明快
簡単明瞭
熱中している
一心不乱
無我夢中
自然の美しい景色など
花鳥風月
春花秋月
雪月風花
自分勝手
我田引水
傍若無人
遠慮なく盛んに議論する
侃々諤々
議論百出
百家争鳴
欠けているところがない
完全無欠
円満具足
十全十美
過去にも将来にもないような珍しいこと
空前絶後
前代未聞
軽々しく動く
軽挙妄動
付和雷同
いばって他人を見下す
傲岸不遜
傲慢無礼
単独で誰の助けも得られない
孤立無援
孤軍奮闘
自分自身を向上させる
自己啓発
自己研鑽
ちりぢりばらばらになる
四分五裂
雲散霧消
最初から最後まで貫く
終始一貫
首尾一貫
徹頭徹尾
ほとんど
十中八九
九分九厘
進歩や変化がない
十年一日
旧態依然
主と従が逆転する
主客転倒
本末転倒
さまざまに違っている
各人各様
十人十色
千差万別
多種多様
その場の意見が一つにまとまる
全会一致
満場一致
正気を失う
前後不覚
人事不省
将来が明るい
前途洋々
前途有為
前途有望
明るく無邪気
天真爛漫
天衣無縫
すばやく機転が利く
当意即妙
臨機応変
あちこち駆け回る
東奔西走
南船北馬
だいたい同じ
大同小異
同工異曲
内外に苦労が尽きない
内憂外患
多事多難
眠らず休まず努力する
不眠不休
昼夜兼行
思いのままに変化する
変幻自在
千変万化
神出鬼没
大食いする
暴飲暴食
牛飲馬食
重要な地位についていない。
無位無官
無位無冠
知恵がなく愚か。
無知蒙昧
無知無能
無知無学
優っているものが勝つ
優勝劣敗
弱肉強食
悪逆非道
悪逆無道
極悪非道
とても苦しい
青息吐息
気息奄々
悪口をならべて罵る
悪口雑言
罵詈雑言
考えがまとまらない
暗中模索
五里霧中
元気いっぱい
意気軒高
意気衝天
意気揚々
多くの人が同じことを言う
異口同音
異口同声
異口同辞
一つのことに集中する
一意専心
一心不乱
専心一意
ほんのわずかの言葉
一言半句
一言一句
一言隻句
一人のように同じ
一心同体
異体同心
一度で二つ得る
一石二鳥
一挙両得
分かりやすくはっきりしている
一目瞭然
単純明快
簡単明瞭
熱中している
一心不乱
無我夢中
自然の美しい景色など
花鳥風月
春花秋月
雪月風花
自分勝手
我田引水
傍若無人
遠慮なく盛んに議論する
侃々諤々
議論百出
百家争鳴
欠けているところがない
完全無欠
円満具足
十全十美
過去にも将来にもないような珍しいこと
空前絶後
前代未聞
軽々しく動く
軽挙妄動
付和雷同
いばって他人を見下す
傲岸不遜
傲慢無礼
単独で誰の助けも得られない
孤立無援
孤軍奮闘
自分自身を向上させる
自己啓発
自己研鑽
ちりぢりばらばらになる
四分五裂
雲散霧消
最初から最後まで貫く
終始一貫
首尾一貫
徹頭徹尾
ほとんど
十中八九
九分九厘
進歩や変化がない
十年一日
旧態依然
主と従が逆転する
主客転倒
本末転倒
さまざまに違っている
各人各様
十人十色
千差万別
多種多様
その場の意見が一つにまとまる
全会一致
満場一致
正気を失う
前後不覚
人事不省
将来が明るい
前途洋々
前途有為
前途有望
明るく無邪気
天真爛漫
天衣無縫
すばやく機転が利く
当意即妙
臨機応変
あちこち駆け回る
東奔西走
南船北馬
だいたい同じ
大同小異
同工異曲
内外に苦労が尽きない
内憂外患
多事多難
眠らず休まず努力する
不眠不休
昼夜兼行
思いのままに変化する
変幻自在
千変万化
神出鬼没
大食いする
暴飲暴食
牛飲馬食
重要な地位についていない。
無位無官
無位無冠
知恵がなく愚か。
無知蒙昧
無知無能
無知無学
優っているものが勝つ
優勝劣敗
弱肉強食