そのほかの言葉
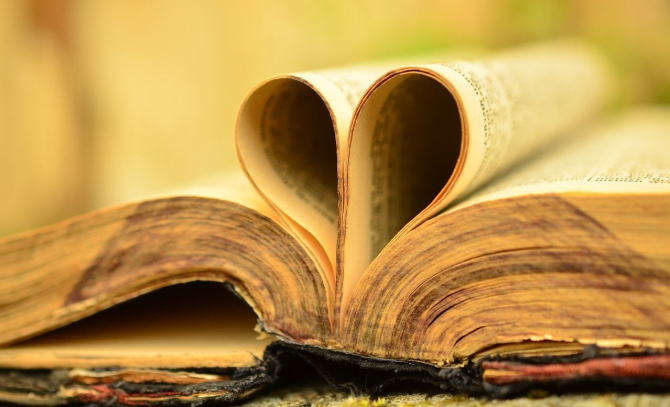
あ行
■ 藹々(あいあい)
おだやかなようす。打ち解けたようす。草木がさかんに茂っているようす。
■ 相合傘(あいあいがさ)
一本の傘に男と女が二人で入ること。
■ 相(あい)半(なか)ばする
互いに半分ずつである。同じくらいである。〔用例〕功罪相半ばする。
■ 逢引(あいびき)
愛し合う男女が、人目を忍んで逢うこと。
■ 相合傘(あいあいがさ)
一本の傘に男と女が二人で入ること。
■ 相俟(あいま)って
二つ以上のものがいっしょになって。互いに作用しあって。〔用例〕昨日は日曜日だったので、好天気と相俟って人出が多かった。
■ あえか
弱々しく、幼いかわいらしさあるさま。いかにもはかなげに見えるさま。〔用例〕彼女のようなあえかな女性には会ったことがない。
■ 青海原(あおうなばら)
青々とした広い海。
■ 購(あがな)う
つぐなう。埋め合わせをする。〔用例〕罪を購う。
■ 朝ぼらけ
夜明け方の、空がほんのりと明るくなったころ。もとは「朝おぼろ明け」。
■ 汗みずく
汗にぐっしょり濡れたようす。汗みどろ。漢字で書くと「汗水漬」。
■ あだ情け
かりそめの情け。
■ 恰(あたか)も好(よ)し
ちょうどよいことに。おあつらえむきに。〔用例〕時恰も好し。
■ あっぱれ
感動して褒め称える気持ちを表す言葉。漢字で書くと「天晴」。
■ 艶姿(あですがた)
女性の美しく色っぽい姿。
■ 当て所(ど)ない
目当てや頼りとするところがない。〔用例〕当て所なく、夜の都会をさまよった。
■ 跡(あと)をとどめる
痕跡を残す。しるしを残す。〔用例〕疲労の跡をとどめる。
■ 豈(あに)図(はか)らんや
意外なことにも。思いがけなくも。〔用例〕豈図らんや、彼が犯人だったとは。
■ 数多(あまた)
数が多くあること。たくさん。〔用例〕数多の苦難を乗り越える。
■ 天つ乙女(あまつおとめ)
天に住む乙女、すなわち天女のこと。「天つ」の「つ」は格助詞で、「天の」という意味。
■ あまねく
広く。一般に。〔用例〕世間にあまねく知れ渡る。
■ 甘(あま)んずる
それ以上を望まず満足する。仕方がないとして我慢する。〔用例〕甘んじて罰を受け入れる。
■ 天(あめ)が下
この国土。日本中。空の下。
■ あやなす
美しい模様をつくる。美しく彩る。うまく扱う。〔用例〕錦あやなす木々。多くの男性をあやなした経験。
■ 文目(あやめ)も分かたぬ
暗くて物の模様や区別がはっきりしないさま。物事の分別がつかないさま。〔用例〕文目も分かたぬ雨夜の暗闇。
■ あらずもがな
あってほしくない。ないほうがよい。〔用例〕あらずもがなの終章。〔類〕無くもがな。
■ ありてい
ありのまま。事実のまま。漢字で書くと「有体」または「有態」。〔用例〕ありていに言う。
■ 案に違(たが)う/案に相違(そうい)する
予想していたことや思案していたことが的中しない。〔用例〕案に違う試合展開になってきた。
■ 言い得(え)て妙(みょう)
「まさにぴったりな表現だ」「うまいこと言うものだ」という趣旨を表す言い回し。〔用例〕バブル経済とは言い得て妙だ。
■ 言い条(じょう)
主張。言い分。〔用例〕彼の言い条はもっともだ。
■ 言い知れぬ
言うに言われない。何とも言えない。〔用例〕言い知れぬ寂しさを覚える。
■ 言うなれば
言ってみるなら。言ってみれば。〔用例〕言うなれば、ここは私の第二の故郷である。
■ いかばかり
どれほど。どんなに。物事の数や程度の多さをおしはかる場合に用いる。〔用例〕悲しみはいかばかりかと思いやる。
■ いかんせん
どうしようもない。残念ながら。〔用例〕いかんせん、手遅れだ。
■幾何(いくばく)か
わずか。いくらか。〔用例〕幾何かの蓄え。
■ 礎(いしずえ)
ものごとの基礎となるもの。家の柱の下にすえる土台。柱石。
■ 居丈高(いたけだか)
気位が高く、相手を見下すような態度。〔用例〕居丈高な物言い。
■ 一分(いちぶん)が立たない
面目が立たない。名誉が保てない。〔用例〕リーダーとしての一分が立たない。
■ いっかな
全く。一向に。どうしても。「如何な」の促音便で、下に打消しの語を伴う。〔用例〕いっかな承知しない。
■ 幼(いと)けない
幼い。あどけない。〔用例〕幼い子どもたちを残しては行けない。
■ いとど
いっそう。ますます。〔用例〕やさしい言葉をかけられ、いとど寂しさが募ってきた。
■ 暇乞い(いとまごい)
別れを告げること。辞めたいと申し出ること。
■ 今を時めく
よい時勢にめぐりあい、今が最高の状態にあること。〔用例〕たちまちのうちに、今を時めく人気歌手となる。
■ いやさか
いよいよ栄えること。漢字で書くと「弥栄」。〔用例〕母国のいやさかを祈る。
■ いやしくも
仮にも。少なくとも。〔用例〕いやしくも人の上に立つ者ならば、そのようなことはすべきでない。
もしも。万一。〔用例〕いやしくもこれが現実なら、早急に手を打つべきだ。
■ いわんや
なおさら。まして。文末に「をや」をつけて、「大人でさえ難しいのに、いわんや子供においてをやだ。
■ 堆(うずたか)い
積み重なって高く盛り上がっている。〔用例〕堆く積もった土砂。
高貴である。高慢である。
■ うたた
いよいよ。ますます。〔用例〕うたた同情の念に堪えない。
■ 諾(うべな)う/宜(うべな)う
もっともなことであると同意する。〔用例〕彼の意見を諾う人が多かった。
■ うらうら
よく晴れて暖かくのどかなようす。
■ 云々(うんぬん)
①引用した文や重要な言葉を示したあとを省略するときに、以下略の意で、その末尾に添える語。〔用例〕この件は誤解を招きやすい云々との指摘があった。
②他人の言動についてとやかく言うこと。〔用例〕軽々に云々すべき問題ではない。
■ えならぬ/えならず
何とも言えないほど素晴らしい。〔用例〕えならぬ美しさに息をのむ。〔類〕えも言われぬ。
■ 老(お)いも若(わか)きも
老人も若者も。
■ おうち
あなた。うちは私のことだが、「お」がつくと対称代名詞になりあなたの意。今ではほとんど聞けなくなったが、大阪の古い仕舞屋などの上品なおばあちゃんやおじいちゃんが使っていた言葉。
■ 桜梅桃李(おうばいとうり)
桜・梅・桃・李(すもも)の花のこと。「それぞれが美しい花を咲かせるように、他人と自分を比べずに個性を磨こう」という教訓も含んだ言葉。
■ おしなべて
全体にわたって。一様に。概して。〔用例〕今年の稲はおしなべて出来がいいようだ。
■ 遠近(おちこち)
あちらこちら。ここかしこ。〔用例〕鶏の声が遠近に聞こえる。
■ 御目文字(おめもじ)
お目にかかることをいう女性語。〔用例〕いちど御目文字いたしたく・・・。
■ 思いなしか
そう思ってみると、そんな気がする。〔用例〕思いなしか、今日の彼は元気がなかった。
■ 思わず知らず
意識することなく。いつの間にか。〔用例〕思わず知らず涙がこぼれてきた。
■ 折(おり)しも
ちょうどその時。折も折。「し」は強意の助詞。〔用例〕折しも雪が降ってきた。
■ 折節(おりふし)
その時々。その場合場合。〔用例〕折節の思いを日記にしたためる。
【PR】
↑ ページの先頭へ
か行
■ 垣間(かいま)見る
物陰からこっそりとのぞき見る。ちらっと見る。〔用例〕大人の世界を垣間見る。
■ 肯(がえん)ずる
承諾する。肯定する。もとは漢文の「不肯」を訓読みした「かへにす」から来た言葉で、音と意味が転じて現在の意味になった。〔用例〕頑として肯んじない。〔類〕首肯(しゅこう)する。
■ かかずらう
かかわりあいを持つ。かかわりがあって離れられない状態になる。関係する。〔用例〕後ろ向きの仕事ばかりにかかずらっていられない。
■ 可及的(かきゅうてき)
できるだけ。なるべく。〔用例〕可及的速やかに提出せよ。
■ 陽炎(かげろう)
春や夏の晴れた日に現れる、空気がゆらゆらと揺れて見える現象。
■ 姦(かしま)しい
やかましい。耳障りでうるさい。〔用例〕女三人寄れば姦しい。
■ 佳人(かじん)
美しい女性。美人。〔用例〕佳人薄命。
■ 数(かず)を尽(つ)くす
すべてにわたってする。残らずやり遂げる。〔類〕限りを尽くす。
■ 糅(か)てて加えて
全体。〔用例〕事業に失敗し、糅てて加えて病魔に冒される。
■ 予言(かねごと)
前もって言いおいた言葉。約束の言葉。
■ 寡聞(かぶん)にして
知るところが少なくて。自分の知識不足を謙遜していう言葉〔用例〕寡聞にして存じません。
■ 仮初(かりそめ)
その場限りで一時的なこと。〔用例〕仮初の恋。
■ 川明かり
辺りが暗いなかで川の水面が反射して明るく見えること。
■ 可愛い訛(なま)り
京都の女性が話す京都弁のこと。
■ 鑑(かんが)みる
照らし合わせて考えること。「鑑」は鏡と同じ字源で、映して見ることから、手本になるという意味が生じた。〔用例〕状況に鑑みて決断する。
■ 閑日月(かんじつげつ)を送る
ひまな月日をのんびりと過ごす。
■ 感に堪(た)えない
非常に感動して、それを表に出さずにはいられない。〔用例〕感に堪えない面持ち。
■絆(きずな)
絶ち難い、人と人との結びつき。一体感。
■ 生粋(きっすい)
まじりけがなく、純粋なこと。その人の性質などが何処からみても言われる通りで、そのもの以外の何ものでもないこと。〔用例〕生粋の江戸っ子。
■ 鏡花水月(きょうかすいげつ)
目には見えるが、手に取ることのできないもののたとえ。また、感じ取れても説明できない奥深い趣のたとえ。
■ 曲(きょく)がない
型どおりで変化がなく、面白みがない。愛想がない。〔用例〕そう言ってしまっては曲がない。
■ 綺羅(きら)を飾る
華美をこらす。きらびやかに着飾る。〔用例〕綺羅を飾った宴。
■ 軌(き)を一(いつ)にする
方針や考え方を同じにする。〔用例〕あの二人は軌を一にするので、話がすぐにまとまる。
■ 草枕(くさまくら)
草を敷いて仮の枕にすることから、旅寝をすること。また、旅そのもの。〔用例〕あてどない草枕も、たまにはいいものだ。
■ 草分け
ある物事を初めて行うこと。また、その人。創始者。〔用例〕わが社は、この業界では草分け的存在だ。
■ 件(くだん)の
前に述べたこと。例の。いつものこと。例のもの。〔用例〕件の要件で話し合いたい。
■ 与(くみ)する
仲間入りする。賛同して味方になる。〔用例〕どちらの立場にも与しない。
■ 暗(く)れ惑う
どうしたらよいか分からず、途方に暮れる。悲しみのために心がふさいで思案に迷う。
■ 気色ばむ
怒りや不満の気持ちが外に現れる。むっとして顔色を変える。〔用例〕気色ばんで、席を立つ。
■ 群青(ぐんじょう)
あざやかな青色。
■ 懸想(けそう)
異性に思いを寄せること。〔用例〕秀吉は、お市の方に懸想した。
■ けだし
多分。おそらく。思うに。〔用例〕あなたの主張は、けだし正論だと思います。
■ 絢爛(けんらん)
目が眩むほど美しいさま。ぜいたくで煌びやかなさま。
■ 妍(けん)を競(きそ)う
美しさを競うこと。〔用例〕百花妍を競う。
■ 恋女房
恋愛して結婚した妻。
■ 希(こいねが)う
強く望む。切に希望する。〔用例〕彼の無事を希う。
■ 恋煩い(こいわずらい)
恋するあまりの悩みや気のふさぎ。 恋のやまい。
■ 行雲流水(こううんりゅうすい)
雲や川の水のように、深く物事に執着せず、自然の成り行きに身をゆだねて行動するたとえ。
■ 嚆矢(こうし)とする
(物事の)一番はじめである。「嚆矢」はかぶら矢の意。〔用例〕その説を唱えたのは彼をもって嚆矢とする。
■ 紅涙(こうるい)を絞(しぼ)る
若く美しい女性が涙を流すようす。
■ 言問(ことと)う
話をする。問いかける。男女が言い交わす。〔用例〕言問う人もいない田舎道。
■ 事程左様(ことほどさよう)に
以上述べてきたように。このようなわけで。それほど。〔用例〕事程左様に人間とは複雑な生き物だ。
【PR】
↑ ページの先頭へ
さ行
■ 逆さ別れ
親より先に子が死ぬこと。〔用例〕逆さ別れほどの親不孝はない。
■ 細(さざ)れ
細かい。小さい。わざかな。〔用例〕細れ石。細(れ)波
■ 沙汰(さた)止(や)み
計画などが中止になること。〔用例〕道路延伸計画が沙汰止みになった。
■ ざっくばらん
遠慮がなく率直なさま。もったいぶったところがなく、素直に心情を表すさま。心をざっくり割って、ばらりと明かすという意味。〔用例〕ざっくばらんに言ってごらん。
■ 然(さ)なきだに
そうでなくてさえ。ただでさえ。〔用例〕然なきだに静かな村が、より一層ひっそりとしている。
■ 然(さ)のみ
それほど。これといって特に。〔用例〕然のみ困難ではない。
■ 然(さ)は然(さ)りながら
それはそうであるけれども。
■ さやか
見た目にはっきりしていること。〔用例〕秋来ぬと目にはさやかに見えねども・・・。
■ 冴(さ)やけさ
冷たく凍りつくとともに、澄み切って鮮やかなようす。〔用例〕月冴ゆる。
■ 冴(さ)ゆる
凛とした寒さが際立つ感じ、寒さがいっそう増す感じを表す語。
■ さようなら
別れを告げるあいさつ。「さようならば」の省略で、「そういう事情だからお暇します」の意味を含む。何かと余韻を残す話し言葉が多い日本語の典型といえるのでは。
■ 然(さ)りとて
そうはいっても。そうかといって。〔用例〕悪くはない。然りとて感心するほどの出来栄えでもない。
■ 燦々(さんさん)
日の光が明るくきらきらと輝くようす。
■ 思案(しあん)に余(あま)る
いくら考えてもよい知恵が浮かばない。〔用例〕思案に余って相談する。
■ 云爾(しかいう)/然(しか)云う
漢文風の文章の末尾に付し、「上述の通り」の意で用いる。〔用例〕予の幸甚とする所なりと云爾。
■ 柵(しがらみ)
水の勢いを弱めるために水中に杭を打ち、それに木の枝や竹などをからませたもの。転じて、身にまとわりついて離れないもの。絶つことのできない関係。〔用例〕恋の柵。
■ 然るに
ところが。そうであるのに。〔用例〕金融緩和政策は実行された。然るに、それが中小零細企業に行き渡っていない。
■ 如(し)くは無し
比較するものがない。〔用例〕油断大敵、身の用心に如くは無し。
■ 静寂(しじま)
静まり返って、物音一つしないこと。〔用例〕夜の静寂。
■ しっぽり
しっとりと全体的に十分ぬれるさま。雨が静かに降るさま。男女間の愛情のこまやかなさま。〔用例〕春雨にしっぽりと濡れる。しっぽりと語り明かす。
■ しどけない
身なりなどがきちんとせず、だらしない。しまりがない様子。〔用例〕しどけないネグリジェ姿。
■ しとど
びっしょり濡れたようす。
■ 忍び逢い
男女がこっそり逢うこと。逢引。
■ 仕舞屋(しもたや)
以前に商売をしていたが、やめてしまった家。商売をしていない一般の家。
■ 朱(しゅ)を注(そそ)ぐ
顔が真っ赤になるたとえ。〔用例〕満面に首を注ぐ。
■ 逍遥(しょうよう)
あちこちをぶらぶら歩くこと。散歩。そぞろ歩き。
■ 白白明け(しらじらあけ)
東の空がしだいに明るくなってくるころ。夜明けのころ。
■ 蜃気楼(しんきろう)
密度が異なる大気の中で光が屈折して虚像が見える自然現象。春から初夏にかけて見られることが多い。
■ 深々(しんしん)
夜が静かに更けていくようす。寒さが身にしみるようす。奥深いようす。
■ 彗星(すいせい)のごとく
突然ななやかに現れるようす。〔用例〕次世代のリーダーとして彗星のごとく現れた。
■ すずろ
心のおもむくままに物事をするさま。これといった当てもないさま。これといった根拠や理由のないさま。本意に反しているさま。風情がないさま。みやみ。やたら。
「すずろ言」はつまらない言葉。「すずろ歩き」は当てもなく歩き回ること。「すずろ心」は浮ついた心。
■ 昴(すばる)
おうし座にある星団の名前。「統一」という意味の「すばまる」という雅語が変化したもの。
■ すべからく
当然。本来ならば。「すべきであること」の約。下に「べし」が来る場合が多い。〔用例〕学生はすべからく勉強すべし。
■ 赤心
いつわりのない心。まごころ。誠意。「赤」は明らかという意味。〔用例〕彼の赤心が通じた。
■ せせらぎ
小川。漢字で書くと「細流」。
■ 雪月花(せつげつか/せつげっか)
四季の自然美として代表的な、冬の雪・秋の月・春の花を表した語。白居易の詩『寄殷協律』の中の一句「雪月花時最憶君(雪月花の時 最も君を憶ふ)」による。
■ 刹那(せつな)
ほんの一瞬、きわめて短い時間。
■ 詮方(せんかた)無(な)い
仕方がない。どうしようもない。「詮方」は当て字で「為ん方」とも書く。
■ 先達(せんだつ)
他の人より先にその分野に進み、業績・経験を積んで他を導くこと。また、その人。先輩。〔用例〕先達に学ぶ。
■ 楚々(そそ)
清らかで美しいようす。あざやかなさま。〔用例〕楚々とした女性。
■ 卒爾(そつじ)ながら
「突然で失礼ですが」というときの決まり文句。〔用例〕卒爾ながらお尋ねいたします。
■ 其文字(そもじ)
あなた。そなた。
■ 忖度(そんたく)
他人の心を推しはかること。推察。推測。
※「美しい大和言葉」も併せて御覧になってください。
 |
ちょっと美しい日本語
昔の人たちが残してくれた、美しい日本語の数々。 |
バナースペース
【PR】
使いこなしたい慣用表現
◎辺りを払う
◎言い得て妙
◎如何せん
◎生き馬の目を抜く
◎委曲を尽くす
◎異彩を放つ
◎潔しとしない
◎いざ知らず
◎居住まいを正す
◎一日の長
◎一も二もなく
◎一線を画する
◎一頭地を抜く
◎言わずもがな
◎因果を含める
◎打てばひびく
◎倦(う)まずたゆまず
◎倦むことなく
◎烏有に帰す
◎得てして
◎得も言われぬ
◎襟(えり)を正す
◎おいそれ
◎推して知るべし
◎惜しむらくは
◎押しも押されもせぬ
◎遅きに失する
◎男を上げる
◎思いきや
◎思い半ばに過ぐ
◎折り紙つき
◎折しも
◎笠に着る
◎肩で風を切る
◎刀折れ、矢尽きる
◎寡聞にして
◎間然するところがない
◎気が置けない
◎機が熟す
◎踵(きびす)を返す
◎肝に銘ずる
◎琴線に触れる
◎釘を刺す
◎口幅ったい
◎酌んでも尽きない
◎軽々に
◎気色ばむ
◎けだし
◎言下
◎後顧の憂い
◎毫(ごう)も
◎心にかかる
◎腰を据(す)える
◎こそすれ
◎事ともせず
◎小耳にはさむ
◎こもごも
◎細大漏らさず
◎沙汰の限り
◎察するに余りある
◎三拍子そろう
◎歯牙にも掛けない
◎(~するに)如くはない
◎忸怩(じくじ)
◎耳朶(じだ)に触れる
◎死命を制する
◎下にも置かない
◎鎬(しのぎ)を削る
◎耳目を集める
◎衆を頼む
◎愁眉を開く
◎十目の見るところ
◎衝に当たる
◎緒に就く
◎知らぬ存ぜぬ
◎心眼を開く
◎人口に膾炙する
◎人後に落ちない
◎進退窮まる
◎水泡に帰す
◎図星を指す
◎正鵠を射る
◎寂(せき)として
◎せつな
◎選を異にする
◎相好を崩す
◎俗耳に入りやすい
◎俎上に載せる
◎底を割る
◎そぞろ
◎高をくくる
◎多言を要しない
◎多とする
◎矯めつ眇めつ
◎端倪すべからざる
◎昼夜をおかず
◎重畳
◎緒に就く
◎頭角をあらわす
◎等閑に付する
◎同日の談ではない
◎堂に入る
◎時を得る
◎どのみち
◎度を失う
◎名にし負う
◎なまじ
◎二の次
◎二の舞を演ずる
◎沛然
◎拍車をかける
◎半畳を入れる
◎万難を排する
◎範を仰ぐ
◎引きも切らず
◎ひそみに倣う
◎筆舌に尽くしがたい
◎ひとしお
◎百も承知
◎平仄が合う
◎非を鳴らす
◎臍(ほぞ)を噛(か)む
◎間尺に合わない
◎眦(まなじり)を決する
◎微塵(みじん)も
◎味噌をつける
◎身を粉にする
◎名状しがたい
◎以て瞑すべし
◎矢も楯もたまらず
◎ややもすると
◎ゆるがせにしない
◎窈窕(ようちょう)
◎由(よし)も無い
◎よしや
◎余人
◎宜しきを得る
◎埒(らち)が明かない
◎論を俟たない
◎我が意を得る

時候の挨拶
初春の侯/新春の候/迎春の候/厳寒の候/厳冬の候/寒中の候/寒風の候/大寒の候/仲冬の候
2月
晩冬の候/立春の候/残冬の候/晩冬の候/向春の候/春雪の候/雪解の候/春寒の候/節分の候
3月
早春の候/浅春の侯/春寒の候/仲春の候/春分の候/春晴の候/若草の候/水ぬるむ候/春暖の候
4月
陽春の候/春風の候/仲春の候/晩春の候/桜花の候/春暖の候/春眠の候/花冷えの候/惜春の候
5月
残春の候/立夏の候/新緑の候/葉桜の候/薫風の候/青葉の候/万緑の候/陽光の候/藤花の候
6月
入梅の候/梅雨の侯/梅雨寒の候/梅雨空の候/長雨の候/初夏の候/向暑の候/新緑の候/初夏の候
7月
向暑の候/小暑の候/盛夏の候/暑中の候/仲夏の候/盛暑の候/猛暑の候/炎熱の候/大暑の候
8月
晩夏の候/残暑の候/残夏の候/残炎の候/処暑の候/立秋の候/秋暑の侯/早涼の候/新涼の候
9月
初秋の候/早秋の候/新涼の侯/孟秋の候/涼風の候/秋分の候/秋涼の侯/清涼の候/白露の候/
10月
秋晴の侯/仲秋の候/秋涼の候/秋冷の侯/秋雨の候/紅葉の候/菊花の候/初霜の候/寒露の候
11月
深秋の候/季秋の候/晩秋の候/暮秋の候/初霜の候/向寒の候/夜寒の候/落葉の候/氷雨の候/立冬の候
12月
初冬の候/寒冷の候/霜夜の候/初冬の候/初雪の候/新雪の候/短日の候/師走の候/歳末の候
なお、「~の候」のほかに「~のみぎり」「~の折」などの用法もあります。

手紙の頭語と結語
【頭語】
拝啓/拝呈/啓上
拝復(返信の場合)
一筆申し上げます
【結語】
敬具/敬白/拝具
かしこ(女性の場合)
丁寧な手紙
【頭語】
謹啓/謹呈/恭啓
謹んで申し上げます
【結語】
謹言/謹白/敬白
かしこ(女性の場合)
前文を省略する場合
【頭語】
前略/冠省
前文お許しください
前略失礼します
前略ごめんください
【結語】
草々(早々)/不一
かしこ(女性の場合)
急用の手紙
【頭語】
急啓/急呈/急白
取り急ぎ申し上げます
【結語】
草々(早々)/不一/不備
かしこ(女性の場合)
ふだんは、目上の人には「拝啓‐敬具」、親しい人には「前略‐草々」で用は足ります。ただし目上の人に「前略」「冠省」は使えないので、注意が必要です。

【PR】

