蕪村の俳句集

春の句
朝日さす弓師(ゆみし)が店(たな)や福寿草
朝日がさしこむ弓師の店先に、ひと鉢の福寿草が誇らしく飾られている。清らかで美しい新春の情景だ。(弓師は武具を作る職人。)〔季語〕福寿草
日の光(ひかり)今朝(けさ)や鰯(いわし)の頭(かしら)より
日の光のおごそかな新年の朝、信心も鰯の頭から。〔季語〕鰯の頭
難波女(なにわめ)や京を寒がる御忌詣(ぎょきもうで)
難波の女が、京都を寒いといって身震いする、御忌詣。(「御忌詣」は、1月19日の夜から知恩院で行われる法然上人の年忌法要。)〔季語〕御忌詣
しら梅に明(あく)る夜(よ)ばかりとなりにけり
白梅のあたりがうっすらと明るくなり、そこからしだいに夜が明けてきた。そういう夜明けがこれから続いていくのだろう。(蕪村の臨終吟の一つ。)〔季語〕しら梅
襟巻(えりまき)の浅黄(あさぎ)にのこる寒さかな
春になってもなお寒く、道行く人はまだ襟巻をはなせない。その襟巻の浅黄色がいっそう寒さを感じさせる。(浅黄色は、黄色がかった薄い藍色。)〔季語〕のこる寒さ
うぐひすの啼(なく)やちひさき口(くち)明(あい)て
庭木を飛び回る鶯が、小さな口をいっぱいに開き、喉をふるわせながら鳴いている。〔季語〕うぐひす
うぐひすのあちこちとするや小家がち
うぐいすが、あちこちと飛び回っている、小さな家々の間を。〔季語〕うぐひす
春水(しゅんすい)や四条五条の橋の下
春の水量を増した水が勢いよく流れて行く、四条五条の橋の下を。〔季語〕春水
二(ふた)もとの梅に遅速(ちそく)を愛すかな
庭の二本の梅は、わずかな日当たりの違いで、一本は早く花が咲き、もう一本はやや遅れて花をつける。そんなところから春の足どりが感じられる。(前書「草庵」)〔季語〕梅
紅梅(こうばい)の落花(らっか)燃ゆらむ馬の糞(ふん)
路上の馬の糞に、紅梅の花が散りかかっている。あざやかな紅の色は、今にも燃えそうだ。〔季語〕紅梅
梅咲て帯(おび)買ふ室(むろ)の遊女かな
早春の梅が咲き、競って帯を買う室の遊女だよ。(「室」は播州〈兵庫県〉の室津。〔季語〕梅
春雨や暮れなむとして今日(けふ)もあり
春雨が降り続いている。夕暮れが迫ってきたが、暮れそうで暮れない一日だ。〔季語〕春雨
一筋も弃(す)たる枝なき柳かな
一筋も無駄な枝のない、見事な柳の木であるよ。(「弃たる」は、廃る、役に立たない意。)〔季語〕柳
春風や堤(つつみ)長うして家遠し
春風がそよそよと吹くなか、堤の上の道を歩き通している。懐かしい故郷ははるか彼方に霞んでいる。〔季語〕春風
遅き日のつもりて遠きむかしかな
遅々とした春の日が続いている。こうした日々を幾年も重ねるうち、昔もはるか遠くなってしまったことだ。(前書「懐旧」。「遅き日」は、春の日が長くなり、日暮れが遅くなること。)〔季語〕遅き日
折釘(おりくぎ)に烏帽子(えぼし)かけたり春の宿
高貴な人が泊まった春の宿。ふだんのように烏帽子をかける場所がないので、とりあえず目に付いた折釘にかけている。〔季語〕春
雛(ひな)祭る都はづれや桃の月
雛人形を祭る都はずれの寂しげな家。空には桃の月が照っている。(「桃の月」は桃の節句にちなむ表現。)〔季語〕雛祭る
雛見世(ひなみせ)の灯(ひ)を引くころや春の雨
雛人形を売る店が店じまいのために灯をおとすちょうどその頃、春の雨が降ってきたよ。〔季語〕春の雨
古庭(ふるにわ)に鶯(うぐいす)啼(な)きぬ日もすがら
古庭にウグイスが一日中鳴き続けているよ。〔季語〕鶯
傾城(けいせい)はのちの世かけて花見かな
遊女は、来世の安楽を願って花見をしている。(外見は華やかでも、来世は自由の身に生まれ変わり、心置きなく花見を楽しみたいだろうと、遊女の心情を思いやった句。)〔季語〕花見
凧(いかのぼり)きのふの空のありどころ
昨日の空のあそこには凧が上がっていた。今はもう何もいない。〔季語〕凧
およぐ時よるべなきさまの蛙(かわず)かな
蛙が泳いでいる。止まっては向きを変え、泳いではまた止まる。そのさまは、いかにも寄る辺のない感じだ。〔季語〕蛙
古びなやむかしの人の袖几帳(そできちょう)
古びた雛人形よ。昔の恋人が袖で顔を隠したしぐさが思い出される。(「袖几帳」は袖をあげて顔を隠すしぐさ。)〔季語〕ひな
片町に更紗(さらさ)染むるや春の風
片側町に紺屋があり、色鮮やかに染められた更紗が、春の風に揺れている。(「片町」は、道の片側だけ家並みが続く町。「更紗」は多色で文様を染めた木綿。)〔季語〕春の風
寝た人に眠る人あり春の雨
やわらかな春の雨が降る中、もう寝た人もいるし、これから眠ろうとする人もいる。〔季語〕春の雨
やぶ入りの夢や小豆(あずき)の煮えるうち
やぶ入りで久しぶりに我が家に帰ってきた子どもが、小豆を煮てやっている僅かの間にも横になって眠ってしまった。疲れているのだろうが、きっと楽しい夢を見ているだろう。(盧生が短いうたた寝の間に栄耀栄華の夢を見たという中国故事を踏まえている。)〔季語〕やぶ入り
燭(しょく)の火を燭にうつすや春の夕(ゆう)
春の日の夕暮れ。燭台から燭台へと灯りをうつしていく。明るくなった室内もまた春らしくのどかであることだ。〔季語〕春の夕
公達(きんだち)に狐(きつね)化けたり宵(よい)の春
なまめかしい春の宵。一人歩いていくと、ふと貴人らしい人に出会った。あれはキツネが化けたに違いない。〔季語〕宵の春
女(おんな)俱(ぐ)して内裏(だいり)拝まん朧月(おぼろづき)
美しい朧月夜、女を連れて御所を拝みに行こう。(『源氏物語』の「花宴」を踏まえ、王朝の色好みの男に仮託した願望を詠んだ句。)〔季語〕朧月
横に降る雨なき京の柳かな
横なぐりの雨が降ることのない京都の、雨に濡れている柳の美しさよ。〔季語〕柳
春雨や小磯(こいそ)の小貝(こがい)ぬるるほど
小磯の砂の上に美しく小さな貝が散らばっている。春雨が降ってはいるが、その貝をわずかに濡らすほどだ。〔季語〕春雨
春の海ひねもすのたりのたりかな
のどかな春の海。一日中、のたりのたりと波打っているばかりだよ。(前書「須磨の海にて」)〔季語〕春の海
春雨にぬれつつ屋根の手毬(てまり)かな
女の子たちの遊んでいる声が聞こえなくなったと思ったら、いつの間にか春雨がしとしとと降っている。屋根の上には、引っかかった手まりが濡れている。〔季語〕春雨
春の夕(ゆう)絶えなむとする香(こう)をつぐ
春の夕闇が迫ってきた。ゆらめいていた香の煙が途切れようとしているので、静かに香をつぎ足した。〔季語〕春の夕
滝口に灯(ひ)を呼ぶ声や春の雨
春雨が降りしきり、辺りがひっそりと暗くなってきた。そんな中、滝口には、禁中警護の武士たちが灯を求める声が響いている。〔季語〕春の雨
高麗舟(こまぶね)のよらで過ぎゆく霞(かすみ)かな
高麗船が沖合いを静かに通り過ぎていく。こちらの港にも寄らないで、そのまま霞の中に消え入ってしまった。〔季語〕霞
さしぬきを足でぬぐ夜(よ)や朧月(おぼろづき)
男がほろ酔い加減で帰宅するなり、部屋の中にごろりと横になる。そのまま足を動かしながら指貫を脱いでいる。夜も更けた空には朧月夜がかかっている。(さしぬきは、略装の袴。)〔季語〕朧月
菜の花や月は東に日は西に
夕方近い、一面の菜の花畑。月が東の空に登り、振り返ると日は西の空に沈もうとしている。(前書「春景」)〔季語〕菜の花
釣鐘(つりがね)にとまりてねむる胡蝶(こちょう)かな
物々しく大きな釣鐘に、小さな蝶々がとまって眠っている。何とも可憐な姿だよ。〔季語〕胡蝶
畑(はた)うつやうごかぬ雲もなくなりぬ
畑を打ち続け、ふと手を止めて空を眺めると、さっきまで動かずにいた雲がどこかへ消えてしまっていた。(「畑うつ」は、彼岸から八十八夜の間に畑を鍬きかえして耕す作業。)〔季語〕畑うつ
ゆく春やおもたき琵琶(びわ)の抱きごころ
春が行き過ぎようとするある日、久しぶりに琵琶を奏でようと抱きかかえると、とても重く感じた。これも晩春の物憂さのゆえだろうか。〔季語〕ゆく春
枕(まくら)する春の流れやみだれ髪
若い女性が肘を枕にうたた寝をしている。長い黒髪が白いうなじから肩のあたりまで波打つように乱れてかかり、あたかも春の水の流れを枕にしているようだ。〔季語〕春の流れ
陽炎(かげろう)や名もしらぬ虫の白き飛ぶ
野原にゆらゆらと陽炎が立ちのぼっている。そんな暖かい日差しのなか、光の筋となって名も知らない白い虫が飛んで行く。(前書「郊外」)〔季語〕陽炎
春雨や人住みて煙(けむり)壁(かべ)を洩(も)る
長く人が住んでいなかった家に、このごろ誰かが住むようになったらしい。春雨の日、壁の隙間から煙が漏れてただよっている。〔季語〕春雨
花ちりて木(こ)の間の寺と成(なり)にけり
花が散って、木の間から透けて見える寺となったことだよ。〔季語〕花
畠(はた)うつや鳥さへ啼(なか)ぬ山陰に
畑を打っている、鳥さえも鳴かない寂しいこの山陰に。〔季語〕畠うつ
象(ぞう)の眼の笑ひかけたり山桜
象の眼が笑かけているように見える、山桜が咲き始めた春の山よ。(前書「象頭山〈ぞうずさん〉」。象頭山は讃岐の金毘羅宮がある山。)〔季語〕山桜
ゆく春や逡巡(しゅんじゅん)として遅ざくら
散らずにいつまでもぐずぐずと咲き続けている遅ざくら。過ぎ行く春を惜しんでいるからなのだろうか。(前書「暮春」)〔季語〕ゆく春・遅ざくら
妹(いも)が垣根さみせん草の花咲きぬ
恋しい女の家のそばまでやって来ると、垣根に三味線草(なずな)の花が咲いている。昔、琴を鳴らして恋心を伝えたという話があるが、三味線草は自分の思いを伝えてはくれないだろうか。(前書に「琴心もて美人に挑む」とあり、司馬相如が富豪の娘に琴を弾いて恋心を伝えたという中国の故事をふまえたもの。)〔季語〕さみせん草
遅き日や雉子(きじ)の下りゐる橋の上
春の日長(ひなが)、人の通る橋の上に一羽の雉が(きじ)が舞い降りている。〔季語〕雉子
立(たつ)雁(かり)のあしもとよりぞ春の水
北へ飛び立っていく雁、その足元には春の水がしたたっている。〔季語〕春の水
春の夜や盥(たらい)をこぼす町外(まちはず)れ
甘美な春の夜、たらいの使い水を捨てる町外れであるよ。〔季語〕春の夜
拾ひのこす田螺(たにし)も月の夕かな
拾い残した田螺にも、月の光が降り注ぐ夕べとなった。〔季語〕田螺
山鳥の尾をふむ春の入日(いりひ)かな
山鳥の尾を踏むかのような、長く伸びた春の入り日であるよ。〔季語〕遅日(春の入日)
誰(た)がための低き枕ぞ春の暮
誰のために用意した枕だろうか、やるせない春の夕暮れ。(「低き枕」は、女性用の高い箱枕に対し、男性用の低いくくり枕。恋人の訪れがなく、孤閨をかこつ女性に思いを寄せた句。)〔季語〕春の暮
春の暮(くれ)家路(いえじ)に遠き人ばかり
春の夕暮れ時、町を行き交う人々は、家に帰るのがもったいなくて、家路に帰ろうともしない。〔季語〕春の暮
筋違(すじかい)にふとん敷(しき)たり宵の春
筋違いにふとんを敷いて寝てみたよ、心地よい宵の春。(前書「几董〈きとう〉とわきのはまにあそびし時」。「几董」は蕪村の弟子。「わきのはま」は神戸の脇浜海岸。「筋違」は斜め向かい。)〔季語〕宵の春
藤の茶屋あやしき夫婦(めおと)休みけり
藤の花が咲く茶屋に、いわくありげな夫婦が休んでいる。(駆け落ちの途中なのか、不自然な感じのする男女を詠んだ句。)〔季語〕藤
ゆく春や撰者(せんじゃ)をうらむ歌の主
春は過ぎ去ろうとしているのに、自分の歌が選にもれた歌詠みが、いつまでも愚痴をこぼしていることよ。〔季語〕ゆく春
【PR】
↑ ページの先頭へ
夏の句
方百里(ほうひゃくり)雨雲(あまぐも)よせぬぼたんかな
真紅のぼたんが空に向かって威勢よく花を開いている。その百里四方に雨雲を寄せつけないかのように。〔季語〕ぼたん
やどり木の目を覚(さま)したる若葉かな
ふだんは目立たない宿り木が目を覚ましたようで、若葉が美しい。〔季語〕若葉
更衣(ころもがえ)野路(のじ)の人はつかに白し
更衣して野の道を行く人が、遠くかすかに白く見える。(「はつかに」は、かすかに。)〔季語〕更衣
うは風に音なき麦を枕もと
麦畑の上を渡った風が音もなく吹き入れてくる、気持ちのよい昼寝の枕元であるよ。(前書「嵯峨の雅因が閑を訪て」。雅因は蕪村の俳友で、嵯峨に閑居した。雅因への挨拶句。)〔季語〕若葉
我庵(わがいお)に火箸(ひばし)を角(つの)や蝸牛(かたつぶり)
わが庵で、火箸を角のようにふりたててみると、まるで蝸牛になったようだ。(前書「東山麓に卜居〈ぼくきょ〉」)〔季語〕蝸牛
骨(こつ)拾ふ人に親しき菫(すみれ)かな
荼毘(だび)に付し、骨を拾う一人ひとりに、可憐な菫が寄り添って咲いている。〔季語〕菫
紙燭(しそく)して廊下通るや五月雨(さつきあめ)
紙燭を灯しながら、長い廊下を通って行く、この五月の暗い長雨に。(「紙燭」は、手で持つ灯火。蕪村特有の王朝懐古の句。)〔季語〕五月雨
きぬきせぬ家中(かちゅう)ゆゆしき衣更(ころもがえ)
絹を着せない、家中が厳粛で質朴な衣更であるよ。〔季語〕衣更
狩衣(かりぎぬ)の袖(そで)のうら這(は)ふほたるかな
手にとらえていたはずの蛍が、いつの間にか狩衣の袖の裏に飛び込んでいた。薄い衣を通して明滅する光が美しい。(「狩衣」は、袖口の広い貴族の常服。平安朝の貴族たちの蛍狩りの場面を想像して詠んだ句。)〔季語〕ほたる
夕風や水(みず)青鷺(あおさぎ)の脛(はぎ)をうつ
夕風が吹く川の水辺に青鷺が立っている。川面のさざ波が、青鷺の脛をしきりと打っている。〔季語〕青鷺
金屏(きんびょう)のかくやくとしてぼたんかな
広間には金屏風が燦然と輝き、その庭先には牡丹が今を盛りと咲き誇っている。〔季語〕ぼたん
広庭(ひろにわ)の牡丹(ぼたん)や天の一方に
広い庭に咲き誇っている牡丹よ、まるで天の一方を占めているかのようだ。(蘇東坡の「美人ヲ望ム天ノ一方ニ」を踏まえているか。)〔季語〕牡丹
地車(じぐるま)のとどろと響く牡丹(ぼたん)かな
地車が轟音を響かせて通る道の傍ら、牡丹は静かに艶然として咲き誇っている。〔季語〕牡丹
閻王(えんおう)の口や牡丹(ぼたん)を吐(はか)んとす
閻魔大王の開いた真っ赤な口が、今にも牡丹を吐こうとしているかのようだ。〔季語〕牡丹
夏川を越すうれしさよ手に草履(ぞうり)
ぞうりをぬいで手に持ち、素足のまま夏の川をわたる。何ともうれしく、気持ちのよいことだ。 〔季語〕夏川
動く葉もなくておそろし夏木立
葉が全く微動だにしない夏木立。あまりの静けさに、かえって恐ろしく感じる。 〔季語〕夏木立
休み日や鶏(とり)なく村の夏木立
仕事休みの日、鶏が鳴く村に繫っている、青々とした夏木立よ。 〔季語〕夏木立
みじか夜や六里の松に更(ふけ)たらず
何とも短い夜である。六里続く天橋立の松に夜が更けきらないうちに、夜が明けてしまう。(前書「青飯法師にはしだてに別る」。青飯法師〈せいはんほうし〉は渡辺雲裡坊〈わたなべうんりぼう〉。近江義仲寺の無名庵5世。蕪村と親しく交際した。)〔季語〕みじか夜
我が影を浅瀬に踏みてすずみかな
川の浅瀬にのびる我が影を踏んで、涼んでいるよ。〔季語〕すずみ
半日の閑(かん)を榎(えのき)やせみの声
半日の閑を得て、のんびりと榎に鳴く蝉の声を聞いている。(「閑を得る」と「榎」を掛けている。)〔季語〕蝉
いづこより礫(つぶて)うちけむ夏木立(なつこだち)
鬱蒼と茂った夏木立の中を歩いていると、近くでばさっと音がした。誰かが礫を打ち込んだのだろうか。 〔季語〕夏木立
寂(せき)として客の絶え間のぼたんかな
牡丹を見物に来ていた客足が途絶えたが、花はひっそりと咲き誇っている。〔季語〕牡丹
落合(おちおう)て音なくなれる清水(しみず)かな
岩の間を音を立てて流れていた幾筋かの清水が、合流してからは静かに流れていく。〔季語〕清水
青梅(あおうめ)に眉(まゆ)あつめたる美人かな
青い梅がなっているのを観た美人が、見ただけで酸っぱそうだと感じて、その美しい眉をひそめた。〔季語〕青梅
牡丹(ぼたん)散つてうちかさなりぬニ三片(にさんぺん)
咲き誇っていた牡丹の花が、わずか数日で衰え始め、地面に花びらがニ、三片と重なって落ちている。〔季語〕牡丹
五月雨(さみだれ)や滄海(あおうみ)を衝(つ)く濁水(にごりみず)
降り五月雨に、川の水は濁り水となって、河口から青い海を衝くように流れ出ていく。〔季語〕五月雨
五月雨(さみだれ)や大河を前に家二軒
五月雨が降り続いて水かさを増した大河がごうごうと流れている。その大河の前に家が二軒建っているが、水の勢いに今にもおし流されてしまいそうだ。〔季語〕五月雨
涼しさや鐘をはなるるかねの声
早朝の涼しさの中、鐘の音が響いている。一つまた一つと鐘をつくたびに、その音は遠くへ離れていくようで、何ともさわやかだ。〔季語〕涼しさ
お手討ちの夫婦(めをと)なりしを更衣(ころもがへ)
不義密通によりお手討ちになるべきところを許された若い男女が、他国に落ちのび世に隠れて暮らし、今こうして、無事に更衣の季節を迎えることができた。〔季語〕更衣
山蟻(やまあり)のあからさまなり白牡丹(はくぼたん)
大きく真っ白な白牡丹の花びらに、山蟻が這っていく。その黒さが何とも印象的だ。〔季語〕牡丹
鮎(あゆ)くれてよらで過行(すぎゆく)夜半(よわ)の門
深夜、門をたたく音がするので、開けてみると、釣りの帰りだという友が、数尾の鮎を差し出して、そのままそそくさと立ち去った。〔季語〕鮎
短夜(みじかよ)や芦間(あしま)流るる蟹(かに)の泡(あわ)
夏の短い夜が明けるころ、川の岸辺に生い茂る芦の間を、蟹が吹いた泡がとぎれとぎれに流れていく。〔季語〕短夜
三井寺(みいでら)や日は午(ご)にせまる若楓(わかかえで)
正午近い初夏の三井寺の境内に、茂った若楓が照り輝いている。〔季語〕若楓
石工(いしきり)の鑿(のみ)冷したる清水(しみず)かな
夏の日盛りの石切り場。人夫の使うのみも熱くなってきたのか、傍らの清水にずぶりと浸けた。〔季語〕清水
不二(ふじ)ひとつうづみ残して若葉かな
辺り一面、若葉にうずめられているが、くろぐろとした富士山だけがぽっかり残っている。〔季語〕若葉
廿日路(はつかじ)の背中に立つや雲の峰
二十日間にわたる長い旅路、背後に雲の峰がそびえ立っている。〔季語〕雲の峰
をちこちに滝の音聞く若葉かな
遠くに近くに、滝の音が聞こえてくる、辺りいっぱいの若葉がくれに。〔季語〕若葉
蚊屋を出て奈良を立ゆく若ばかな
蚊帳を出て、奈良を出立する。辺り一面若葉の爽快さよ。〔季語〕若ば
絶頂(ぜっちょう)の城たのもしき若葉かな
山頂の城がたのもしくそびえ立っている。その下の全山を、輝かしい若葉が覆っている。〔季語〕若葉
行々(ゆきゆき)てここに行々(ゆきゆく)夏野かな
炎天下の夏野を旅人がずんずん歩いていく。旅はまだまだ続く。〔季語〕夏野
愁(うれ)ひつつ岡にのぼれば花いばら
もの悲しい思いに心を閉ざされ丘の上に登って来ると、そこには郷愁を感じさせる野いばらが花を咲かせ、香りを漂わせている。〔季語〕花いばら
烏(からす)稀(まれ)に水また通し蝉の声
烏の声も稀で、水音もまた遠い。辺りは蝉の声ばかりである。。〔季語〕蝉
目にうれし恋君(こいぎみ)の扇(おうぎ)真白(ましろ)なる
大勢が集まっている場所に、ひそかに思いを寄せる男性がいる。その人は、真っ白な扇を手にしてゆったりとあおいでいる。(女性の心情を詠んだ句)〔季語〕扇
鮒(ふな)ずしや彦根(ひこね)の城に雲かかる
琵琶湖畔を過ぎ、茶店で鮒ずしを食べていて、ふと見上げると、遠い彦根城に雲がかかっている。〔季語〕鮒ずし
夕立や草葉をつかむ群雀(むらすずめ)
突然の夕立に、群れていた雀の中で、飛び立ちかねて必死に草葉をつかんでいるのがいる。〔季語〕夕立
若竹や橋本の遊女ありやなし
若竹が茂る橋本(京都府八幡市)の遊女は、いまも無事に暮らしているだろうか。(「ありやなし」は、『伊勢物語』で業平が隅田川で詠んだ「名にし負はばいざこと問はん都鳥わが思ふ人はありやなしやと」を踏まえている。)〔季語〕若竹
河童(かわたろ)の恋する宿や夏の月
いかにも河童が棲んでいそうな水辺を、夏の月があかるく照らしている。今夜あたりは恋をしにやって来るかもしれない。(「かわたろ」は河童をいう京都地方の方言。)〔季語〕夏の月
堂守(どうもり)の小草ながめつ夏の月
お堂の番人が小草をぼんやり眺めている。空には夏の月が照っている。〔季語〕夏の月
ほととぎす平安城(へいあんじょう)を筋違(すじかい)に
ほととぎすが鋭い声で鳴きながら、碁盤の目のような平安京を、斜め一直線に飛んでいった。〔季語〕ほととぎす
【PR】
※順不同。なお、ふりがなは現代仮名遣いによっています。
 |
古典に親しむ
万葉集・竹取物語・枕草子などの原文と現代語訳。 |
バナースペース
【PR】
与謝蕪村について
20歳ごろ江戸に出て夜半亭(早野)巴人の門人となるが、巴人没後、結城の砂岡雁宕ら巴人門下の縁故を頼り、約10年にわたり常総地方を歴遊する。宝暦1年(1751年)、36歳のとき上京、その後丹後や讃岐に数年ずつ客遊するが、京都を定住の地と定めてこの地で没した。この間、明和7年(1770年)、55歳のときには巴人の後継者に押されて夜半亭2世を継いだが、画業においても、53歳のときには『平安人物志』の画家の部に登録されており、画俳いずれにおいても当時一流の存在であった。
池大雅と蕪村について,田能村竹田が『山中人饒舌』の中で「一代、覇を作すの好敵手)と述べている通り、早くから文人画の大家として大雅と並び称せられていた。俳諧はいわば余技であり、俳壇において一門の拡大を図ろうとする野心はなく、趣味や教養を同じくする者同士の遊びに終始した。死後は松尾芭蕉碑のある金福寺に葬るように遺言したほど芭蕉を慕ったが、生き方にならおうとはしなかった。
芝居好きで、役者や作者とも個人的な付き合いがあり、自宅でこっそりと役者の真似をして楽しんでいたという逸話もある。
小糸という芸妓と深い関係があったらしく、門人の樋口道立 から意見され、「よしなき風流、老の面目をうしなひ申候」とみずから記している。彼が故郷を出たのは何か特別な事情があったらしく、郷愁の思いを吐露しながらも京都移住後、故郷に帰った形跡はない。

(与謝蕪村)
与謝蕪村の略年譜
摂津国東成郡毛馬村に生まれる。早くに両親を亡くす
徳川吉宗が将軍となる
1717年
このころ江戸に出る
1722年
このころから絵を学ぶ
1737年
早野巴人(夜半亭宋阿)に師事して俳諧を学ぶ
このときは「宰鳥」と号す
1732年
享保の大飢饉
1740年
冬、筑波山麓あたりに滞在
1742年
師の巴人が死去
下総国の砂岡雁宕に師事
以後、松尾芭蕉に憧れて奥羽に行脚
1744年
このころ「蕪村」を号す
1745年
江戸大火
徳川家重が将軍になる
1746年
江戸へ行き、芝の増上寺裏門あたりに住む
1751年
京に上る
京都の寺院に保管されている古典絵画から絵を学び、絵画の制作に励む
1754年
母の故郷、丹後与謝に移る
絵画の制作に没頭
1757年
京に戻る
このころ「与謝」を名乗る
1761年
45歳ごろ結婚
一人娘「くの」をもうける
1766年
このころから妻子を京に残し讃岐に行き、多くの絵画作品を手掛ける
1767年
田沼意次が側用人になる
1770年
早野巴人の俳諧一派「夜半亭」を引き継ぐ
1771年
池大雅との合作「十便十宜図」成る
1772年
田沼意次が老中になる
1776年
娘くのが結婚
1781年
芭蕉庵を再興
1782年
天明の大飢饉
1783年
心筋梗塞で死去(享年68歳)


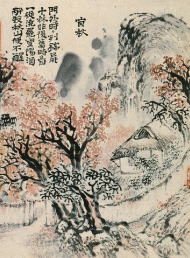
画家としての与謝蕪村
蕪村の画名が大いに上がったのは、宝暦元年(1751年)に京都に移住してからの約10年間とされる。蕪村自身は、俳諧はいわば余技であって、俳壇において一門の拡大を図ろうとする野心などはなく、もっぱら趣味や教養を同じくする者同士の高雅な遊びに終始したという。
蕪村とほぼ同時代に活躍した文人画家に、蕪村と並び称される池大雅がおり、共同して「十便十宜図」とよばれる画帖を制作している。蕪村と池大雅との比較では、技術的には大雅が上回るものの、蕪村の画には大雅にない風雅があるとされる。
深く静かな趣をたたえる自然の情景、のびのびとして洒脱な俳画、苦みのある人物画などは、いずれも晩年に到達した画境で、とりわけ自然の情景を描いた作品が絶賛される。その一方で、多くの作品に感じられる、線描やかたちのある種の「ぎこちなさ」も指摘され、それがかえって親しみやすさ、かわいらしさを生み出しているといえる。
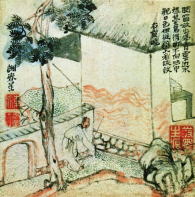
【PR】
