一茶の俳句集

春の句
元日や我のみならぬ巣なし鳥
元日だというのに、多くの人が焼け出され、宿なしになったのは自分だけではないのだ。(文化6年(1809年)正月元日の夕刻に、日本橋佐内町から出火、折からの強風に延焼し、多くの市民が焼け出された。その惨事を目前にして詠んだ句。)〔季語〕元日
春めくややぶありて雪ありて雪
道を行くと藪があり、その根元には雪がまだ深く残っている。進んで行くとまた藪があり、また雪が続く。けれども、何となく春めいて、春はもう近いと感じられる。〔季語〕春めく
蓬莱(ほうらい)に南無南無といふ童かな
お正月飾りの蓬莱に向かって、子供が手を合わせ、南無南無とお唱えをしていることだよ。〔季語〕蓬莱
めでたさも中位(ちゅうくらい)なりおらが春
めでたい新年を迎えた。自分にとっては上々吉のめでたさとはいえないが、まずまず中くらいといったところだろう。(このころの一茶は生涯でも幸せな時期にあり、妻は元気に働き、長女のさとはかわいい盛りだった。)〔季語〕春
つくばねの下(おり)る際(きわ)なり三ケ(みか)の月
舞い上がった羽根が空中で一瞬静止し、そしてゆらゆらと下り始める。その向こうに淡く三日月がかかっているのが見える。〔季語〕つくばね
正月の子供になりて見たきかな
お正月になるとお年玉をもらい、凧揚げや駒回しをする、そんな子供のようになってみたい。〔季語〕正月
門々(かどかど)の下駄の泥より春立ちぬ
新年の挨拶にやってくる人たちの下駄の泥から春がやって来たことだ。〔季語〕春立つ
目出度(めでたし)といふも二人の雑煮(ぞうに)かな
めでたいと言っても、夫婦二人きりで雑煮を食べていることであるよ。〔季語〕雑煮
這(は)へ笑(わら)へ二つになるぞけさからは
這って、そして笑っておくれ。この子は今日から二歳になったのだから。(娘のさとが数えで二歳を迎えた時の喜びの句。ただし、さとは半年後に痘瘡によって死んでしまう。)〔季語〕今朝の春
紫の袖(そで)にちりけり春の雪
思いがけず降り始めた春の淡雪が、紫色の袖に散りかかってくる。(前書に「緑兮〈りょくけい〉、忘らるる身とは思はずちかひてし人の命のおしくもあるかな」とあり、『詩経』の『緑衣』の主題「我、古人〈女性〉ヲ思フ」を踏まえ、生のあはれを詠んだ句。紫衣に散りかかる雪を生のはかなさに譬えている。)〔季語〕春の雪
雪解けて嬉しさうなり星の顔
雪解けを喜び、星の顔が嬉しそうだ。〔季語〕雪解け
もう一度せめて目を明け雑煮膳(ぞうにぜん)
せめてもう一度だけ目をあけて見ておくれ、食い初めの雑煮膳なのだよ。(一茶は晩婚ながら五人の子をもうけたが、そのうち四人を病や事故で亡くしている。この句は、生後百日足らずの二男石太郎が、正月十一日に、妻が背負っているうちに誤って窒息死させてしまった時のもの。亡骸を前に雑煮膳を据えて、亡き子に呼びかけている。)〔季語〕雑煮膳
雪とけて村いっぱいの子どもかな
雪国の長い冬がようやく終わり、雪が解け出した。家の中にこもっていた子どもたちがいっせいに外へ出て遊んでいて、村じゅうが子どもたちでいっぱいだ。〔季語〕雪とく
雪汁(ゆきじる)のかかる地びたに和尚顔(おしょうがお)
雪解けの泥がかかる地べたに座らされ、さらし物になっている和尚の顔であるよ。(女犯の罪を犯して日本橋にさらし者になった鎌倉円覚寺の僧を見て詠んだ句。前書で一茶は、女に迷うことは雲に住む仙人すら踏みとどみ難いものの、高僧のあるまじき行為として苦々しく思う、と言っている。)〔季語〕雪汁
梅が香(か)やどなたが来ても欠茶碗(かけぢゃわん)
春が来て我が家にも梅の香りが漂っているが、こんな貧しい暮らしでは、どなたが訪ねて来ても、欠けた茶でしかもてなすことができない。〔季語〕梅が香
春雨や食はれ残りの鴨(かも)が鳴く
春雨がしとしとと降る中、鴨の鳴き声が聞こえてくる。あの鴨は、冬の間にうまく猟師から逃れた、食われ残りの鴨なのだ。〔季語〕春雨
菜の煮える湯の湧き口や春の雨
温泉の湧き口に青い菜を突っ込んで煮ている。春雨が静かに降りそそぎ、辺り一面が煙っているようだ。〔季語〕春の雨
浅間根のけぶるそばまで畑かな
浅間山では、煙の出るすぐそばまで耕されて畑になっているよ。〔季語〕畑
子守唄(こもりうた)雀(すずめ)が雪も解けにけり
子守唄が聞こえ、雀が遊んでいた雪も解け出してきたよ。〔季語〕雪解け
土焼(つちやき)の姉様(あねさま)うれし春の雨
土で焼いた女雛(めびな)を求めて嬉しく思い、外ではやわらかな春の雨が降っている。(土人形の女雛を「姉様」と呼ぶのは田舎の風習だったという。)〔季語〕春の雨
悠然(ゆうぜん)として山を見る蛙(かえる)かな
一匹の蛙が悠然と、はるかかなたの山を眺めていることだ。〔季語〕蛙
われと来て遊べや親のない雀
親のない子すずめよ、私も親のない寂しさは、おまえと同じだ。こっちへ来て、さあいっしょに遊ぼうじゃないか。(巣から落ちて、親と離れて鳴いている子雀に呼びかけた句。)〔季語〕雀
雀の子そこのけそこのけお馬が通る
道に遊んでいるすずめの子よ、そこを早くのけよ。お馬が通るからあぶないぞ。〔季語〕すずめの子
やせ蛙(がへる)まけるな一茶これにあり
蛙がけんかをしている。やせた蛙よ、がんばれ負けるな。おれ(一茶)がここについているぞ。(前書「蛙たたかひ見にまかる」。「蛙たたかひ」は、蛙が群れて行う生殖活動のこと。一匹の雌をめぐって雄同士が激しく争い、負けて押しのけられたやせ蛙を見て声援を送っている句。)〔季語〕蛙
鳴く猫に赤ん目をして手まりかな
女の子が鞠(まり)をついている。猫がやって来て、遊んでくれとしきりに鳴いてじゃれつくが、女の子はあかんべえをしてまた鞠つきを続けている。〔季語〕手まり
夕月や鍋(なべ)の中にて鳴く田螺(たにし)
夕月がかかってきた。台所の鍋の中では、タニシがこれから煮られることも知らずに鳴いている。〔季語〕田螺
春風や侍(さむらい)二人犬の供(とも)
春風が吹く市中を、犬を先頭にして、お犬番の侍二人が後についてお供をしているよ。〔季語〕春風
夕燕(ゆうつばめ)我には翌(あす)のあてはなき
夕闇がせまる軒端に、親燕が子の世話のためにせわしく出入りしている。しかし、自分はあてのない日々を過ごしている。〔季語〕夕燕
花さくや目を縫(ぬわ)れたる鳥の鳴く
春の花が咲いているというのに、薄暗い鳥小屋に閉じ込められている鳥が、あわれに鳴いている。〔季語〕花
象潟(きさがた)もけふは恨まず花の春
雨の似合う象潟も、今日は恨みの雨は降らずに晴れ渡っている。花の春であることだから。(芭蕉の句「象潟や雨に西施がねぶの花」を踏まえている。)〔季語〕春の春
一つ舟に馬も乗りけり春の雨
春の雨が降りしきるなか、馬も、人と同じ一つの舟に乗り合わせている。〔季語〕春の雨
長閑(のどか)さや浅間(あさま)のけぶり昼の月
のどかであるよ、遠くに浅間山の煙がたなびき、空には昼の月が出ている。(昼の月は役に立たないため「のどかさ」の象徴。)〔季語〕長閑
春の日や暮(くれ)ても見ゆる東山
のんびりした春の日は、暮れても東山がぼんやり見える。(「東山」は京都の東山。)〔季語〕春の日
三文(さんもん)が霞(かすみ)見にけり遠眼鏡(とおめがね)
三文払って遠眼鏡をのぞいてみたけれど、見えたのは霞ばかりであった(前書に「白昼、湯島の台上に登り」の旨の記述あり。)〔季語〕霞
白魚(しらうお)のどつと生(うま)るるおぼろかな
朧夜(おぼろよ)の川底を見れば、白魚の稚魚がどっとひと固まりになって生まれている。〔季語〕白魚、おぼろ
鶏(にわとり)の人の顔見る日永(ひなが)かな
鶏がおれの顔をじっと見ている、春の日長であるよ。〔季語〕日永
一村(ひとむら)はかたりともせぬ日永(ひなが)かな
村は眠ったようにかたりとも音がしない、春の日長であるよ。〔季語〕春立つ
見かぎりし古郷(こきょう)の山の桜かな
いったんは見限って出てきた故郷ではあるが、今ごろは山桜が咲いていることだろう。(題に「黄鳥〈こうちょう〉」とあり、『詩経』の詩を俳訳した句とされる。)〔季語〕桜
さくらさくらと唄はれし老木(おいき)かな
これが、桜々ともてはやされた有名な桜か。今はすっかり老木になって、花の数も少ない。〔季語〕桜
亡き母や海見る度(たび)に見る度に
大きく自分を包み込んでくれるような豊かな海を見る度に、亡き母を思う。〔季語〕(無季)
又(また)ことし娑婆(しゃば)塞(ふさ)ぎぞよ草の家
また今年も、草の家に住み、世間の邪魔者になって過ごすことだ。(前書「遊民遊民とかしこき人に叱られても、今更せんすべなく」)〔季語〕ことし
斯(こ)う活(い)きて居るも不思議ぞ花の陰
花の陰にたたずむように、今日までつないで生きてきたわが命の、不思議であることよ。〔季語〕花
茹汁(ゆでじる)の川にけぶるや春の月
夕飯のゆでた汁の湯気が川面にけぶっている。見上げれば春の月が出ている。〔季語〕春の月
ゆさゆさと春が行(ゆく)ぞよのべの草
草むらに風が吹き渡り、草々がゆさゆさと波打っている。その風といっしょに春が立ち去ってゆくようだ。〔季語〕春
長き日の壁に書きたる目鼻かな
春の日長に何となく壁を眺めていると、目鼻の落書きが書かれている。〔季語〕長き日
大名を馬からおろす桜かな
大名さえ馬から降りて見るほどに、見事な桜であるよ。〔季語〕桜
春雨に大欠伸(おおあくび)する美人かな
春雨が降っている。おや、素敵な美人がいる。あ、大きな欠伸をしたよ。〔季語〕春雨
亀の甲並べて東風(こち)に吹かれけり
春の長閑な日、亀が並んで、東風に吹かれながら甲羅干しをしている。〔季語〕東風
春風に箸(はし)を掴(つか)んで寝る子かな
春風の心地よさに、箸をつかんだまま寝ている子どもの無邪気さよ。〔季語〕春風
春風や牛に引かれて善光寺
心地よい春風が吹くなか、牛に引かれて善光寺参り。(諺の「牛に引かれて善光寺参り」を生かした句。)〔季語〕春風
陽炎(かげろう)や手に下駄はいて善光寺
陽炎が立ち上る中、手に下駄をはいて善光寺参りをしているよ。(「手に下駄はいて」、すなわち四つん這いになりながらの善光寺参りは、腰の曲がった老人の姿か、あるいは這い這いする赤ん坊の姿か。)〔季語〕陽炎
米まくも罪ぞよ鶏(とり)が蹴合(けあ)ふぞよ
米をまいてやったら、鶏がそれを争ってけんかする。罪なことをしたものだ、これではうっかり米もまけない。〔季語〕(無季)
【PR】
↑ ページの先頭へ
夏の句
五月雨(さみだれ)や烏(からす)あなどる草の家
五月雨が降るなか、烏さえも馬鹿にする粗末な家であることだ。〔季語〕五月雨
入梅晴(つゆばれ)や佐渡の御金(おかね)が通るとて
梅雨があがった空の下、佐渡金山から掘り出された御金が街道をものものしくお通りになる。〔季語〕入梅晴
紫陽花(あじさい)の末一色(すえひといろ)となりにけり
色を変えて咲き続けた紫陽花の花が、最後の一色になってしまったなあ。〔季語〕紫陽花
母馬(ははうま)が番して呑(の)ます清水かな
母馬が見張り番をして子馬に飲ませている、その水の清らかさよ。〔季語〕清水
青梅に手をかけて寝る蛙かな
青梅にちょいと手をかけて寝ている蛙だよ。〔季語〕青梅
大蟾(おおひき)は隠居気どりのうらの藪(やぶ)
おおきなヒキガエルは、隠居を気取っているようだ、裏の藪で。〔季語〕蟾
わんぱくや縛られながらよぶ蛍(ほたる)
わんぱくな子どもが、悪さをして縛られていながらも蛍を呼んでいる。〔季語〕蛍
指(ゆびさし)もならぬ葵(あおい)の咲きにけり
指を指してもならない、葵の花が咲いたことだよ。(「葵」は徳川将軍家の家紋。)〔季語〕葵
蟻(あり)の道(みち)雲の峰よりつづきけん
夏空の下、黒い蟻が延々と列を作っている。この列はいったいどこから来ているのか。ひょっとしてあの雲の峰から続いているのではないだろうか。〔季語〕蟻、雲の峰
ざぶざぶと白壁(しらかべ)洗ふ若葉かな
土蔵のすぐそばにある樹木の若葉が、風が吹くたびに、その白壁をざぶざぶと洗うようになでている。〔季語〕若葉
遠し給へ蚊蠅(かはえ)の如(ごと)き僧一人
蚊や蠅のような僧一人ですから、どうぞ関所を通してください。(西国行脚の途次、箱根の関所にさしかかったときの句。)〔季語〕蚊、蠅
短夜(みじかよ)を継(つぎ)たしてなく蛙かな
夏の短夜は、鳴き足らないのだろう、次の夜も次の夜も続けて鳴く蛙よ。〔季語〕短夜
大空の見事に暮(くる)る暑さかな
大空が見事に暮れていくが、暑さはそのまま変わりない。〔季語〕暑さ
君が世や茂りの下の耶蘇仏(やそぼとけ)
夏木立の茂みの陰に、キリシタンの耶蘇仏があった。こうして無事なのもご時世であることよ。(九州行脚中、隠れキリシタンに縁のあった土地を旅したときの句。このころは禁制も厳しくはなかった。)〔季語〕茂り
五十婿(ごじゅうむこ)天窓(あたま)をかくす扇(おうぎ)かな
五十歳の婿となり、恥ずかしさで扇で白髪頭を隠すことだよ。(一茶が52歳の時、はじめて年若い妻を迎え、結婚の披露に隣近所に酒をふるまいながら、挨拶回りをした時の句。)〔季語〕扇
泣虫(なきむし)と云(いわ)れてもなく袷(あわせ)かな
泣き虫だと言われてもまだ泣いている子どもが、袷に着替えている。〔季語〕袷
更衣(ころもがえ)山より外(ほか)に見る人もなし
更衣したものの、山よりほかに、この姿を見てくれるものはいない。〔季語〕更衣
空豆(そらまめ)の花に追(おは)れて更衣(ころもがえ)
旅の途中で衣更えの季節を迎えた。田園のなかを歩いていると、空豆の小さな白い花の黒点がこちらを見つめている。何だか衣更えをせき立てられているようだ。〔季語〕更衣
夏山や一足(ひとあし)づつに海見ゆる
夏の山を汗まみれになって登り、頂上近くになると、ひと足ごとに明るい海がせり上がって見えてくる。〔季語〕夏山
夏山や一人きげんの女郎花(おみなえし)
夏の山に、一人だけご機嫌に身をくねらせている女郎花よ。〔季語〕夏山
宵越(よいごし)のとうふ明りや蚊のさわぐ
昨夜から台所に置いてある豆腐が、明け方の薄暗がりの中で、ほのかに白く、それに引かれて周りに蚊が群れている。〔季語〕蚊
涼風(すずかぜ)や何喰はせても二人前
赤子に乳を飲ませている妻は、何を食わせても二人前だ。(前書「菊女祝」。三男の金三郎が生まれた。妻の菊は病臥したが、まもなく回復して大いに食欲も出てきた。一茶らしい愛情表現の句。)〔季語〕涼風
はつ袷(あわせ)にくまれ盛(さかり)にはやくなれ
初袷を着せたわが子、早く憎まれ口をたたくような年齢に育ってほしい。(54歳で初子をもうけた喜びと願望の句。しかし、一か月足らずで夭折してしまう。「はつ袷」は、その年に最初に袖を通す着物)〔季語〕はつ袷
人来たら蛙(かえる)となれよ冷(ひや)し瓜(うり)
人が来たら、食べられないように蛙になれよ、冷やし瓜。(縞模様のある甜瓜が、トノサマガエルの背を連想させることから)〔季語〕冷し瓜
昼顔やぽつぽと燃える石ころへ
噴き上げられた溶岩が、じりじりと、ゆっくりとした速度で山を流れ下ってゆく。可憐な昼顔が、何も知らぬげにその傍で花を咲かせている。そして、ぽっぽと燃える溶岩に巻きつこうと、つるを伸ばしている。〔季語〕昼顔
涼風(すずかぜ)の曲がりくねつて来たりけり
裏長屋の奥のわが家には、涼風も曲がりくねって、ようやくたどり着くことだ。(前書「裏店(うらだな)に住居(すまい)して」)〔季語〕涼風
涼まんと出れば下に下にかな
涼もうとして外に出れば、大名行列の「下に、下に」の掛け声がして、夕涼みどころではない。〔季語〕涼む
涼しさや半月うごく溜(たま)り水
小さな水溜まりに半月が映り、やがて通り過ぎていった。ようやく涼しくなってきたよ。〔季語〕涼しさ
あこよ来よ転ぶも上手夕涼
わが子よ、こっちへおいで。転ぶのも上手。いっしょに夕涼みをしよう。〔季語〕夕涼
蚊帳(かや)つりて喰(くひ)に出るなり夕茶漬(ゆうちゃづけ)
宵のうちに蚊帳をつって、散歩がてら、町に茶漬け飯を食いに出ることだ。〔季語〕蚊帳
目出度さはことしの蚊にも喰れけり
目出度さは、今年の蚊にも食われたことだ。まだ若いということ。〔季語〕蚊
笠の蠅(はえ)我より先へかけ入(いり)ぬ
笠にとまっていた蠅が、我が家の前まで来ると、自分より先に門口へ駆け込んだ。(前書「帰庵:旅から帰る」)〔季語〕涼風
行々(ぎょうぎょう)し大河はしんと流れけり
葦の生い茂る水辺で仰仰子(ぎょうぎょうし:ヨシキリ)がやかましく鳴いているが、大河は音もなく静かに流れている。〔季語〕行々子
雲の岑(みね)の下から出たる小舟かな
雲の峰から湧き出たように、小舟があらわれたことだ。(芭蕉の「雲の峰いくつ崩れて月の山」の句をふまえている。)〔季語〕雲の岑
ふるさとや寄るもさはるも茨(ばら)の花
故郷の柏原に帰ってきた。しかし、会う人はことごとくトゲのある茨の花のようなもので、誰ひとり自分を暖かく迎えてはくれない。〔季語〕茨の花
大蛍(おほぼたる)ゆらりゆらりと通りけり
大きな源氏蛍が、暗やみの中を大きな弧を描きながらゆらりゆらりと飛んでゆく。〔季語〕蛍
大の字に寝て涼しさよ寂しさよ
わが家の座敷で大の字に寝そべると、折から涼しい風が吹いてきて、とても気持ちがよい。しかし、故郷では誰ひとり暖かく迎えてくれる人もなく、一人ぼっちとなった自分の寂しさがこみあげてくる。〔季語〕涼しさ
寝せつけし子の洗濯(せんたく)や夏の月
夜になって子どもを寝かしつけた農家の女が、休む間もなく小川で洗濯をしている。夏の夜の月がその流れにきらめいている。〔季語〕夏の月
蚤(のみ)の跡(あと)かぞへながらに添乳(そへぢ)かな
赤ん坊に添い寝をして乳をやっている母親が、わが子の体の蚤に食われた跡を数えて嘆いている。何とも愛情深い姿だ。〔季語〕蚤
蝉(せみ)鳴くや我が家も石になるやうに
蝉が鳴いている。その声を聞いていると、我が家が石のように固まってしまう感じがしてくる。〔季語〕蝉
蚤(のみ)の跡(あと)それもわかきはうつくしき
蚤に食われたあと、それも若い人のは美しい。(老人が食われたあとは汚らしいばかり。)〔季語〕蚤
暑き夜をにらみ合たり鬼瓦
暑い夜に、一晩中にらみ合っているよ、鬼瓦が。(前書「隣二階住」。鬼瓦は、屋根の棟の両端に備え付ける鬼の面のような瓦。)〔季語〕暑き夜
焼け土のほかりほかりや蚤(のみ)さわぐ
火事で焼けたあとの土が、ほかりほかりとまだ熱い。そんな中で、蚤どもが騒ぎまわっている。(前書「土蔵住居して」。柏原で大火が起こり、一茶の家も類焼して焼け残りの土蔵に移り住んだ時の句。)〔季語〕蚤
やれ打つな蝿(はへ)が手をすり足をする
それ、蝿を打ち殺してはいけない。よく見ると、手をすり合わせて命乞いをしているではないか。〔季語〕蝿
武士(さむらい)に蠅(はえ)を追(おわ)する御馬かな
侍に蠅を追わせているお馬であるよ。〔季語〕蠅
いざいなん江戸は涼みもむつかしき
馴染めない江戸暮らしは、縁台に腰かけて夕涼みをするにも周りに気兼ねしなければならない。さっさと生まれ故郷に帰ろう。〔季語〕涼み
投出した足の先なり雲の峰
投げ出した足の先に、雲の峰がそびえている。〔季語〕雲の峰
里の女や麦にやつれしうしろ帯
身請けされた遊女が、今では麦刈りに疲れて後ろ帯になっている。(「里の女」は、遊郭の遊女や芸妓のこと。「うしろ帯」は背中側で結んだ帯で、堅気の女性の帯の結び方。)〔季語〕麦
麦秋(むぎあき)や子を負(おい)ながらいわし売り
実った麦畑の中の道を、旅姿をした鰯(鰯)売りの女が歩いている。見れば、思い荷をたずさえた上に、背には赤子を背負っている。〔季語〕麦秋
【PR】
※順不同。なお、ふりがなは現代仮名遣いによっています。
 |
古典に親しむ
万葉集・竹取物語・枕草子などの原文と現代語訳。 |
バナースペース
【PR】
小林一茶について
29歳の時、故郷に帰り、翌年より36歳の年まで俳諧の修行のため近畿・四国・九州を歴遊する。39歳のとき再び帰省。病気の父を看病したが1ヶ月ほど後に死去、以後遺産相続の件で継母と12年間争う。一茶は再び江戸に戻り俳諧の宗匠を務めつつ遺産相続権を主張し続けた。50歳で再度故郷に帰り、その2年後28歳の妻きくを娶り、3男1女をもうけるが何れも幼くして亡くなり、特に一番上の子供は生後数週間で亡くなった。きくも痛風がもとで37歳の生涯を閉じた。
その後、2番目の妻(田中雪)を迎えるも老齢の夫に嫌気がさしたのか半年で離婚。3番目の妻やをとの間に1女・やたをもうける(やたは一茶の死後に産まれ、父親の顔を見ることなく成長し、一茶の血脈を後世に伝えた。1873年に46歳で没)。
文政10年(1827年)閏6月1日、柏原宿を襲う大火に遭い、母屋を失い、焼け残った土蔵で生活をするようになった。そして翌年1月5日その土蔵の中で、中風の発作により65歳の生涯を閉じた。
一茶が生涯に詠んだ句は約2万句とされ、芭蕉の約1000句、蕪村の約2800句と比べて圧倒的に多い。日々の生活の中で触れる情念や感慨を、その都度メモにとり、日記をつけるように、生涯にわたって句を詠み続けた俳人である。
《一茶の句集》
『一茶自筆句集』
・・・寛政5年~文政8年
『我春集』
・・・文化8年
『株番』
・・・文化9~10年
『志多良』
・・・文化10年
『浅黄空』
・・・文化期後半~文政
『おらが春』
・・・文政2年
『まん六の春』
・・・文政5年
また、一茶の没後に、門人らの手によって『一茶発句集』『俳諧一茶発句集』『一茶発句集続編』などが出版されている。
小林一茶の略年譜
信濃国の農家の長男として生まれる。本名は弥太郎
1765年
母親が死去
1770年
継母を迎える
後に腹違いの弟・仙六が生まれる
1776年
継母との仲がこじれたことがきっかけで、奉公のため江戸に出る。その後10年間の消息不明
1779年
田沼父子が権力をふるう
1783年
天明の大飢饉
1787年
松平定信が老中になる
葛飾派の一員として俳人になり、当時葛飾派の重鎮だった二六庵竹阿・溝口素丸・森田元夢らを師匠とする
1789年
東北地方を巡る
1791年
14年ぶりに柏原へ帰郷
1792年
京阪・四国・九州地方へ
俳諧行脚(約7年間)
1799年
江戸に戻ると師匠の俳号を継ぎ、二六庵一茶を名乗るように。しかし周囲の妬みなどから、2年後に二六庵の名をなくす
1801年
帰郷の際に父親が倒れ、死去。死に際に遺産を弟と二分するよう言い渡されるが。以後、これを巡って13年間におよぶ相続争いに
1808年
遺産の半分を取得
本百姓に登録される
1811年
「我春集」を書く
1814年
相続争いが決着
柏原に住居を定め、24歳年下の菊と結婚する
その後3男1女をもうけるがいずれも早世
1819年
「おらが春」を書く
1821年
伊能忠敬による「大日本沿海輿地全図」が完成
1823年
シーボルトが鳴滝塾を開く
1823年
妻の菊が病死
1824年
2度目の結婚、すぐ離婚
1825年
幕府が外国船打払い令を出す
1826年
3度目の結婚
1827年
火事で母屋を失い、かろうじて残った土蔵で暮らす
1828年
中風の発作で死去(65歳)
死後に女児(やた)が生まれる

(小林一茶)
俳句の歴史
連歌とは、和歌の上下2句を二人で詠み分けるもので、即興と機智とを重んじる遊戯的なものだった。それが鎌倉時代になると、5・7・5に7・7をつけ、さらにそれに5・7・5をつけるという具合に、50も100も長く続ける連歌が生まれてきた。これを従来の「短連歌」に対し、「長連歌(または鎖連歌)」という。この長連歌は、中世の和歌衰退の気運にかわって、「有心(うしん)連歌」と称して、高度の芸術性と完成度を求めるようになった。
その一方、連歌本来の諧謔性を求める「無心連歌」は、おもに僧侶・武家・下級貴族の間で行われ、これも同じく長連歌化しつつあった。有心連歌を行った人々を「柿の本衆」というのに対し、無心連歌の人々は「栗の本衆」と称した。
有心連歌は室町初期に最も盛んになったが、その後は衰退、中世末期になると、次第に無心連歌が民衆の間に広まった。
安土桃山期になると、山崎宗鑑、荒木田守武の二人が出て、無心連歌をさらに滑稽化して、俳諧の連歌というものを創り出し、既成の和歌的情緒を破壊し、大胆な諧謔精神を発揮した。これが俳諧の文学の本格的な開始となった。
貞門がやや格式重視だったのに対し、その枠を破り、まったく自由奔放な俳諧を唱えたのが西山宗因であり、その門流を「談林(だんりん)」と呼ぶ。この派は町人の旺盛な生活力を基盤としたが、次第に無秩序に流れ、品位を失うに至った。
江戸時代になると、松永貞徳が出て、俳諧を用語上から連歌と区別し、俳諧とは俳言(はいごん)をもってよむ連歌なりと定義、その法則を定めた。彼の門流を「貞門(ていもん)」と呼ぶ。
これらの反省は、池西言水、小西来山、上島鬼貫らによって唱えられていたが、松尾芭蕉の出現をみて、俗語を用い俗生活を題材としながら古典的伝統の品位を保持する排風(蕉風)が確立した。
芭蕉の時代には、俳句は連句ともいわれ、やはりいくつかの続く形でよまれるのが原則だった。特に36句でよむ歌仙形式が行われたが、一方、発句(連句の一番初めの句)の独立性も次第に確立してきた。
芭蕉の死後、その弟子たちの活躍はあったものの、俳諧は次第に芸術的香気を失っていったが、天明期に与謝蕪村が現れ、空気を刷新した。
天明以後は、小林一茶など人生派の俳人を除けば、俳諧は再び衰退し、いわゆる月並調の平凡な詠風に堕し、その復興は明治の正岡子規に待たねばならなかった。
子規は、蕪村を尊重し、明治の俳壇を革新したが、その際、連句を遊戯とみなし、文学としては発句のみがその独自性を持ちうると主張し、「俳句」と称した。
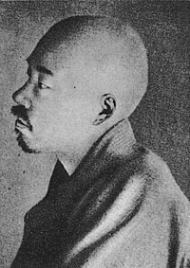
(正岡子規)
【PR】
