
持統天皇の御製歌
巻第1-28
| 春過ぎて夏(なつ)来(きた)るらし白妙(しろたへ)の衣(ころも)乾したり天の香具山(かぐやま) |
【意味】
春が過ぎて、もう夏がやって来たらしい。聖なる香具山の辺りには真っ白な衣がいっぱい乾してある。
【説明】
第41代持統天皇(645~702年)は、天智天皇の皇女で、姉の大田皇女とともに大海人皇子の妃となり、草壁皇子を生みました。壬申の乱に際しては、妃の中でただ一人、挙兵した夫に従っています。戦いに勝利した夫は天武天皇となり、皇后として常に天皇を助け、そばにいて政事について助言したといわれます。天皇の没後は、しばらく皇后のまま政治を執り、一人息子の草壁皇子を天皇に立てようとしました。しかし、皇子が間もなく死去したため自ら即位、夫の偉業を受け継ぎ、精力的に国家建設に取り組むこととなります。
持統天皇は、694年に都を藤原京に遷します。新都を囲む大和三山のうちで、最も神聖とされたのが香具山です。標高わずか152mの低い山ですが、「天の」は、香具山が天から降ったという古伝説に基づいて、香具山に冠される語です。もしこの歌が藤原の宮の宮殿で詠まれたのだとしたら、宮の東門は香具山に向かっていましたから、ごく近くに見えたことでしょう。香具山に真っ白な衣が乾かされている。その光景に、天皇は夏の季節の到来を直感したのでしょう。あまり好まれることのない夏が力強くさわやかに表現されており、天皇の気丈さがうかがえる歌であり、また、王者らしい、大らかでゆったりした詠みぶりのうちにも、「衣」に触発されるところに女性らしさが窺えます。
ただ、藤原京造営については、巻第1-50に「藤原京の役民の作れる歌」、51に「明日香京より藤原京に遷居りし時に、志貴皇子の作りませる歌」、52に「藤原宮の御井の歌」とありますので、作歌の時期順に配列されているとしたら、この歌は藤原京以前に詠まれた歌となります。藤原京遷都の計画のもと造営工事が進展しているなか、その地を象徴する天の香具山を讃える歌を詠んだのかもしれません。
また、この歌は、『万葉集』の中ではじめて季節感を詠んだものとされますが、それにとどまらず、大化改新以来うち続いた蘇我一族との抗争、壬申の乱、大津皇子事件などの苦悩と暗黒の時を過ぎ、ようやく得られた一種の安堵感のような深い感慨と、さらにこれから将来に向けての強い祈りが込められているようにも感じられる歌です。あるいは、こちらの方が本当の意味なのかもしれません。
香具山の辺りに干されている白い衣は、常用の衣ではなく、毎年、何らかのお祭りで使われた衣(斎衣:おみごろも)だろうといわれます。それらを神聖な香具山に干すことも、年中行事の一つだったのでしょう。香具山には甘橿明神(あまかしみょうじん)という神がいて、衣を濡らして人の言葉のうそかまことかを糾(ただ)したという伝説もあるそうです。
この歌は『新古今集』や『百人一首』などにも採られ、古来名歌とされてきましたが、そちらでは「春過ぎて夏来にけらし白たへの衣ほすてふ天の香具山」という形に改められています。「来にけらし」では、夏の到来を目前でとらえたのではなく、「もう夏が来てしまっているらしい」の意となり、「衣ほすてふ」では想像や伝聞の句となるため、全体として穏やかな感じになっています(「てふ」は「といふ」のつづまった形)。なぜこのように変化したかについては、万葉仮名で「春過而 夏来良之 白妙能 衣乾有 天之香来山」と書かれているのを、藤原定家が自分の思うままに読んだとする説や、実際に香具山に白い衣を干すのを見たことがないため伝聞の形にしたなどの説があります。いずれにしても、定家の時代には断言調や直言風の歌は嫌われ、しらべを重視し、婉曲で優美な口ぶりが好まれたので、自分たちの嗜好に合うよう強引にこのような改変が行われたのでしょう。万葉の訓みに新説をたてたというものでは決してありません。
藤原京
藤原京は飛鳥京の西北部、現在の橿原市の位置にあった日本初の都城です。 南北中央に朱雀大路を配し、南北の大路と東西の大路を碁盤の目のように組み合わせて左右対称とする「条坊制」を、日本で初めて採用した唐風都城です。持統天皇8年(694年)から和銅3年(710年)まで、持統・文武・元明天皇の3代にわたり16年間続きました。
藤原宮は、約900m四方の区画に、内裏、大極殿、朝堂院が南北に並び、その両側に官衛がありました。現在、大極殿跡に「大宮土壇」と呼ばれる基壇が残っています。宮殿造営のための用材は、近江国の田上山で伐り出され、筏に組まれて、宇治川と木津川の水域を利用して泉津まで運ばれ、陸路で奈良山を越えて、再び佐保川の水運を利用して、藤原宮の建設現場まで運ばれました。
藤原宮の労役に従事した民の作った歌
巻第1-50
| やすみしし 我(わ)が大君(おほきみ) 高(たか)照らす 日の皇子(みこ) あらたへの 藤原が上(うへ)に 食(を)す国を 見(め)したまはむと みあらかは 高知らさむと 神(かむ)ながら 思ほすなへに 天地(あめつち)も 依りてあれこそ 石走(いはばし)る 近江(あふみ)の国の 衣手(ころもで)の 田上山(たなかみやま)の 真木(まき)さく 檜(ひ)のつまでを もののふの 八十宇治川(やそうぢがは)に 玉藻なす 浮かべ流せれ そを取ると 騒(さわ)く御民(みたみ)も 家忘れ 身もたな知らず 鴨(かも)じもの 水に浮き居(ゐ)て 我(わ)が作る 日の御門(みかど)に 知らぬ国 よし巨勢道(こせぢ)より 我(わ)が国は 常世(とこよ)にならむ 図(あや)負(お)へる くすしき亀も 新代(あらたよ)と 泉の川に 持ち越せる 真木のつまでを 百(もも)足らず 筏(いかだ)に作り のぼすらむ いそはく見れば 神(かむ)からにあらし |
【意味】
天下を支配される我が大君、高く天上を照らしたまう日の御子が、ここ藤原の地で、国じゅうをお治めになろうと、宮殿を高々とお造りになろうと、神としてのお考えのままに、天地も神も心服しているからこそ、近江の国の田上山の檜を、宇治川に美しい藻のように浮かべて流し、それを引き取る作業に騒々しく働く民たちは、家のことを忘れ、我が身のことも忘れ、鴨のように水に浮かびながら、我らが造る日の御子の宮殿に、平服しない国々も寄しこせという、その巨勢の方から、我が国は常世になるだろうというめでたい模様のある神秘的な亀も、新しい時代を祝福して出ずるという泉川に持ち運んだ檜を筏に組み、川を遡らせているのだろう。人々が争うように精を出しているのを見ると、これはまさに大君の神慮のままであるらしい。
【説明】
持統7年(693年)8月、持統天皇が、造営中の藤原の宮地視察のために行幸したころの詠とみられ、題詞には「役民(官命によって労役に徴発された民)の作る歌」とあります。しかし、歌の内容は、役民が奉仕しているさまを第三者として見たものであり、実際の作者は官人だろうとされます。
「やすみしし」「高照らす」「あらたへの」は、それぞれ「我が大君」「日」「藤原」の枕詞。「日の御子」は、ここは持統天皇。「みあらか」は「御在ら処」で、貴人の居所、宮殿。「石走る」「衣手の」は、それぞれ「近江」「田上」の枕詞。「田上山」は、大津市南部、大戸川上流の山。「真木さく」「もののふの」「玉藻なす」は、それぞれ「檜」「八十宇治川」「浮かべ」の枕詞。宇治川は支流が多いので八十宇治といいます。「巨勢」は、奈良県御所市古瀬。「くすしき」は、神秘的な。「泉の川」は、木津川。「百足らず」は「筏」の枕詞。「いそはく」は、競って励むこと。「神からにあらし」は、現人神である大君の御心のままであるらしい。
藤原京の建設は、これまでにない大規模な工事となり、また、大量の資材調達が必要となりました。この歌からは、近江の国の田上山で伐採した木材を筏に組み、琵琶湖から宇治川、巨椋池、木津川という経路で運搬し、さらに陸路で奈良山を越え、藤原宮の建設現場まで届けたという、当時の流通事情も窺えます。巨椋池というのは、当時、宇治川と木津川の流れ込むところにあった広大な池で、ここに流してきた木材を、今度は木津川の逆流にそって上げ、その上流から陸路を経て佐保川に流して下し、佐保川と泊瀬川の合流点から泊瀬川を逆流させて藤原へ運んだとされます。その距離の合計は約100kmにも及んでいます。
新しい都城の造営は天武天皇の遺志であり、持統天皇の悲願でもありました。藤原を宮城の地に選んだのは持統天皇4年(690年)10月とされ、太政大臣の高市皇子が当地を視察しています。以後4年2か月の歳月を費やして新都は完成しましたが、その過程で、持統天皇みずからもしばしば藤原へ行幸しています。藤原の宮はわが国最初の都城であり、次の奈良京の原型をなすものでした。
藤原宮の御井の歌
巻第1-52~53
| 52 やすみしし わご大君 高照らす 日の皇子(みこ) 荒栲(あらたへ)の 藤井が原に 大御門(おほみかど) 始めたまひて 埴安(はにやす)の 堤(つつみ)の上に あり立たし 見したまへば 大和の 青香具山(あをかぐやま)は 日の経(たて)の 大き御門(みかど)に 春山と 茂(し)みさび立てり 畝傍(うねび)の この瑞山(みづやま)は 日の緯(よこ)の 大き御門に 瑞山と 山さびいます 耳成(みみなし)の 青菅山(あをすがやま)は 背面(そとも)の 大き御門に よろしなへ 神(かむ)さび立てり 名ぐはしき 吉野の山は 影面(かげとも)の 大き御門ゆ 雲居(くもゐ)にそ 遠くありける 高(たか)知るや 天(あめ)の御陰(みかげ) 天(あめ)知るや 日の御陰の 水こそば 常にあらめ 御井(みゐ)の清水(ましみづ) 53 藤原の大宮仕(おほみやつか)へ生(あ)れつくや娘子(をとめ)がともは羨(とも)しきろかも |
【意味】
〈52〉我が大君、日の皇子がここ藤井が原の地に、大宮をお造りになり、埴安の池の堤の上にお立ちになってご覧になると、ここ大和の国の青々とした香具山は、東の御門の向かいに、春山らしく木々を茂らせている。畝傍の瑞々しい山は、西の御門の向かいに、いかにも瑞山らしく鎮まり立っている。青菅に包まれた耳成山は、北の御門の向かいに、美しく神々しく立っている。名も妙なるの吉野の山は、南の御門から雲の彼方遠くに連なっている。立派な山々に囲まれたこの地で、高々と天の影になり、太陽の影になる大宮。その宮の水こそは、永久に湧き出るであろう。御井の真清水よ。
〈53〉藤原の大宮に仕える者として、この世に生まれついた乙女たちの、何と羨ましいことか。
【説明】
題詞に「藤原の宮の御井(みい)の歌」とある、作者未詳の藤原宮に対する賀歌です。藤原宮へ遷都されるまでは、天皇一代ごとに宮が造られるのが習いでしたが、藤原宮からは恒常的に宮が置かれるようになります。以来、持統・文武・元明の三代にわたって使用されることとなりました。「御井」は、土地の命の根源となる聖泉のことで、その井の存在が藤原宮造営の理由の一つであったようです。湧き出る御井の清水に寄せて、宮の永久不変を賀しています。「井」は、いわゆる掘り抜き井戸のほか、川や池に設けられた水場や水が湧き出る場所なども、すべて「井」と呼ばれました。生活用水だけでなく宗教的行事にも用いられ、古代、水がほとばしり出る場や水の激(たぎ)ち流れる場は、聖なる場所とされ、その水は聖水とされました。
52の「やすみしし」は、安らかに天下を支配される意で、「わが大君」の枕詞。「わご大君」は「わが大君」の転。「高照らす」は、高く照らしているで、「日の皇子」の修飾。「荒栲の」の「栲」は、藤や葛などの繊維の意で「藤井」の枕詞。「藤井が原」は「藤原」と同じで、藤原は藤井が原とも呼んでいたことが分かります。「大御門」は、ここは宮殿の意。「埴安」は、香具山の近くにあった池。「青香具山」の「青」は、繁茂のようすを賛美する語。「日の経」「日の緯」「背面」「影面」は、それぞれ、東、西、北、南の意。「茂みさび」「山さび」「神さび」の「さび」は、それにふさわしい状態である意の接尾語。「よろしなへ」は、いかにも具合よろしく。「雲居」は、雲のかかっている所。「高知るや」は、高々と領知する。「天の御陰・日の御陰」は、上代からの成語で、日光を遮る影、すなわち宮殿。「天知るや」は、天界を領知する。「清水」を「ましみづ」訓んでいるのは、調べのためとされますが、「しみづ」に「ま」を添える例は古文献にはないといいます。
53の「大宮仕へ」は、大宮に仕える者として。「生れつくや」は、生まれついた。「娘子がとも」の「とも」は、伴、仲間で、複数を示します。「羨しきろかも」は、羨ましい限りだ。「ろ」は、音調のための接尾語。「かも」は、詠嘆。大宮の御井に仕える娘子たちへの賛美を羨望のかたちによって述べることで、大宮の無窮をたたえています。
歌の内容から、藤原宮造営の当初、持統天皇は、しばしば飛鳥浄見原宮から藤原の地へ行幸になっていたことが知られ、作者は天皇に側近しうる立場にあったものの、采女を羨んでいるところから、身分の低い官人であったことが察せられます。また、藤原宮は、香具山・畝傍山・耳成山の大和三山の中心に位置しており、この歌ではそれぞれの山についてうたわれています。まず、香具山には「大和の」という語が冠されており、他では「天の」という修飾句も冠されている山です。香具山は天から降ってきたという伝説があり、また『古事記』や『日本書紀』には神話の舞台のように書かれています。こうしたことから、持統期には、香具山が大和を代表する山であるという考え方があったようです。歌の中で「青香具山」といっているのは、青が陰陽五行説の東にあたる色であることを意味します。東をいう「日の経」の門の向かいに、東の季節である「春山」として立っているといっています。
畝傍山のことは「瑞山」といっています。「瑞」には神聖という意味があり、西をいう「日の緯」の門の向かいに神聖な山として立っていると表現されています。また、その姿を「山さびいます」、すなわち、山らしい山であると讃えています。耳成山は、青菅(あおすげ)が多く生えていたのか、「青菅山」とよび、また、北にあるのを「背面」にあるといっています。なぜ北が背面かというと、天子南面の思想、つまり天皇は南を向いて拝礼を受けるものとされていたためです。その山姿は、いかにも神々しいと表現されています。さらに、南をいう「影面」の門から雲の彼方にある吉野の山もうたわれています。吉野は、持統天皇にとっては亡き夫・天武天皇と苦難を共にした想い出の地でもあります。壬申の乱の前に近江朝廷を逃れた二人は吉野に潜み、挙兵に備えたのでした。その後の、持統天皇の度重なる吉野行幸には、天武皇統が持統へ受け継がれたことを確認する目的もあったのでしょう。
【PR】
『万葉集』の時代背景
万葉集の時代である上代の歴史は、一面では宮都の発展の歴史でもありました。大和盆地の東南の飛鳥(あすか)では、6世紀末から約100年間、歴代の皇居が営まれました。持統天皇の時に北上して藤原京が営まれ、元明天皇の時に平城京に遷ります。宮都の規模は拡大され、「百官の府」となり、多くの人々が集住する都市となりました。
一方、地方政治の拠点としての国府の整備も行われ、藤原京や平城京から出土した木簡からは、地方に課された租税の内容が知られます。また、「遠(とお)の朝廷(みかど)」と呼ばれた大宰府は、北の多賀城とともに辺境の固めとなりましたが、大陸文化の門戸ともなりました。
この時期は積極的に大陸文化が吸収され、とくに仏教の伝来は政治的な変動を引き起こしつつも受容され、天平の東大寺・国分寺の造営に至ります。その間、多大の危険を冒して渡航した遣隋使・遣唐使たちは、はるか西域の文化を日本にもたらしました。
ただし、万葉集と仏教との関係では、万葉びとたちは不思議なほど仏教信仰に関する歌を詠んでいません。仏教伝来とその信仰は、飛鳥・白鳳時代の最大の出来事だったはずですが、まったくといってよいほど無視されています。当時の人たちにとって、仏教は異端であり、彼らの精神生活の支柱にあったのはあくまで古神道的な信仰、すなわち森羅万象に存する八百万の神々をおいて他にはなかったのでしょう。
【PR】
 |
古典に親しむ
万葉集・竹取物語・枕草子などの原文と現代語訳。 |
バナースペース
【PR】
大和三山
香具山(かぐやま)
標高152m
畝傍山(うねびやま)
標高199m
耳成山(みみなしやま)
標高140m
三山のうちもっとも神聖視されているのが香具山で、「天の」を冠するのは、天から降り来たという伝説によっていますが、その山の位置や山容が古代神事にふさわしいゆえに、あがめられたとも考えられています。この大和三山に囲まれるように、日本で初めて本格的な都となった藤原京の藤原宮跡があります。

(耳成山)
万葉時代の天皇
第30代 敏達天皇
第31代 用明天皇
第32代 崇俊天皇
第33代 推古天皇
第34代 舒明天皇
第35代 皇極天皇
第36代 孝徳天皇
第37代 斉明天皇
第38代 天智天皇
第39代 弘文天皇
第40代 天武天皇
第41代 持統天皇
第42代 文武天皇
第43代 元明天皇
第44代 元正天皇
第45代 聖武天皇
第46代 孝謙天皇
第47代 淳仁天皇
第48代 称徳天皇
第49代 光仁天皇
第50代 桓武天皇
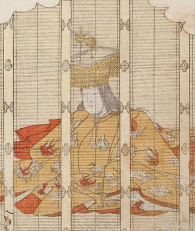
(持統天皇)
律令制度の歴史
668年、天智天皇の時代に中臣鎌足が編纂したとされるが、体系的な法典ではなく、国政改革を進めていく個別法令群の総称と考えられている。重要なのは、670年に、日本史上最初の戸籍とされる庚午年籍が作成されたことで、氏姓の基準が定められ、その後の律令制の基礎ともなった。
飛鳥浄御原令
681年に天武天皇が律令制定を命ずる詔を発し、持統天皇の時代の689年に「令」の部分が完成・施行された。現存していないが、後の大宝律令に受け継がれる基本的な内容を含む、日本で初めての体系的な法典であったとされている。
大宝律令
藤原不比等や刑部親王らによって701年に制定・施行された。唐の律令から強い影響を受けた日本初の「律」と「令」が揃った本格的な法典であり、奈良時代以降の中央集権国家体制を構築する上での基本的な内容が盛り込まれた。
養老律令
大宝律令と同じく藤原不比等らにより718年から編纂が開始され、不比等の死後も編纂が続き、757年に完成・施行された。なお、律令制は平安時代の中期になるとほとんど形骸化したが、廃止法令は特に出されず、形式的には明治維新期まで存続した。

(藤原不比等)
関連ページ
【PR】
