
丹生女王が大伴旅人に贈った歌
巻第4-553~554
| 553 天雲(あまくも)のそくへの極(きは)み遠けども心し行けば恋ふるものかも 554 古人(ふるひと)の飲(たま)へしめたる吉備(きび)の酒(さけ)病(や)めばすべなし貫簀(ぬきす)賜(たば)らむ |
【意味】
〈553〉あなたのおられる筑紫は、天雲の果ての遥か遠い地ですが、心はどんなに遠くても通って行くので、このようにも恋しいのですね。
〈554〉老人が贈ってくださった吉備のお酒も、悪酔いしてしまったらどうしようもありません。(吐くかもしれないので)貫簀もいただきとう存じます。
【説明】
丹生女王(にふのおほきみ)が大宰帥の大伴旅人に贈った歌。丹生女王は伝未詳ですが、天平11年(739年)に従四位下から従四位上に、天平勝宝2年(750年)に正四位上に昇叙されたことが分かっています。巻第3-420の作者、丹生王と同一人かともいわれます。ここの歌は、旅人から何らかの事情で吉備の地酒を贈られたのに対し、喜びの心をもって詠んでいます。
553の「そくへ」は「退(そ)く方(へ)」、遠く隔たったところの意。「そきへ」という場合もあります。「心し行けば」の「し」は強意の副助詞で、心が通って行けば。「恋ふるものかも」の「かも」は、詠嘆を含んだ疑問。この句の主語を相手の旅人だとして、「遠くあってもこちらの心が通えば、恋しく思ってくださるものでしょうか」のように解するものもあります。
554の「古人」は、老人または昔馴染みの人の意で、ここでは旅人を指しています。「飲へしめたる」の「飲ふ」は、神や貴人から飲食物を頂くこと。「吉備」は、備前・備中・備後の総称、現在の岡山県、広島県東部にあたり、特に備後は古くから酒の産地として有名でした。旅人は、神亀4年(727年)大宰府赴任途上に、丹生女王にこの酒を贈ったようです。「病めば」は、二日酔いのこと。「貫簀」は、洗い桶の上に、水が飛ばないように敷く竹で編んだすのこ。ここでは、酔って吐くときの用意のための物として言っています。「賜らむ」は、いただきとう存じます。なお、「貫簀」を竹の敷物とする説もあり、その場合は、「酔って横になる竹の敷物をください」という意味になります。
丹生女王は、旅人を老人と言ったり、「吐くかもしれない」と突拍子もない冗談を言ったりで、旧知の親しい間柄だったとみられます。ただ、旅人は天平3年に亡くなり、女王は天平11年から『続日本紀』に出ているので、20歳くらいの年齢の差はあったようです。巻第8-1610にも、太宰帥当時の旅人に女王が贈った歌があります。また、巻第5の808・809も、署名はないものの、旅人が贈った歌に女王が答えた歌ではないかとの説があります。
巻第8-1610
| 高円(たかまと)の秋野(あきの)の上(うへ)のなでしこが花 うら若み人のかざししなでしこが花 |
【意味】
高円の秋野に咲いたナデシコの花。その初々しさにあなたが挿頭になさった、そのナデシコの花。
【説明】
丹生女王が、大宰帥の大伴旅人に贈った旋頭歌形式(5・7・7・5・7・7)の歌。「高円」は、奈良市の東南の、春日山の南の一帯。「うら若み」は「うら若し」のミ語法で、初々しいので。「人」は、ここは旅人のこと。「かざしし」は、ここでは愛した意。表面的には風雅な便りとなっていますが、女王が若かりしころに、旅人に愛されたことを懐かしみつつ、ナデシコの花を自分自身に譬えています。古風な旋頭歌にしたのもその心にふさわしい、と窪田空穂は言っています。
挿頭は、髪や冠り物に挿した草木の花や枝のことで、本来は草木の生命力にあやかったものでした。挿頭にするものとして、『万葉集』には、もみじ、萩、梅、柳、ナデシコなどがあります。ナデシコは、ナデシコ科の多年草(一年草も)で、秋の七草の一つ。夏にピンク色の可憐な花を咲かせ、我が子を撫でるように可愛らしい花であるところから「撫子(撫でし子)」の文字が当てられています。数多くの種類があり、ヒメハマナデシコとシナノナデシコは日本固有種です。
大伴旅人が丹比県守に贈った歌
巻第4-555
| 君がため醸(か)みし待酒(まちざけ)安(やす)の野にひとりや飲まむ友なしにして |
【意味】
あなたと飲み交わそうと醸造しておいた酒も、安の野で一人寂しく飲むことになるのか。友がいなくなってしまうので。
【説明】
大宰帥の大伴旅人が、民部卿(民部省の長官)として転任することになった大弐(大宰府の首席次官)の丹比県守(たじひのあがたもり)に贈った歌。丹比県守は、左大臣正二位・多治比嶋の子で、遣唐押使として渡唐を果たしたのち、按察使・征夷将軍などを歴任して地方行政に従事、後に藤原四子政権で昇進し正三位・中納言に至った人です。家柄からして、旅人にとっては胸襟を開いて接することができた、ごく少数の友だったとみえます。「醸みし待酒」は、訪れ来る人を接待するために醸造して用意していた酒。「安の野」は、大宰府の東南にあった野で、大宰府から東南約12km、大宰府の官人がよく野遊びをしていた所です。
酒の醸造方法は、古くは「口醸(くちか)み」とされ、女性が蒸し米を口でよく噛み、唾液の作用で糖化させ、容器に吐き入れたものを、空気中の酵母によって発酵させるというものでした。そこから醸造することを「醸(か)む」「醸(かも)す」と言います。ただし、この歌が詠まれた奈良時代には、すでに麹を用いた酒造が行われていたことが、播磨風土記や職員令集解造酒司条古記の記事からも知られます。
この歌が詠まれたのは、神亀6年(729年)2月の頃と見られ、丹比県守の後任が、巻第5の「梅花の歌」32首の最初の歌を詠んだ紀男人(きのおひと)だろうとされます。なお、家持の妹の留女之女郎(りゅうじょのいらつめ)が丹比(多治比)家に居住していたと見られることから、丹比郎女(たじひのいらつめ:生没年未詳)が、旅人の妻で家持および留女之女郎の生母と考えられています。また、ここの丹比県守が丹比郎女の父ではなかいかとの説があります。
【PR】
賀茂女王の歌
巻第4-556
| 筑紫船(つくしふね)いまだも来(こ)ねばあらかじめ荒(あら)ぶる君を見るが悲しさ |
【意味】
筑紫へ向かう船はまだ来てもいないのに、その前からよそよそしくしているあなたを見るのが悲しい。
【説明】
賀茂女王(かものおおきみ)が、大伴三依(おおとものみより)に贈った歌。賀茂女王は、故左大臣、長屋王の娘。大伴三依は、壬申の乱で活躍した大伴御行の子で、大伴旅人が太宰帥だった頃に筑紫に赴任したとされます。歌によると、二人は夫婦関係になっており、三依が筑紫へ出立する前の歌であることが知られます。「筑紫船」は、筑紫への航路を往き来する官船。「いまだも来ねば」は、まだ来てもいないのに。「あらかじめ」は、その前から。「荒ぶる」は、疎遠になる、よそよそしくする。「君」は、三依を指します。「見るが悲しさ」は、見ることの悲しさよ。
ただでさえ遠い別れとなるのに、折から三依が通って来ないのを、別れた後に忘れられるのなら仕方ないけれども、まだ別れないうちから冷たく扱われるのを悲しんでいる歌とされますが、そうではなく、筑紫から帰る三依の変心を予想して悲しんだものとする説があります。それによると、「筑紫からの船はまだ帰って来ないけれど、冷たくなったあなたのお顔を見るのは悲しい」のような解釈になります。それまでの便りのやり取りなどから、既に破局を予感していたのでしょうか。
巻第4-565
| 大伴(おほとも)の見つとは言はじあかねさし照れる月夜(つくよ)に直(ただ)に逢へりとも |
【意味】
筑紫船は大伴の御津(みつ)に泊てますが、あなたに逢っていたとは言いません、誰が見ても分かるほど明々と照らす月の夜にじかにお逢いしているとしても。
【説明】
「大伴の御津は」、難波の港のことで、それを踏まえて「御津」と同音の「見つ」に掛けた枕詞。「見つ」は、男女が関係を持つ意。「あかねさし」は、明々と照り差し。この「あかね」は、植物の茜から採った黄赤色の色名。鮮やかな黄赤色というより、かなり落ち着きのある色相だったといいます。「月夜」は、月そのものを指す場合がありますが、ここは月のある夜の意。「直に」は、直接に。筑紫へ向かう三依との別れを惜しむため御津に出向いた女王が、月夜の下でひそかに逢い、その喜びを詠った歌とされますが、あるいは短い逢瀬に満足できなかったため「見つとは言はじ」と言ったのでしょうか。
巻第8-1613
| 秋の野を朝ゆく鹿(しか)の跡(あと)もなく思ひし君に逢へる今宵(こよひ)か |
【意味】
秋の野を朝行く鹿の通った跡も分からないように、どこへ行ったか見当のつかなかったあなたに、お逢いできた今宵です。
【説明】
上2句は、鹿の通った跡が分からない意で「跡もなく」を導く序詞。秋は鹿の恋の季節であり、「朝ゆく」は、野で寝ていた鹿が、朝になって山へ帰っていくこと。「跡もなく」は、夫婦関係を結んだ後朝の別れの後、それきりで途絶えてしまった意。しばらく消息の途絶えていた男に、思いがけず再び逢えた喜びを詠んでいる歌です。ただし、左注に「右の歌は、或いは倉橋部女王の作、或いは笠縫女王の作という」とあります。倉橋部女王は巻第3-441に長屋王に対する挽歌を残し。笠縫女王は巻第8-1611に1首を残しています。
窪田空穂はこの歌について、「当時の夫婦関係にあっては、この歌のような状態が稀れなものではなかったろうと思われる。序詞がその季節をあらわすとともに、きわめて自然で、また気分のつながりをもったものてある上に「朝」と「今夜」の照応もあって、全体の上に大きく働いている。一首、おおらかで、気品のある歌である」と述べています。
【PR】
 |
古典に親しむ
万葉集・竹取物語・枕草子などの原文と現代語訳。 |
バナースペース
【PR】
大宰府の官職
帥(そち:長官)
従三位
弐(すけ)
大弐・・・正五位上
少弐・・・従五位下
監(じょう)
大監・・・正六位下
少監・・・従六位上
典(さかん)
大典・・・正七位上
少典・・・正八位上
その他、大判事、少判事、大工、防人正、主神などの官人が置かれ、その総数は約50名。
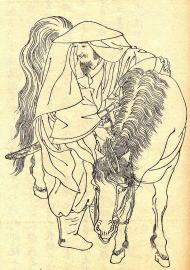
(大伴旅人)
万葉時代の年号
645~650年
白雉
650~654年
朱鳥まで年号なし
朱鳥
686年
大宝まで年号なし
大宝
701~704年
慶雲
704~708年
和銅
708~715年
霊亀
715~717年
養老
717~724年
神亀
724~729年
天平
729~749年
天平感宝
749年
天平勝宝
749~757年
天平宝字
757~765年

(聖武天皇)
【PR】

