
大伴旅人が松浦佐用姫伝説を歌った歌
巻第5-871~875
| 871 遠つ人 松浦佐用姫(まつらさよひめ)夫恋(つまご)ひに領巾(ひれ)振りしより負(お)へる山の名 872 山の名と言ひ継(つ)げとかも佐用姫(さよひめ)がこの山の上(へ)に領巾(ひれ)を振りけむ 873 万世(よろづよ)に語り継(つ)げとしこの岳(たけ)に領巾(ひれ)振りけらし松浦佐用姫(まつらさよひめ) 874 海原(うなはら)の沖行く船を帰れとか領布(ひれ)振らしけむ松浦佐用姫(まつらさよひめ) 875 ゆく船を振り留(とど)みかね如何(いか)ばかり恋しくありけむ松浦佐用姫(まつらさよひめ) |
【意味】
〈871〉松浦の佐用姫が夫恋しさに領巾(ひれ)を振った時から、今に伝わる山の名前だ。
〈872〉山の名として言い伝えてほしいというので、佐用姫はこの山の上で領巾を振ったのだろうか。
〈873〉後々までも語り継げよとばかり領巾を振ったらしい、松浦佐用姫は。
〈874〉海原の沖へと走り行く船に、帰ってきてと領布を振られたのだろうか、松浦の佐用姫は。
〈875〉遠ざかる船を、領布を振っても留めることができず、どんなに悲しかっただろう、松浦佐用姫は。
【説明】
佐賀県の松浦地方に伝わる伝説をもとに作った歌です。序文によれば、「朝廷の命令で朝鮮半島の任那、百済の救援に派遣された青年武将・大伴狭手彦(おおとものさでひこ)は、停泊地である松浦の地で、身の回りの世話をしてくれた土地の長者の娘・佐用姫(さよひめ)と恋に落ちた。やがて、出帆の時が来て、別離の悲しみに耐えかねた佐用姫は鏡山に駆け登り、軍船をはるかに眺めたが、悲しみで胸はつぶれ、魂は消えてしまいだった。ついにたまらず身にまとっていた領巾を手にとって、打ち振ると、その姿を見て、傍らの者はみな涙を流した。これによってこの山を領巾振(ひれふ)りの嶺(みね)と名づけた。そこで歌を作った」。
871の「遠つ人」は「松浦佐用姫」の枕詞。狭手彦を待つ意も込められています。「領布」は、女性が肩にかける細長い布の装身具。呪力があり、振ると願いが叶うと考えられていました。「負へる」は、今に至るまで言い継がれている。872以下の歌には「後の人の追ひて和ふる」、「最後の人の追ひて和ふる」との題詞が付いていますが、いずれも旅人の作とされます。872の「山の名と」は、山の名として。「言ひ継げとかも」の「かも」は、疑問。「振りけむ」の「けむ」は、過去推量。873の「語り継げとし」の「し」は、強意の副助詞。「振りけらし」の「らし」は、確信ある推定。874の「振らしけむ」の「し」は、尊敬、「けむ」は、過去推量。「領巾振りの嶺」と名づけられたこの山は、今の佐賀県唐津市東方にある鏡山のことで、鏡山の北には、虹ノ松原が美しい弧を描いています。
佐用姫のこの伝説は、『肥前風土記』にも載っています。さらに後世(鎌倉~室町時代)になると、名残がつきない佐用姫は、山から飛び降り、呼子の加部島まで追いすがったものの、すでに船の姿はなく、悲しみのあまり七日七晩泣き続け、ついに石に化したという話が付加されています。
山上憶良が大伴旅人に贈った歌
巻第5-868~870
| 868 松浦(まつら)がた佐用姫(さよひめ)の児(こ)が領巾(ひれ)振りし山の名のみや聞きつつ居(を)らむ 869 足日女(たらしひめ)神の命(みこと)の魚釣(なつ)らすとみ立たしせりし石を誰(た)れ見き 870 百日(ももか)しも行(ゆ)かぬ松浦道(まつらぢ)今日(けふ)行きて明日(あす)は来(き)なむを何か障(さや)れる |
【意味】
〈868〉松浦の県の佐用姫が領巾を振ったという、あの有名な山の名だけ聞かされているのでしょうか。
〈869〉足日女(神功皇后)が鮎を釣ろうとお立ちになった石を実際に見たのはどこのどなたでしょうか。
〈870〉百日もかけて行く道ではない松浦への道を、今日行って明日は帰って来られるのに何の支障があるのでしょうか。
【説明】
山上憶良が旅人に贈った歌で、次のような内容の手紙が添えられています。――憶良、畏れ謹んで申し上げます。聞くところによると、「郡県の長官なるものは、法の定めにより管内を巡ってその風俗を視察する」ということであります。しかるに、この私は同行できなかったことが無念でならず、心中思うことはあれこれございますが、それを言葉で申すことは困難です。それで、謹んで三首の拙い歌を詠み、五臓の鬱憤を晴らしたいと思います。―― 旅人の管下巡行で松浦の辺を遊覧したことを聞き、何らかの公務のせいで同行できなかったことを大変悔しがっている文面です。憶良は国司として中央から派遣された立場にあったものの、大宰府との関係、とりわけその長官である旅人との間は、一種の扈従(こしょう:貴人への随従)関係に近かったようで、旅人との親密な心の交流が窺えます。
868の「松浦がた」は松浦県で、佐用姫の住地。「佐用姫」の伝説は、上掲参照。「領巾」は、女性の肩にかけて垂らした装飾用の細長い薄布。869の「足日女」は、神功皇后のこと。『古事記』に、神功皇后が松浦川(現在の玉島川)で裳の糸を抜いて、飯粒を餌に鮎を釣ったとあり、また『日本書紀』には、新羅国を攻めるにあたり、神功皇后が占いをして吉兆の鮎を手に入れた、という話が書かれています。「み立たしせりし」の「み」は、敬語の接頭語。「立たし」は、立ツの敬語「立たす」の連用形で名詞。「せりし」は、していた。870の「百日し」の「百日」は、多くの日数の意。「し」は、強意の副助詞。旅人と憶良に神功皇后にかかる歌があるのは、太宰帥や筑前守という役職上、神功皇后を祀る香椎の宮との関係が深かったこと、香椎の宮が造営されて間もなくその祭祀と神功皇后信仰が生き生きと働いていた時期であったこと、また当時、新羅との緊張関係が高まっている時期であったこと等が背景にあると見られています。
三島王が後に松浦佐用姫の歌に追和した歌
巻第5-883
| 音(おと)に聞き目にはいまだ見ず佐用姫(さよひめ)が領布(ひれ)振りきとふ君(きみ)松浦山(まつらやま) |
【意味】
噂には聞いて目にはまだ見たことがない、佐用姫が領布を振ったという、君待つと言う名の松浦山は。
【説明】
三島王(みしまのおほきみ)は、天武天皇の孫で、舎人皇子(とねりのみこ)の子。養老7年に無位から従四位下を授けられています。この歌は、帰京した旅人から披露された歌(871~875)に和したもののようです。「音に聞き」は、評判に聞いて。「振りきとふ」の「とふ」は、「といふ」の約。「君松浦山」は、君を待つ意を同音の「松」に続けた序詞の形になっています。「松浦山」は、松浦の領巾振山(鏡山とも)。
帰京する大伴旅人への送別の歌
巻第5-876~879
| 876 天(あま)飛ぶや鳥にもがもや都まで送り申(まを)して飛び帰るもの 877 人もねのうらぶれ居(を)るに龍田山(たつたやま)御馬(みま)近づかば忘らしなむか 878 言ひつつも後(のち)こそ知らめとのしくも寂(さぶ)しけめやも君いまさずして 879 万代(よろづよ)にいましたまひて天(あめ)の下(した)奏(まを)したまはね朝廷(みかど)去らずて |
【意味】
〈876〉空飛ぶ鳥になれたなら、都までお送り申し上げて、飛んで帰ってこれますものを。
〈877〉私たち一同ががっかりしていますのに、龍田山にお馬がさしかかる頃には、私たちのことをお忘れになってしまわれるのでしょうか。
〈878〉お別れの寂しさを今は口先であれこれ申していますが、後になって本当に思い知らされるのでしょう、貴方様がいらっしゃらなくなったら。
〈879〉万年もご健勝でいらして、天下の政(まつりごと)をご立派に司ってくださいませ、朝廷を去られることなく。
【説明】
題詞に「書殿(ふみどの)の餞酒(せんしゅ)の日の倭歌(やまとうた)」とある4首。天平2年(730年)10月、大宰帥として筑紫に赴任していた大伴旅人が大納言に昇進し、平城京に帰任することになり、その送別宴で山上憶良が詠んだ歌です。「倭歌」とあるのは、当日の宴では漢詩も披露されたので、わざわざ「倭歌」と記しているものと思われます。文人の旅人の送別会らしく、大宰府の書殿(書院または文書館)で行われていますが、見送り歌はずいぶん拗ねた気分で詠まれています。ただ、憶良一人の作ではなく、数人による作とみる説もあります。
876の「天飛ぶや」は「鳥」の枕詞。「や」は、感動の助詞。「もがも」は、願望。「飛び帰るもの」の「もの」は、ものを、の意。『文選』蘇子卿「詩四首」の二にある「願ハクハ双黄鵠ト為リテ、子ヲ送リテ俱ニ遠ク飛バンコトヲ」を踏まえているとされます。877の「人もね」は、語義未詳、あるいは「人みなの」の筑紫の方言か。「うらぶれ」は、憂えしおれて。「龍田山」は、生駒連峰の一峰で、難波から奈良に向かう道がある山。大和を象徴する山であり、西から戻ってくる都人の帰京の目途とされていました。「忘らしなむか」の「忘らし」、忘レの敬語。「か」は、疑問の終助詞。878の「とのしくも」は、語義未詳。879の「天の下奏し」は、天下の政事を奏上しで、政事を執る意の成語。「たまはね」の「ね」は、希求の助詞。「朝廷去らずて」は、朝廷を離れずに。
窪田空穂は、877について、「旅人が道中無事で、京近くまで行った時の楽しい心持を、想像で具象的に描き出したものである。それをするに、後に残される諸人の深いさみしさを絡ませてやすらかに綜合させているのは、非凡な手腕というべきである。儀礼のもので、一種の題詠であるが、いささかもその匂いを見せていない」と評し、878についても、「旅人が居なくなった後に感じる寂莫の感を思いやることによって、その徳望の高く温情の深かったことを讃えて言っている歌である。きわめて要を得た讃え方であるが、同時にきわめて捉えて言い難い境でもある。それを、その事を感じ合っている官人の雰囲気をとおして言うという、実際に即しての詠み方をしているもので、きわめて手腕の現われている歌である」と評しています。憶良の、上司である旅人との交遊は短い期間であったものの、何物にも換えがたい大切な経験だったのでしょう。この歌の次には、同じ席で詠んだ歌3首(巻第5-880~882)が載っています。
【PR】
 |
古典に親しむ
万葉集・竹取物語・枕草子などの原文と現代語訳。 |
バナースペース
【PR】
大宰府
政庁の中心の想定範囲は現在の福岡県太宰府市・筑紫野市にあたり、主な建物として政庁、学校、蔵司、税司、薬司、匠司、修理器仗所、客館、兵馬所、主厨司、主船所、警固所、大野城司、貢上染物所、作紙などがあったとされます。その面積は約25万4000㎡に及び、甲子園球場の約6.4倍にあたります。国の特別史跡に指定されています。
長官の大宰帥は従三位相当官、大納言・中納言クラスの政府高官が兼ねていましたが、平安時代になると、親王が任命され実際には赴任しないケースが大半となり、次席の大宰権帥が実際の政務を取り仕切るようになりました。
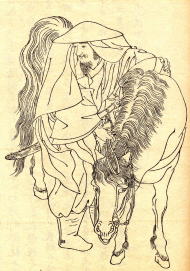
(大伴旅人)
万葉時代の年号
645~650年
白雉
650~654年
朱鳥まで年号なし
朱鳥
686年
大宝まで年号なし
大宝
701~704年
慶雲
704~708年
和銅
708~715年
霊亀
715~717年
養老
717~724年
神亀
724~729年
天平
729~749年
天平感宝
749年
天平勝宝
749~757年
天平宝字
757~765年

(聖武天皇)