
高市黒人の歌
巻第1-32~33
| 32 古(いにしへ)の人に我(わ)れあれや楽浪(ささなみ)の古き京(みやこ)を見れば悲しき 33 楽浪(ささなみ)の国つ御神(みかみ)のうらさびて荒れたる京(みやこ)見れば悲しも |
【意味】
〈32〉私は遥かなる古(いにしえ)の人なのだろうか、まるでそんな人のように、楽浪の荒れ果てた都を見ると、悲しくてならない。
〈33〉楽浪の地を支配された神の御魂(みたま)も衰えて、荒れ廃れた都の姿を見ると、悲しくてならない。
【説明】
題詞に、高市古人(たけちのふるひと)が近江の旧都を悲しんで作った歌とありますが、その下に「或る書には高市連黒人(たけちのむらじくろひと)という」と注されているので、高市黒人の誤伝とされます。高市黒人は柿本人麻呂とほぼ同時代の下級官人(生没年未詳)。大和国6県の一つである高市県の統率者の家筋で、その氏人の一人だと見られています。『万葉集』に収められている18首の短歌はすべて大和以外の旅先(東海道・北陸路・摂津・吉野など)のもので、とくに舟を素材とし、漠とした旅愁を漂わせる作品に特色があります。当時の下級役人が自由気ままに旅ができたとは考えられないことから、黒人は風俗民謡を採集する採詞官(さいしかん)だったという説があります。
ここの歌は、柿本人麻呂による29~31の歌と同様に、壬申の乱によって廃墟となった近江大津の宮を嘆き悲しむ歌です。天智天皇とその王朝の霊魂への畏怖、そして、旧都の土地の鎮静しない霊魂への関心は、天武天皇とその王朝にとっては、忘れてはならないことだったはずですから、その王朝に宮廷歌人として仕えた人麻呂・黒人にこのような歌があるのは、むしろ当然といえましょう。ただ、人麻呂が都の荒廃の原因を、神武天皇以来の「天つ神」の皇統譜の上に天智天皇を神と位置づけ、その現人神(あらひとがみ)が事もあろうに畿内以外の鄙の地に都を遷したという点に求めているのに対し、黒人は大津宮の地主の神「国つ神」がその霊威を衰えさせてしまったと言っています。二人が同じ時に歌ったものではなく、黒人の方がやや後に人麻呂の歌を意識しつつ歌ったであろうというのが通説です。
また、文芸評論家の山本憲吉は、「人麻呂の方が古式であり、廃墟の精霊に呼びかけるような態度で作っているが、黒人のは後の赤人の歌風へ道を展くような、孤独な詩人としての詠みぶりである。歌の作られる場が、公的なものから私的なものに移ってきている。自分の悲しみの抒情として、うるおいを感じさせる。人麻呂に見られた、ややもすれば空疎に流れがちな、形式的な修辞がない。だが、人麻呂に較べて、歌柄がずっと小さくなってきていることも事実だ」と述べています。
32の「古」は、近江朝時代を念頭に漠然と言ったもの。「我れあれや」の「や」は疑問の係助詞で、私はなっているのか。「見れば悲しき」の「悲しき」は、上の「や」の係り結びで連体形。33の「楽浪」は、琵琶湖西南岸の一帯。「国つ御神」は、ここは楽浪の地を支配する神。「うらさびて」の「うら」は心で、心が楽しまずして。上代に用いられた「心」の類語に「うら」と「した」があり、『万葉集』では「うら」は26首、「した」は23首の用例が認められます。「うら」は、隠すつもりはなく自然に心の中にあり、表面には現れない気持ち、「した」は、敢えて隠そうとして堪えている気持ちを表わしています。また、「荒れたる都」の「荒」は、本来は始原的で霊力を強く発動している状態をあらわす言葉だともいわれます。人の手による華麗な都が廃墟と化し、草木の繁茂する本来の自然に立ち返ったことを始原の神意によるものと考え、その落差のある光景に強い喪失感を意識しています。
【年表】
663年 白村江の戦い
667年 大津宮に都を遷す
668年 中大兄皇子が即位、天智天皇となる
671年 天智天皇が死去
672年 壬申の乱、勝利した大海人皇子が即位し天武天皇となる
686年 天武天皇が死去
690年 皇后が即位し持統天皇となる
694年 持統天皇が飛鳥の藤原京に都を遷す
巻第1-58
| いづくにか船泊(ふなは)てすらむ安礼(あれ)の埼(さき)漕(こ)ぎたみ行きし棚(たな)無し小舟(をぶね) |
【意味】
今ごろいったい何処で舟どまりしているのだろう、安礼の崎を先ほど漕ぎめぐっていった、船棚のない小さな舟は。
【説明】
大宝2年(702年)10月、持統太上天皇の三河国(今の愛知県東部)行幸に従駕しての作。「太上天皇」は、退位した天皇のこと。「船泊て」は、船どまりする意の熟語。「安礼の崎」は、今の愛知県宝飯郡御馬の南にある岬ではないかとされます。「こぎ回み」は、船を漕いで海岸線に沿って巡る意。この時代の舟行きは、風の危険を防ぐため、岸に近接して漕ぐのがふつうでした。「棚無し小舟」は、船棚(ふなだな)のない小さな舟で、原始的な丸木舟に近い形の舟。この「棚無し小舟」の語で舟を歌ったのは黒人が最初で、『万葉集』では3回出ているうち2回は黒人が歌っているので、彼の造語かもしれません。決して強い調べではないものの、体言止めが余韻を長く残す効果と相俟って、しっとりとした情感を漂わせている歌であり、黒人の歌の特色となっています。
文学者の犬養孝は、この歌について次のように述べています。「船の行方を追いもとめる主観をはじめにうち出して、それを三句目の地名”安礼の崎”で具体の場に定着させ、ついで漕ぎ・廻み・行きし、と、こきざみに水脈を残すようにして消えていった、網膜に残る小船を点出する。標々と小さく一点となって消え去った船の姿は、そのまま漂泊寂寥の作者の心の姿ともなっている」。
なお、この行幸は10月10日に出立、11月13日に尾張国到着、11月25日に帰朝とあり、実に46日間にわたる長旅でした。その約1ヵ月後の12月22日に持統女帝はこの世を去っていますから、生涯最後の大旅行だったことになります。旅好きだった女帝自身に旅を詠んだ歌はありませんが、さまざまな旅の場を提供してきたことから、人麻呂や黒人などによる数多くの名歌を生んだことになります。ただ、黒人の歌で行幸従駕歌と認められるのは、この歌と次の70の歌の2首のみです。
巻第1-70
| 大和には鳴きてか来(く)らむ呼子鳥(よぶこどり)象(きさ)の中山(なかやま)呼びぞ越(こ)ゆなる |
【意味】
呼子鳥が、象の中山を人を呼びながら鳴き渡っている声が聞こえる。たぶん大和の方へ鳴いて行くのだろう。
【説明】
「太上天皇、吉野の宮に幸す時に作る」歌。太上天皇は持統天皇で、行幸に従駕した作者の正式な宴遊歌として現存する唯一の歌です。郷愁を感じている折から、呼子鳥が妻のいる大和(藤原京)の方角へ鳴きながら飛んでゆくのを見て、その鳥に自身の気持ちを伝えさせようという心をもって詠んだ歌です。「鳴きてか来らむ」の「らむ」は、現在推量。「呼子鳥」は、子すなわち妻を呼ぶ鳥の意で、カッコウまたはホトトギス。この名は時代と共に変化しており、「喚子鳥」と書いた字面から「閑古鳥」といわれ、やがて郭公(カッコウ)になったとされ、カッコウを呼子鳥といった例が最も多いようですが、未だ定説がありません。「象の中山」の「象」は、吉野離宮の上の象山(きさやま)、「中山」は、そこにある山。「呼びぞ越ゆなる」の「なる」は連体形で「ぞ」の係り結び。
【PR】
忍坂部乙麻呂の歌
巻第1-71
| 大和(やまと)恋ひ寐(い)の寝(ね)らえぬに心なくこの洲崎廻(すさきみ)に鶴(たづ)鳴くべしや |
【意味】
大和が恋しくて寝るに寝られないのに、思いやりもなく、この洲崎あたりで鶴が鳴いてよいものだろうか。
【説明】
題詞に、大行天皇(さきのすめらみこと)が難波宮に行幸されたときの歌とあります。「大行天皇」とは、本来天皇崩御後、御謚号を奉らない間の称であったのが、この頃には、先帝の意味で用いるようになっており、『万葉集』の例ではすべて文武天皇を指しています。行幸の時期は明らかでありません。
作者の忍坂部乙麻呂(おさかべのおとまろ)は、伝未詳。『万葉集』には、この1首のみ。「寐の寝らえぬに」は、寝ても眠れないのに。「心なく」は、思いやりなく。「洲崎」は、海上に長く突き出た渚の崎。「廻」は、~の辺り。「鳴くべしや」の「や」は、反語。鳴いてよいものか、鳴くべきではない。同じ難波の「鶴」でも、その妻呼ぶ声にあやかって旅愁を慰めたいという歌がある(巻第1-67)一方、ここでは、妻が思われてならないから鳴くべきでないと訴えています。
窪田空穂はこの歌に関して次のように述べています。「旅愁を、我と慰めるための歌であるが、調べに迫るものがあって、その平淡なのを救っている。この歌に限らず、この種の歌のすべてに通じてのことであるが、旅愁の大半は旅の侘びしさより起こるものである。行幸の供奉としての旅は、侘びしさにも限度があって、その家居の時とさして異なったものではなかろうと思われる。異なるのは、妹の添っていないことだけである。すなわち旅愁は、いわゆる旅愁とは異なって、妹と別れていることによって起こってくるものなのである。ここに当時の人の、いかに善意に富んでいたかを思わせるものがある」
和歌の前に平等な日本人~渡部昇一氏の著書から引用
古代の日本人たちは、(中略)詩、すなわち和歌の前において平等だと感じていたように思われる。われわれの先祖が歌というものに抱いていた感情はまことに独特なものであって、よその国においてはあまり例がないのではないかと思われる。
たとえば上古の日本の社会組織は、明確な氏族制度であった。天皇と皇子の子孫は「皇別」、建国の神話と関係ある者は「神別」、帰化人の子孫は「蕃別」と区別されたほかに、職能によって氏族構成員以外の者も区別されており、武器を作る者は弓削部、矢作部とか、織物を作るのは服部とか錦織部というふうであった。これは一種のカースト制と言うべきであろう。このカースト制の実体はよくわからないし、現在のインドのように厳しかったかどうかもわからない。しかしカーストはカーストである。
ところが、このカーストを超越する点があった。それが和歌なのである。
『万葉集』を考えてみよう。これは全20巻、長歌や短歌などを合わせて4500首ほど含まれている。成立の過程の詳細なところはわかっていないが、だいたい巻ごとに編者があり、その全体をまとめるのに大伴家持が大きな役割を果たしていたであろうと推察される。大伴氏の先祖である天忍日命(アメノオシヒノミコト)は、神話によれば、高魂家より出て天孫降臨のときは靭負部をひきいて前衛の役を務めるという大功があり、古代においては朝臣の首位を占め、最も権力ある貴族であった。
その大伴氏が編集にたずさわっていたとすれば、カースト的偏見がはいっていたとしてもおかしくないはずである。それがそうではないのだ。この中の作者は誰でも知っているように、上は天皇から下は農民、兵士、乞食に至るまではいっており、男女の差別もない。また地域も、東国、北陸、九州の各地方を含んでいるのであって、文字どおり国民的歌集である。
一つの国民が国家的なことに参加できるという制度は、近代の選挙権の拡大という形で現れたと考えるのが普通である。選挙に一般庶民が参加できるようになったのは新しいことであるし、女性が参加できるようになったのはさらに新しい。しかしわが国においては、千数百年前から、和歌の前には万人平等という思想があった。
『万葉集』に現れた歌聖として尊敬を受けている柿本人麻呂にせよ山部赤人にせよ、身分は高くない。特に、柿本人麻呂は、石見国の大柿の股から生まれたという伝説があり、江戸時代の川柳にも「九九人は親の腹から生まれ」(百人一首に人麻呂がはいっていることを指す)などというのがある。これは人麻呂が素性も知れ微賤の出身であることを暗示しているが、この人麻呂は和歌の神様になって崇拝されるようになる。
このように和歌を通じて見れば、日本人の身分に上下はないという感覚は、かすかながら生き残っていて、現在でも新年に皇居で行われる歌会始には誰でも参加できる。
毎年、皇帝が詩の題、つまり「勅題」を出して、誰でもそれに応募でき、作品がよければ皇帝の招待を受けるというような優美な風習は世界中にないであろう。
【PR】
 |
古典に親しむ
万葉集・竹取物語・枕草子などの原文と現代語訳。 |
バナースペース
【PR】
万葉集の三大部立て
公的な歌。宮廷の儀式や行幸、宴会などの公の場で詠まれた歌。相聞歌、挽歌以外の歌の総称でもある。
相聞歌(そうもんか)
男女の恋愛を中心とした私的な歌で、万葉集の歌の中でもっとも多い。男女間以外に、友人、肉親、兄弟姉妹、親族間の歌もある。
挽歌(ばんか)
死を悼む歌や死者を追慕する歌など、人の死にかかわる歌。挽歌はもともと中国の葬送時に、棺を挽く者が者が謡った歌のこと。
『万葉集』に収められている約4500首の歌の内訳は、雑歌が2532首、相聞歌が1750首、挽歌が218首となっています。

万葉時代の天皇
第30代 敏達天皇
第31代 用明天皇
第32代 崇俊天皇
第33代 推古天皇
第34代 舒明天皇
第35代 皇極天皇
第36代 孝徳天皇
第37代 斉明天皇
第38代 天智天皇
第39代 弘文天皇
第40代 天武天皇
第41代 持統天皇
第42代 文武天皇
第43代 元明天皇
第44代 元正天皇
第45代 聖武天皇
第46代 孝謙天皇
第47代 淳仁天皇
第48代 称徳天皇
第49代 光仁天皇
第50代 桓武天皇
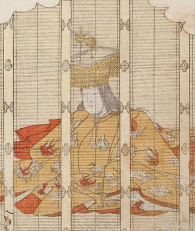
(持統天皇)
【PR】