
山上憶良の歌
巻第1-63
| いざ子どもはやく日本(やまと)へ大伴(おほとも)の御津(みつ)の浜松(はままつ)待ち恋ひぬらむ |
【意味】
さあ皆の者どもよ、早く日本に帰ろう。大伴の御津の浜のあの松原も、我々を待ち焦がれているだろうから。
【説明】
山上憶良が、遣唐使の一員として大唐(もろこし)にいたとき、故郷・日本を思って作った歌です。山上憶良は、藤原京時代から奈良時代中期に活躍した万葉第三期の歌人(660~733年)で、文武天皇の大宝2年(702年)、43歳で、遣唐大使・粟田真人に少録(第四等官:書記兼通訳)として従い入唐しました。山上氏は粟田氏の庇護下にあった小族で、憶良も粟田真人の家に仕えていたのかもしれません。漢詩文などをもってその子女の傅育に当たっていたものか、少録への抜擢は真人の推挽によるものと見られています。一行は、3年ほど在唐して帰国。この歌はその出帆間近のころに作られたとされ、都長安での別れの宴席での歌だったかもしれません。また、『万葉集』中、唯一、外国で作られた歌となっています。
歌中の「いざ」は、人を誘う意の副詞。原文の「去来」は、日本語の「いざ」に相当する語として用いられた中国の俗語。「子ども」は、部下や年少者等を親しんで呼ぶ語で、大使の粟田真人の立場を代弁して詠んだもの。「大伴」は、今の難波の辺り一帯の津で、古く大伴氏の領地だったところから地名になったとされます。「御津」は、難波の港で、遣唐使はここから出入りしていました。「御」は美称。「浜松」の「松」には「待つ」の意を込めています。そのころの大阪湾一帯には松がたくさんあったようで、日本を発つ時に、浜松の枝を結んで平安を祈ったのかもしれません。憶良らしい率直、単純な表現の歌です。
この時の遣唐使派遣は第8次にあたり、天智朝以来37年ぶりに行われたものでした。その目的は、第一に、完成したばかりの大宝律令をより確実なものとするための調査・研究、第二に、近く計画される都城造営のための実地調査と研究だったとされます。遣唐使のたどった航路は、朝鮮半島に沿って進む「北路」と、南シナ海を渡る「南路」がありましたが、日本と新羅の関係が悪化してからは北路を通れなくなり、渡航が危険な南路をとらざるをえなくなりました。南路のルートは、瀬戸内海を抜けて博多湾の娜津を通り、五島列島の値嘉島(ちかのしま:今の福江島)から東シナ海を渡って、上海あたりに上陸するというものでした。唐僧の鑑真が日本に渡ろうとして何度も失敗したのが南路で、この時は奄美大島に漂着しています。憶良の時も南路を往復し、3分の2の人たちが帰って来れなかった中、憶良は運よく無事に帰国できました。ちなみに、この時の遣唐使一行が謁見した唐の皇帝は、かの則天武后でした。
なお、それまで無位だった憶良は、帰国後、渡唐の功によって正六位下に叙せられ、さらに従五位下に昇叙、後に伯耆守(ほうきのかみ)となり、1年余りの赴任の後には皇太子(聖武天皇)の侍講を拝命しています。筑前守として大宰府に下ったのはその10年後の726年ごろとされ、この地で大伴旅人と出会うこととなります。憶良が遣唐少録になるまでの前半生は謎に包まれており、出自や経歴は未詳です。憶良と似た名前が百済からの渡来人の名に見えることや、漢籍の影響が著しい歌が多いことなどから、渡来人であるとする説が有力であるものの、定説には至っていません。
巻第3-337
| 憶良(おくら)らは今は罷(まか)らむ子泣くらむその彼(こ)の母も吾(わ)を待つらむぞ |
【意味】
私、憶良はもう失礼いたします。今ごろ家では子供が泣いているでしょう、その母親も私を待っていますから。
【説明】
この歌は筑前守として大宰府にいた時の歌とされ、この前後に大宰帥(だざいのそち:大宰府の長官)の大伴旅人、防人司佑(さきもりのつかさのすけ)の大伴四綱、沙弥満誓の歌等があるため、大宰府における宴会の時の歌とみられています。題詞には、宴席から退出する時の歌とあり、憶良が宴席を中座する時の歌との見方がありますが、自ら名乗りをしての宴の「お開き」を告げる挨拶の歌と見るべきもののようです。
「憶良ら」の「ら」は複数の意味ではなく、自ら名乗るときに謙遜の意を表す接尾語で、今でいう「わたくしめ」の「め」のようなものです。自分の妻を「彼(こ)の母」と表現したところに、憶良ならではのおかしみがあります。しかし、「子どもが泣いて、妻も待っていますから・・・」というのは、この時、60歳を遥かに越えていた憶良には相応しくないため、「お開き」専用の歌代わりによく歌われていた一種の笑わせ歌だったと見ることもできます。なお、「その彼の母も」の原文「其彼母毛」の訓みは定まっておらず、「それその母も」「そもその母も」などの訓みも提唱されています。「待つらむぞ」の「らむ」は現在推量の助動詞で、待っていようぞ。歌は、計3回の「む」「らむ」と5つの「ら」音によって明るく軽快な調べとなっており、楽しく締めくくった宴席のようすが目に浮かぶようです。
斎藤茂吉は、憶良について次のように言っています。「憶良は万葉集の大家であるが、飛鳥朝、藤原朝あたりの歌人のものに親しんできた眼には、急に変わったものに接するように感ぜられる。その声調がいかにもごつごつしていて、流動の響きに乏しい。そういう風でありながら、どこかに実質的なところがあり、軽薄平俗になってしまわない。またそういう滑らかでない歌調が、当時の人にも却って新しく響いたのかもしれない。憶良は、大正昭和の歌壇に生活の歌というものが唱えられた時、いち早くその代表的歌人のごとくに取扱われたが、そのとおり憶良の歌には人間的な中味があって、憶良の価値を重からしめている」
山上憶良の歌には恋歌や叙景詩はなく、漢文学や仏教の豊かな教養をもとに、貧・老・病・死、人生の苦悩や社会の矛盾を主題にしながら、下層階級へ温かいまなざしを向けた歌が収められています。
→ 山上憶良による貧窮問答の歌(巻第5-892~893)
山上憶良の略年譜
660年 このころに生まれる
701年 第8次遣唐使の少録に任ぜられ、翌年入唐。この時までの冠位は無位
704年 このころ帰朝。渡唐の功によって正六位下に叙爵
714年 正六位下から従五位下に叙爵
716年 伯耆守に任ぜられる
720年 このころまでに帰京か
721年 東宮・首皇子(後の聖武天皇)の侍講に任ぜられる
724年 左大臣・長屋王邸で七夕歌を詠む
726年 このころ筑前守に任ぜられ、筑紫に赴任
728年 このころまでに太宰帥として赴任した大伴旅人と出逢う
728年 大伴旅人の妻の死去に際し「日本挽歌」を詠む
730年 帰京する大伴旅人に対し国司館書殿で餞別の宴を張り歌を作る
731年 筑前守の任期を終えて帰京
731年 「貧窮問答歌」を詠む
733年 遣唐大使多治比広成あてに「好去好来歌」を詠む
733年 病没。享年74歳
【PR】
『類聚歌林(るいじゅうかりん)』
『万葉集』の巻第1、2、9の左注の中に9か所、「山上憶良大夫の類聚歌林に曰く」云々と書かれており、『万葉集』編纂の資料として用いられたことが分かります。現存していないものの、平安末期ごろまでには伝わっていたようで、憶良が古歌、とりわけ宮廷関係伝誦歌の作者や作歌事情などを類纂し、校注を加えたものらしく、全7巻と想定されています。唐に『芸文類聚』という、古来の典故を分類し関係詩文を配した書物があるため、あるいはこれに倣ったのではないかともいわれます。ただし憶良がこの書をなしたのは唐からの帰国後であり、その時期は、憶良が東宮侍講を務めた期間だった可能性が高いとされます。『万葉集』で見る限りでは、収録歌は万葉初期の天皇・皇族の歌や行幸従駕歌などの宮廷関係歌であるため、東宮への進講のためだったか、それとも教養書としての献呈だったか、その動機と条件がよく説明できるからです。
【PR】
 |
古典に親しむ
万葉集・竹取物語・枕草子などの原文と現代語訳。 |
バナースペース
【PR】
万葉集の代表的歌人
磐姫皇后
雄略天皇
舒明天皇
有馬皇子
中大兄皇子(天智天皇)
大海人皇子(天武天皇)
藤原鎌足
鏡王女
額田王
第2期(白鳳時代)
持統天皇
柿本人麻呂
長意吉麻呂
高市黒人
志貴皇子
弓削皇子
大伯皇女
大津皇子
穂積皇子
但馬皇女
石川郎女
第3期(奈良時代初期)
大伴旅人
大伴坂上郎女
山上憶良
山部赤人
笠金村
高橋虫麻呂
第4期(奈良時代中期)
大伴家持
大伴池主
田辺福麻呂
笠郎女
紀郎女
狭野芽娘子
中臣宅守
湯原王
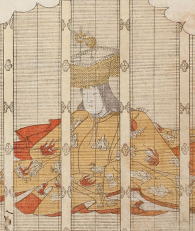
(持統天皇)

(柿本人麻呂)

(山部赤人)
【PR】
