
筑紫で妻をなくした大伴旅人が帰京途上に作った歌
巻第3-446~450
| 446 吾妹子(わぎもこ)が見し鞆(とも)の浦のむろの木は常世(とこよ)にあれど見し人ぞなき 447 鞆(とも)の浦の磯(いそ)のむろの木見むごとに相(あひ)見し妹(いも)は忘らえめやも 448 磯(いそ)の上に根(ね)這(は)ふむろの木見し人をいづらと問はば語り告げむか 449 妹と来(こ)し敏馬(みぬめ)の崎を還(かへ)るさに独りし見れば涙ぐましも 450 行くさにはふたり我が見しこの崎をひとり過ぐれば心悲しも [一に云ふ、見もさかずきぬ] |
【意味】
〈446〉大宰府に赴任する時には、一緒に見た鞆の浦のむろの木は、そのままに変わらずあるけれど、このたび帰京しようとしてここを通る時には妻は今はもうこの世にいない。
〈447〉鞆の浦の磯に生えているむろの木を見るたびに、共に見た妻を忘れることはできない。
〈448〉磯のほとりに太い根を這わせるむろの木よ、かつて見た人はどこにいるかと尋ねたら、お前は教えてくれるだろうか。
〈449〉妻と通った敏馬の崎を、帰りに一人で見ると、ふと涙がにじんでしまう。
〈450〉太宰府に赴任する行きしなには、二人で我らが見たこの岬を、帰りは一人で過ぎると、心悲しいことだ。(見ることもなく帰って来た)
【説明】
大伴旅人が太宰帥として筑紫に赴任して間もない初夏の頃、妻の大伴郎女(おおとものいらつめ)が病で亡くなりました。その2年後の天平2年(730年)11月、旅人は大納言へと昇格し、12月に都に帰ることになります。これらの歌は、その途上に詠んだ歌です。しかし、待ち焦がれた帰京の喜びを共にするはずだった妻は、もうこの世にはいません。2年前に都から筑紫に赴く際、亡き妻と二人見た風物を、独り見て涙にむせんでいます。
446~448は「鞆の浦」を通り過ぎた日に作った歌。「鞆の浦」は、広島県福山市鞆町の海岸。かつては瀬戸内海航路の要港で、潮待ちの港として栄えました。港の形が巴(ともえ)形をしていることから巴津(ともえつ)とも呼ばれたようです。446の「むろの木」は、マツ科の常緑樹である杜松(ねず)の古名で、備後地方では寿命を司る霊木とされていたという説があります。「常世にあれど」の「常世」は永久の意で、「むろの木」を不老不死の霊木と見て、妻の死と対比した表現。「見し人」は、旅人の妻のこと。
447の「相見し妹は」は、一緒に見た妻のことは。「忘らえめやも」の「やも」は、反語的詠嘆。448の「根這ふ」は、根の這っている意で、根が横に広くひろがっている老木を思わせます。「いづら」は「何処(いずく)」と同じで、どこにいるかの意。「語り告げむか」は、霊木である「むろの木」だったら霊界のことは知っているだろうと、霊界での妻の消息を教えてくれと問いかけているものです。一方、主語を作者と見て、「むろの木が、前に一緒に我を見たもう一人はどこにいるのかと尋ねたならば、我はその理由を知らせたものであろうか」のように解する説もあります。いずれにせよ、松や島に問いかけるのは、上代人の心だったといいます。
449~450は「敏馬の崎」を通り過ぎた日に作った歌。449の「敏馬の岬」は神戸市灘区岩屋のあたりの岬で、「見ぬ女(め)」と掛けています。難波津を出ての行きしなに、郎女が深く感動した思い出の地だったのかもしれません。敏馬は難波津と淡路島の中間にある港、鞆の浦からさらに都に近づいたところで、妻のいない寂しさがますます募っています。「還るさ」の「さ」は、時・場面を表す接尾語で、帰りしなの意。「独りし」の「し」は、強意の副助詞。450の「行くさ」は、行きしな。「ふたり我が見し」は「二人」を強調した表現。「見もさかず」は、見ることもしないで。
ここの5首に共通して歌われているのは、「見る」という語です。上代人は、「見る」ことによって自身の魂振り(魂の再生)と密接な関係があると信じていたといいます。とくに446~448で歌われている、旅の途上において霊木を見ることは、生命の永遠性、従って旅の安全無事を保証することでありました。しかし、帰路に妻は亡く、その空しさは倍増して旅人の胸に迫っています。それでも、この「むろの木」に呼びかけ、哀願・祈念せずにはいられない旅人の気持ちが窺われます。
旅人は、亡き妻への思慕を歌った歌を13首作っています。万葉集の歌人のなかで、これほど多くの「亡妻挽歌」を歌った人はいません。また、短歌を連作として一まとまりの詠とするのは、旅人の創案によるといいます。
筑紫で妻を亡くし、都に戻った大伴旅人が作った歌
巻第3-451~453
| 451 人もなき空しき家は草枕(くさまくら)旅にまさりて苦しくありけり 452 妹として二人作りしわが山斎(しま)は木高く繁くなりにけるかも 453 我妹子(わぎもこ)が植ゑし梅の木見るごとに心(こころ)咽(む)せつつ涙し流る |
【意味】
〈451〉妻のいない空しい我が家は、異郷筑紫にあった時より辛く苦しいものだ。
〈452〉大宰府から京にたどり着いた。亡くなった妻と二人で作り上げたわが家の庭は、木がずいぶん高くなってしまった。
〈453〉我が妻が、庭に植えた梅の木を見るたび、胸が一杯になって涙にむせんでしまう。
【説明】
妻を亡くして帰京した作者が、わが家に帰り着いて作った歌。1首目で家を歌い、2首目で庭全体を歌い、3首目ではその中で妻が植えた梅の木をクローズアップして歌っています。451の「人もなき」の「人」は、妻を指します。「空しき家」は、空虚な家。「草枕」は「旅」の枕詞。旅人は大宰府を出発する前に「都なる荒れたる家にひとり寝ば旅にまさりて苦しかるべし」(440)と詠んでおり、それがまさに現実になったという嘆きの歌です。「苦しくありけり」の「けり」は、気づきの助動詞。452の「妹として」は、妻と協力して。「山斎」は、池や築山などのある庭。「木高く繁く」は、庭木が伸びて荒れているさま。都を出て4年ぶりに見た我が家の庭ですが、一緒に協力して作った妻はもういません。
453について、旅人が大宰府を発ったのが12月、陸路で1か月近く要しましたから、京に着いたのは1月に入ってのこと。ようやく家に帰り、妻との思い出がもっとも鮮明に残っている場所が、「山斎」だったようです。かつて妻が好んで植えた、あるいは梅を愛する旅人のために妻が植えてくれた梅の木は、すでに蕾を膨らませつつあったのかもしれません。植えた人は世を去ったのに、植えられた木はもうすぐ花を咲かせようとしている。その対照に、なおいっそう悲しみがこみあげています。「心咽せつつ」は、胸が一杯になる意。この歌をもって、旅人の亡妻挽歌は終わります。
そして正月27日、叙位が行われ、旅人は正三位から従二位へと昇進します。67歳にして人臣第一の地位に昇り詰めたことになり、父安麻呂の生前の正三位大納言を越えるものです。しかし、当時はすでに藤原四兄弟が政治的結束を固めつつあった時期であり、旅人は長老として祭り上げられたのみで、政治の動きを左右する力は持ち合わせていませんでした。自身はそこまで昇り詰めても素直に喜べるものではなかったはずです。なぜなら、それはあくまで花道として用意された位階・官職であり、それが継承され進展する条件は何もなく、大伴氏の将来にはむしろ暗澹たるものがあったからです。そして、帰京してわずか数か月の後に病の床に臥すことになり、天平3年(731年)秋7月に、67歳で亡くなりました。
巻第6-969~970
| 969 須臾(しましく)も行きて見てしか神名火(かむなび)の淵は浅(あ)せにて瀬にかなるらむ 970 指進(さしずみ)の栗栖(くるす)の小野の萩(はぎ)の花散らむ時にし行きて手向(たむ)けむ |
【意味】
〈969〉ほんのちょっとの間でも訪ねてみたいものだ。神名火の川の淵は、浅くなってしまって、今では瀬になっているのではなかろうか。
〈970〉栗栖の小野に咲く萩の花、その花が散る頃には、きっと出かけていって、神社にお供えをしよう。
【説明】
天平3年(731年)に「大納言大伴卿の奈良の家に在りて故郷を思(しの)へる」歌2首。大宰府から帰京して間もなく、旅人は病に臥せってしまいます。その孤愁の病床にあって、旅人の胸に去来したのは、自分の本当の故郷であったようです。大伴氏の荘園として、竹田庄(橿原市東竹田町)や跡見庄(桜井市外山)が知られており、一族の本拠もこの辺りだったと考えられ、従って旅人は平城京遷都までの30年間をこの地で過ごしてきたことになります。念願の都に帰っても、妻のいない家に失望し、心がまっすぐ大和へと向かうのは、何よりもそこが最後に身を預けるべき安住の地だとの思いがあったからでしょう。
969の「須臾も」は、ちょっとの間でも。「見てしかの「てしか」は、願望。「神名火の淵」の「神名火」は、神の来臨される場所。ここは、飛鳥川の雷丘(いかづちのおか)付近の淵。「浅せにて」の原文「浅而」は訓みが定まっていませんが、浅くなって、の意。「瀬にかなるらむ」の「か」は疑問、「らむ」は現在推量。970の「指進の」は意味不詳ながら、大工の用いる墨斗(すみさし)のことで、それを繰って墨糸を出す意から「繰る」と続け、同音で「栗栖」へ続けたのだろうといわれます。「栗栖」は、明日香の小地名か。「小野」の「小」は、美称。「散らむ時にし」は、散るであろう時に。「し」は、強意の副助詞。「手向けむ」は、神に物を供えよう。
丈夫(ますらお)の旅人も、最晩年は、妻の死、老齢、病気、そして時流の変化のなかで、さすがに心の弱りを見せており、この2首は辞世の句とも受け取れる内容になっています。7月になり、結局、旅人は、念願の生まれ故郷に戻ることも叶わず、大伴氏の将来とまだ14歳の家持の行く末を案じつつ、遂に帰らぬ人となりました。家持や異母妹の坂上郎女に看取られながらの最期、時に67歳。無念の重なる晩年でしたが、遂にこの世の長い旅を終えたのでした。
大伴旅人が亡くなった時に余明軍が作った歌ほか
巻第3-454~458
| 454 はしきやし栄(さか)えし君のいましせば昨日(きのふ)も今日(けふ)も我(わ)を召さましを 455 かくのみにありけるものを萩(はぎ)の花咲きてありやと問ひし君はも 456 君に恋ひいたもすべなみ蘆鶴(あしたづ)の音(ね)のみし泣かゆ朝夕(あさよひ)にして 457 遠長(とほなが)く仕(つか)へむものと思へりし君しまさねば心どもなし 458 みどり子の這(は)ひた廻(もとほ)り朝夕(あさよひ)に音(ね)のみそ我(あ)が泣く君なしにして |
【意味】
〈454〉ああ、お慕わしい、あれほどに栄えたわが君がご健在でおられたら、昨日も今日も私をお呼びになったはずなのに。
〈455〉こんなにもはかなくなられるお命であったのに、「萩の花は咲いているか」とお尋ねになったあなた様でありました。
〈456〉わが君をお慕いしながら、葦辺に騒ぐ鶴のように、ただ泣くばかりで他になすすべがありません、朝も夕べも。
〈457〉いついつまでも末長くお仕えしようと思っておりました我が君が、この世においでにならないので、心の張りが抜けてしまいました。
〈458〉幼児のように這い回り、朝にも夕べにも、声をあげて泣くばかりいます。我が君がおいでにならなくて。
【説明】
妻を亡くして帰京した旅人は、甚だしく気落ちしてしまったのか、その翌年の天平3年(731年)秋7月に亡くなります。この歌は、その時に資人(つかいびと:従者)の余明軍(よのみょうぐん)が「犬馬の慕(したひ)に勝(あ)へずして(犬馬が飼い主を慕うように主人を慕う心中の思いに耐えきれず)」詠んだ歌とあります。余明軍は、百済の王族系の人で、「余」が氏、「明軍」が名。帰化して大伴旅人の資人となった人です。ただ、その時期についてははっきりしていません。
これらの歌には少しも儀礼的な歌い方はなく、ひたすら主人としての旅人を懐かしむ哀切の気持ちが率直に歌われています。とくに455は、明軍が重病の床にあった主人から尋ねられた言葉を思い出し、生死のほども測られない時に、秋の萩の花に関心をもって尋ねるというのはいかにも優しい心と思え、忘れ難い言葉であったろうと察せられるところです。
454の「はしきやし」は、ああ慕わしい、ああ愛しい、と哀惜や追慕の感情をあらわす語。「召さましを」の「まし」は、反実仮想の助動詞。456の「かくのみに」の「かく」は、旅人の死を指します。「いたもすべなみ」は、ひどくて仕方がないので。「蘆鶴の」は、葦辺にいる鴨が声を立てて鳴くことから、「音のみし泣かゆ」に掛かる比喩的枕詞。457の「心ど」は原文「心神」で、気力。458の「みどり子」は、3歳くらいまでの赤子、幼児のことで、「這ひた廻り」の枕詞。「た廻り」の「た」は、語調を整える接頭語。「廻り」は、徘徊して、廻って。
なお、余明軍は、1年間の服喪を終えて解任され、式部省に送られることになりましたが、その際に家持に与えた歌が、巻第4-579~580に載っています。
巻第3-459
| 見れど飽(あ)かずいましし君が黄葉(もみちば)の移りい行(ゆ)けば悲しくもあるか |
【意味】
見ても見ても見飽きることのなく立派でいらした君が、黄葉の散りゆくように逝ってしまわれたので、何とも悲しくてならない。
【説明】
左注に次のような説明があります。「内礼正の県犬養宿祢人上(あがたのいぬかいのすくねひとかみ)が勅により遣わされ、旅人卿に医薬を給わったがその効なく、逝く水留まらず。そこで悲しんでこの歌を作った」。「内礼正」は、中務省所管の、宮中の礼儀・非違を検察する役所の長官。「逝く水留まらず」は、旅人の死を喩えた中国の成語。「見れど飽かず」は、幾度見ても見飽きない、の意で、最も良いものや人に対しての讃詞として成語となっていたもの。「移りい行けば」の「い」は、接頭語。色あせる・衰える・散るなどの変化を示す意で、黄葉の散るのを旅人の死に譬えています。「悲しくもあるか」の「か」は、詠嘆。
【PR】
大伴家の人々
大伴安麻呂
壬申の乱での功臣で、旅人・田主・宿奈麻呂・坂上郎女らの父。大宝・和銅期を通じて式部卿・兵部卿・大納言・太宰帥(兼)となり、和銅7年(714年)5月に死去した時は、大納言兼大将軍。正三位の地位にあった。佐保地内に邸宅をもち、「佐保大納言卿」と呼ばれた。
巨勢郎女
安麻呂の妻で、田主の母。旅人の母であるとも考えられている。安麻呂が巨勢郎女に求婚し、それに郎女が答えた歌が『万葉集』巻第2-101~102に残されている。なお、大伴氏と巨勢氏は、壬申の乱においては敵対関係にあった。
石川郎女(石川内命婦)
安麻呂の妻で、坂上郎女・稲公の母。蘇我氏の高貴な血を引き、内命婦として宮廷に仕えた。安麻呂が、すでに巨勢郎女との間に旅人・田主・宿奈麻呂の3人の子供をもうけているにもかかわらず、石川郎女と結婚したのは、蘇我氏を継承する石川氏との姻戚関係を結びたいとの理由からだったとされる。
旅人
安麻呂の長男で、母は巨勢郎女と考えられている。家持・書持の父。征隼人持節使・大宰帥をへて従二位・大納言。太宰帥として筑紫在任中に、山上憶良らとともに筑紫歌壇を形成。安麻呂、旅人と続く「佐保大納言家」は、この時代、大伴氏のなかで最も有力な家柄だった。
稲公(稲君)
安麻呂と石川郎女の子で、旅人の庶弟、家持の叔父、坂上郎女の実弟。天平2年(730年)6月、旅人が大宰府で重病に陥った際に、遺言を伝えたいとして、京から稲公と甥の古麻呂を呼び寄せており、親しい関係が窺える。家持が24歳で内舎人の職にあったとき、天平13年(741年)12月に因幡国守として赴任している。
田主
安麻呂と巨勢郎女の子で、旅人の実弟、家持の叔父にあたる。『万葉集』には「容姿佳艶、風流秀絶、見る人聞く者、嘆せずといふことなし」と記され、その美男子ぶりが強調されている。しかし、兄弟の宿奈麻呂や稲公が五位以上の官職を伴って史書にしばしば登場するのに対し、田主は『続日本紀』にも登場しない。五位以上の官位に就く前に亡くなったか。
古麻呂
父親について複数の説があり確実なことは不明。長徳あるいは御行の子とする系図も存在するが、『万葉集』には旅人の甥とする記述がある。旅人の弟には田主・宿奈麻呂・稲公がいるので、古麻呂はこのうち誰かの子であったことになる。天平勝宝期に左少弁・遣唐副使・左大弁の職をにない正四位下となる。唐から帰国するとき、鑑真を自らの船に載せて日本に招くことに成功した。のち橘奈良麻呂らによる藤原仲麻呂の排除計画に与し、捕縛されて命を落とした。
坂上郎女
安麻呂と石川郎女の子で、旅人の異母妹、家持の叔母にあたる。若い時に穂積皇子に召され、その没後は藤原不比等の子・麻呂の妻となるが、すぐに麻呂は離れる。後に、前妻の子もある大伴宿奈麻呂(異母兄)に嫁して、坂上大嬢と二嬢を生む。後に、長女は家持の妻となり、次女は大伴駿河麻呂(おおとものするがまろ)の妻となった。家持の少・青年期に大きな影響を与えた。
書持
旅人の子で、家持の弟。史書などには事績は見られず、『万葉集』に収められた歌のみでその生涯を知ることができる。天平18年(746年)に若くして亡くなった。
池主
出自は不明で、池主という名から、田主の子ではないかと見る説がある。家持と長く親交を結んだ役人として知られ、天平年間末期に越中掾を務め、天平18年(746年)6月に家持が越中守に任ぜられて以降、翌年にかけて作歌活動が『万葉集』に見られる。
【PR】
 |
古典に親しむ
万葉集・竹取物語・枕草子などの原文と現代語訳。 |
バナースペース
【PR】
大宰府の官職
帥(そち:長官)
従三位
弐(すけ)
大弐・・・正五位上
少弐・・・従五位下
監(じょう)
大監・・・正六位下
少監・・・従六位上
典(さかん)
大典・・・正七位上
少典・・・正八位上
その他、大判事、少判事、大工、防人正、主神などの官人が置かれ、その総数は約50名。
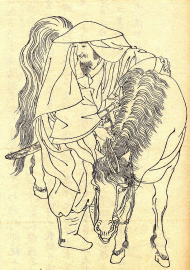
(大伴旅人)
万葉時代の年号
645~650年
白雉
650~654年
朱鳥まで年号なし
朱鳥
686年
大宝まで年号なし
大宝
701~704年
慶雲
704~708年
和銅
708~715年
霊亀
715~717年
養老
717~724年
神亀
724~729年
天平
729~749年
天平感宝
749年
天平勝宝
749~757年
天平宝字
757~765年

資人(しじん)
「位分資人」は一位に 100人、二位に 80人、三位に 60人、四位に 40~35人、五位に 25~20人がつけられた。「職分資人」は太政大臣に 300人、左右大臣に 200人、大納言に 100人がつけられ、ともに主人の警固や雑役に従事した。
大伴旅人が亡くなった時に5首の歌(巻第3-454~458)を詠んだ余明軍(よのみょうぐん)は、旅人の資人だったとされます。