
紀女郎(きのいらつめ)の歌
巻第4-643~645
| 643 世間(よのなか)の女(をみな)にしあらば我(わ)が渡る痛背(あなせ)の河を渡りかねめや 644 今は吾(あ)は侘(わ)びそしにける息(いき)の緒(を)に思ひし君をゆるさく思へば 645 白妙(しろたへ)の袖(そで)別るべき日を近み心にむせび哭(ね)のみし泣かゆ |
【意味】
〈643〉私が世間一般の女だったら、恋しい人のもとへ行くため、この痛背川をどんどん渡っていき、渡りかねてためらうなどということは決してないでしょう。
〈644〉今となっては、私は苦しみに沈むばかりです。命のように大切だったあなたなのに、とうとうお別れすると思うので。
〈645〉白い夜着の袖を分かつ日が近づいたので、その悲しみに心が咽び、声をあげて泣いてばかりいます。
【説明】
紀女郎の怨恨の歌3首。紀女郎は紀朝臣鹿人(きのあそみかひと)の娘で、名を小鹿(おしか)といいます。紀氏は、現在の和歌山市一帯を本拠地とした古い由緒のある豪族です。紀女郎は、養老年間(717~724年)に安貴王(あきのおおきみ:志貴皇子の孫で春日王の子)に娶られましたが、彼女が17歳の時に事件が起きます。夫の安貴王が、因幡の八上采女(やがみのうねめ)と契りを結び、その関係が世間の人に知られることとなったのです。不敬罪が定まり、勅命によって采女は本郷の因幡国に帰されました。しかし、そうした一大スキャンダルの中でも、夫は妻の紀女郎に謝罪するどころか、引き離された愛人を思い続け、せっせと歌を書き送るというありさまでした。
643の「世の中の」は、世間一般の。「女にしあらば」の「し」は、強意の副助詞。「痛背川」は、三輪山の北麓を流れる巻向川のこと。「あな背」(ああ、あなた)と嘆く意も込められています。「渡りかねめや」の「や」は、反語。怒りに震える紀女郎は、夫を問い詰めるため、二人の家の間にある痛背川を渡ろうとしつつ、なかなか足を踏み出せない、でも渡ろうと意を強めています。川を渡るというのは、本来は恋を成就させる行為であるはずなのに、また夫が渡るべきものなのに、自分は何という悲しい思いで渡るのだろうかと心打ちひしがれています。
644の「侘びぞしにける」は、落胆するばかりだ。「息の緒に」は、命にかけて、命の限りの意の慣用句。「君を」は、君なのに。「ゆるさく」は「ゆるす」のク語法の名詞形で、自由にさせること、手放すこと。「思へば」は、思っているので。前の歌から時間が経過し、夫の気持ちを理解したのか、もはや戻らぬ愛とあきらめ、心を鎮めていくようすがうかがえます。
645の「白妙の」は「袖」の枕詞。「袖別る」は、袖を分かつ、つまり夫婦が別れる意。「日を近み」は、日が近いので。「哭のみし泣かゆ」の「し」は強意の副助詞で、声を立ててただ泣けてくる。夫から疎遠にされ、やがて別れの日が来るのを予想して嘆いているもので、前の2首のような激しい憤りを帯びていません。そのことから、前の2首より後のものではなく、前のものだろうとする見方があります。これらの歌に対し、あまり感情的な批評を加えない契沖でさえ、「アハレナル歌ナリ。女ハカク有ベキ事ナリ」と言っています(『代匠記』)。
安貴王(あきのおほきみ)の歌
巻第4-534~535
| 534 遠妻(とほづま)の ここにしあらねば 玉桙(たまほこ)の 道をた遠(どほ)み 思ふそら 安けなくに 嘆くそら 苦しきものを み空行く 雲にもがも 高飛ぶ 鳥にもがも 明日(あす)行きて 妹(いも)に言問(ことど)ひ 我(あ)がために 妹も事(こと)なく 妹がため 我(あ)れも事なく 今も見るごと たぐひてもがも 535 しきたへの手枕(たまくら)まかず間(あひだ)置きて年そ経(へ)にける逢はなく思へば |
【意味】
〈534〉妻は遠くの地にいてここにはいない。妻のいる所への道は遠く、逢う手立てのないまま、妻を思って心が休まらず、嘆くばかりで苦しくてならない。大空を流れ行く雲になりたい、高く飛ぶ鳥になりたい。そうして明日にでも行って妻に話しかけ、私のために妻が咎められることなく、妻のためにこの私も無事でありたい。今でも面影に見るように、互いに寄り添っていたい。
〈535〉共寝できなくなってからとうとう年を越してしまった。逢えなくなってからもうそんなにも。
【説明】
安貴王は、志貴皇子の孫、市原王の父。天平元年(729年)従五位下、同17年、従五位上。左注には「安貴王、因幡の八上采女(やがみのうねめ)を娶る。係念きはめて甚しく、愛情もとも盛りなり。時に勅して、不敬の罪に断め、本郷に退却く。ここに、王の意悼び悲しびて、いささかにこの歌を作る」とあります。安貴王の八上采女への懸想と愛情の程度があまりに甚だしく、また、采女と関係を持つことは固く禁じられていましたから、二人の恋は勅命によって不敬罪に断じられ、采女は本郷の因幡国に帰されました。歌の前後の配列から、神亀元年(724年)、聖武天皇が即位した年の出来事とみられています。安貴王に対する処罰内容は明らかではありませんが、後に赦され従五位下に叙爵されています。(処罰され本郷に帰されたのは安貴王の方だとする見方もあります)
534の「遠妻」は、遠くに離れている妻、八上采女を指します。「玉桙の」は「道」の枕詞。「た遠み」の「た」は、接頭語。遠いので。「思ふそら」の「そら」は気持ち。「安けなくに」の「安け」は形容詞の未然形。「なく」は、否定の助動詞「ず」の未然形「な」に「く」を添え名詞形としたもの。「み空」の「み」は、美称。「雲にもがも」の「もがも」は、願望の助詞。「言問ひ」は、物を言い。「事なく」は、無事に。「今も見るごと」の「見る」は、ここでは面影に見る意。「たぐひてもがも」の「たぐふ」は、一緒にいる、並ぶ意。なお、歌の最後が5・7・7・7の形で終わっているのは歌いものに多く見られることから、安貴王の作ではなく、事件が知られて、誰かがこういうふうに歌ったのではないかとする見方や、あるいは「我れも事なく」の下に1句5字が脱落したのではないかとの見方があります。
535の「しきたへの」は「枕」の枕詞。「手枕まかず」は、共寝をせずに、の意。「間置きて」の「間」は、時。「年そ経る」は、年が改まったことを言います。「逢はなく」は「逢はず」のク語法で名詞形。
安貴王と別れた紀女郎は、その後、年若い大伴家持と出会い、恋歌を交わしています。家持は、安貴王の息子、市原王の友人でありました。
⇒紀女郎と大伴家持の歌(巻第4-762~764,775~776ほか)
巻第8-1555
| 秋立ちて幾日(いくか)もあらねばこの寝(ね)ぬる朝明(あさけ)の風は手本(たもと)寒しも |
【意味】
秋が立ってまだ幾日も経っていないのに、起き抜けのこの夜明けの風は、袂(たもと)に寒く吹いている。
【説明】
秋の季節感を言っている歌です。『拾遺集』には、「秋たちていくかもあらねどこの寝ぬる朝明の風は袂涼しも」として載っています。「朝明」は、朝明けの約。「手本」は、手首のあたり。筒袖の袖口。「も」は、詠嘆。
なお、『万葉集』には、春の到来や秋の到来を「春立つ」「秋立つ」と表現する歌が散見されます。これらは二十四節気の「立春」「立秋」から来ているともいわれますが、しかし「立夏」「立冬」に対応するはずの「夏立つ」「冬立つ」の表現は見られません。「立つ」とは、神的・霊的なものが目に見える形で現れ出ることを意味する言葉であることから、農耕生活にもっとも大切な季節とされた春と秋が、そうした霊威の現れとして意識されていたと窺えます。
【PR】
三大歌集の比較
■万葉集
①歌を呪術とする意識が残り、対象にはたらきかける積極的な勢いが、力強く荘重な調べとなる。
②実感を抑えず飾らず大胆率直に表現する。簡明にして力強く、賀茂真淵は「ますらをぶり」と評する。
③日常生活そのままでないにしても、現実の体験に即して歌うことが多く、具象的、写実的で印象が鮮明。
④用語、題材についてすでに雅俗を分かつ意識が生じているが、なお生活に密着したものが比較的多く、素朴、清新の感をもって訴えかける。時に粗野。
⑤五七調で、短歌は二句切れ、四句切れが多く、重厚な調べ。後期には七五調も現れる。歌謡の名残をとどめ音楽的効果をねらった同音同語の反復もある。
⑥素朴な枕詞、序詞を多用。ほかに掛詞、比喩、対句を使用。
⑦率直に表現するため、断言的な句切れが多い。終助詞による終止、詠嘆「も」「かも」を多用。
■古今集
①宗教や政治を離れ、歌それ自体が目的となり、洗練された表現により美の典型をひたすら追求する。
②感情を生のまますべてを表すことを避け、屈折した表現をとる。その婉曲さが優美繊細の効果を生む。
③日常体験から遊離した花鳥風月や恋・無常など、情趣化された世界を機知に富んだ趣向や見立てにより表現する。理知がまさり、時に観念の遊戯に陥る。
④優雅の基準にかなう題材を雅かなことばで詠ずるため、流麗であるが、単調となる弊がある。
⑤七五調で、三句切れが多く、流暢な調べとなる。
⑥掛詞、縁語の使用が多い。それらが観念的な連想を生み、虚実あるいは主従二様のイメージを交錯させ、纏綿たる情緒を楽しませる。掛詞がさらに進んでことばの遊戯となったものが物名であり、それで一巻をなす。ほかに枕詞、序詞、比喩、擬人法などを用いる。
⑦理知的に屈折した表現をとるため、推量、疑問、反語による句切れが多い。助動詞による終止が目立つ。詠嘆の終助詞は「かな」を用いる。
■新古今集
①乱世の現実を忌避し、王朝に憧れる浪漫的な気分が支配し、唯美的、芸術至上主義的な立場に立つ。
②世俗的な感情を拒否し、「もののあはれ」という伝統的な感覚を象徴的な手法で縹渺とただよわせる。幽玄余情の様式を完成するが、時に晦渋に陥る。
③客観的具象的な世界を浪漫的な心情風景に再構成し、現実を超えた絵画あるいは物語のごとき世界をつくる。
④選び抜かれた素材を言語の論理性を超えた技巧によって表現し、幽玄妖艶の美、有心の理念を追求する。
⑤七五調で、三句切れが多く、また初句切れも目立つ。
⑥掛詞、縁語、比喩はかなり用いられるが、枕詞、序詞の使用は著しく減少する。古歌の句を借用しただけの単純な本歌取りは古今集にもみられるが、新古今集では高度な表現技法にまで磨かれ、物語的な情緒を醸し出す象徴の手法として用いられる。
⑦体言止めを多く用いる。
【PR】
 |
古典に親しむ
万葉集・竹取物語・枕草子などの原文と現代語訳。 |
バナースペース
【PR】
万葉集の代表的歌人
磐姫皇后
雄略天皇
舒明天皇
有馬皇子
中大兄皇子(天智天皇)
大海人皇子(天武天皇)
藤原鎌足
鏡王女
額田王
第2期(白鳳時代)
持統天皇
柿本人麻呂
長意吉麻呂
高市黒人
志貴皇子
弓削皇子
大伯皇女
大津皇子
穂積皇子
但馬皇女
石川郎女
第3期(奈良時代初期)
大伴旅人
大伴坂上郎女
山上憶良
山部赤人
笠金村
高橋虫麻呂
第4期(奈良時代中期)
大伴家持
大伴池主
田辺福麻呂
笠郎女
紀郎女
狭野芽娘子
中臣宅守
湯原王
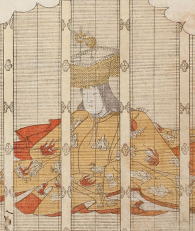
(持統天皇)

(山部赤人)

(大伴旅人)
【PR】
