
豊浦寺の尼の歌
巻第8-1557~1559
| 1557 明日香川(あすかがは)行き廻(み)る丘(をか)の秋萩(あきはぎ)は今日(けふ)降る雨に散りか過ぎなむ 1558 鶉(うづら)鳴く古(ふ)りにし里の秋萩(あきはぎ)を思ふ人どち相(あひ)見つるかも 1559 秋萩(あきはぎ)は盛(さか)り過ぐるを徒(いたづら)にかざしに挿(さ)さず帰りなむとや |
【意味】
〈1557〉飛鳥川が裾を流れる丘に咲いている萩の花は、今日降っている雨のために散ってしまわないだろうか。
〈1558〉寂しい古里に咲く萩の花を、気の合った人たちが集まってご一緒に眺めたことです。
〈1559〉萩の花が盛りを過ぎようとしているのに、むなしくそのまま髪に挿すこともなく、お帰りになるというのですか。
【説明】
旧都・飛鳥の豊浦(とゆら)寺の尼が、自分の房で宴会した時の歌。豊浦寺はわが国最初の尼寺とされ、飛鳥の雷丘(いかずちのおか)の麓にありました。その私房(尼の私室)で、男も参加しての宴会が開かれました。その男というのが丹比真人国人(たじひのまひとくにひと)で、1557は国人の歌、1558・1559は、沙弥の尼たちが詠んだ歌です。国人はこのころ従五位か四位の中堅官僚で、のち、遠江守の時に、橘奈良麻呂の乱で奈良麻呂側に与したために伊豆に配流された人物です。
1557の「明日香川」は、奈良県高市郡の高取山に発し、雷丘と甘樫丘との間を過ぎ、藤原京の南部を斜めに横切り大和川に注ぐ川。「丘」は雷丘のことで、都が飛鳥にあった時代は尊く畏れる丘とされていましたが、旧都となったこの頃には、萩の多い丘だったとみえます。満開の萩の花を見ることができた喜びを、宴の客の立場で歌っています。1558は、それに答えた歌。「鶉鳴く」の「鶉」は、荒れた地に棲むところから「古り」にかかる枕詞。「思ふどち」は、気の合った者同士。趣味を同じくする客人を迎えて萩の花を見ることができた喜びを、主人の立場から歌っています。1559、は別れを惜しみ、客人を引き留めようとする儀礼の歌です。「徒に」は、むなしく。「かざし」は、髪刺しの略で、花や小枝を折って髪飾りにしたもの。「帰りなむとや」の「と」は、引用を表す助詞。「や」は、疑問の助詞。
当時は「僧尼令」という法律によって、僧尼の飲酒が禁じられており、反すると30日の労役が課されたといいます。宴というからには酒肴も並んだと思われますが、ましてや男も交えての宴に、いったいどんないきさつがあったのでしょうか。ここの尼は「沙弥尼(さみに)等」とあり、正式な尼である「比丘尼(びくに)」ではなく修行中の尼だったので、そうしたことも許されていたのでしょうか。なお、宴席では、時の花を「かざしに挿す」風習があったようで、非日常的な状態に転位するための装いだったとされます。一方では男女の抱擁を意味するとの指摘もあります。
仏前の唱歌
巻第8-1594
| 時雨(しぐれ)の雨(あめ)間(ま)なくな降りそ紅(くれなゐ)ににほへる山の散らまく惜(を)しも |
【意味】
しぐれ雨よ、そんなに絶え間なく降らないでくれ。紅に色づいた山の紅葉が散ってしまうのが惜しいではないか。
【説明】
左注に「冬十月(天平11年10月)、皇后の宮(光明皇后)の維摩講(ゆいまこう)の結願の日に、大唐・高麗等の種々の音楽を供養し、そのときこの歌を歌った。琴を弾いたのは市原王(いちはらのおおきみ)、忍坂王(おさかのおおきみ:後に姓(かばね)大原真人赤麻呂を賜わった〉、歌子(歌い手)は田口朝臣家守(たぐちのあそみやかもり)、河辺朝臣東人(かわへのあそみあずまひと)、置始連長谷(おきそめのむらじはつせ)など十数人だった」旨の記載があります。
維摩講は、維摩経を講ずる法会のこと。藤原鎌足が始めたもので、死後30年間絶えていたのを不比等が再興し、天平5年(733年)以降、毎年10月10日から16日まで興福寺で行われました。ここは、光明皇后の祖父・藤原鎌足の70周忌の供養のため、皇后宮で営まれたもの。維摩経は、維摩羅詰(維摩居士)の教理を記した経典で、維摩経を講ずるのは僧侶ですが、この唱歌が琴にあわせて歌子(うたびと)の十数人によって唱われたようです。和歌が仏教にも取り入れられたという、文化的な発展が窺えます。
この歌の作者は、不明。「時雨」は、晩秋から初冬にかけて降る小雨。「間なくな降りそ」の「な~そ」は、懇願的な禁止。「紅ににほへる山」は、紅葉に照り映えている山。鎌足の人生を象徴した表現です。「散らまく」は「散らむ」のク語法で名詞形。
丹比真人の歌
巻第8-1609
| 宇陀(うだ)の野(の)の秋萩(あきはぎ)しのぎ鳴く鹿も妻に恋ふらく我(わ)れにはまさじ |
【意味】
宇陀の野の秋萩を押し分けて鳴く鹿も、妻に恋い焦がれることでは、この私にはかなうまい。
【説明】
丹比真人(たじひのまひと)は、注に「名は欠けたり」とあり、伝未詳。巻第2-226、巻第9-1726にも「丹比真人」とだけ記されて名を欠く人物の作歌があります。巻第8には、丹比真人屋主(1442)、丹比真人乙麻呂(1443)、丹比真人国人(1557)の名が見えますが、この3人のうちの誰かなのか、また全くの別人なのか分かりません。「宇陀の野」は、奈良県宇陀市大字宇陀にある野で、草壁皇子の御狩場だった地。「しのぎ」は、押し分けて、押し伏せて。「恋ふらく」は「恋ふ」のク語法で名詞形。秋、萩を凌いで妻恋いをする牡鹿の声に触発され、妻への恋しさを訴えた歌です。
巻第9-1726~1727
| 1726 難波潟(なにはがた)潮干(しほひ)に出でて玉藻(たまも)刈る海人娘子(あまのをとめ)ら汝(な)が名(な)告(の)らさね 1727 あさりする人とを見ませ草枕(くさまくら)旅行く人に妾(あれ)は敷(し)かなく |
【意味】
〈1726〉難波潟の潮が引いた浜に出て、玉藻を刈り取っている海人の娘さん、あなたの名を教えてください。
〈1727〉ただ玉藻を刈っている賤しい者とだけ見ておいてください。旅行く立派なお方には及びもつかない私です。
【説明】
1726の「難波潟」は、難波宮に近い海岸。「潮干」は、潮が引いた後の海岸。「玉藻」の「玉」は、美称。「海人娘子ら」の原文「海未通等」は「女」の字が漏れているとされます。「等」をドモと訓むか、ラと訓むか両様考えられますが、呼びかけて求婚する場合であるので単数であるべきとの立場に従い、「ら」は接尾語と見ます。「告らさね」の「さ」は敬語、「ね」は願望で、言ってほしい。
1727は、それに答えた歌。作者名が記されていないので、同じ丹比真人の作とされます。「あさり」は、魚介や海藻をとること。「人とを見ませ」の「を」は詠嘆で、人と見てください。「草枕」は「旅」の枕詞。なお、「妾は敷かなく」の原文「妾者不敷」は「妾名者不教」の誤りだとして「ワガ名ハノラジ」と訓む立場もあります。しかし窪田空穂は、「旅人であるがゆえに拒むというのは、意としては通じやすいが、そのために誤写説を設けた迎えての解である」と批判しており、ここは上掲どおり「我が身分は及ぼない」として拒んだとする解釈に従います。宴で作者が披露した歌であろうとされ、また、巻第5にある「松浦河に遊ぶ序」あるいは『游仙窟』のような漢籍に影響されて作ったものだろうとの見方があります。
笠縫女王の歌
巻第8-1611
| あしひきの山下(やました)響(とよ)め鳴く鹿の言(こと)ともしかも我(わ)が心夫(こころつま) |
【意味】
山の麓まで響かせて妻を呼んで鳴く鹿の声に心惹かれるように、あなたのお言葉が懐かしく思われます。わが心に秘めたお方よ。
【説明】
笠縫女王(かさぬいのおおきみ)は、題詞の下に「六人部王(むとべのおおきみ)の娘、母は田形皇女(たがたのひめみこ)という」との注記があるものの、それ以外の伝は不明。六人部王(身人部王とも記す)は、和銅3年(710年)従四位下、天平元年(729年)正四位上にて没。風流侍従の一人だった人。田形皇女は、天武天皇の皇女。笠縫女王の歌は『万葉集』にはこの1首のみ。
「あしひきの」は「山」の枕詞。「山下」は、山の麓。上3句は「言ともし」を導く序詞。「ともし」は、羨ましい、心惹かれる、懐かしい。序詞からの続きでは鹿の声について、下への続きでは消息について言っています。「心夫」は、心中で思っている夫、心の中で夫と決めた人。牡鹿がはげしく妻恋いの声をあげているのを聞き、それがうらやましくてならず、自分も意中の人の言葉に触れたいとの女心を詠んだ歌、あるいは、疎遠になった夫に訴えかけたものとも取れます。
石川賀係女郎の歌
巻第8-1612
| 神(かむ)さぶと否(いな)にはあらず秋草の結びし紐(ひも)を解(と)くは悲しも |
【意味】
もう年だからといってあなたを拒むわけではありません。秋草のようにしっかりと結んだ、この紐を解くのが悲しいのです。
【説明】
石川賀係女郎(いしかわのかけのいらつめ)は、伝未詳。「神さぶ」は神々しくなる意ですが、ここは年老いる意。「否にはあらず」は、拒むわけではない。「秋草の」は、草結びをする意で「結びし」にかかる枕詞。集中ではこの一例のみ。「結びし紐」は、決して解くまいと誓って結んだ下着の紐。「解くは悲しも」の「解く」は、男の求婚を受け入れる意。「も」は、詠嘆。求婚を婉曲に断った歌、あるいは、もう男には逢うまい、共寝をすまいと心に誓ったことを言っている歌とされます。
紀女郎が大伴家持に贈った歌のなかに「神さぶと否にはあらずはたやはたかくして後に寂しけむかも」(巻第4-762)という、同じ言い方をした歌があります。「神さぶと否にはあらず」は、年上の女が相手の男に対して用いる常套句だったのかもしれません。
石川卿の歌
巻第9-1728
| 慰(なぐさ)めて今夜(こよひ)は寝なむ明日(あす)よりは恋ひかも行かむ此(こ)ゆ別れなば |
【意味】
慰め合って今夜は寝よう。明日からは、あなたを恋いつつ旅行くことになるのだろうか。ここを別れて発ったなら。
【説明】
石川卿(いしかわのまえつきみ)が誰であるかは不明で、天平宝字6年(762年)に正三位で没した石川年足(いしかわのとしたり)、あるいは和銅6年(713年)に従三位で没した石川宮麻呂かともいわれます。「慰めて」は、心を安らげ、なごまして、で、別れの前夜のこと。「恋ひかも行かむ」の「かも」は疑問、「む」は推量。「此ゆ別れなば」の「ゆ」は、起点・経過点を示す格助詞で、ここを発って別れたら。宮人として旅をして、ある地で契った女と別れを惜しむ心の歌です。窪田空穂は、「別れの歌としては心の淡いものであるが、これは双方の身分に関係してのことであろう」と述べています。
一方で、女との共寝が実現できず、一人で気を紛らせて寝るのであり、その不満足感が尾を引いて明日からの旅路が思いやられる、と解釈する立場もあります。宴席に侍る女性にそのように言って愚痴っぽく口説いた歌ではないか、と。
碁師の歌
巻第9-1732~1733
| 1732 大葉山(おほばやま)霞(かすみ)たなびきさ夜(よ)更(ふ)けて我(わ)が舟(ふね)泊(は)てむ泊(とま)り知らずも 1733 思ひつつ来(く)れど来(き)かねて三尾(みを)の崎(さき)真長(まなが)の浦(うら)をまたかへり見つ |
【意味】
〈1732〉大葉山に霞がかかり、夜も更けてきたというのに、われらの舟を泊める港が分からない。
〈1733〉思いを残して来はしたたが、やはり素通りしかねて、三尾の崎やら真長の浦を幾度も振り返って見たことだ。
【説明】
碁師(ごし)がどういう人であるか不明で、碁氏出身の法師、あるいは碁打ちかともいわれます。1732は、巻第7-1224の作者未詳歌との重出。「大葉山」は、紀伊国の山とされますが、近江国の説もあり、所在未詳。海または湖に近く、航海の目標になった山と見られます。「さ夜」の「さ」は、接頭語。「霞」は、ここは夜霧。「知らずも」の「も」は、詠嘆。
1733は、琵琶湖を舟行した時の歌。「思ひつつ」は、発って来た地(港町)で歓待してくれた人々(女たち)を思いながら。「三尾の崎」「真長の浦」は、いずれも琵琶湖西岸の高島市の地。三尾は、水陸の交通の要衝であったと共に、軍事上の要地でもあり、壬申の乱や藤原仲麻呂の乱で戦場となった所です。この歌は、あるいは前歌の続きからすると、停泊する港を探しあぐねて、通り過ぎた真長の浦あたりで停泊すべきだったと歌っているものかも知れません。
小弁の歌ほか
| 1734 高島(たかしま)の安曇(あど)の港を漕(こ)ぎ過ぎて塩津(しほつ)菅浦(すがうら)今か漕ぐらむ 1735 我(わ)が畳(たたみ)三重(みへ)の川原(かはら)の礒(いそ)の裏(うら)にかくしもがもと鳴くかはづかも 1736 山(やま)高(たか)み白木綿花(しらゆふはな)に落ちたぎつ夏身(なつみ)の川門(かはと)見れど飽かぬかも 1737 大滝(おほたき)を過ぎて夏身(なつみ)に近づきて清き川瀬を見るが明(さや)けさ |
【意味】
〈1734〉高島の安曇の港を漕ぎ過ぎて、今ごろは、塩津か菅浦あたりを漕いでいるのだろうか。
〈1735〉三重の川原の岩蔭で、かくしもがも(いつまでもこうしていられたら)と鳴いているように聞こえる河鹿であるよ。
〈1736〉山が高いので、水が真っ白な白木綿のように落ちて激するこの夏身の川門は、見ても見ても見飽きない。
〈1737〉大滝を通り過ぎ、夏身の川原に近づいてその清らかな川瀬を見ると、実に心さわやかであることよ。
【説明】
1734は、小弁(しょうべん)の歌。小弁は名か官名か不明で、1719の左注にも出た名です。弁官の官名であるなら「少弁」と記すはずであり、春日蔵首老の僧名が弁基であったことから、僧時代の「小弁」の通称(あだ名)が還俗後にも用いられたのではないかとの見方があります。「高島の阿渡の湊」は、滋賀県高島市の安曇川の河口。「塩津」は、琵琶湖北端の塩津山がある地。「菅浦」は、同じく琵琶湖の北部にある浦。琵琶湖に漕ぎ出していった知人の行程を思いやっている歌です。
1735は、伊保麻呂(いほまろ:伝未詳)の歌。「我が畳」は、重ねて敷く意で「三重」にかかる枕詞。「三重の川原」は、今の四日市市にある内部川の河原。「礒の裏」は、岩陰。磯は、海だけでなく川にも池にも言います。「かくしもがもと」の「かく」はこのように、「しも」は強意、「がも」は願望。このようにばかりあってほしいと。「かはづ」は、清流に棲むカジカガエル。窪田空穂は、「河鹿の声を、河鹿自身が、その生存を喜んでいる声と聞きなしたのである。これは珍しく、例の少ないものである。言いあらわしも、その心にふさわしいもので、・・・『かくしもがもと鳴く』というのは、河鹿を擬人化したという程度のものでなく、むしろ作者の生活気分を反映したものとみえる。安らかに人生の深所に触れ得ている歌である」と評しています。
1736は、式部大倭(しきぶのおおやまと)が吉野で作った歌。「式部」は式部省の官人。「大倭」は、神護景雲3年(769年)に没した大和宿祢長岡(やまとのすくねながおか)か。若くして法学に長じ、文章を能くしたといわれる人です。「山高み」は、山が高いので。「白木綿花」は、木綿でつくった造花、または、木綿の白さを花に喩えたもの。「夏身」は、吉野町菜摘で、離宮の上流地点。「川門」は、川の幅が狭くなっている所。なお、巻第6-909に笠金村の類歌「山高み白木綿花に落ちたぎつ滝の河内は見れど飽かぬかも」があり、どちらが先か分かりません。
1737は、兵部川原(ひょうぶのかわら)の歌。「兵部川原」は、兵部省の官人の川原氏と取れますが、誰であるかは不明。「大滝」は、夏身との位置関係から、宮滝ではないかともいわれます。「近づきて」の原文「傍爲而」は難訓とされ、ソヒテヰテ、ソヒヲリテ、チカクシテなどとも訓まれています。「明けさ」は、心のさわやかなことよ。サヤケシに「明」を用いているのは集中この一首のみとされ、通常は「清」を用い、その対象についてはキヨシと言い、対象から受けた印象についてサヤケシと言います。
万葉仮名
『万葉集』には、和歌だけでなく、分類名・作者名・題詞・訓注・左注などが記載されていますが、和歌以外の部分はほとんどが漢文体となっています。これに対して和歌の表記には、漢字の本質的な用法である表意文字としての機能と、その字音のみを表示する表音文字としての機能が使われており、後者の用法を万葉仮名と呼びます。漢字本来の意味とは関係なく、その字音・字訓だけを用いて、ひらがな・カタカナ以前の日本語を書き表した文字であり、『万葉集』にもっとも多くの種類が見られるため「万葉仮名」と呼ばれます。
当時の日本にはまだ固有の文字がなかったため、中国の漢字が表記に用いられたわけです。たとえば、伊能知(=いのち・命)、於保美也(=おほみや・大宮)、千羽八振(=ちはやぶる・神の枕詞)などのように、漢字そのものに意味はなく、単にかなとして用いられます。むろん、漢字の意味どおりに用いられる場合もあります。ちなみに、巻第8-1418番の志貴皇子の歌は、原文では次のように書かれています。
石激 垂見之上乃 左和良妣乃 毛要出春尓 成来鴨
・・・石(いわ)走る 垂水の上の さわらびの 萌え出(い)ずる春に なりにけるかも
また、奈良時代の音節数は、清音60(古事記・万葉集巻第5は61)・濁音27だったことが分かっています。たとえばア行のえ(e)とヤ行のえ(ye)、ず(zu)とづ(du)などは区別されており、そのため現代語の清音44・濁音18に比べてはるかに多くありました。
【PR】
 |
古典に親しむ
万葉集・竹取物語・枕草子などの原文と現代語訳。 |
バナースペース
【PR】
万葉集の代表的歌人
磐姫皇后
雄略天皇
舒明天皇
有馬皇子
中大兄皇子(天智天皇)
大海人皇子(天武天皇)
藤原鎌足
鏡王女
額田王
第2期(白鳳時代)
持統天皇
柿本人麻呂
長意吉麻呂
高市黒人
志貴皇子
弓削皇子
大伯皇女
大津皇子
穂積皇子
但馬皇女
石川郎女
第3期(奈良時代初期)
大伴旅人
大伴坂上郎女
山上憶良
山部赤人
笠金村
高橋虫麻呂
第4期(奈良時代中期)
大伴家持
大伴池主
田辺福麻呂
笠郎女
紀郎女
狭野芽娘子
中臣宅守
湯原王

(柿本人麻呂)

(山部赤人)
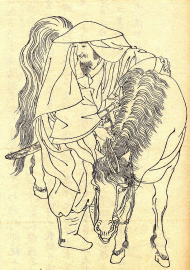
(大伴旅人)
月の異名と二十四節気
1月 睦月(みつき)
2月 如月(きさらぎ)
3月 弥生
夏
4月 卯月(うづき)
5月 皐月(さつき)
6月 水無月(みなづき)
秋
7月 文月(ふづき/ふみづき)
8月 葉月(はづき)
9月 長月(ながつき)
冬
10月 神無月(かんなづき)
11月 霜月(しもつき)
12月 師走(しわす)
1月
立春(りっしゅん)
雨水(うすい)
2月
啓蟄(けいちつ)
春分(しゅんぶん)
3月
清明(せいめい)
穀雨(こくう)
4月
立夏(りっか)
小満(しょうまん)
5月
芒種(ぼうしゅ)
夏至(げし)
6月
小暑(しょうしょ)
大暑(たいしょ)
7月
立秋(りっしゅう)
処暑(しょしょ)
8月
白露(はくろ)
秋分(しゅうぶん)
9月
寒露(かんろ)
霜降(そうこう)
10月
立冬(りっとう)
小雪(しょうせつ)
11月
大雪(たいせつ)
冬至(とうじ)
12月
小寒(しょうかん)
大寒(だいかん)

【PR】
