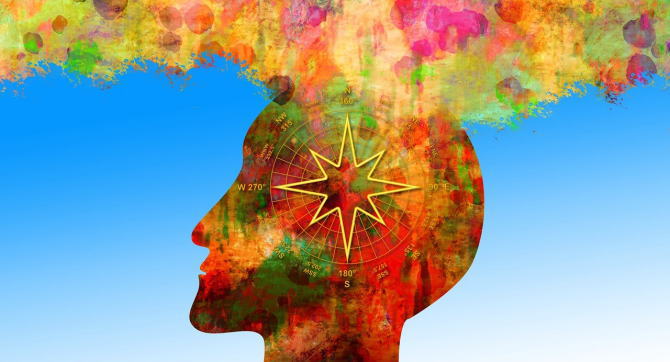
カント

近世哲学を代表する最も重要な哲学者の一人であり、またフィヒテ、シェリング、ヘーゲルと展開した、いわゆるドイツ観念論の起点となった哲学者。自由で自律的な近代的人間の理性に基礎づけられたカントの思想は、現代においてもさまざまな領域で読み直しが図られている。
ドイツ生まれの哲学者カントは、現代哲学の源流といわれ、「カント以前の哲学は全てカントに流れ込み、それ以後の哲学は全てカントから流れ出る」などと表現されます。カントによって哲学のベクトルが大きく変わってしまったとされますが、彼の哲学思想はどのようなものだったのでしょうか。
それまでの西洋哲学には「合理論」と「経験論」の2つの考え方がありました。理性の万能性を信じ、理性によって必ず普遍の真理に到達できると考えたのが「合理論」で、「経験論」はあらゆる偏見(イドラ)を排除し、観察された事実をもとに一般法則を導く帰納法を重視するという考え方です。カントはもともと合理論者でした。
ところが、経験論者の一人であるヒュームが唱える「懐疑論」を知って、カントは強い衝撃を受けます。それまで疑うこと自体がタブーだった神の存在に対しても疑いの目を向け、さらに科学(因果律)までもを疑うヒュームの徹底ぶりに接し、カントは「ヒュームの警告こそが、独断のまどろみから私の目を覚まさせ、私の探求にまったく新しい方向を示してくれた」と述べています。
そうしてカントはヒュームの懐疑に立ち向かおうと決意しました。そもそもヒュームの主張とは「すべての知識や概念は、人間か経験から作り出したものにすぎない」というものでしたが、そこでカントに新たな疑問が生じます。もし人間が想像する概念がすべてバラバラの経験による結果であるならば、別々の世界で違う経験をした人間が、幾何学や論理学などのように同じ結論に至ることに説明がつかない、と。
そこでカントは、ヒュームの結論を乗り越えるための仮説を立てます。人間の知識は確かに経験の束といえるが、その経験の受け取り方には、先天的に特有のパターンがあるのではないか、と。そうして、たとえば人間が何かのモノを見るときは、必ず空間的・時間的にそれを見ているというふうに、人間にはあらかじめ組み込まれている共通の「感性」の形式があることを見出します。
しかし、それだけで認識が成立するのではなく、もう一つの共通規格である「悟性」が、そうした感覚的素材を量、質、関係、様態といった「カテゴリー」に当てはめて統一することで、初めて万人が共有できる「知」が成り立つのだと考えました。そして、そうした共通の形式に基づく範囲でしか、普遍的な真理を打ち立てることはできないのだと主張します。
さらにカントは、 人間は何かの物事を認識する際に、必ず先天的な受け取りのパターンを利用するものの、「そのモノ」はすでに経験のプロセスを経由しているから、その時点で「そのモノ自体」ではなくなっている。認識に際して何某かのフィルターが存在する以上、それを飛び越えてそのモノ自体を観測することは不可能である。つまり、真理は構築可能だが、それはあくまで人間が規定する人間のための真理にすぎないというのです。だから、共通の経験の形式をもたない他の生物とは真理を共有できない!
ということは、私たちが認識している「そのモノ」も、本当の世界の「モノ」であるとはいえないし、人間は、自分たちの形式に変換される前の本当の「モノ自体」には決して到達できないということになります。でも、カントはそれで構わないのだと考えます。分からないものはどう考えたって分からないのだから、人間の形式に変換されたあとの現実の世界に限定して探求を進めるべきだと唱えたのです。
カントの著作
- 『純粋理性批判』
1781年刊。1787年に第2版。 人間の理性の能力を精密に分析し、「人間が知りうるものの範囲をどう確定するか」や「人間が知りえないものについてどんな態度をもつべきか」などの根本的な問題を明らかにしようとした。 - 『実践理性批判』
1788年刊。『純粋理性批判』で認識原理の批判を行なった後、「第二批判」とよばれる本書において道徳原理の批判を主題とし、義務のための義務を説いた道徳観を厳密な論理によって展開している。 - 『判断力批判』
1790年刊。「第三批判」とよばれ、上級理性能力のひとつである判断力の統制的使用の批判を主題とする。判断力に理性と感性を調和的に媒介する能力を認め、これが実践理性の象徴としての道徳的理想、神へ人間を向かわせる機縁となることを説く。
【PR】
カントの言葉から
- 私が生きている間、ずっと幸せである必要はない。しかし、生きている限りは立派に生きるべきである。
- 我は孤独である。
我は自由である。
我は我みずからの王である。 - 善行はこれを他人に施すものではない。これをもって自分自身の義務を済ますのである。
- 理論のない経験は盲目である。しかし、経験のない理論は単なる知的ゲームに過ぎない。
- 自分の一つ一つの行為が普遍的法則になるかのように生きるのだ。
- あらゆる宗教は道徳をその前提とする。
- 徳にとってまず要求されることは、自己自身を支配することである。
- 科学とは体系化された知識で、知恵とは整理された生活である。
- 内容のない思考は空虚であり、概念のない直観は盲目である。
- 最も平安な、そして純粋な喜びの一つは、労働をした後の休息である。
- もし虫けらのように振る舞うのならば、踏み付けられても文句を言ってはならない。
- 恩知らずとは、卑劣さの本質だ。
- あらゆる事物は価値を持っているが、人間は尊厳を有している。人間は決して目的のための手段にされてはならない。
- 動物に対して残酷な人は、人間関係においても容赦ない。我々は動物の扱い方によって、その人の心を判断することができる。
- 高慢な人は常に心の底では卑劣である。
- 宗教とは、我々の義務のすべてを神の命令とみなすことである。
- 努力によって得られる習慣だけが善である。
- 互いに自由を妨げない範囲において、我が自由を拡張すること、これが自由の法則である。
- 法律においては、他人の権利を侵害する時には罰せられる。道徳においては、侵害しようと考えるだけで罪である。
- 真の人間性に最もよく調和する愉しみは、よき仲間との愉しい食事である。
- 笑いは消化を助ける。胃酸よりはるかに効く。
- 酒は口を軽快にする。だが、酒はさらに心を打ち明けさせる。こうして酒はひとつの道徳的性質、つまり心の率直さを運ぶ物質である。
- 真面目に恋をする男は、恋人の前では困惑したり拙劣であり、愛嬌もろくにないものである。
- 美には客観的な原理はない。
- 人生の苦労を持ちこたえるには三つのものが役に立つ。希望・睡眠・笑い。
- 年齢とともに判断力は増し、天才は減っていく。
- 趣味については争うことが出来ない。
- 民主政治は専制政体と変わらない。なぜならば、民主政治とは全員がひとりの意志を無視し、時にはこれに逆らって議決し得る、という全員ならぬ全員が議決し得る執行権を認めるからである。
- 哲学は学べない。学べるのは哲学することだけである。
【PR】
→目次へ
 |
がんばれ高校生!
がんばる高校生のための文系の資料・問題集。 |
バナースペース
【PR】
カントという人①
意外にも本を読むのが嫌いで、蔵書も少なく、友人に「自分の代わりに本を読んで、自分の考えと何が違うか教えてくれ」と頼んでいた。
気難しい性格だったかというとそうではなく、とても社交的で、食事の席には頻繁に多くの知人が訪れ、彼が行う講義はユーモアあふれる内容で学生の人気が高かったという。たたし女性には距離を置き、生涯独身を通した。
日ごろから健康に気を配り、食事は1日1回、時間をかけてゆっくり食べた。焼いた肉が好物だったが、その食べ方が風変わりで、噛んで肉の汁だけを飲み込み、残った肉片は皿に戻していたという。そのおかげか、79歳まで長生きした。
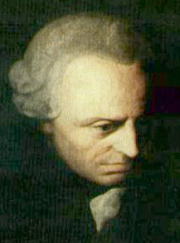
カントという人②
たまりかねた妹の一人がカントのもとを訪れると、カントは相手が誰なのかすら分からなかったという。 妹が名乗ると、今度は居合わせた人たちに、 妹の教養のなさを詫びたという。 カントがようやく手にした教授の地位を鼻にかけていたわけではない。
よく知られているように、カントは「馬鹿」に我慢ができなかったのだ。 たとえ自分の身内であっても、「馬鹿」を許すことはできなかった。 ただそれだけだった。
~ポール・ストラザーン
クラシック音楽案内
【PR】