
大伴旅人の歌
巻第3-315~316
| 315 み吉野の 吉野の宮は 山からし 貴くあらし 川からし 清(さや)けくあらし 天地(あめつち)と 長く久しく 万代(よろづよ)に 変はらずあらむ 幸(いでま)しの宮 316 昔見し象(きさ)の小川を今見ればいよよ清(さや)けくなりにけるかも |
【意味】
〈315〉美しい吉野の宮は、山の品格のゆえに貴い。川の品格ゆえに清らかだ。天地とともに永く久しく万代に変らずあってほしい、天皇がお出かけになる吉野宮よ。
〈316〉昔見た象の小川を今再び見ると、ますます冴え冴えと美しくなった。
【説明】
暮春の月(春の3月)、聖武天皇が吉野の離宮に行幸なさった時、天皇の仰せを受けて大伴旅人(おおとものたびと)が作った長歌と反歌。年次が記されていませんが、題詞から旅人が中納言だったことがわかり、神亀元年(724年)のことらしいと推定されています。すると、旅人は60歳、聖武天皇の即位は2月4日なので、それからひと月そこそこの行幸だったことになります。遊楽というより、多分に信仰的神事の目的によるものだったとみられます。
こうした行幸のような改まった際の賀歌には、古風に長歌形式をもってするのが先例となっていました。また、最高の敬意をもって天皇を讃える場合、親近しているかのように言うのはかえって非礼とされましたから、距離を置いた宮そのものや土地、山川を讃えています。ただし、旅人の吉野行幸歌は、人麻呂や赤人らとは異なる詠みぶりであり、『懐風藻』に載る吉野詩群によった漢文臭の強い作品であることが指摘されています。歌詞の「み吉野の吉野」ほか「山からし」「川からし」「清けくあらし」「天地と長く久しく」「幸しの宮」などは、いずれも『万葉集』中には見られない語です。
315の「山からし」の「から」は、物の本体・素性の意、「し」は、強意の副助詞。山の品格ゆえに。「貴くあらし」の「あらし」は「あるらし」の約で、「らし」は推量。「天地と長く久しく」は「天地長久」の翻読語。「幸しの宮」は、吉野の離宮。316の「昔」は、天武・持統朝の時代のこと。「象の小川」は、吉野を流れる現在の貴佐谷川。「いよよ」は、いよいよ、ますます。国文学者の池田彌三郎は、この歌を評し、「従来の儀礼歌の類型的な形式によりながら、形式的な空疎にとどまることがなく、しかも名族の氏の上(かみ)らしい、大がらな、こだわりのないよさを十分に持っている」と述べています。反歌の下2句は、魂が洗われ生き返るような感動表現であり、また60歳を迎えた自祝の思いが込められているかのようです。
旅人は行幸歌を詠むにあたって、語彙の上でも様式の上でも、人麻呂や赤人の模倣はしませんでした。なぜなら、それまでの旅人がもっぱら馴れ親しんできたのは、大和歌(やまとうた)ではなく漢詩・漢文学だったからです。それは律令制下に生きる高級官僚として当然の教養であり、たしなみでもありました。この時には、彼の歌は上奏するに至らなかったとの注記があり、人々の耳目に触れることはなかったのですが、その後も、彼はしばしば漢文と和歌との融合という手法を用いて歌作りに挑戦しています。(巻第5-810~811・巻第5-853~863など)
大伴旅人は、安麻呂(やすまろ)の子で、家持(やかもち)の父、同じく万葉歌人の大伴坂上郎女(さかのうえのいらつめ)は異母妹にあたります。大伴氏は、新興の藤原氏と比べても、古くから政治の中枢にいた名門の豪族であり、旅人は710年に左将軍正五位上、718年に中納言、720年に征隼人持節(せいはやとじせつ)大将軍に任ぜられ、隼人を鎮圧しました。727年ごろ大宰帥(だざいのそち)として九州に下り、730年12月に大納言となって帰京。翌年従二位となり、その年の7月に67歳で没しました。
なお、旅人は『万葉集』に70首前後の歌を残していますが、ここの長・短歌以外はすべて大宰府への赴任が決定して以降の作となっています。つまり旅人の作歌は、大宰府時代とその後帰京して亡くなるまでの間、すなわち晩年の3年間(64~67歳)に集中しており、彼が60歳まで沈黙していたことは謎とされます。青年期には一門の長としての教育を強いられ、壮年期には官位が上がるにつれて高級官僚としての政務に忙殺されていたのでしょうか。一つの考え方として、晩年に作歌が集中している理由に次の3点が掲げられています。①老身であるがために予期しなかった人生体験にいくつも遭遇したこと。②文芸の創作と享受を共にする歌友・詩友が周囲に存在したこと。③筑紫という鄙の地に在らねばならなかったこと。
巻第3-331~333
| 331 わが盛(さかり)また変若(をち)めやもほとほとに平城(なら)の京(みやこ)を見ずかなりけむ 332 わが命(いのち)も常にあらぬか昔見し象(きさ)の小河(をがは)を行きて見むため 333 浅茅原(あさぢばら)つばらつばらにもの思(も)へば古(ふ)りにし里し思ほゆるかも |
【意味】
〈331〉私の盛りはひょっとして再び若返ることがあるだろうか、いや殆ど奈良の都を見ずじまいになってしまうのだろうな。
〈332〉我が命がいつまでもあってほしい。昔見た象の小川を見にいくために。
〈333〉あれこれと物思いに耽っていると、過ぎ去った昔の故郷がしみじみ思い出される。
【説明】
旅人は和歌や漢文学に優れていただけでなく、政界においても順調に昇進を重ねました。728年には、大宰帥(だざいのそち)に任命され筑紫に赴任します。大宰帥は名誉ある役職でしたが、奈良の都を愛してやまない旅人にとっては本意ではありませんでした。この人事は、長屋王排斥をねらう藤原氏にとって、保守派の長老である旅人の存在が目障りだったための左遷だとする見方がありますが、当時は隼人・蝦夷の背叛を患えた時代だったため、武門の名門として輿望のある旅人に白羽の矢が立ったとも見られています。しかし、60歳を過ぎた身には過酷な異動でもありました。ここの歌は、63、4歳ぐらいの時の作だろうとされ、奈良の都を思う、強い望郷の念が生じている歌です。
331の「変若」は、若返ること。「やも」は、反語。「ほとほとに」は、ひょっとして。332の「常にあらぬか」は、いつまでもあってほしい。「象の小川」は、吉野を流れる現在の貴佐谷川で、「昔見し」といっているのは、上の316の聖武天皇の吉野行幸に供奉の一人として加わった時のことのようです。333の「浅茅原」は、類音で「つばらつばらに」にかかる枕詞。「つばらつばらに」は、つくづく、しみじみと、の意。旅人の歌には同一単語を重ねて一語とした言葉が目立ちます。「古りにし里」は、旅人が35歳まで住んでいた明日香とされますが、次の歌(334)で香具山を詠んでいるので、藤原京だとする見方もあります。「し」は、強意の副助詞。
331について斉藤茂吉は、「旅人の歌は、彼は文学的にも素養の豊かな人であったので、極めて自在に歌を作っているし、寧ろ思想的抒情詩という方面にも開拓していった人だが、歌が明快なために、一首の声調に暈(うん)が少ないという欠点があった。その中にあってこの歌の如きは、さすがに老に入った境界の作で、感慨もまた深いものがある」と言い、332についても、「分かり易い歌だが、平俗でなく、旅人の優れた点をあらわし得たものであろう。哀韻もここまで目立たずに籠れば、歌人として第一流といっていい」と述べています。
巻第3-334~335
| 334 忘れ草 我が紐(ひも)に付く香具山(かぐやま)の古(ふ)りにし里を忘れむがため 335 わが行きは久(ひさ)にはあらじ夢のわだ瀬にはならずて淵(ふち)にあらなも |
【意味】
〈334〉忘れ草を下紐につけました。香具山がある故郷を忘れようと思って。
〈335〉私が筑紫に行く期間は長くはないだろう。吉野の夢のわだは、瀬に変ることなく、帰ってきたときも淵であってほしいものだ。
【説明】
334は、旅人が大宰府に赴任中の歌です。「忘れ草」は、身につけると憂いを忘れさせてくれるというヤブカンゾウのこと。中国の『詩経』に出ているのが我が国に伝わったもので、「忘れ草」という名を得ると、その名に伴う神秘の力をもつという信仰によって広まったようです。集中では恋の苦しさを一時的に忘れさせてくれるのに付けるのを詠んだ歌が多くありますが、旅人は、故郷を思う気持ちを押さえるためのものとして詠んでいます。「古りにし里」は、旅人が35歳まで住んでいた明日香とされますが、香具山があるのは藤原京です。旅人が大宰府に赴任中の都では、左大臣長屋王が自尽、藤原不比等の娘が立后するなど、政治の中枢は藤原氏によって完全に握られました。はるか遠い地にあって、旅人は何を思っていたのでしょうか。
335は大宰府に赴任する直前の歌とされます。「我が行き」は、私の旅行。大宰府に赴任して大和を留守にすることを指しています。「久にはあらじ」は、そう長くはあるまい。大宰帥は任期の定まった官だったことから、それほど長い赴任ではないだろうと推測しています。「夢のわだ」は、奈良県吉野町の宮滝付近の淵の名で、離宮のやや上流あたりから川が大きく湾曲し、底が深くなっている所。流れが緩やかになるので、船を浮かべて遊覧でき、夢心地になるところから名付けられたとされます。「淵にあらなも」は原文「淵有毛」は難訓で、疑問、希望のいずれと見るかによっても訓みが分かれ、さまざまの説がありますが、ここは希望と見て「あらなも」としています。旅人は、いつか必ず再訪するので、「夢のわだ」に昔通りの姿で待っていてほしいと言っており、聖武天皇の吉野行幸に従駕したときに見た吉野宮滝の幽邃神仙の景趣は鮮烈で、忘れがたい魅力になったようです。
【PR】
| 338 験(しるし)なき物を思(おも)はずは一坏(ひとつき)の濁(にご)れる酒を飲むべくあるらし 339 酒の名を聖(ひじり)と負(おほ)せし古(いにしへ)の大(おほ)き聖(ひじり)の言(こと)の宜(よろ)しさ 340 古(いにしへ)の七(なな)の賢(さか)しき人たちも欲(ほ)りせしものは酒にしあるらし 341 賢(さか)しみと物言ふよりは酒飲みて酔(ゑ)ひ泣きするし優(まさ)りたるらし 342 言はむすべ為(せ)むすべ知らず極(きは)まりて貴(たふと)きものは酒にしあるらし 343 なかなかに人とあらずは酒壺(さかつほ)になりにてしかも酒に染みなむ 344 あな醜(みにく)賢(さか)しらをすと酒飲まぬ人をよく見ば猿(さる)にかも似む |
【意味】
〈338〉思ったところでどうにもならないことをくよくよ思うより、一杯の濁り酒を飲む方がよほどましだと思われる。
〈339〉酒の名を聖(ひじり)と名付けた昔の大聖人がいる。その言葉のまことに結構なことよ。
〈340〉昔の中国の七賢人たちでさえ、欲しくてならなかったのは、この酒であったようだ。
〈341〉利口ぶって説き立てるより、酒を飲んで酔い泣きする方がずっとまさっている。
〈342〉言いようもなく、なすすべもないほどに、この上もなく貴いものは酒であるらしい。
〈343〉かえって人間であるよりは、いっそ酒壺になってしまいたい。そうすれば、存分に酒に浸ることができよう。
〈344〉ああ見苦しい。酒も飲まずに利口ぶっている人の顔をよく見ると、猿に似ているではないか。
【説明】
「大宰帥大伴旅人卿の酒を讃える歌13首」とあるなかの前半7首で、旅人65歳の作です。宴席で詠まれた歌とみられ、酒飲みが喜びそうな歌がずらりと並んでいます。近世以前は、酒は祝いの日など特別な機会に、大きな杯に注いで大勢で回し飲みして飲み干すものでしたが、旅人は一人で飲むのも好きだったようです。ただ、この前年(神亀5年:728年)に、旅人は筑紫に伴った愛妻大伴女郎を亡くしており、また当年2月には、皇親政治の推進者である長屋王が藤原氏の策略によって自尽しています。ここの歌は、それらの悲しみを引きずり続ける苦しみからの解放を願って詠んだものとされます。
338の「験なき物」は、思ったところでどうにもならないこと。「濁れる酒」は、糠を漉さない白濁した酒、どぶろくのこと。短期間で発酵させるため、今日の酒に比べて甘く、アルコール度数も低いものでした。当時は既に清酒も醸造されていましたが、冒頭に濁り酒を掲げたのは、次歌に中国の故事を踏まえることや漢詩文の隠士の風貌を彷彿させるためともいわれます。「飲むべくあるらし」の「らし」は、推定の助動詞で、旅人の愛用語でもあります。339は、中国・魏の時代に太祖(曹操)が出した禁酒令を破って酒を飲んだ徐邈(じょばく)が、清酒を聖人、濁酒を賢人とひそかに呼んだという故事を言っています。「古の大き聖」は、昔の中国の大聖人で、徐邈を指しています。
340の「古の七の賢しき人」とは、俗世を避け、竹林のもとに集まり酒を交わして清談(老子の思想を断じること)に耽ったという晋の阮籍(げんせき)、
康(けいこう)、山濤(さんとう)、向秀(しょうしゅう)、劉伶(りゅうれい)、阮咸(げんかん)、王戎(おうじゅう)の7人の隠士のこと。前歌の「聖人」に続き、ここでは「賢人」を持ち出しています。ただし5世紀ごろに書かれた『世説新語』には、彼ら7人は決していわゆる聖人君子などではなく、妻にさからって酒を飲んだり、酒が飲みたいばかりに役所の調理場で働く姿が描かれています。旅人が彼らを理想としたのは、むしろそうした人たちだったのかもしれません。
341の「賢しみ」は、利口ぶって、賢ぶって。「酔泣き」は、いわゆる泣き上戸のことで、泣き上戸の酔人であっても、利口ぶる、賢ぶる人よりもまだましだと言っています。「酔泣き」は347・350にも繰り返されているところから、窪田空穂は、「旅人にはそうした性癖があったのではないかとも思われる」と言っています。342の「言はむすべ為むすべ知らず」は、言いようもなく為すすべもないほどに。「極まりて貴き」は、この上なく貴い。漢語の「極貴」の訓読語です。「酒にし」の「し」は、強意の副助詞。
343の「なかなかに」は、中途半端な状態、転じて、かえって、むしろ。「なりにてしかも」は、なりたいものだなあ。中国三国時代、呉の鄭泉(ていせん)という男が、自分が死んだら、土となって酒壺として焼かれるように窯の側に埋めよと遺言した故事によっています。344の「あな」は、強い感情から発する語。ああ。「賢ら」は名詞で、利口ぶること。「猿にかも似る」の「かも」は、詠嘆を込めた疑問の係助詞。この歌を13首の中心に位置に置き、しかも初句切れとしたのは享受者に強く印象づける意図があるともいわれ、都の誰か特定の人のことを念頭に置いた歌かもしれません。また、「猿」が出てくるのは『万葉集』中、この1首のみです。
巻第3-345~350
| 345 価(あたひ)なき宝といふとも一杯(ひとつき)の濁(にご)れる酒にあにまさめやも 346 夜(よる)光る玉といふとも酒飲みて心を遣(や)るにあに及(し)かめやも 347 世間(よのなか)の遊びの道に冷(すず)しくは酔(ゑ)ひ泣きするにあるべくあるらし 348 この世にし楽しくあらば来(こ)む世には虫に鳥にも我れはなりなむ 349 生ける者つひにも死ぬるものにあれば今ある間(ほど)は楽しくをあらな 350 黙然(もだ)居(を)りて賢(さか)しらするは酒飲みて酔(ゑ)ひ泣きするになほ如(し)かずけり |
【意味】
〈345〉どんなに値がつけられないほど貴重な宝でも、一杯の濁り酒より価値のあるものなどありはしないだろう。
〈346〉たとえ夜光る玉であっても、酒を飲んで憂さを晴らすことにかなうものはない。
〈347〉世の中のさまざまな風雅の道に心楽しむことができないのなら、酒に酔い泣きするのがよいように思う。
〈348〉この世さえ楽しかったら、あの世では虫にも鳥にも、私はなってしまおう。
〈349〉生きている者は必ず死ぬと決まっているのだから、この世にいる間は楽しく過ごそう。
〈350〉黙りこくって分別のある顔をしているのも、酒を飲んで酔い泣きするのにはやはり及ばないことだ。
【説明】
「大宰帥大伴旅人卿の酒を讃える歌13首」とあるなかの後半6首。345の「価なき宝」は、仏典にある「無価宝珠(むげのほうじゅ)」の訳語で、仏法を値段で量れないほどの無上の貴い珠に喩えた表現。「あにまさめやも」の「あに~めやも」は、どうして~だろうか、いやそうではない、の意で、反語の詠嘆表現。。どうしてまさろうか。346の「夜光る玉」は、『文選』ほか漢籍に多くみられる「夜光珠」「夜光璧」の訳語で、宝玉の名。「心を遣る」は、憂さを晴らす。
347の「遊びの道」は、俗世間の遊びの方面。琴・棋・書画などを指します。「冷しくは」の原文「冷者」で、「まじらはば」「おかしきは」「さぶしくは」などのほか、「冷」は「怜」の誤りだとして「たのしきは」と訓む説などがあり、定まっていません。「あるべかるらし」は、あるように思われる。「たのしきは」と訓む説に従えば、歌の解釈は「世の中の遊びの道で一番楽しいことは、酒を飲んで酔い泣きすることであるらしい」のようになります。
348の「この世にし」の「し」は、強意の副助詞。「なりなむ」の「なむ」は未来完了の助動詞。きっとなろう。349の「生ける者つひにも死ぬるもの」は、仏説にいう「生者必滅」の思想で、生ある者は必ず死ぬと決まっていること。「あらな」は、ありたい。前の歌とともに、仏教的な輪廻の思想や無常観に基づいています。350の「黙然」は名詞で、黙っていること。「賢しらする」は、賢げにする、分別のありそうにする。「なほ如かずけり」は、やはり及ばないことだ。世間体を繕うのは、酒を飲んで感情を解き放つことに及ばないと言って、またも「酔泣き」を賞賛して締めくくっています。
斎藤茂吉は、これらの歌について次のように言っています。「一種の思想ともいうべき感懐を詠じているが、いかに旅人はその表現に自在な力量を持っているかが分かる。その内容は支那的であるが、相当に複雑なものを一首一首に応じて毫も苦渋なく、ずばりずばりと表している」。作家の田辺聖子は、「旅人は讃酒歌というけれど、この一連の歌、どこやら酔うて酔い切れぬ一抹のにがみがある」とも。
また、国文学者の窪田空穂は、「この酒を讃むる心は、酒を享楽の対象として、その味わいを愛でるのではなく、酒を憂えを忘れしめる物として、酔泣きを導き出す力を讃めているのである。すなわち必要を充たしうる物としてである。その背後には大いなる悲しみがあったのであるが、旅人自身は直接には一言もそれに触れていず、ただ、暗示にとどめている。・・・・・・これらの歌の背後にある悲しみは、妻の死ではなかったかと思われる。それをほかにしては、これほどに深い悲しみは想像し難いものだからである」
一方、文芸評論家の山本憲吉は、「13首の連作として面白いとしても、一作一作独立して味わえば、なにか物足りない。概念的な発想が、一首一首の結晶度を弱めたのだろうか。始めから興に乗じて連作として作ったもので、一首一首の完成にさほど力を注いではいないのだ。
人麻呂・黒人・赤人・笠金村らの詞人たちが、専門の作者であったのに対して、旅人も憶良も、専門家とは言えない。アマチュア詩人なのである。その点でも、一首の修辞の巧みを凝らすといった気持ちは、始めから持っていなかった。歌は、時に応じ、場に応じての、思想・感情の吐露の具であった。ことに旅人・憶良らは、新しい漢学の素養があり、人生的感懐をそのまま歌に詠みこむ傾向があった。この讃酒歌も、酒の讃め歌がいつか老荘思想的な人生観の吐露になっていくのである。その点では、当時の第一級の知識人の試作としての意味を帯びてくる。
旅人が老荘思想や仏教思想をどの程度に理解していたか、さまで深かったとは思えないが、老荘の無為自然の教えから、彼なりに一つの享楽主義的思想を引き出していた。その思想を一つの枠組として、自家製の哲学を歌い上げたと言ってもよい。豪族大伴氏の氏の上として、政府の高官に位置しながら、いつか政争から遠ざかり、政治の場からはみ出して、自分の教養人としての生活をうち立てていたようである。その一端が、この13首の歌にうかがわれる」
【PR】
大伴氏について
大伴氏は建国以来の名門であり、主に軍事・防衛の領域を統括してきた武門の名族でした。天孫降臨の際にその前衛を務めた天忍日命(あめのおしひのみこと)、神武建国の功臣道臣命(みちのおみのみこと)を先祖とし、また日本武尊(やまとたけるのみこと)の東征にも大伴連武日(おおとものむらじたけひ)が従いました。さらに氏族制のもとでも、武烈天皇から、継体、安閑、宣化、欽明天皇の5代にわたって、大連(おおむらじ)として大伴金村(おおとものかなむら)が国家の枢機に参画してきました。
しかし、金村は、晩年にいたって、半島政策の軍事的失敗の責任を、同僚の大連物部尾輿(もののべのおこし)に追及されて失脚し、それに代わって蘇我氏一族が大陸からの帰化人の勢力を背景にして急速に台頭してきました。大伴氏が政治的復権を果たすかのように見えたのは、大化改新のさいに活躍した大伴長徳(ながとこ:旅人の祖父)が右大臣に任じられ、さらにその子の安麻呂(やすまろ:旅人の父)と御行(みゆき)の兄弟をはじめ一族の大伴馬来田(まぐた)や吹負(ふけい)などが、壬申の乱で大海人皇子側に立って、その勝利に貢献したことでした。
しかし、政治の実権はすでに旧氏族から離れ、旧氏族勢力を解体させた大化改新の功労者、中臣鎌足の藤原氏一族に握られ、かつての名門大伴氏の存在は見る影もなく衰退したのでした。旅人は父・安麻呂の後継者として一門の長となり、政治的実権はなかったものの、ともかく官途には就いていました。
 |
古典に親しむ
万葉集・竹取物語・枕草子などの原文と現代語訳。 |
バナースペース
【PR】
大伴旅人の略年譜
711年 正五位上から従四位下に
715年 従四位上・中務卿に
718年 中納言
719年 正四位下
720年 征隼人持説節大将軍として隼人の反乱の鎮圧にあたる
720年 藤原不比等が死去
721年 従三位
724年 聖武天皇の即位に伴い正三位に
727年 妻の大伴郎女を伴い、太宰帥として筑紫に赴任
728年 妻の大伴郎女が死去
729年 長屋王の変(2月)
729年 光明子、立后
729年 藤原房前に琴を献上(10月)
730年 旅人邸で梅花宴(1月)
730年 大納言に任じられて帰京(12月)
731年 従二位(1月)
731年 死去、享年67(7月)
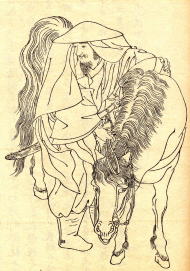
主要歌人の生年
614年 藤原鎌足
626年 天智天皇
630年 額田王
631年 天武天皇
640年 有馬皇子
645年 持統天皇
654年 高市皇子
660年 山上憶良
660年 元明天皇
661年 大伯皇女
662年 柿本人麻呂
663年 大津皇子
665年 大伴旅人
668年 志貴皇子
673年 弓削皇子
676年 舎人皇子
680年 元正天皇
681年 藤原房前
683年 文武天皇
684年 長屋王
684年 橘諸兄
694年 藤原宇合
700年 山部赤人
700年 大伴坂上郎女
701年 聖武天皇
701年 光明皇后
706年 藤原仲麻呂
715年 笠金村
715年 藤原広嗣
718年 大伴家持
718年 孝謙天皇
721年 橘奈良麻呂
(生年不詳の歌人を除く)

(藤原房前)

(橘諸兄)

(藤原宇合)
【PR】