
山上憶良の歌
巻第5-894~896
| 894 神代(かみよ)より 言ひ伝(つ)て来(く)らく そらみつ 大和(やまと)の国は 皇神(すめかみ)の 厳(いつく)しき国 言霊(ことだま)の 幸(さき)はふ国と 語り継(つ)ぎ 言ひ継がひけり 今の世の 人もことごと 目の前に 見たり知りたり 人さはに 満ちてはあれども 高(たか)光る 日の大朝廷(おほみかど) 神(かむ)ながら 愛(め)での盛りに 天(あめ)の下 奏(まを)したまひし 家の子と 選(えら)ひたまひて 勅旨(おほみこと) 戴(いただ)き持ちて 唐国(からくに)の 遠き境(さかひ)に 遣(つか)はされ 罷(まか)りいませ 海原(うなはら)の 辺(へ)にも沖にも 神(かむ)づまり うしはきいます 諸(もろもろ)の 大御神(おほみかみ)たち 船舳(ふなのへ)に 導きまをし 天地(あめつち)の 大御神たち 大和(やまと)の 大国御魂(おほくにみたま) ひさかたの 天(あま)のみ空ゆ 天翔(あまかけ)り 見渡したまひ 事終はり 帰らむ日には また更に 大御神たち 船舳(ふなのへ)に 御手(みて)うち掛けて 墨繩(すみなは)を 延(は)へたるごとく あぢかをし 値嘉(ちか)の崎(さき)より 大伴(おほとも)の 御津(みつ)の浜(はま)びに 直泊(ただは)てに 御船(みふね)は泊(は)てむ つつみなく 幸(さき)くいまして 早(はや)帰りませ 895 大伴の御津(みつ)の松原かき掃(は)きて我(わ)れ立ち待たむ早帰りませ 896 難波津(なにはつ)に御船(みふね)泊(は)てぬと聞こえ来(こ)ば紐(ひも)解き放(さ)けて立ち走りせむ |
【意味】
〈894〉神代から言い伝えてきたことがある。この大和の国は皇祖神の御霊(みたま)の厳かな国、言霊(ことだま)が幸いをもたらす国と、語り継ぎ、言い継いできた。このことは、今の世の人々もことごとく目の当たりにし、知っている。人が多く満ちているけれど、日の御子であられる天皇が盛んに慈しまれ、名だたるお家の子としてお選びになったあなた。その勅命を持って大唐の遠い境に差し向けられてご出発になる。海原の岸にも沖にも鎮座して支配しておられる大御神たちは、御船の舳先に立ってお導きになり、天地の大御神たち、とりわけ大和の大神は、大空を駆けめぐってお見渡しになる。使命を終えてお帰りになる日には、再び大御神たちが御船の舳に御手をお掛けになり、墨縄を張ったように値嘉の崎から大伴の御津の浜辺にまっすぐに向かわれ、到着されるでしょう。障りなくご無事に、一刻も早くお帰りください。
〈895〉大伴の御津の松原をはき清めては、ひたすらお帰りをお待ちします。早くお帰りください。
〈896〉難波津に御船が到着したと聞いたなら、着物の帯紐も結ばないまま走り出てお迎えにあがりましょう。
【説明】
題詞に「好去好来(かうきよかうらい)の歌」とある長歌と反歌2首。「好去好来」は中国の口語、無事に行って無事に帰ってくることを祈る意で、天平5年(733年)3月、新任の第9次の遣唐大使として出発する丹治比広成(たじひのひろなり)に献上された歌です。この時の憶良は74歳で、自身が第7次の遣唐使として中国に渡ったのは31年前の43歳の時でした。無事に役目を終えて帰ってきた人として有名だった憶良のところへ、新任の広成が挨拶に来たものとみえます。広成は4月3日に4隻の船で唐に向けて出航、その2年後に、先に唐に渡っていた吉備真備(きびのまきび)や玄昉(げんぼう)らと共に無事帰国しました。しかし、この時すでに憶良は亡くなっていました。
894の「そらみつ」は「大和」の枕詞。「皇神」は、国土を統治する神、天照大神のこと。「厳しき国」は、神威が盛んに発揮される国。「言霊の幸はふ国」は、言葉に宿る力で幸福がもたらされる国。「人さはに」の「さはに」は、大勢。「高光る」は「日」の枕詞。「日の大朝廷」は、皇居。「天の下奏したまひし」は、天下の政事をお執りになった、で、文武朝の左大臣だった広成の父島のことを言ったもの。文武朝の左大臣だった、広成の「勅旨」は、遣唐大使としての勅命。「神づまり」は、神々がとどまりいますの意。「うしはきいます」は、支配していらっしゃる。「大和の大国御魂」は、天理市新泉の大和神社の祭神。「ひさかたの」は「天」の枕詞。「墨縄」は、直線を引く大工道具。「延へ」は、繩を長く延ばす意。「あぢかをし」は語義未詳ながら、同音で「値嘉」に掛かる枕詞。「値嘉」は、長崎県五島列島、平戸島とその周辺の島々。当時はここからが故国の日本とされていました。「大伴の御津」は、難波の港。末尾の「早帰りませ」は、反歌(895)にも使われている表現で、遠い所に旅立つ人を送る気持ちとして非常に大事な言葉でした。また、憶良がかつて在唐のとき、「・・・大伴の御津の浜松待ち恋ひぬらむ」(巻第1-63)と望郷の思いを詠んだのを念頭においていたことでしょう。
このときの憶良は老齢というだけでなく、かなり病が重かったのではないかと言われています。広成が憶良を自邸に招かず、みずから憶良邸を訪問したのは、憶良がすでに立ち居不自由だったからかもしれません。3月3日にこの「好去好来の歌」を贈った後、6月3日作の歌との間に、憶良は「痾(おもきやまひ)に沈み自らを哀しむ文」と題した漢文を残しています。中国古典を引用した傑作とされ、漢字1300字にも及ぶ長文ですが、そこには「手足は非常に思い、関節という関節はみな痛む、まるで背中に重い重しを背負ったようなものだ」と書かれています。憶良は、最後の元気を出して、若き遣唐大使への送別と励ましの心を示したのではないでしょうか。
巻第5-897~903
| 897 たまきはる うちの限りは 平らけく 安くもあらむを 事もなく 喪なくもあらむを 世間(よのなか)の 憂けく辛けく いとのきて 痛き瘡(きず)には 辛塩(からしほ)を 注(そそ)くちふがごとく ますますも 重き馬荷(うまに)に 表荷(うはに)打つと いふことのごと 老いにてある 我が身の上に 病をと 加へてあれば 昼はも 嘆かひ暮らし 夜はも 息づき明かし 年長く 病みしわたれば 月重ね 憂へさまよひ ことことは 死ななと思へど 五月蝿(さばへ)なす 騒く子どもを 打棄(うつ)てては 死には知らず 見つつあれば 心は燃えぬ かにかくに 思ひ煩ひ 音(ね)のみし泣かゆ 898 慰むる心はなしに雲隠り鳴き往く鳥の哭(ね)のみし泣かゆ 899 術(すべ)もなく苦しくあれば出(い)で走り去ななと思へど児等(こら)に障(さや)りぬ 900 富人(とみひと)の家の子どもの着る身なみ腐(くた)し捨つらむ絹綿(きぬわた)らはも 901 荒栲(あらたへ)の布衣(ぬのきぬ)をだに着せかてにかくや嘆かむ為(せ)むすべをなみ 902 水沫(みなわ)なすもろき命も栲縄(たくづな)の千尋(ちひろ)にもがと願ひ暮らしつ 903 しつたまき数にもあらぬ身にはあれど千年(ちとせ)にもがと思ほゆるかも |
【意味】
〈897〉この世に生きている限りは、平穏で安らかにありたいのに、無事でありたいのに、世の中の憂鬱と辛さは、「とりわけ痛い傷に辛い塩をふりかける」という諺のように、「重い馬荷にいっそう上荷を積み重ねる」という諺のように、年老いてしまった我が身の上に、病気まで重なっているので、昼はずっと歎いて過ごし、夜はずっと溜息をついて明かし、そうやって長の年月病み続けてきたので、幾月も呻吟した挙句、いっそ死のうと思うけれども、騒ぎ回る子供たちを残したまま死ぬことはできず、その子たちを見つめていると、心は燃え立ってくる。あれこれと思い悩み、声を上げて泣くばかりだ。
〈898〉自分で自分を慰めることもできずに、雲に隠れながら鳴いていく鳥のように声をあげて鳴いている。
〈899〉どうしようもなく苦しいのでいっそ死んでしまおうかと思うが、子らのために妨げられて、それもできない。
〈900〉裕福な家の子供が着余して、腐らせて捨てる絹や綿の着物は、何とまあ。
〈901〉粗末な布の着物すら、なかなか着せてやることができず、こうして嘆くのだろうか、どうする手立ても無くて。
〈902〉あぶくのように脆い命も、千尋の長さであってほしいと願いながら、一日一日を送っている。
〈903〉物の数にも入らない我が身ではあるけれども、やはり千年でも生きられるなら生きたいと思われるよ。
【説明】
憶良が筑前守の任を終えて帰京後の70歳を過ぎた頃の作で、「痾(おもきやまひ)に沈み自らを哀しむ文」と題された漢文に続き、「老身に病を重ね、年を経て辛苦(くる)しみ、また児等を思ふ歌」とある7首。末尾に、天平5年(733年)6月3日に作る、とあり、巻第5-978の歌がその後の歌として辞世の歌らしくありますが、日付のあるものとしては、これが憶良の最後の歌となっています。
漢文では、生まれてこのかた身を修め善行を積み、毎日勤行し精神を敬拝してきたにも拘らず、十余年もの間この病苦に悩まねばならぬ不合理を訴え、自身の病状については、手足は動かず、関節はすべてうずき、身体はだるく重りを背負ったようだ、梁(はり)などから垂らした布紐にとりすがって立とうと思うが翼を傷めた鳥のようで、杖を頼りに歩こうとするが足悩む驢馬(ろば)のようだ、などと書かれています。また、五臓をえぐり割いて病原にどこまでも迫り、探り当て、撲滅を願う、とすさまじい気魄を見せている一方、結局、長寿短命は妖鬼のしわざなどというものではなく、あくまでその人の善・不善の因果の報いであり、わが病は自身の飲食の不摂生の業報による、だから自分で治せるようなものではない、と悲観しています。
897の「たまきはる」は「うち」の枕詞。「うちの限りは」の「うち」は「現(うつ)」の転音で、現実に生きている、すなわち命。「喪」は、凶事。「憂けく辛けく」は形容詞「憂し・辛し」の名詞形。「いとのきて痛き瘡には辛塩を注く」は、当時の諺。「注くちふ」の「ちふ」は、という。「ますますも重き馬荷に表荷打つ」も「いとのきて・・・」と類似の諺。「表荷」は、荷の上にさらに積む荷。「ことことは」は、同じことなら、いっそのこと。「死なな」の「な」は、願望。「五月蝿なす」は、五月の蠅のごとくで「騒く」の枕詞。「打棄てては」は、残したままでは、見捨てては。「死には知らず」の「知らず」は、知られずで、できない。「かにかくに」は、とやかくと、あれこれと。「泣かゆ」の「ゆ」は、自発の助動詞。
898の「雲隠り鳴き往く鳥の」は「哭のみし泣かゆ」を導く譬喩式序詞。899の「出で走り去なな」の「な」は、願望。「障りぬ」の「ぬ」は、完了。900の「着る身なみ」は、着物が多くて着る身がないので、の意。「腐し」は、腐らせて。「捨つらむ」は、捨てていることだろう。「はも」は、強い詠嘆で、眼前にないものをあげて、それが今欲しいと思う気持ちを表します。901の「荒栲」は、麻衣や藤衣などの縫い目の粗い布。「着せかてに」は、着せてやれなくて。「すべをなみ」は、どうしようもないので。902の「水沫なす」は「もろき」の枕詞。「栲縄の」は「千尋」の枕詞。「尋」は、男が両手を広げた長さ。「もが」は、願望。903の「しつたまき」は、安物のありふれた腕輪のことで「数にもあらぬ」の枕詞。「もが」は、願望。この歌には「去る神亀二年(725年)作る」との注が付いており、同類の歌なのでここに載せたとあります。
これらの歌について窪田空穂は、次のように評しています。「ここに言っていることは、老齢に加うるに病苦の甚しいものがあり、おなじことならば死にたいと思うが、弁別のつかない幼い児を見ると、死ぬことも出来ないという嘆きである。この嘆きは無知な庶民のこうした際の嘆きといささかの異なりもないものである。その学問をもって起用され、国守としての官に久しくあり、七十四の老齢に至っている憶良であるから、その最後に持った心境は、何らかの特色があるのではないかと想像されるが、その実は全く常凡なもので、それらしいものも持ってはいない。それにまたこの歌の詠風は、素朴で率直でその点では他に例のないものであって、おのずから一種の歌品をなしているのは、これが憶良の心の生地(きじ)であったろうと思わせる」
巻第5-904~906
| 904 世の人の 貴び願ふ 七種(ななくさ)の 宝も我は 何(なに)為(せ)むに わが中の 生まれ出(い)でたる 白玉の わが子 古日(ふるひ)は 明星(あかぼし)の 明くる朝(あした)は 敷妙(しきたへ)の 床の辺(へ)去らず 立てれども 居(を)れども 共に戯(たはぶ)れ 夕星(ゆふつづ)の 夕(ゆうべ)になれば いざ寝よと 手を携(たづさ)はり 父母(ちちはは)も 上は勿(な)下(さか)り 三枝(ささくさ)の 中に寝むと 愛(うつく)しく 其(し)が語らへば 何時(いつ)しかも 人と成り出でて 悪(あ)しけくも 善(よ)けくも見むと 大船(おほぶね)の 思ひ憑(たの)むに 思はぬに 横風(よこしまかぜ)の にふふかに 覆(おほ)ひ来(きた)れば 為(せ)む術(すべ)の 方便(たどき)を知らに 白妙(しろたへ)の 襷(たすき)を掛け まそ鏡 手に取り持ちて 天(あま)つ神 仰ぎ乞(こ)ひ祈(の)み 地(くに)つ神 伏して額(ぬか)つき かからずも かかりも 神のまにまにと 立ちあざり われ乞ひ祈(の)めど 須臾(しましく)も 快(よ)けくは無しに 漸漸(やくやく)に 容貌(かたち)つくほり 朝な朝な 言ふこと止み たまきはる 命絶えぬれ 立ち踊り 足(あし)摩(す)り叫び 伏(ふ)し仰ぎ 胸うち嘆き 手に持てる 吾(あ)が児(こ)飛ばしつ 世間(よのなか)の道 905 若ければ道行き知らじ幣(まひ)はせむ黄泉(したへ)の使(つかひ)負(お)ひて通らせ 906 布施(ふせ)置きてわれは乞(こ)ひ祈(の)む欺(あざむ)かず直(ただ)に率(ゐ)去(ゆ)きて天路(あまぢ)知らしめ |
【意味】
〈904〉世間の人が貴び欲しがる七種の宝であろうと、私にとって何になろう。私たち夫婦の間に生まれてきた白玉のようなわが子古日は、明けの明星が輝く朝になっても、白い布を敷いた寝床を離れず、立っていても座っていても私たちにまとわりつき、宵の明星が出る夕方になると、さあ寝ようと手を取って、父さんも母さんもぼくの側から離れないで、三枝のようにぼくが真ん中に寝るよと、かわいらしくあの子が繰り返し言うので、早く一人前になって悪くも良くもその将来を見たいと、大船に乗ったつもりで頼りにしていたのに、思いもかけずすさまじい風が突然に襲ってきて、どうする方法も手段も分からず、白い布のたすきをかけ、まそ鏡を手に持ちかざして、天の神を仰いでは願い祈り、地の神に伏して額をつき、いかようになりましょうとも、すべては神の思し召し通りにと、立ち上がって狂ったように私は願い祈ったが、しばらくも快方に向かうことなく、だんだん元気がなくなり、日ごとに物も言わなくなり、命が絶えてしまった。飛び上がり地団駄を踏んで叫び嘆き、地に伏し天を仰いで、胸をたたいて嘆いたが、掌中にいつくしんだわが子を、横風に飛ばされて失ってしまった。これが世の中の道なのか。
〈905〉まだ幼いので、黄泉の国への道が分からないだろう。贈り物をするから黄泉の国の使よ、どうかわが子を背負って行ってやってください。
〈906〉お布施を奉って、私はお願いしお祈りします。別の道に誘うことなく、まっすぐ連れて行って、天までの道を教えてやってください。
【説明】
古日(ふるひ)という名の男の子を恋い慕う歌3首とある歌です。憶良帰京後の作と認められ、亡くなった男の子は憶良の子であるのか他人の子であるのか不明ですが、この時の憶良は70歳ぐらいの老齢だったため、知人の子だったかもしれません。歌中の「わが中の生まれ出でたる」「白玉の」「三枝の中に寝む」などの表現から、古日は夫婦の間にやっと授かった子であったことが窺われます。
904の「七種の宝」は仏典にいう七種の珍宝。経典によって異なり、法華経では金・銀・瑠璃(るり)・碼碯(めのう)・硨磲(しゃこ)・真珠・玫瑰(ばいかい)の七つ。「我が中」は、我ら夫婦の間。「白玉のわが子古日」は、白玉のようなかわいい子古日。「明星の」は「明け」の枕詞。「敷妙の」は「床」の枕詞。「夕星の」は「夕」の枕詞。「三枝の」は「中」の枕詞。「人と成り出で」は、一人前の人となり。「悪しけくも善けくも見む」の「悪しけく・善けく」は、いずれも名詞形。悪い者であろうと善い者であろうとも見よう。「大船の」は「憑む」の枕詞。「横風」は、横から吹きつける突風で、子供に突然襲いかかった病を表現したもの。「にふふかに」は未詳ながら、にわかに、か。「方便」は、手段。「白妙の」は「襷」の枕詞。「かからずもかかりも」は、どうなろうとこうなろうと。「立ちあざり」は、取り乱し。「須臾も」は、少しの間も。「漸漸に」は、しだいに。「容貌つくほり」の「つくほり」は未詳ながら、容貌が衰え、か。「たまきはる」は「命」の枕詞。「足摩り」は、じだんだ踏んで悲しがって。「飛ばしつ」は、世間の理法の前には一切の所有が風に吹き飛ばされる塵のようなものだという表現。
905の「道行き」は、死後行くべき冥途への道の行き方。「幣」は、神に捧げる謝礼。「黄泉」は、下方。古来、死後に行く道は地下にあるとされていました。「黄泉の使」は、地下の死の国から死者を迎えに来る使者。「負ひて」は、背に負って。「通らせ」は「通れ」の敬語の命令形。906の「布施」は、仏や僧に贈る品。「欺かず」は、だます意のほかに、誘惑するの意があり、ここはその例。「直に率去きて」は、まっすぐに連れて行って。「天路」は仏教用語で、死後の世界への道。かわいい盛りの幼な子の死後までも思いやり、せめて幣、布施などを尽くしたいとの哀切極まりない気持ちが歌われています。なお、左注に、右の一首は作者未詳ながら、作風が憶良に似ているので、資料の順のまま載せたとあり、右の一首とは906の歌を指すとされます。
窪田空穂によれば、長歌は、明らかに挽歌であるものの、集中に見られる挽歌は、臣下がその主人を悲しんだものや、夫がその妻を哀れんだものが主で、兄が弟を悲しんだものが1首あるほかは、親が子を悲しんだものはこの1首のみです。また、感情のみで終始させ、ひたすらその心を尽くし、子の状態を細かく叙し、それによってしみじみと悲嘆を表している詠み方をしているのもこの1首があるだけで、「歌人としての憶良を見る上では、この歌は『貧窮問答』と相並ぷ代表作と目すべきものである」と述べています。
| 士(をのこ)やも空(むな)しくあるべき万代(よろづよ)に語り継ぐべき名は立てずして |
【意味】
男子たるもの、このまま空しく世を去ってよいものか。いつのいつの代までも語り継がれるほど立派な名を立てないまま。
【説明】
左注に、「山上憶良が重病となった時、藤原朝臣八束(ふじわらのあそみやつか)が河辺朝臣東人(かわべのあそみあずまひと)を使者として容態を尋ねに来させた。憶良は返事を終え、しばらくして涙をぬぐい、悲しみ嘆いて、この歌を口ずさんだ」とある歌です。藤原八束は北家房前の子で、この時19歳。房前が大伴旅人と親交があったことは巻第5-810~820で知られますが、その子の八束が使者を立てて見舞ったことから、藤原北家と旅人・憶良との親密な関係が窺えます。あるいは、若い八束は、憶良を尊敬し師事していたのかもしれません。
「士やも」の「士」は、ヲトコと訓む説があります。ヲノコ説が有力ですが、ヲコトは男子、立派な男子、ヲノコは侍者、従者の意になりゆく語という解釈もあり、決定は難しいとされます。「や」は、反語。「空しくあるべき」は、上掲のような解釈のほか、無為に過ごしてよいものか、あるいは、国歌に対して事功のない意で言っていると解するものもあります。「名」は、名声。憶良は、もはや再起の出来難いことを覚悟していたと思われ、国文学者の土橋寛は、13歳から16歳までの大学の課程を終えた藤原八束が、憶良を教師として招いていたものと推定し、次のように述べています。「『孝経』の”身ヲ立テ道を行ヒ、名ヲ後世ニ揚ゲ、以テ父母ヲ顕スハ孝ノ終リ也”の教えに従うことのできなかった臨終の心情を吐露するものであると同時に、教え子である八束に対して、この教えを実現してほしいとの願いをこめたもの」。
大宰府に赴任していた憶良は大伴旅人に後れて奈良に帰京し、その翌年に、74歳で没したと推定されています。従ってこの歌は天平5年(733年)の作、つまり彼の死の直前の歌であり、生涯最後となった一首です。「口吟此歌」とあるので、この時憶良は既に筆を執ることもできず、筆録したのは河辺東人だったのでしょう。それが八束に伝えられ、のち橘諸兄宅で同席したことのある家持の手に渡り、『万葉集』に残されたものと考えられています。それまでも死を恐れ、生に執着してきた憶良ですが、この辞世の歌ともいうべき歌においても、徹底した執念が感じられます。
憶良が亡くなった時の官位は従五位下・筑前守でしたから、貴族社会での地位は高いとは言えず、自身が思っていたような官吏としての出世は果たせなかったのでしょう。さらに、漢文学の素養が深かった憶良としては、中国の士大夫(したいふ)思想、つまり名を立てることこそが男子の理想像だと考えていたのかもしれません。歌にある「士」は、中国では志を持って徳行を積んだ人のことで、憶良のそうした高いプライドも窺えます。しかし、最終官位こそ高くはなかったものの、大歌人としての彼の名はその後今に至るまで語り継がれ、憶良を知らない人はいないはずです。「語り継ぐべき名」は、十分すぎるほど立てています。
明くる天平6年正月、聖武天皇は宮中に五位以上を集めて宴を賜わりましたが、憶良の姿はもはや無かったことでしょう。
【PR】
山上憶良の略年譜
660年 このころに生まれる
701年 第8次遣唐使の少録に任ぜられ、翌年入唐。この時までの冠位は無位
704年 このころ帰朝。渡唐の功によって正六位下に叙爵
714年 正六位下から従五位下に叙爵
716年 伯耆守に任ぜられる
721年 東宮・首皇子(後の聖武天皇)の侍講に任ぜられる
726年 このころ筑前守に任ぜられ、筑紫に赴任
728年 このころまでに太宰帥として赴任した大伴旅人と出逢う
728年 大伴旅人の妻の死去に際し「日本挽歌」を詠む
731年 筑前守の任期を終えて帰京
731年 「貧窮問答歌」を詠む
733年 病没。享年74歳
 |
古典に親しむ
万葉集・竹取物語・枕草子などの原文と現代語訳。 |
バナースペース
【PR】
遣唐使について
通常4隻の船から構成されたことから「四(よ)つの船」と呼ばれ、1隻あたりの構成員は120~160人だったとみられています。当初は朝鮮半島沿いの北路がとられましたが、新羅との関係が悪化してからは東シナ海を横断する南路をとるようになり、途中で難破することが多くなりました。
遣唐使の目的は、唐の先進的な技術、政治制度や文化、ならびに仏教の経典等の収集にありました。吉備真備・僧玄昉などの留学生・留学僧が唐の文化を日本に持ち帰り、天平文化を開花させました。また754年には唐から高僧鑑真が日本に渡り、唐招提寺を建て日本の仏教に大きな役割を果たしました。遣唐使を通じての日本と唐の関係は非常に密接であったといえます。

万葉集の代表的歌人
磐姫皇后
雄略天皇
舒明天皇
有馬皇子
中大兄皇子(天智天皇)
大海人皇子(天武天皇)
藤原鎌足
鏡王女
額田王
第2期(白鳳時代)
持統天皇
柿本人麻呂
長意吉麻呂
高市黒人
志貴皇子
弓削皇子
大伯皇女
大津皇子
穂積皇子
但馬皇女
石川郎女
第3期(奈良時代初期)
大伴旅人
大伴坂上郎女
山上憶良
山部赤人
笠金村
高橋虫麻呂
第4期(奈良時代中期)
大伴家持
大伴池主
田辺福麻呂
笠郎女
紀郎女
狭野芽娘子
中臣宅守
湯原王

(額田王)
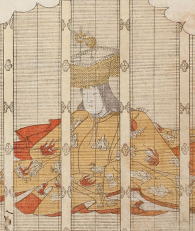
(持統天皇)

(山部赤人)
『万葉集』以前の歌集
これら2つが同一のものか別のものかは定かではありませんが、『万葉集』巻第2・7・9・10・11の資料とされています。
■「柿本人麻呂歌集」
人麻呂が2巻に編集したものとみられていますが、それらの中には明らかな別人の作や伝承歌もあり、すべてが人麻呂の作というわけではありません。『万葉集』巻第2・3・7・9~14の資料とされています。
■「類聚歌林(るいじゅうかりん)」
山上憶良が編集した全7巻と想定される歌集で、何らかの基準による分類がなされ、『日本書紀』『風土記』その他の文献を使って作歌事情などを考証しています。『万葉集』巻第1・2・9の資料となっています。
■「笠金村歌集」
おおむね金村自身の歌とみられる歌集で、『万葉集』巻第2・3・6・9の資料となっています。
■「高橋虫麻呂歌集」
おおむね虫麻呂の歌とみられる歌集で、『万葉集』巻第3・8・9の資料となっています。
■「田辺福麻呂歌集」
おおむね福麻呂自身の歌とみられる歌集で、『万葉集』巻第6・9の資料となっています。
なお、これらの歌集はいずれも散逸しており、現在の私たちが見ることはできません。
【PR】