
由縁ある雑歌(巻第16)~その2
巻第16-3842~3843
| 3842 童(わらは)ども草はな刈(か)りそ八穂蓼(やほたで)を穂積(ほづみ)の朝臣(あそ)が腋草(わきくさ)を刈れ 3843 いづくにぞま朱(そほ)掘る岡(をか)薦畳(こもたたみ)平群(へぐり)の朝臣(あそ)が鼻の上を掘れ |
【意味】
〈3842〉おい、みんな、草なんか刈らなくていいぞ。刈るなら、いっぱい生えているあの穂積のおやじの臭い腋くさを刈れ。
〈3843〉どこにあるのか、朱を掘るのによい岡は。ほら、薦畳のような平群の朝臣の鼻の上を掘れ。
【説明】
3842は、平群朝臣(へぐりのあそみ)が穂積朝臣(ほづみのあそみ)をからかった歌。3843は、穂積朝臣が答えた歌。平群朝臣は、天平勝宝5年(753年)従四位上・武蔵守で没した平群朝臣広成、また穂積朝臣は、天平9年(737年)に外従五位下になった穂積朝臣老人かといわれます。
3842の「草はな刈りそ」の「な~そ」は、禁止。「八穂蓼を」は、多くの穂がある蓼の意から、「穂積」にかかる枕詞。「腋草」は、わき毛。「草」に「臭」を掛けています。3843の「いづくにぞ」は、どこにあるのか。「ま朱」は、水銀の原料にする赤い土。「薦畳」は、薦で編んだ畳で、畳の重(へ)の意で「平群」に掛かる枕詞。平群朝臣の赤い鼻をからかい返しています。
| 3844 ぬばたまの斐太(ひだ)の大黒(おほぐろ)見るごとに巨勢(こせ)の小黒(をぐろ)し思ほゆるかも 3845 駒(こま)造る土師(はじ)の志婢麻呂(しびまろ)白くあればうべ欲しからむその黒き色を |
【意味】
〈3844〉真っ黒な斐太の大黒顔を見ると、そのたびに巨勢の小黒の顔が思い浮かぶことだ。
〈3845〉埴輪の馬づくりの土師の志婢麻呂(しびまろ)は青白いものだから、なるほどその黒色が欲しいのだろうな。
【説明】
色黒を笑った歌。左注に、次のような言い伝えがあるとの説明があります。大舎人(おおとねり)の土師宿祢水通(はにしのすくねみみち)、字(あざな)を志婢麻呂という人がいた。時に、同じく大舎人の巨勢朝臣豊人(こせのあそみとよひと)、字を正月麻呂という者と、巨勢斐太朝臣(こせのひだのあそみ)〈名と字は忘れた。島村大夫(しまむらだいぶ)の息子である〉の二人は、ともにいずれ劣らず顔の色が黒かった。そこで土師宿祢水通がこの歌(3844)を作ってからかったところ、巨勢朝臣豊人はこれを聞いて、即座に答える歌(3845)を作ってからかい返した、という。
3844の「ぬばたまの」は「黒」の枕詞。「斐太の大黒」は、巨勢斐太朝臣のあだ名で、「巨勢の小黒」は、巨勢朝臣豊人のあだ名。前者は色黒で体が大きかったところから飛騨産の大黒馬の意味が込められ、後者は色黒で体が小さかったところから巨勢産の小黒馬の意味が込められているとされます。「大黒」「小黒」というのは、黒毛の馬を呼ぶ通称であり、躰の大きいのが大黒、小さいのが小黒と呼ばれていたといいます。作者の志婢麻呂は、同じ色黒でも、当事者でない人を「大黒」と呼んで表立て、当の相手の巨勢朝臣豊人を「小黒」と呼んでおとしめています。
そうしたことから、3845では「駒造る」の語をもって切り返しています。「駒造る」の「駒」は埴輪の馬のことで、「土師」にかかる枕詞。「土師」は、埴輪などの土器を作る職人。「うべ」は、なるほど、いかにも、の意。作者の巨勢豊人は、こちらを馬に見立てたのなら、お前はその馬を作る立場の土師氏ではないか、しかも、その馬は生きた馬ではなく、土でできたちっぽけな馬ではないか、とやり返したわけです。
巻第16-3846~3847
| 3846 法師(ほふし)らが鬚(ひげ)の剃り杭(くひ)馬つなぎいたくな引きそ法師(ほふし)半(なから)かむ 3847 壇越(だにをち)やしかもな言ひそ里長(さとをさ)が課役(えだち)徴(はた)らば汝(なれ)も半(なか)らむ |
【意味】
〈3846〉法師がそり残した杭のような髭に馬を繋いでも、ひどく引っぱるな、法師が半分になってしまうだろうから。
〈3847〉檀家衆や、そんなことひどいことを言いなさんな。里長が課役を徴収したら、あんたがたも半分になってしまおう。
【説明】
3846は、檀家の者がたわむれて法師(僧侶)をからかった歌、3847は、法師が答えた歌。当時の一人前の男は髭をたくわえていましたが、僧は俗人と区別するために髭を剃っていました。この僧は、剃り残しの髭がずいぶん見苦しかったと見えます。ここでの「鬚」は、耳のあたりの無精鬚。「剃り杭」は、剃った鬚の伸びたのが杭を打ち並べたように見える譬え。結句の原文「僧半甘」を「法師は泣かむ」と訓む説が定説のようですが、斎藤茂吉は、それでは諧謔歌(かいぎゃくか)としては平凡でつまらないとして「法師半かむ」と訓み「半分になってしまうだろう」と解釈しています。
「半らく」と訓む立場は、用例は見られないながらも、ナカラクという動詞があり、半分になるの意であったと想定し、その未然形ナカラカに助動詞のムが接したものとしています。他に「枕く」「鬘く」という動詞があったので、こうした動詞があったとしてもさして不自然とはいえない、と言います。
そして、からかわれた法師も黙ってはいません。3847の「壇越」は、檀家の人々。「な言ひそ」の「な~そ」は、禁止。「里長」は、村長。「課役」は、労役や物納。「徴らば」の「徴る」は、徴収する、無理に取り立てること。50戸を里とし、里ごとに里長を置いて課役を司っていましたが、法師には課役の義務がなかったので、このように言って檀家たちをおどしています。こちらの結句「汝毛半甘」も「汝(いまし)も泣かむ」と訓む立場が有力です。この応酬はどちらが勝ったのか分かりませんが、このようなやり取りが『万葉集』に記録されているのが面白いところです。
なお、奈良朝の時代は仏教の隆盛期だったにもかかわらず、『万葉集』には仏教に関係する歌はあまり見られません。この歌からは、農民階級における仏教の位置や農民と法師との関係性を窺い知ることができ、宗教としての仏教はあくまで上層階級のもので、下層にはそれほど深く浸透しなかったと見えます。
巻第16-3848
| 荒城田(あらきだ)の鹿猪田(ししだ)の稲を倉に上げてあなひねひねし吾(あ)が恋ふらくは |
【意味】
新たに開墾した田の稲、鹿や猪が荒らす田で刈り取った稲を、高床の倉に上げて古米にしたように、ああ、すっかり古びてしまった、私の恋は。
【説明】
題詞に「夢の裏に作れる歌」とあり、左注に、忌部首黒麻呂(いむべのおびとくろまろ)が夢の中でこの恋の歌を作って友に贈った。目が覚めてからその友に暗誦させたところ、夢で贈った通りの歌であったという、とあり、集中、特異な事例です。黒麻呂は、天平宝字2年(758年)に外従五位下、同6年(762年)に内史局図書寮(文書類の管理をする役所)の次官になった人。『万葉集』に短歌4首を残します。
「荒城田」は、新たに開墾した田。「鹿猪田」は、猪や鹿が荒らす田。「倉に上げて」は、税として官倉に上げ納めて、の意。上3句は、そうして倉に納めた稲は、新米でありながら古びた干稲(ひね:前年以前に収穫した稲)のようになってしまうことから「ひね」を導く譬喩式序詞。「あな」は、嘆息。「ひねひねし」は、名詞の「干稲」を形容詞化し「ふるぶるし」の意に転じたもので、干からびている、盛りが過ぎている意。「恋ふらく」は「恋ふ」のク語法で名詞形。この時代、田は平地に作り、住居は山寄りに構えていましたが、新たに開墾する田は次第に山寄りとなってきました。そうした田は鹿や猪に荒らされやすく、稲もよくできなかったのです。
巻第16-3849~3850
| 3849 生き死にの二つの海を厭(いと)はしみ潮干(しほひ)の山を偲(しの)ひつるかも 3850 世間(よのなか)の繁(しげ)き仮廬(かりほ)に住み住みて至(いた)らむ国のたづき知らずも |
【意味】
〈3849〉生と死の二つの苦えあるこの世が厭わしいので、苦海が干上がっところにあるという山(須弥山)にたどり着きたいと、心から思い続けている。
〈3850〉世の中という、煩わしいことばかり多い仮の宿に住み続けながら、願い求める浄土に至ろうと思うけれど、手掛かりも知られないことだ。
【説明】
「世間の無常を厭う」歌。この2首は、かつて明日香村にあった河原寺の仏堂の中にある倭琴(やまとごと)の面に書かれていたという歌で、『万葉集』には珍しい欣求浄土(ごんぐじょうど)の仏教思想が詠まれています。河原寺の一僧侶が、本心を託しひそかに願をかけた歌だろうとされます。河原寺は敏達天皇の御代の創建で、飛鳥寺・薬師寺・大官大寺とともに「飛鳥四大寺」に数えられていたといわれます。歌が書かれていたという倭琴は、日本古来の6弦の琴であり、本来は神前の物だったのが、この時代には仏寺の斎会にも用いられるようになったようです。また、『日本書紀』には、686年に新羅からの客をもてなすために河原寺の伎楽団を筑紫に送ったことが記されています。河原寺の僧たちも倭琴を奏でる練習に励んでいたのでしょうか。
3849の「生き死にの二つの海」は現世のことで、この世の苦しみを海に譬えた「苦海(くかい)」という仏教語から来ています。「潮干の山」は、生死を解脱した涅槃の地である須弥山(しゅみせん)のことで、古代インドの世界観のなかで中心にそびえる山。3850の「仮廬」は仮に造った小屋で、現世を具象的に言ったもの。「住み住みて」は「住み」を重ねて、住み続けの意を表したもの。「至らむ国」は至るべき国で、極楽浄土。「たづき知らずも」の「たづき」は、方法、手掛かり。手掛かりが知られないことだ。
これらの歌は琴への落書きとはいえ、思いがけぬ場所に先人のこういう歌を発見した時の感慨は一入で、その感慨が口から口へと語り伝えられ、やがて『万葉集』に収録されることになったのでしょう。悟りの境地に達したいと願う真摯な思いが込められており、内容も極めて高度なもので、河原寺での厳しい規律下での修行生活を窺い知ることができます。
巻第16-3851
| 心をし無何有(むがう)の郷(さと)に置きてあらば藐孤射(ばこや)の山を見まく近けむ |
【意味】
心さえ無何有の郷に置いていれば、藐孤射の山を見ることのできる日も近いだろう。
【説明】
「心をし」の「し」は、強意の副助詞。「無何有の郷」は、『荘子』逍遥遊篇に見える、自然のままで何の作為もない理想郷。無心(無念無想)の譬え。「藐孤射の山」は、同じく『荘子』に見える、中国で不老不死の仙人が住んでいるという想像上の山。奈良時代に流行っていた神仙思想につながりがあり、『荘子』を読んだことのある奈良朝の知識人が作った歌とされます。「見まく」は、見ること。「近けむ」は、近く見ることができるであろう。
巻第16-3852
| 鯨魚(いさな)取り海や死にする山や死にする 死ぬれこそ海は潮干(しほひ)て山は枯れすれ |
【意味】
海は死んだりするだろうか。山は死んだりするだろうか。いや、死ぬからこそ、海は干上がり、山は枯れ山になる。
【説明】
旋頭歌形式(5・7・7・5・7・7)の歌で、問答を1首にしたもの。「鯨魚取り」は、鯨(くじら)を獲る所の意で「海」にかかる枕詞。「海や死にする」の「や」は、疑問の係助詞で、反語となるもの。海が死のうか、死にはしない。「山や死にする」も同じ。しかし、常住不変に見える海や山でさえも、衰亡を免れることができないと歌い、もともと常住の存在でない人のはかなさをより際立たせています。深い無常観が窺われる歌であり、迷いや悲しみを永久に繰り返すのだという輪廻の思想も、意識の根底にありそうです。なお、シンガーソングライターのさだまさしさんの曲に『防人の詩』というのがあり、「海は死にますか、山は死にますか」の歌詞で有名ですが、その原案となったのが、この詠み人知らずの歌です。
巻第16-3853~3854
| 3853 石麻呂(いしまろ)に我(わ)れ物申(ものまを)す夏痩(なつや)せによしといふものぞ鰻(むなぎ)捕(と)り食(め)せ 3854 痩(や)す痩(や)すも生けらばあらむをはたやはた鰻(むなぎ)を捕(と)ると川に流るな |
【意味】
〈3853〉石麻呂さんにあえて物申しましょう。夏痩せによく効くというウナギを捕ってお食べなさい。
〈3854〉(いや待てよ)いくら痩せていても生きてさえいればいいのだから、万が一にも鰻を捕ろうとして川に流されなさんなよ。
【説明】
題詞に「痩せる人を嗤笑(わら)へる歌」とあり、左注に次のような説明があります。吉田連老(よしだのむらじおゆ)、通称、石麻呂という人がおり、世に仁敬(じんけい)と呼ばれている人の息子である。生まれつき体がひどく痩せていて、どれほどたくさん飲み食いしても、姿は飢饉によって飢えた餓者のようであった。そこで大伴家持が気まぐれにこの歌を作ってからかった。石麻呂は、百済から渡来した医師・吉田連宜(よしだのむらじよろし)の息子で、家持とは父の旅人とともに親交があったようです(巻第5-864~847ほか)。「むなぎ」は、鰻の古名。3854の「はたやはた」は、万が一にも。1首目には敬語を用いて鄭重に言っているのに対し、2首目では敬語を取り払い、おちょくった物言いになっています。
史料上で「鰻」が初出となるのが家持のこの歌です。土用の丑の日に鰻を食べるようになったのは、江戸時代の蘭学者・平賀源内の発案によるとされますが、はるか上代のころに、すでに夏痩せには鰻がいいとされていたことが窺えます。もっとも当時は、今のように開いて蒸したり焼いたりする蒲焼ではなく、鰻を丸ごと火にあぶって切り、酒や醤(ひしお)などで味付けしたものを山椒や味噌に付けて食べていたといいます。あまり美味しそうではありません。
巻第16-3855~3856
| 3855 皂莢(さうけふ)に延(は)ひおほとれる屎葛(くそかづら)絶ゆることなく宮仕(みやつか)へせむ 3856 波羅門(ばらもん)の作れる小田(をだ)を食(は)む烏(からす)瞼(まぶた)腫(は)れて幡桙(はたほこ)に居(を)り |
【意味】
〈3855〉サイカチの木に這いまつわるヘクソカズラのように、絶えることなく宮仕えしたいものだ。
〈3856〉波羅門さまが耕してらっしゃる田の稲を食い荒らしたカラスは、瞼ががふくれあがって旗竿にとまっている。
【説明】
高宮王(たかみやのおおきみ:伝未詳)が、数種の物を詠んだ歌2首で、題詠であったと見られます。。3855の「皂莢」は、マメ科の落葉高木のサイカチで、その実を薬用とします。「延ひおほとれる」の「おほとれる」は、乱れからみつく。「屎葛」は、悪臭を放つ蔓草のヘクソカズラ。以上3句は、葛の蔓の絶えない意で「絶ゆることなく」を導く譬喩式序詞。清浄な「皂莢」と不浄な「屎葛」とを取り合わせて序詞に持ち込んだのが眼目になっており、我が身を「屎葛」に寓していると見られ、いささか自嘲の念が込められているようです。
3856の「波羅門」は、インド四姓の最高位で、ここでは、天平8年(736年)に中国から渡来したインドの仏教僧で、波羅門僧正とよばれた菩提僊那(ぼだいせんな)を指すとされます。東大寺大仏開眼の際に導師を務め、その功により僧正に任ぜられ、荘田を賜わりました。「小田」の「小」は、美称。「幡桙」は、法事の際に寺の庭に立てる幡(ばん)を支える竿。カラスはもともと瞼が腫れているように見えるのを、仏罰が当たったものと見ています。また、頭音ハの語が多くあり、数種の物を任意に詠む歌の一つの特徴を追っています(3832・3833)。
なお、和歌は、和語(大和言葉)で歌われることを原則とし、漢語は排除され、『万葉集』においてもその徹底が見られますが、巻第16には、仏教語を中心に漢語を意識的に使った歌が何首かあり、ここの「波羅門」のほかには、「餓鬼(がき)」「檀越(だんをち)」などの語が見られます。
巻第16-3857
| 飯(いひ)食(は)めど うまくもあらず 行き行けど 安くもあらず あかねさす 君が心し忘れかねつも |
【意味】
ご飯を食べても美味しくないし、いくら歩き回っても心は落ち着きません。あなたの真心を忘れようにも忘れることができません。
【説明】
題詞に「夫君に恋ふる歌」とある『万葉集』最短の長歌で、左注に「伝へて云はく」と、次のような説明があります。「佐為王(さいのおおきみ)のお邸に、お傍近く仕える召使いの女がいた。夜も昼も仕えているので、夫になかなか逢えなかった。心は鬱々として晴れず恋しさに沈みきっていた。すると、宿直の夜に夢の中で夫と逢い、驚いて目覚め、手探りで抱きつこうとしたが、まったく手に触れることができない。そこで涙にむせんですすり泣き、大きな声でこの歌を吟詠した。王はこれを聞いてあわれに思い、それからはずっと宿直を免じた」。
佐為王は、葛城王(橘諸兄)の弟で、天平8年に兄とともに臣籍に下り、橘宿禰の姓氏を賜わった人。「あかねさす」は、血色のよい意で、「君」の枕詞。「行き行けど」は、原文「雖行往」で「寝(い)ぬれども」と訓み、「寝ても安らかに眠れない」と解釈するものもあります。「心し」の「し」は、強意の副助詞。「心」は原文では「情」という字になっており、それを「こころ」と読ませています。そのような例は『万葉集』には多くあり、情と書いた場合と、心と書いた場合とでは、同じ「こころ」でも、何かニュアンスの広がりの違いが感じられるところです。
この歌は、中国古典の恋愛文学『遊仙窟』 を下敷きにしており、伊藤博は次のように述べています。「歌が中国の名句によって操られたという推察は、左注のありようによっても納得がいく。この話は、中国色を背景に据えながら日本の王の慈愛を伝えるものとしてもてはやされたのであろう。この場合、歌は、近習の婢が詠んだという形にしたもので、実作者は別にいることはいうまでもない」。実際の作者は山上憶良、あるいは竹取翁の歌などと同様、下級官人層の某人ではないかとも言われます。
巻第16-3858~3859
| 3858 このころの我(あ)が恋力(こひぢから)記(しる)し集め功(くう)に申(まを)さば五位の冠(かがふり) 3859 このころの我(あ)が恋力(こひぢから)給(たま)らずは京兆(みさとづかさ)に出(い)でて訴(うれ)へむ |
【意味】
〈3858〉近ごろ、私が恋に費やしている労力を記録して集め、功績に換算して願い出たら、五位の冠に匹敵するだろう。
〈3859〉このところの恋に費やした私の労力にごほうびを頂けないなら、京の役所に行って訴え出てやる。
【説明】
恋の苦しさを、労役や位階昇進にたとえ、エリート官僚になり損ねた自身を滑稽に歌っている男の歌です。3858の「恋力」は、恋に要した苦労。「功」は、官位昇進の根拠となる功績。「功に申さば」は、功績として上申したならば。当時の官人の人事制度では、考課令に、官人は年に一回、自らの行跡の功過(功績と過失)を記録して上申することと定められていました。勤務評定の等階は、上上、上中、上下、中上、中中、中下、下上、下中、下下の9つに分かれており、さらに細かい規定がありました。「五位」は、宮中の位階のことで、従五位下以上が勅叙で貴族とされ、およそ150名ばかり。五位以上は殆どが出自によりましたから、下級官人からみればはるかに遠い雲の上の存在でした。
3859の「給らずば」は、賞をくださらないなら。里に住んでいる者に対し、里長がくれる賞のことを言っています。「京兆」は、本来は都の警察・司法・行政を司る役所のことで、右京と左京に分かれ、左右2人の長官がいました。ただし官人の人事は管轄外でしたから、ここでは広く都の役所の意味で言っているようです。いずれの歌も、恋と官位の双方に対する憧憬が込められており、多くの下級官人たちの間で折あるごとに誦われたものかもしれません。
巻第16-3870~3873
| 3870 紫(むらさき)の粉潟(こかた)の海に潜(かづ)く鳥(とり)玉潜き出(で)ば我(わ)が玉にせむ 3871 角島(つのしま)の瀬戸(せと)のわかめは人のむた荒かりしかど我(わ)れとは和海藻(にきめ) 3872 我(わ)が門(かど)の榎(え)の実(み)もり食(は)む百千鳥(ももちとり)千鳥(ちとり)は来(く)れど君ぞ来(き)まさぬ 3873 我(わ)が門(かど)に千鳥(ちとり)しば鳴く起きよ起きよ我(わ)が一夜夫(ひとよづま)人に知らゆな |
【意味】
〈3870〉粉潟(こがた)の海に潜ってあさる鳥が、真珠をくわえて出てきたら、それは私の玉にしてしまおう。
〈3871〉角島の瀬戸のわかめは、人の前では荒々しいけれど、私の前では柔らかいわかめ。
〈3872〉私の家の門口に立つ榎(えのき)の実をついばむ鳥たちはたくさん集まってくるけど、あなたは一向にいらっしゃらない。
〈3873〉もう門のところには、多くの鳥がしきりに鳴いて夜が明けました。あなたよ、起きて起きて。私がはじめてお逢いしたあなたよ、人に知られずにお帰りください。
【説明】
3870の「紫の」は「粉潟」の枕詞。紫はその根を粉末にして染料にするので、その粉の意か。「粉潟」は所在未詳ながら、巻第12-3166に「越の海の子難(こがた)の海の島ならなくに」とあるので、越の海のどこかではないかとする説があります。一方、前歌群や次歌との配列から見て、筑前圏に関係する歌であろうとする見方もあります。「潜く鳥」は、餌をとるために海に潜る鳥。「玉」は真珠で、女性の比喩。すると、「潜く鳥」は、娘を育てる母親あるいは仲介者を意味していると考えられます。中央官人の旅の歌かもしれません。
3871の「角島」は、山口県の西北端にある島で、牛の角のように2つの岬が突き出ているところから、この名が付いたとされます。『延喜式』に「角島牛牧」とあって官牧が行われたところです。この海域も志賀の海人たちの漁撈領域であったと考えられます。「瀬戸」は、狭い海峡。「わかめ」は、ワカメと若妻を掛けています。「人のむた」は、人と共にあれば。「荒かりしかど」は、食べての舌触りが荒かったことに、態度が荒々しかったことを喩えています。「和海藻」は、柔らかい海藻、ワカメ。角島に住んでいる男が、土地の若い娘を得ようとして他の男たちと競い、我がものとしたのを喜んでいる歌です。
3872は、女が男を待つ歌、3873は、女が男を送り出す歌。3872の「もり食む」は、もいでついばむ意か。「百千鳥」「千鳥」は多くの鳥。「榎」が歌われていますが、『万葉集』の中で、榎を詠んだ歌はこの1首のみです。秋にはたくさんの丸い実がなり、その実を目当てに多くの鳥が集まってきます。ここは、女好きの男が大勢寄って来る譬えとなっています。「来まさぬ」は「来ぬ」の敬語。3873の「一夜夫」は、一夜だけ床を共にした行きずりの男、あるいは初めて一夜を共寝した夫。「知らゆな」の「ゆ」は、受身、「な」は、禁止。浮気の発覚を心配する女が、早々に男を追い出そうとする歌になっています。ここの歌は、何故に「由縁」ある歌とされたのかよく分からないという見方がありますが、伊藤博は、「2首相寄ってしたたかな女を語って、ひとかどの由緒を持つといえる」と述べています。
巻第16-3874
| 射(い)ゆ鹿(しし)を認(つな)ぐ川辺(かはへ)のにこ草(ぐさ)の身の若(わか)かへにさ寝(ね)し子らはも |
【意味】
射られた手負い鹿の跡を追っていくと、川辺ににこ草が生えていた。そのにこ草のように若かった日に、あの子と寝たのが忘れられない。
【説明】
年配の男の歌。「射ゆ鹿」は、矢で射られた手負いの鹿。この時代、鹿狩りは、天皇から狩人まで上下の身分を問わず好まれた狩猟でした。「認ぐ」は、足跡を追っていく。「にこ草」は、若くてやわらかい草。上3句は「身の若かへに」を導く譬喩式序詞。「若かへ」は他に例がなく語義未詳ながら、若いころの意か。「さ寝し」の「さ」は、接頭語。「子らはも」の「子ら」は、複数形ではなく男性が女性を親しんで呼ぶ語。
第2句の「認ぐ」には目当ての女性を追い求めて行く意が寓されており、「にこ草」は、結句の「さ寝し」とある共寝の床をにおわせているとされます。草に共寝を歌う歌は、集中に多く見られます。二度と戻らない、青春時代の恋人との甘美な思い出に浸っている歌です。
巻第16-3875
| 琴酒(ことさけ)を 押垂小野(おしたれをの)ゆ 出(い)づる水 ぬるくは出でず 寒水(さむみづ)の 心もけやに 思ほゆる 音(おと)の少なき 道に逢はぬかも 少なきよ 道に逢はさば 色(いろ)げせる 菅笠小笠(すがかさをがさ) 我(わ)がうなげる 玉の七つ緒(を) 取り替へも 申(まを)さむものを 少なき 道に逢はぬかも |
【意味】
押垂小野から湧き出す水は、ぬるくはなく、冷たい水で、そんな水のように心がひやりとする人の声のしない道で、あなたと逢えないものか。
人声の少ない道でお逢いしたなら、あなたの色美しい菅笠小笠と、私が首にかけている七連の玉飾りをお取り替えしようものを。人声の少ないこの道でお逢いできないかしら。
【説明】
1首の長歌ですが、2段構成の歌で、前半と後半で男女の問答のようになっています。「琴酒を」の「琴酒」は「殊酒」すなわち上等な酒の意で、押して(圧して)搾り垂らして作るところから「押垂」にかかる枕詞。「押垂小野」は地名ととれ、岩を垂れて流れる滝が存在したことによる名らしくありますが、所在未詳。「ゆ」は、起点・経由点を示す格助詞。「琴酒を~寒水の」は「心もけやに」を導く序詞。「けやに」は、際立って。「音」は、人の気配。「逢はぬかも」の「ぬかも」は、願望。「色げせる」は、色どったの意か。「菅笠小笠」の「小」は愛称で、菅を編んで作った笠。「うなげる」は、首にかけている。「取り替へ」は、交換して、で、契りの証し。
清涼な泉の描写と静かな道を背景に、淡い恋心や切なさを詠んでいるように感じられる歌ですが、どういう状況で詠まれたものか明確でなく、これを歌垣のような場での掛け合いであるとする見方があります。男の「音の少なき道に逢はぬかも」と女の「少なき道に逢はぬかも」は双方が同じことを述べて同調しているように見えるものの、男の意図が、逢って共寝をしたい点にあるのに対し、女の「道に逢ふ」は「取り替へも申さむものを」を前提としており、互いの持ち物を交換する、つまりまずは夫婦のきちんとした約束を結ぶために逢いたいという意になるといいます。共寝には同意するものの、まずは約束を固めてからでないと信用できない、と。
巻第16-3876~3877
| 3876 豊国(とよくに)の企救(きく)の池なる菱(ひし)の末(うれ)を摘(つ)むとや妹(いも)がみ袖(そで)濡(ぬ)れけむ 3877 紅(くれなゐ)に染めてし衣(ころも)雨降りてにほひはすとも移(うつ)ろはめやも |
【意味】
〈3878〉豊国の企救(きく)の池に浮かぶ菱の実、その実を摘み取ろうとして、お前さんの袖は濡れてしまったのかい。
〈3877〉紅に染め上げた着物は、雨が降ったからといって、色はいっそうあざやかに映えることはあっても、色あせることなどあるものですか。
【説明】
3876は、豊前国(ぶぜんのくに)の海人の歌。「豊前」は、福岡県東部から大分県北部にあたり、「豊国」が豊前と豊後に分割された後の称。「企救」は、北九州市門司区・小倉北区・小倉南区。瀬戸内海を船で下った場合、ここに着いてから大宰府に向かうので、交通の要衝だった地です。「菱」は、池や沼に自生する水草。根は泥の中にあり、水中茎が水面の上に出て葉を付けます。「末」は、枝や葉の先端。「み袖」の「み」は美称。企救はまた、遊行女婦が多くいた地とされ、そういう女たちとの宴飲の場で詠まれた歌だったかもしれません。
3877は、豊後国(ぶんごのくに)の海人の歌。「豊後」は、大分県の大部分。「にほひ」は、色の美しく照り映えること。「移ろふ」は、色が褪せる。「やも」は、反語。紅花で染めた紅色は退色しやすいけれども、自分の着ている紅染めだけは違う、つまり「自分は決して心変わりなどしない」と言っている恋歌です。男女どちらの歌とも取れますが、着物を染めるのは女の業であるので、女の誓いであろうとされます。
巻第16-3878
| はしたての 熊来(くまき)のやらに 新羅斧(しらきをの) 落(おと)し入れ わし かけてかけて な泣かしそね 浮き出(い)づるやと見む わし |
【意味】
熊来の沼に新羅の斧を落っことしてしまったどうしよう、わっしょい。気にしすぎて泣きなさんな、浮き出てくるかもしれんぞ、見ていてやろう、わっしょい。
【説明】
能登の国の民謡とされる歌です。左注に、伝わるところでは、あるとき愚かな木こりが斧を海に落としてしまったが、鉄が水に沈んでしまえば浮かび上がることがないのを理解できなかった。そこでもう一人の木こりが即興でこの歌を作り、口ずさんで諭(さと)してやった、とあります。しかし、歌にある「浮き出づるや見む」というのが「諭す」ことになるのか、理解に苦しむところです。むしろ、泣いている木こりは鉄が浮かんでこないのを理解しているから泣いているのであり、諭す方が、それを理解できない愚か者で「浮き出づるや見む」と言っているとみるべきではないでしょうか。
「はしたての」は「熊木」の枕詞ですが、その意味はよく分かっていません。「熊木」は、能登湾西岸の七尾市中島町にあった村。「高麗木(こまき)」から来た言葉で、朝鮮半島からの渡来人が多く住んでいたといいます。現在では「熊木川」という川にその名が残っています。「やら」は語義未詳ながら、水底の意か。「新羅斧」は、新羅から渡来した斧。「かけてかけて」は、気にしすぎて。「な泣かしそね」の「泣かす」は「泣く」の敬語、「な~そね」は禁止。「わし」は「わっしょい」とか「よいしょ」などに類する囃し言葉。
巻第16-3879
| はしたての 熊来(くまき)酒屋(さかや)に まぬらる奴(やつこ) わし さすひ立て 率(ゐ)て来(き)なましを まぬらる奴 わし |
【意味】
熊来の酒屋で怒鳴られている奴さん、わっしょい。引っ張り出して連れてきたい、どなられている奴さんを、わっしょい。
【説明】
酒を造る店で働いている男が主人に怒鳴られている、あるいは酒を盗んで捕まって怒鳴られている男に同情して詠んだ歌のようです。「はしたての」は「熊来」の枕詞。「まぬらる」は、怒鳴られる意とされます。「さすひ立て」の「さすひ」は「さそふ」の訛り。「立て」は、立ち上がらせ。「率て」は、連れて。3878の歌にもあった「わし」という囃し言葉は能登の歌以外に見られないことから、当地独特の歌い方であったようです。前の3878と同一の作者とみられます。
巻第16-3880
| 鹿島嶺(かしまね)の 机(つくゑ)の島の しただみを い拾(ひり)ひ持ち来て 石もち つつき破(やぶ)り 速川(はやかは)に 洗ひ濯(すす)ぎ 辛塩(からしほ)に こごと揉(も)み 高坏(たかつき)に盛(も)り 机に立てて 母にあへつや 目豆児(めづこ)の刀自(とじ) 父にあへつや 身女児(みめこ)の刀自 |
【意味】
鹿島嶺近くの机の島のしただみ貝を拾い集めてきて、石でこつこつ突き割り、早い川の流れで洗いすすぎ、辛い塩でごしごし揉んで、高坏の器に盛って机の上にきちんと立てて、お母さんにご馳走したのかい、可愛いおかみさん、お父さんにご馳走したかい、かわいいおかみさん。
【説明】
能登国の歌。子どもに料理の手順を教える童歌ではないかとされますが、何とも微笑ましく愛らしい歌で、まだ幼い女の子が一生懸命に料理の真似ごとをしている姿が目に浮かぶようです。また一方、主婦権を委譲された若い主婦が両親に食事を差し上げていることをうたった歌ではないかとの見方もあります。「鹿島嶺」は、石川県七尾市付近の山、「机の島」は、和倉沖の小島とされます。「しただみ」は、円錐形の小さな巻貝。「い拾ひ」の「い」は、接頭語。「拾ひ(ひりひ)」は「ひろひ」の古語。「速川」は、水の流れの速い川。「こご」は、ごしごしと揉み洗う音。「目豆児」は、可愛い子、珍しい子。幼女を主婦に見立てて「刀自」と呼んでいます。「身女児」は語義未詳ながら、華奢な体つきからとらえた語ではないかとみられます。”めづこ”と”みめこ”、どちらも可愛いらしい呼び名です。
庶民のほのぼのとした生活風景が込められた作品であり、鴻巣盛広による『全釈』では次のように述べられています。「集中に多い民謡の中でも、内容的に珍しい佳作である。父母に侍養せよと教える孝道のあらわれなどと、道徳的に見るわけではないが、和平悦楽、上代の朗らかな民族があらわれていると思う」。
巻第16-3881~3884
| 3881 大野道(おほのぢ)は茂道(しげち)茂路(しげみち)茂(しげ)くとも君し通(かよ)はば道(みち)は広けむ 3882 渋谿(しぶたに)の二上山(ふたがみやま)に鷲(わし)ぞ子(こ)産(む)といふ 翳(さしは)にも君のみために鷲(わし)ぞ子(こ)産(む)といふ 3883 弥彦(いやひこ)おのれ神(かむ)さび青雲(あをくも)のたなびく日すら小雨(こさめ)そほ降る [一云 あなに神さび] 3884 弥彦(いやひこ)神(かみ)の麓(ふもと)に今日(けふ)らもか鹿(しか)の伏(ふ)すらむ皮衣(かはころも)着て角(つの)つきながら |
【意味】
〈3881〉大野へ続く道は茂りに茂っているけれど、あなたがこうしてしげしげと通っておいでになれば、道はきっと広がるでしょう。
〈3882〉渋谷の二上山に鷲が子を産むといいます。翳(さしは)にでもなって君のお役に立とうと、鷲が子を産むといいます。
〈3883〉弥彦の山はおのずと神々しくて(ほんとうに神々しくて)、青雲のたなびくこんな晴れた日ですら、小雨がしとしとと降っている。
〈3884〉弥彦の山の麓では、今日もまた鹿がひれ伏しているだろうか。毛皮の着物を着、角を立てたまま。
【説明】
越中(こしのみちなか)の国の歌4首。「越中」は、富山県。3881の「大野」は、礪波(となみ)郡大野の地とされます。女による誘い歌のようですが、本来は女の恋歌で、通ってくる男の身分や勢いを讃えた歌だったのを、新任の国守を迎えた郡司などが歓迎ぶりを表すために利用した歌といわれます。国守を歓迎し賛美するに相応しいものになっています。
3882は旋頭歌形式(5・7・7・5・7・7)の歌。「渋谿」は、越中国府の北、高岡市の海岸で、二上山の麓にあたります。「二上山」は、国府の傍の小山。「翳」は、貴人の後ろや左右からさしかける柄の長い団扇。郡司たちがその地で捕った鷲の羽毛で作った翳を国守のためにしつらえ、それを題材に歌って讃えたものでしょうか。この歌について窪田空穂は、「二上山に鷲の卵を見出したという珍しい噂の立った時、その国の何者かが、それを領主の瑞兆であるとして、その心をいったものである」と説明しています。
3883の「弥彦」は、新潟県西蒲原郡にある山で、もと信濃川以西は越中に所属していましたが、大宝2年(702年)に越中の4郡を越後所属に変更しています。この地は古来、地元の農漁民の信仰を集めたところで、東麓にある弥彦神社は越後一の宮と称され、北国街道に沿って門前町をなしています。「おのれ」は、自然に、おのずから。「神さび」は、神々しいさま。「青雲」は、青天に薄くたなびく灰色がかった雲。当時の「青」は、黒と白の中間色を漠然と指していたらしく、緑、藍から灰色までをも含む色とされました。この「青雲」は雨雲ではなく、聖なる山には、晴れの日でも、天つ水すなわち天の呪力を宿す小雨が降ることを歌っています。
3884は、『万葉集』唯一の仏足石歌体の歌(5・7・5・7・7・7)。弥彦の神に詣でた人が、鹿が伏すようすを、神に仕えるため畏まって平伏していると見ています。「今日らもか」の「ら」は、接尾語。「伏すらむ」の「らむ」は、現在推量。前歌とともに弥彦の神のあらたかさに畏まる歌であり、3883は山を眼前にしての詠、3884は山を想像しての詠という形になっています。
巻第16-3885
| いとこ 汝背(なせ)の君 居(を)り居(を)りて 物にい行くとは 韓国(からくに)の 虎(とら)といふ神を 生け捕りに 八(や)つ捕り持ち来(き) その皮を 畳(たたみ)に刺(さ)し 八重畳(やへたたみ) 平群(へぐり)の山に 四月(うづき)と 五月(さつき)との間(ま)に 薬狩(くすりがり) 仕(つか)ふる時に あしひきの この片山に 二つ立つ 櫟(いちひ)が本(もと)に 梓弓(あづさゆみ) 八(や)つ手挟(たばさ)み ひめ鏑(かぶら) 八(や)つ手挟(たばさ)み 鹿(しし)待つと 我(わ)が居(を)る時に さ雄鹿(をしか)の 来立ち嘆かく たちまちに 我(われ)は死ぬべし 大君(おほきみ)に 我(われ)は仕(つか)へむ 我(あ)が角(つの)は み笠(かさ)のはやし 我(あ)が耳は み墨壺(すみつほ) 我(あ)が目らは ますみの鏡 我(あ)が爪は み弓の弓弭(ゆはず) 我(あ)が毛らは み筆(ふみて)はやし 我(あ)が皮は み箱の皮に 我(あ)が肉(しし)は み膾(なます)はやし 我(あ)肝(きも)も み膾はやし 我(あ)がみげは み塩(しほ)のはやし 老(お)いはてぬ 我(あ)が身一つに 七重(ななへ)花咲く 八重(やへ)花咲くと 申(まを)しはやさね 申しはやさね |
【意味】
さあ、そこのすてきな旦那さん、いつもお家にいらっしゃるのに、どこかにお出かけになるなんて、からっきし億劫なもの。その韓(から)の国の虎という怖い神様を、八頭も捕らえて持ち帰り、その皮を畳のように敷物に織って八重の敷物になさる、その八重に畳み重なる平群の山で、四月から五月にかけて薬狩りの行事があり、ご奉仕申し上げた次第。山の斜面に二本立っている櫟の木の根元で、八本の弓矢を構え、ひめ鏑を八本掴んで、鹿を待ってたら、ひょこっと雄鹿がやってきて嘆くのだ。私は射られてもうすぐ死ぬはずの身。どうせ死ぬなら大君のお役に立ちたい。私の角は御笠の飾り、私の耳はお墨を入れる壺、私の目は澄んだ鏡、私の爪は弓弭、私の毛はお筆の材料、私の皮はお箱の皮に、私の肉はお膾の材料、私の肝もお膾の材料、私の胃袋は塩辛の材料。老い果てた私の身一つに、七重にも花が咲いた、八重にも花が咲いたことよと、大君に申し上げてほめてやってください、申し上げてほめてやってください。
【説明】
「乞食者(ほかいびと)が詠ふ歌」と題された1首目で、「鹿のために痛みを述べて作った歌」と左注にあります。「乞食者」がどんな人を指すのかについては、古来議論がなされ、文字通りの乞食という意味ではなく、芸を売る見返りに食を得ていた、芸能民の類だろうというのが有力説となっています。さらに歌が、天皇のお役に立ち、奏上申し上げるという祝言の歌の形式(寿歌)になっているところから、お祝いの席でいつも詠まれる歌ではなかったかとする見方もあります。
歌の内容は極めて痛烈であり、死を目前にした鹿が、みずからの体の各部分について、その用途を逐一述べ立てており、そうして天皇のお役に立つことを自分に代わって奏上し、ほめてやってください、と乞食者に懇願しているというものです。家々の門口や辻などで、その鹿に乞食者が扮し、鹿の身振りで演技しながら詠じたのかもしれません。
この歌が作られたのは飛鳥時代だったろうと考えられており、天武・持統朝を中心に、古代天皇制が隆盛をきわめた時代でした。天皇が「現(あき)つ神」として意識された時代であり、天皇のために死ぬことが無上の歓びだとする思想が、この歌の根本にあるとされます。しかしながら、左注には「鹿のために痛みを述べて」作った歌とあり「寿歌」というような捉え方はなく、そうした人たちの意識とは、大きな懸隔があることが窺えます。とは言ってもそれは人間批評とか天皇批判とかを意識したものではなく、あくまで人間という動物が、他の動物を平然と料理して生活を楽しむことに対する痛恨、人間としての深い同情を述べたものと考えられるのです。
「いとこ」は、親しい者への呼びかけの語。「汝背の君」は、相手を親しんでの呼びかけ。聴衆あての表現。「居り居りて物にい行くとは」は、家にずっと居てどこかに出かけるというのは面倒で辛い意で「辛(から)し」を起こし、「韓国(中国・朝鮮)」を導く序詞。さらに「韓国の~畳に刺し」が「八重畳」の譬喩式序詞。「八重畳」は「隔(へ)の意で「平群」の枕詞。「平群の山」は、奈良県生駒市の南部から生駒郡平群町にかけての山地で、これ以下が本題。「薬狩」は、陰暦5月5日、薬用に鹿の生え変わったばかりの角などを採る宮廷行事。「櫟」は、ブナ科の常緑高木。「梓弓」は、梓の木で作った弓。「ひめ鏑」は、鏑矢の一種。「嘆かく」は、嘆くことには。「たちまちに」以下が、鹿の言葉。「はやし」は、引き立たせるもの、美しくさせるもの、の意の名詞。「弓弭」は、弓の両端の弦をかけるもの。「膾」は、生肉を刻んだ料理。「みげ」は、胃袋。「申しはやさね」の「はやす」は、褒め讃える。「ね」は、願望の助詞。
巻第16-3886
| おしてるや 難波(なには)の小江(をえ)に 廬(いほ)作り 隠(なま)りて居(を)る 葦蟹(あしがに)を 大君(おほきみ)召すと 何せむに 我(わ)を召すらめや 明けく 我が知ることを 歌人(うたひと)と 我を召すらめや 笛(ふえ)吹きと 我を召すらめや 琴(こと)弾きと 我を召すらめや かもかくも 命(みこと)受けむと 今日(けふ)今日と 飛鳥(あすか)に至り 立つれども 置勿(おくな)に至り つかねども 都久野(つくの)に至り 東(ひむがし)の 中の御門(みかど)ゆ 参入(まゐ)り来て 命受くれば 馬にこそ ふもだし懸(か)くもの 牛にこそ 鼻縄(はなづな)はくれ あしひきの この片山の もむ楡(にれ)を 五百枝(いほえ)剥(は)き垂れ 天(あま)照(て)るや 日の異(け)に干し さひづるや 韓臼(からうす)に搗(つ)き 庭に立つ 手臼に搗き おしてるや 難波の小江の 初垂(はつたり)を からく垂れ来て 陶人(すゑひと)の 作れる瓶(かめ)を 今日行きて 明日(あす)取り持ち来(き) 我が目らに 塩塗りたまひ きたひはやすも きたひはやすも |
【意味】
難波の江に庵を作って隠れて暮らしているこの蟹の私を、大君がお召しになるというけど、そんなはずはない、何のために私などをお召しになるのだろうか、歌人としてだろうか、笛吹きとしてだろうか、それとも琴弾きとしてだろうか、そんなことはありはしない。まあいい、とにかく仰せを承ろうと、今日か明日かの飛鳥にたどり着き、立てても横には置くなの置勿に至り、杖を突かねどたどり着くの都久野に至り、東の中門から入って仰せを承れば、何と意に反して、馬になら絆を掛け、牛になら使う鼻縄をつけるのに、蟹のこの私を楡の枝でくくりつけ、毎日、天日にこってり干した挙句、韓渡りの臼で荒搗きし、庭の手臼で粉々に搗き、難波の入江の初垂れ、その辛い塩を持ち帰り、陶人の作った瓶に私を入れると、私の目にまで塩を塗りこんで、干物にしてお食べなさるよ、お食べなさるよ。
【説明】
「乞食者(ほかいびと)が詠ふ歌」と題された2首目で、「蟹のために痛みを述べて作った歌」と左注にあります。前の3855の歌が、山野に生きる動物の代表として鹿を歌っていたのに対し、こちらは海浜の生物の代表として蟹を採り上げており、両者相まって、天皇の権威が広く行き渡っていることを謳い上げているものとされます。
しかしながら、上の3885と同様に、左注に「蟹のために痛みを述べて」作った歌とあるのは、この歌が作られた時代の、天皇を「現つ神」として絶対視した思想とは大きな隔たりがあると感じられるところです。注をつけた『万葉集』の編者も、前歌と同様に、人間以外の動物への人間の所業に対する痛恨、同情を述べたものと理解していたのでしょう。あるいは、歌の内容が、大君から召され、お役に立とうと喜んで参上したところ、意に図らず食われてしまったという悲惨なものであることから、当時の民衆の、蟹のように干からびるという強い皮肉の気持ちが込められていると考えたのでしょうか。
「おしてるや」は「難波」の枕詞。「難波の小江」は、難波の地の入江。「廬」は、草木を結んで作った粗末な小屋で、蟹を擬人化してその棲みかとして言っているもの。「隠りて」は、隠れて。「葦蟹」は、葦の生えている所にいる蟹。「何せむに」は、何のために。「召すらめや」の「や」は、反語。召すのだろうか、召すはずはない。「明けく」は、はっきりと。「笛吹きと」は、笛を吹く者として。「琴弾きと」は、琴を弾く者として。「かもかくも」は、とにかくも。「今日今日と」は「飛鳥」の枕詞。「立つれども」は「置き」の枕詞。「置勿」は、地名ながら所在未詳。「つかねども」は「都久野」の枕詞。「都久野」は、橿原市鳥屋町の地かといいます。この地に皇居があったという記録はないので、大君は天皇ではなく皇族だったかもしれません。「東の中の御門」は、皇居の外郭の中央にある門。「ゆ」は、起点・経由点を示す格助詞。「ふもだし」は、馬の脚をつないでおく綱。「あしひきの」は「片山」の枕詞。「もむ楡」は、未詳。「日の異に」は、毎日。「さひづるや」は「韓臼」の枕詞。「初垂」は、製塩の際に最初にしたたる濃い塩水。「陶人」は、堺市南部にいた須恵器の工人。「きたひはやすも」の「きたふ」は、干し肉にする意。
3885の歌と同様に文飾の多い歌となっており、序詞や枕詞を駆使し、念は念を入れて制作した跡が窺え、乞食者のような職業的な言葉の技術者の作品としては、そこが大いなる腕の見せ所だったのかもしれません。いずれにしても、これらの歌が、鹿や蟹の奉仕を説いた寿歌や讃歌であるという捉え方には首肯できかねるところです。
巻第16-3887~3889
| 3887 天(あめ)にあるやささらの小野(をの)に茅草(ちがや)刈り草(かや)刈りばかに鶉(うづら)を立つも 3888 沖つ国うしはく君の塗(ぬ)り屋形(やかた)丹塗(にぬ)りの屋形(やかた)神の門(と)渡る 3889 人魂(ひとだま)のさ青(を)なる君がただひとり逢へりし雨夜(あまよ)の葉非左し思ほゆ |
【意味】
〈3887〉天界のささらの小野で茅草を刈っていたら、私の草刈り場の草陰から、だしぬけにウズラが飛び立った。
〈3888〉沖の果ての冥界をお治めになる大君の、丹塗りの屋形丹、その丹塗りの屋形丹が、神霊のとどまる狭い所をお渡りになる。
〈3889〉人魂である真っ青な顔の君が、ただ一人さまよっている。その君に私が出くわした雨の夜の葉非左を思うと、ぞっとする。
【説明】
「怖ろしき物の歌」3首とあり、畏怖の対象となる物を題材にした歌で、当時の人々の怪異なるものへの志向が窺えるものとなっています。3887の「天にあるやささらの小野」は、天上霊異の世界にある、ささら小野。「ささら小野」は、想像上のもので、詳細不明。巻第3の挽歌「天なるささらの小野の七節菅手に取り持ちてひさかたの天の川原に出で立ちてみそぎてましを」(420)とあり、天界のささらの小野の菅を取り持って天の川でみそぎをすれば、死を免れるとしています。「刈りばか」は、自分が分担する範囲の草刈り場。「鶉を立つも」の「を」は、間投助詞。作者が誰かの死を救うためだったのか、天のささら小野のような寂しい野で独りで草を刈っていたら、急にウズラがバサバサと音を立てて飛び立ち度肝を抜かれたというもので、取るものも取りあえず逃げ帰ったことが知られます。
3888の「沖つ国」は、海の彼方にある国で、死者の行く常世の国または黄泉の国。「うしはく」は、支配する、領有する。「丹塗りの屋形」は、冥府の支配者が乗る屋形船。「丹」の原文「黄」で、黄泉を暗示する色。「神の門」は、神霊のとどまる狭い所。「渡る」は、通り過ぎて行く。地界へ逃げ帰ってしまっては呪力の効などなく、誰もが死んで、屋形船に乗せられて死霊の赴く沖つ国に行かねばならない、あの神の門を通り過ぎたら、もはやこの世ならぬ沖つ国なのだ、と言っています。
3889の「人魂」は、人の身から抜け出た魂。この時代、身体と魂は別なものであり、魂が身体に宿っていることが「生」、抜け出るのが「死」であるとされ、魂はそれ自体が地上を彷徨うことがあるとされていました。「葉非左」は、訓義未詳。誤字説、脱字説などあって、文脈上、焼き場、墓場を想起させる語ともいいますが、何のことか分からないのでかえって気味悪くあります。死んで沖つ国に遣られてしまえば、二度と生き返ることはなく、懐かしい地界を訪れようとすれば、誰しも幽霊になるほかない。そういえば、人魂そのままの真っ青な顔をした、この間死んだかの君が突然現れた雨夜、それは葉非左の傍だったが、ああ思えばぞっとする、というものです。
ここの3首は、1首1首が恐ろしいにとどまらず、人間の霊の推移・行方に従って、一まとまりの話になっています。方々で怖がらせ歌としてもてはやされたものと見られますが、とりわけ3首目で「君」という直接的呼称を用いているのは、聴く人々の周囲を取り巻く死者、ならびに自身の果ての姿を想起、映像化させて怖がらせるのにまことに効果的となっています。
【PR】
正岡子規による「巻第16」評
巻第16は、巻第15までの分類に収めきれなかった歌を集めた付録的な巻とされ、伝説的な歌やこっけいな歌などを集めています。しかし、かの正岡子規は、この巻第16について、次のように述べています。
万葉20巻のうち、最初の2、3巻がよく特色を表し、秀歌に富めることは認めるが、ただ、万葉崇拝者が第16巻を忘れがちであることには不満である。寧ろその一事をもって万葉の趣味を解しているのか否かを疑わざるを得ない。第16巻は主として異様な、他に例の少ない歌を集めており、その滑稽、材料の複雑さ等に特色がある。しかし、その調子は万葉を通じて同じであり、いかに趣向に相違があるとしても、それらはまごうことなき万葉の歌である。
そして、はるか千年前の歌にこのような歌が存在したことを人々に紹介し、万葉集の中にこの一巻があることを広く知らしめたい、と。
 |
古典に親しむ
万葉集・竹取物語・枕草子などの原文と現代語訳。 |
バナースペース
【PR】
万葉集の時代背景
一方、地方政治の拠点としての国府の整備も行われ、藤原京や平城京から出土した木簡からは、地方に課された租税の内容が知られます。また、「遠(とお)の朝廷(みかど)」と呼ばれた大宰府は、北の多賀城とともに辺境の固めとなりましたが、大陸文化の門戸ともなりました。
この時期は積極的に大陸文化が吸収され、とくに仏教の伝来は政治的な変動を引き起こしつつも受容され、天平の東大寺・国分寺の造営に至ります。その間、多大の危険を冒して渡航した遣隋使・遣唐使たちは、はるか西域の文化を日本にもたらしました。
ただし、万葉集と仏教との関係では、万葉びとたちは不思議なほど仏教信仰に関する歌を詠んでいません。仏教伝来とその信仰は、飛鳥・白鳳時代の最大の出来事だったはずですが、まったくといってよいほど無視されています。当時の人たちにとって、仏教は異端であり、彼らの精神生活の支柱にあったのはあくまで古神道的な信仰、すなわち森羅万象に存する八百万の神々をおいて他にはなかったのでしょう。

官人の位階
一品~四品
諸王
一位~五位(このうち一位~三位は正・従位、四~五位は正・従一に各上・下階。合計十四階)
諸臣
一位~初位(このうち一位~三位は正・従の計六階。四位~八位は正・従に各上・下があり計二十階。初位は大初位・少初位に各上・下の計四階)
これらのうち、五位以上が貴族とされた。また官人は最下位の初位から何らかの免税が認められ、三位以上では親子3代にわたって全ての租税が免除された。
さらに父祖の官位によって子・孫の最初の官位が決まる蔭位制度があり、たとえば一位の者の嫡出子は従五位下、庶出子および孫は正六位に最初から任命された。

万葉集に詠まれた動物
あきづ
あゆ
あわび
いかるが
いぬ
う
うぐいす
うさぎ
うし
うずら
うなぎ
うま
おしどり
かいこ・くはこ
かいつぶり・におどり
かじか
かつお
かも
かり
きざし
こおろぎ・きりぎりす
さぎ
さる
しか
しぎ
すずき
たい
たか
たにぐく
ちどり
ぬえどり
ひぐらし
ひばり
ほたる
ほととぎす
まぐろ
むささび
もず
やまどり
わし

『再び歌よみに与ふる書』
紀貫之は下手な歌人で『古今集』は下らない歌集である。その貫之や『古今集』を崇拝するのは誠に気の知れないことなどと言うものの、実はかく言う私も数年前までは『古今集』を崇拝する一人だったので、今日世間の人が『古今集』を崇拝する気分はよく承知している。崇拝している間は歌というものは誠に優美で、ことに『古今集』はその粋を抜いたものとのみ思っていたが、三年の恋が一時にさめて見れば、「あんないくじのない女に今まで化かされていたことか」と、悔しくも腹立たしくもなる。まず『古今集』という書物を手に取って第一頁を開くと、直ちに「去年こぞとやいはん今年ことしとやいはん」という歌(下掲①)が出てくる、実に呆れ返った無趣味な歌である。日本人と外国人との「あいの子」を「日本人と言おうか外国人と言おうか」と洒落たと同じことで、洒落にもならないつまらない歌である。この他の歌も大同小異で、駄洒落か理屈っぽいもののみである。それでも強いて『古今集』を褒めて言えば、つまらない歌ながら『万葉集』以外に一つの流儀をなしたところが取り柄で、どのようなものでも初めてのものは珍しく思われる。ただこれを真似るをのみ芸とする後世の奴こそ、気の知れない奴である。それも十年か二十年のことならともかくも、二百年たっても三百年たってもその糟粕を嘗めている不見識には驚き入る。何代集だの彼ん代集だのと言っても、皆『古今集』の糟粕の糟粕の糟粕の糟粕ばかりである。
貫之とても同じこと。歌らしい歌は一首も見えない。かつてある人に言った所、その人が「川風寒み千鳥鳴くなり」の歌(下掲②)はどうかと言われて閉口した。この歌だけは趣味のある面白い歌だ。しかし他にはこれくらいのものは一首もない。「空に知られぬ雪」(下掲③)とは駄洒落であり、「人はいさ心もしらず」(下掲④)とは、浅はかな言いざまだと思う。ただし貫之は初めてこのようなことを言った者であり、古人の糟粕ではない。漢詩について言えば、『古今集』時代は、宋の時代にも比較することができ、俗気が紛々としているところはとても唐詩と比べるべくもないが、とはいえそれを宋詩の特色として見れば全体の上から変化があるのも面白く、宋詩はそれでよろしいのだろう。それを本尊にして人の短所を真似る寛政以後の漢詩人は、よい笑い者である。
『古今集』以後では『新古今集』がやや優れていると見える。『古今集』よりもよい歌を見かける。しかしそのよい歌と言うのも、指を折って数えるほどのこと。藤原定家という人は上手か下手か訳の分からない人で、『新古今集』の撰定を見ると少しは訳が分かっているのかと思えば、自分の歌にはろくなものはなく、「駒とめて袖うちはらふ」(下掲⑤)、「見わたせば花も紅葉も」(下掲⑥)などが、人にもてはやされるくらいのものである。定家を狩野派の絵師に比較すれば、狩野探幽とよく似ているのかと思う。定家には傑作がなく探幽にも傑作がない。しかし定家も探幽も相当に練磨の力はあって、どのような場合にも相当程度にやりこなす。両人の名誉は互いに匹敵するほどの位置にいて、定家以後は歌の門閥を生じ、探幽以後は画の門閥を生じ、両家とも門閥を生じた後は、歌も画も全く腐敗した。いつの時代でもいかなる技芸でも、歌の格、画の格などというような「格」が決まったら、もはや進歩はしない。(以下割愛)
① 年のうちに春は来にけり一年を去年とや言はむ今年とや言はむ
②思ひかね妹がり行けば冬の夜の川風寒み千鳥鳴くなり
③桜散る木の下風は寒からで空に知られぬ雪ぞ降りける
④人はいさ心も知らずふるさとは花ぞ昔の香ににほひける
⑤駒とめて袖うちはらふかげもなし佐野のわたりの雪の夕暮
⑥見わたせば花も紅葉もなかりけり浦の苫屋の秋の夕暮
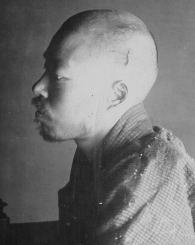
参考文献
~講談社
『NHK100分de名著ブックス万葉集』
~佐佐木幸綱/NHK出版
『大伴家持』
~藤井一二/中公新書
『古代史で楽しむ万葉集』
~中西進/KADOKAWA
『誤読された万葉集』
~古橋信孝/新潮社
『新版 万葉集(一~四)』
~伊藤博/KADOKAWA
『田辺聖子の万葉散歩』
~田辺聖子/中央公論新社
『超訳 万葉集』
~植田裕子/三交社
『日本の古典を読む 万葉集』
~小島憲之/小学館
『ねずさんの奇跡の国 日本がわかる万葉集』
~小名木善行/徳間書店
『万葉語誌』
~多田一臣/筑摩書房
『万葉秀歌』
~斎藤茂吉/岩波書店
『万葉秀歌鑑賞』
~山本憲吉/飯塚書店
『万葉集講義』
~上野誠/中央公論新社
『万葉集と日本の夜明け』
~半藤一利/PHP研究所
『萬葉集に歴史を読む』
~森浩一/筑摩書房
『万葉集のこころ 日本語のこころ』
~渡部昇一/ワック
『万葉集の詩性』
~中西進/KADOKAWA
『万葉集評釈』
~窪田空穂/東京堂出版
『万葉樵話』
~多田一臣/筑摩書房
『万葉の旅人』
~清原和義/学生社
『万葉ポピュリズムを斬る』
~品田悦一/講談社
『ものがたりとして読む万葉集』
~大嶽洋子/素人社
『私の万葉集(一~五)』
~大岡信/講談社
ほか
【PR】