徒然草
ある人のいはく~第一五一段
ある人の云はく、年五十になるまで上手(じやうず)に至らざらん芸をば捨つべきなり。励み習ふべき行く末もなし。老人のことをば、人もえ笑わず。衆(しゆ)に交はりたるも、あいなく見苦し。大方(おほかた)、万(よろづ)の仕業(しわざ)はやめて、暇(いとま)あるこそ、めやすくあらまほしけれ。世俗(せぞく)のことに携(たづさ)はりて生涯を暮らすは、下愚(かぐ)の人なり。ゆかしく覚えんことは、学び聞くとも、その趣(おもむき)を知りなば、おぼつかなからずしてやむべし。もとより望むことなくしてやまんは、第一のことなり。
【現代語訳】
ある人が言うには、五十歳になっても上手に至らない芸は、捨てるべきであると。その年齢では懸命に習うほどの余生もない。老人のことだと、人は遠慮して笑うこともできない。それをよいことに大勢の人の中に立ち交わっているのも、疎ましくて見苦しい。およそ、あらゆる仕事はやめて、のんびりしているのが、見た目にもよく望ましい。世俗に関わって生涯を費やすのは、最低の愚か者である。また、知りたいと思ったことは、人に学んで聞くとしても、大体のところが分かったなら、不案内でない程度でやめておくべきだ。もとより、最初からそのような望みを抱かずに終わるなら、それが第一である。
↑ ページの先頭へ
西大寺静然上人~第一五二段
西大寺(さいだいじの)静然上人(じやうねんしやうにん)腰かがまり、眉(まゆ)白く、まことに徳たけたる有様(ありさま)にて、内裏(だいり)へ参られたりけるを、西園寺(さいをんじの)内大臣殿、「あなたふとの気色(けしき)や」とて、信仰の気色(きそく)ありければ、資朝卿(すけともきやう)、これを見て、「年の寄りたるに候ふ」と申されけり。
後日に、尨(むく)犬のあさましく老いさらぼひて、毛剥げたるをひかせて、「この気色(けしき)尊くみえて候ふ」とて、内府(だいふ)へ参らせられたりけるとぞ。
【現代語訳】
西大寺の静然上人が、年を取って腰が曲がり、眉毛も白く、まことにありがたそうな徳の高い様子で、宮中へ参られたのを、西園寺内大臣殿が、「ああ、何と尊いご様子であろうか」と言って、信仰の念が顔に表れた、資朝卿がそれを見て、「年寄りなだけでございます」と申されたという。
そして幾日か後、資朝卿はむく毛の犬で、ひどく年老いてやせ衰え、毛の抜けているのを従者に引かせて、「この犬の様子も尊く見えてございます」と言って、内大臣殿に差し上げられたという。
(注)資朝卿・・・後醍醐天皇の側近の日野資朝。
↑ ページの先頭へ
為兼大納言入道召し捕られて~第一五三段
為兼(ためかね)大納言入道召し捕られて、武士どもうち囲みて、六波羅へ率(ゐ)て行きければ、資朝(すけとも)卿、一条わたりにてこれを見て、「あな羨(うらや)まし。世にあらん思ひ出、かくこそあらまほしけれ」とぞ言はれける。
【現代語訳】
為兼の大納言入道が召し捕られて、武士たちが取り囲んで、六波羅へ連行する様子を、資朝卿は一条あたりでこれを見て、「ああ羨ましい。この世に生きたという思い出は、このようにありたいものだ」と言われた。
(注)為兼大納言・・・藤原定家の曾孫、京極為兼。鎌倉幕府への謀略の疑いで捕えられた。
(注)資朝卿・・・後醍醐天皇の側近の日野資朝。
↑ ページの先頭へ
この人、東寺の門に~第一五四段
この人、東寺の門に雨宿りせられたりけるに、かたは者どもの集りゐたるが、手も足も捩(ね)ぢ歪(ゆが)み、うち反(かへ)りて、いづくも不具に異様(ことよう)なるを見て、とりどりに類(たぐひ)なき曲者なり、尤も愛するに足れりと思ひて、目守(まも)り給ひけるほどに、やがてその興尽きて、見にくく、いぶせく覚えければ、ただ素直に珍らしからぬ物には如かずと思ひて、帰りて後、この間、植木を好みて、異様に曲折あるを求めて目を喜ばしめつるは、かのかたはを愛するなりけりと、興なく覚えければ、鉢に植ゐられける木ども、皆堀り捨てられにけり。さも有りぬべき事なり。
【現代語訳】
この人(資朝卿)が、東寺の門に雨宿りなさったところ、かたわ者(身体障害者)たちが門の下に群れ集まっていたが、手足は捻じ曲がり、反りかえって、誰もが不具であり異形なのを見て、それぞれが比べようもない変わり者であった、大いに面白いと思って見守っているうち、すぐにその興味も消えて、見るに堪えなくなり不快に感じた。ただ素直で珍しくないのに及ばないと思って、家に帰った後、自分が趣味で好んでいた盆栽を見て、枝や幹の異様な曲がり具合を求めて楽しんでいたのは、あのかたわ者を愛でるのと同じだと思い、急に興醒めがして、鉢に植えられた木々を、みな土ごと捨ててしまったという。いかにもありそうなことだ。
↑ ページの先頭へ
世に従はむ人は~第一五五段
世に従はん人は、まづ機嫌を知るべし。ついで悪しきことは、人の耳にも逆(さか)ひ、心にも違(たが)ひて、そのことならず。さやうの折節を心得べきなり。但し、病を受け、子産み、死ぬることのみ、機嫌をはからず。ついで悪しとて止(や)むことなし。生住異滅(しやうぢゆういめつ)の移り変はる、まことの大事は、たけき川のみなぎり流るるが如し。しばしも滞らず、直ちに行ひゆくものなり。されば、真俗につけて、必ず果たし遂げんと思はんことは、機嫌を言ふべからず。とかくのもよひなく、足を踏みとどむまじきなり。
春暮れて後、夏になり、夏果てて秋の来たるにはあらず。春はやがて夏の気を催し、夏より既に秋は通ひ、秋はすなはち寒くなり、十月(かみなづき)は小春の天気、草も青くなり、梅もつぼみぬ。木の葉の落つるも、まづ落ちて芽ぐむにはあらず。下より兆しつはるに耐へずして落つるなり。迎ふる気、下にまうけたるゆゑに、待ち取るついで甚だ速し。生老病死(しやうらうびやうし)の移り来たること、またこれに過ぎたり。四季はなほ定まれるついであり。死期(しご)はついでを待たず。死は前よりしも来たらず、かねて後ろに迫れり。人皆死あることを知りて、待つこと、しかも急ならざるに、覚えずして来たる。沖の干潟(ひかた)遥かなれども、磯より潮の満つるが如し。
【現代語訳】
世間に順応して生きようと思う人は、まずは時機を知らなくてはいけない。順序が悪いと、人の耳にも逆らい、気持ちにも背いて、しようとしたことが成就しない。そういう時機をわきまえるべきだ。但し、病気になったり、子供を産んだり、死ぬことだけは、時機を考えることはできない。順序が悪いからとて止まるものではない。万物が生じ、とどまり、変化し、なくなっていくという四相の移り変わりの大事は、勢いのある川が満ちあふれて流れていくようなものだ。少しも停滞せず、まっすぐに進んでいくものだ。だから、仏道修行でも日常生活でも、必ず成し遂げようとすることは時機のよしあしを言ってならない。あれこれ準備などせず、足踏みしてとどまってはいけない。
四季の移り変わりにおいても、春が終わった後に夏になり、夏が終わって秋が来るのではない。春はやがて夏の気配を生じ、夏にはすでに秋が入り交じり、秋はすぐに寒くなり、十月は小春日和で、草も青くなり梅もつぼみをつける。木の葉が落ちるのも、まず葉が落ちて芽ぐむのではない。下から芽が突き上げるのに耐え切れなくて落ちるのだ。次の変化を迎える気配が下に醸成されているために、交替する順序が速やかなのだ。生・老・病・死という人生の四苦が次々にやってくる速さは、この四季の移り変わり以上だ。四季には決まった順序があるが、人の死ぬ時期は順序を待たない。死は必ずしも前からやってくるとは限らず、気づく前から背後に迫っている。人は皆、死が訪れることを知りながら、それほど急であるとは思っていない、しかし、死は思いがけずにやってくる。ちょうど、沖の干潟は遥かに遠いのに、急に足下の磯から潮が満ちてくるようなものだ。
【PR】
↑ ページの先頭へ
人間の営みあへるわざ~第一六六段
人間の、営(いとな)み合へるわざを見るに、春の日に雪仏(ゆきぼとけ)を作りて、そのために金銀、珠玉の飾りを営み、堂を建てんとするに似たり。その構(かま)へを待ちて、よく安置してんや。人の命ありと見るほども、下より消ゆること、雪のごとくなるうちに、営み待つこと甚(はなた)だ多し。
【現代語訳】
人間が、それぞれに励んでいる仕事を見ると、春の日に雪仏を作って、金銀・珠玉の飾りをあれこれ取り付け、さらにその雪仏を納める堂を建てようとすることに似ている。堂が完成したところで、雪仏をうまく安置できるだろうか。人の命も、まだ先が長いと思っているうちにやがて死に向かうさまは、表面からは見えない、下の地面のほうから解けていく雪のようである。それなのに、あくせく働いてその成果を将来に期待している場合がほとんどだ。
↑ ページの先頭へ
一道に携はる人~第一六七段
一道(いちだう)に携(たづさ)はる人、あらぬ道の筵(むしろ)に臨みて、「あはれ、我が道ならましかば、かくよそに見侍らじものを」と言ひ、心にも思へること、常のことなれど、よにわろく覚ゆるなり。知らぬ道のうらやましく覚えば、「あなうらやまし。などか習はざりけん」と言ひてありなん。我が智を取り出でて人に争ふは、角(つの)あるものの角を傾け、牙(きば)あるものの牙を咬(か)かみ出だす類(たぐひ)なり。
人としては善にほこらず、物と争はざるを徳とす。他に勝(まさ)ることのあるは、大きなる失なり。品(しな)の高さにても、才芸のすぐれたるにても、先祖の誉(ほまれ)にても、人にまされりと思へる人は、たとひ言葉に出でてこそ言はねども、内心にそこばくの咎(とが)あり。慎しみてこれを忘るべし。をこにも見え、人にも言ひ消(け)たれ、禍(わざはひ)をも招くは、ただこの慢心(まんしん)なり。
一道にもまことに長じぬる人は、みづから明らかにその非を知る故に、志(こころざし)常に満たずして、終(つひ)に物に伐(ほこ)ることなし。
【現代語訳】
一つの道に専従している人が、自分の専門とはちがう場に出て、「ああ、これが私の専門だったら、こんなふうに傍観などしないのに」と言って、心の中ではがゆく思うことはよくあるが、とてもみっともなく感じられる。自分の知らない道を羨ましく思うのなら、「ああ羨ましい。なぜ習わなかったのだろう」と言っておればよかろう。自分の知識をひけらかして人と争うのは、角のある動物が角を傾けて相手を突こうとし、牙のある動物が牙をむき出して相手に嚙みつこうとするのと同じだ。
人としては自分の長所を誇らず、人と争わないのを徳とする。他人よりまさっていると意識するのは大きな欠点だ。身分や家柄の高さでも、才芸にすぐれていても、先祖の名誉でも、自分が人よりまさっていると思う人は、たとえ言葉に出して言わなくても、心の中には多くの欠点がある。自分で自分を戒めて、そういう長所を忘れるのがよい。馬鹿げて見え、人にもそしられ、禍をも招くのは、ひとえにこの慢心である。
一つの道に本当に精通している人は、おのずと自分の欠点を察するから、これでよいと自己満足することなく、結局、何事も人に自慢などしないのだ。
↑ ページの先頭へ
年老いたる人の~第一六八段
年老いたる人の、一事(いちじ)すぐれたる才(ざえ)のありて、「この人の後には、誰にか問はん」など言はるるは、老の方人(かとうど)にて、生けるも徒らならず。さはあれど、それも廃れたる所のなきは、一生この事にて暮れにけりと、拙(つたな)く見ゆ。「今は忘れにけり」と言ひてありなん。大方は、知りたりとも、すずろに言ひ散らすは、さばかりの才にはあらぬにやと聞え、おのづから誤りもありぬべし。「さだかにも弁(わきま)へ知らず」など言ひたるは、なほまことに、道の主(あるじ)とも覚えぬべし。まして、知らぬ事、したり顔におとなしく、もどきぬべくもあらぬ人の言ひ聞かするを、「さもあらず」と思ひながら聞きゐたる、いと侘(わび)し。
【現代語訳】
一芸に秀でた老人がいて、「この人がいなくなった後には、誰に尋ねたらよいものか」などと言われるのは、年寄り冥利につき、長生きしたのも無駄ではない。しかし才能を持て余し続けたとしたら、一生この一事だけに費やしたのだと、つまらなく思われる。「今は呆けて忘れてしまった」と、とぼけていればよい。大体において、自分の専門で詳しく知っていることでも、無闇に話しまくると小者にしか見えず、どこかで間違えることもあるだろう。「はっきりとは知らないのです」などと謙虚に言えば、本物らしく、その道の大家とも思われるはずだ。ところが、知らないくせに、したり顔で出鱈目を話す人もいる。老人が言うことだけに誰も非難できず、「そうでもないな」と思いながら聞いているのは、たいそう侘しいものだ。
↑ ページの先頭へ
さしたることなくて~第一七〇段
さしたることなくて人のがり行くは、よからぬことなり。用ありて行きたりとも、そのこと果てなば、とく帰るべし。久しく居(ゐ)たる、いとむつかし。
人の向かひたれば、詞(ことば)多く、身もくたびれ、心も閑(しづ)かならず、万(よろづ)のこと障(さは)りて時を移す、互ひのため益(やく)なし。いとはしげに言はんもわろし。心づきなきことあらん折(をり)は、なかなか、その由(よし)をも言ひてん。
同じ心に向かはまほしく思はん人の、つれづれにて、「今しばし、今日(けふ)は心(こころ)閑(しづ)かに」など言はんは、この限りにはあらざるべし。阮籍(げんせき)が青き眼(まなこ)、誰(たれ)もあるべきことなり。そのこととなきに人の来たりて、のどかに物語りして帰りぬる、いとよし。また、文(ふみ)も、「久しく聞えさせねば」などばかり言ひおこせたる、いとうれし。
【現代語訳】
さしたる用事もないのに人を訪ねるのは、よくないことである。用事があって訪ねたとしても、用が済んだらすぐに帰るのがよい。長居するのは、相手にとって非常にわずらわしいものだ。
人と向かい合えば 、しぜん言葉は多くなり、体もくたびれ、心も休まらない。いろんなことに支障が生じ、時間ばかりが過ぎる。お互いのために無益なことだ。かといって、不愉快そうに話すのもよくない。気持ちが乗らない場合は、かえってその事情を言ってしまうのがよい。
ただし、お互いに気が合い対面したいと思う相手が、ちょうど時間が空いていて、「もう少し、今日は心静かにご一緒しましょう」などと言ってくれるのは、この限りではない。阮籍は、気の合う客を青い眼で歓迎したというが、それは誰にもあるに違いない。特に用事もないのに親しい人が訪ねて来て、のんびりと話をして帰るのは、実にいい。また手紙でも、「長い間ご無沙汰しておりますので」などという具合に言いよこしてくるのは、実に嬉しい。
(注)阮籍・・・中国晋代の人で、竹林の七賢人の一人。
【PR】
↑ ページの先頭へ
貝を覆ふ人の~第一七一段
貝を覆(おほ)ふ人の、我が前なるをば惜(お)きて、よそを見渡して、人の袖のかげ、膝の下まで目を配る間(ま)に、前なるをば人に覆はれぬ。よく覆ふ人は、余所(よそ)までわりなく取るとは見えずして、近きばかり覆ふやうなれど、多く覆ふなり。碁盤の隅に石をたてて弾(はじ)くに、向ひなる石をまぼりて弾くは、当らず、我が手許(てもと)をよく見て、ここなる聖目(ひじりめ)を直(すぐ)に弾けば、立てたる石必ず当る。
万(よろづ)の事、外(ほか)に向きて求むべからず。ただ、ここもとを正しくすべし。清献公(せいけんこう)が言葉に、「好事(かうじ)を行(ぎやう)じて、前提を問ふことなかれ」と言へり。世を保たん道も、かくや侍らん。内を慎まず、軽く、ほしきままにして濫(みだ)りなれば、遠国(をんごく)必ず叛(そむ)く時、初めて謀(はかりごと)を求む。「風に当り、湿(しつ)に臥して、病を神霊(しんれい)に訴ふるは、愚かなる人なり」と医書に言へるが如し。目の前なる人の愁(うれ)へをやめ、恵みを施し、道を正しくせば、その化(くわ)遠く流れん事を知らざるなり。禹(う)の行きて三苗(さんべう)を征せしも、師(いくさ)を班(かえ)して、徳を敷くには如(し)かざりき。
【現代語訳】
貝覆いの遊びをする人が、自分の前にある貝を差し置いて、よそを見渡して、人の袖の陰や膝の下まで目を配っている間に、自分の前にある貝を人に覆われてしまう。うまく覆う人は、遠くの貝まで無理に取るようには見えずに、近くばかりを覆うようであるが、それでも多く覆うのである。碁盤の隅に碁石を置いて弾くのに、当てようとする石を狙って弾くと当たらず、自分の手許をよく見て、目の前にある聖目を見ながら弾けば、必ず当たる。
あらゆる事は、外に向けて成果を求めてはならない。ただ、手近なところを正しくすべきだ。清献公の言葉に、「目の前にある善事を行い、遠い将来を問題にしてはならない」とある。世を治める道もこの通りであろうか。内政をいい加減にしていれば、やがて遠国が必ず謀反を起こす、その時になって初めて対策を講ずる。そんなことでは、「風に当たり、湿気の多い所で寝ておいて、病気が治るのを神に訴えるのは愚か者である」と医学書に言っているのと同じだ。目の前にいる民の心配を除き、恵みを施し、道を正しくすれば、その感化ははるか遠くに及ぶことを知らないのだ。あの名君と伝えられる禹が異民族の三苗を征服したのも、軍隊を戻し国内で善政を敷いたからに他ならない。
(注)貝を覆ふ・・・平安末期から行われた「貝覆い」という遊び。360個のハマグリの貝殻を数人に配り、左貝(出し貝)・右貝(地貝:じがい)の両片に分けたうえ、右貝を全部伏せて並べ、左貝を一つずつ出しながら、これと対になる右貝を多く選んだ者を勝ちとする。後には、左右の貝を合わせやすいように、同趣の絵を描いたり、和歌の上の句と下の句に分けて書いたりするようになった。
(注)聖目・・・碁盤の対角線上に9個付した黒点。
(注)清献公・・・北宋の名臣、趙抃(ちょうべん)。
(注)兎・・・中国古代の聖天子。夏王朝の租。
↑ ページの先頭へ
若き時は~第一七二段
若き時は、血気(けつき)内(うち)に余り、心、物に動きて、情欲多し。身を危ぶめて、砕(くだ)けやすきこと、球(たま)を走らしむるに似たり。美麗(びれい)を好みて宝を費し、これを捨てて苔(こけ)の袂(たもと)にやつれ、勇める心盛りにして、物と争ひ、心に恥ぢうらやみ、好むところ日々に定まらず。色にふけり情けにめで、行ひを潔くして、百年(ももとせ)の身を誤り、命を失へる例(ためし)願(ねが)はしくして、身の全(また)く久しからんことをば思はず、好ける方(かた)に心ひきて、ながき世語りともなる。身を過(あやま)つることは、若き時の仕業(しわざ)なり。
老いぬる人は、精神衰へ、淡(あは)く疎(おろそ)かにして、感じ動く所なし。心おのづから静かなれば、無益(むやく)のわざをなさず、身を助けて愁(うれ)へなく、人の煩(わづら)ひなからんことを思ふ。老いて智の若き時に勝(まさ)れること、若くして、かたちの老いたるに勝れるが如し。
【現代語訳】
若い時は血気が体内にあり余り、心は何かにつけて動揺しやすく、情欲も多いものだ。身を危険にさらして破滅しやすいさまは、砕けやすい玉を転がすのに似ている。華美を好んで財産を浪費したかと思うと、突然そうした生活を捨てて出家し、みすぼらしい僧衣に身をやつす。また、闘志さかんで、人と争ったかと思うと、心に恥じたり他人をうらやんだり、好むところは日々定まらない。女色にふけり色恋に夢中になり、思い切りよすぎる行動をして将来を台無しにしたり、命を失うような前例を好ましいこととして、身の安全や長命などは頭になく、好きなことにのめり込み、長く世間の噂となったりする。このように、身を誤ることは、まさしく若い時のしわざである。
老いた人は、気力が衰え、何事も淡泊でこだわりがなく、欲望にかられることもない。心は自然と静かであるので、無益なことをせず、わが身を大切にして心配事もなく、他人の迷惑にならないことを思う。老人の知恵が若者に勝っているのは、若者の容貌が老人に勝っているのと同じだ。
↑ ページの先頭へ
相模守時頼の母は~第一八四段
相模守(さがみのかみ)時頼(ときより)の母は、松下禅尼(まつのしたのぜんに)とぞ申しける。守(かみ)を入れ申さるる事ありけるに、煤(すす)けたる明り障子の破ればかりを、禅尼、手づから、小刀(こがたな)して切り廻しつつ張られければ、兄(せうと)の城介義景(じようのすけよしかげ)、その日のけいめいして候ひけるが、「給はりて、なにがし男(をのこ)に張らせ候はん。さやうの事に心得たる者に候ふ」と申されければ、「その男、尼が細工によも勝り侍らじ」とて、なほ一間(ひとま)づつ張られけるを、義景、「皆を張り替へ候はんは、はるかにたやすく候ふべし、斑(まだら)に候ふも見苦しくや」と重ねて申されければ、「尼も、後は、さはさはと張り替へんと思へども、今日ばかりは、わざとかくてあるべきなり。物は破れたる所ばかりを修理(しゅり)して用ゐる事ぞと、若き人に見習はせて、心づけんためなり」と申されける、いと有難かりけり。
世を治むる道、倹約を本(もと)とす。女性(によしやう)なれども聖人の心に通へり。天下を保つ程の人を子にて持たれける、まことに、ただ人にはあらざりけるとぞ。
【現代語訳】
相模守北条時頼の母は、松下禅尼という方であった。ある日、相模守を屋敷にお招きすることがあった。煤けた障子の破れている所を、禅尼が自ら、小刀であちこち切っては張り替えておられたので、それを見た兄の城介義景が、その日の接待のために立ち働いていたのだが、「私が、某という男に張らせましょう。手先が器用な男です」と言われたところ、禅尼は、「その男は、私の手仕事にはとても及びますまい」と、障子を一ますずつ張り替えていかれた。義景は、「全部張り替えたほうが、はるかに楽でしょう。新しい所と降り所がまだらになるのは見苦しくありませんか」と重ねて言われると、「私も、後できれいに張り替えるつもりですが、今日だけは、わざとこのようにするのです。物は壊れた所だけを修繕して使うべきと、若い時頼に見習わせて、覚えさせるのです」と答えられた。まことに殊勝なことであった。
世を治める道は、倹約が基本とする。女性ではあるが、聖人と同じ心を持つ人である。天下を統治するほどの人を息子としてお持ちになっている禅尼は、まことに普通の人とは違う。
↑ ページの先頭へ
ある者、子を法師に~第一八八段
ある者、子を法師(ほふし)になして、「学問して因果(いんが)の理(ことわり)をも知り、説教などして世渡るたづきともせよ」と言ひければ、教へのままに、説教師にならんために、先(ま)づ馬に乗り習ひけり。輿(こし)、車は持たぬ身の、導師(だうし)に請(しやう)ぜられん時、馬など迎へにおこせたらんに、桃尻(ももじり)にて落ちなんは、心憂かるべしと思ひけり。次に、仏事の後、酒など勧(すす)むることあらんに、法師の無下(むげ)に能なきは、檀那(だんな)すさまじく思ふべしとて、早歌(さうか)といふことを習ひけり。二つのわざ、やうやう境に入りければ、いよいよよくしたく覚えて嗜(たしな)みけるほどに、説教習ふべき隙(ひま)なくて、年寄りにけり。
この法師のみにもあらず、世間の人、なべてこの事あり。若きほどは、諸事(しよじ)につけて、身を立て、大きなる道をも成(じやう)じ、能をも付き、学問をもせんと、行く末久しくあらますことども心には懸けながら、世を長閑(のどか)に思ひてうち怠りつつ、先(ま)づ、差し当たりたる目の前のことにのみ紛(まぎ)れて月日を送れば、ことごと成すことなくして、身は老いぬ。つひに物の上手にもならず、思ひしやうに身をも持たず、悔ゆれども取り返さるる齢(よはひ)ならねば、走りて坂を下る輪(わ)の如くに衰へゆく。
されば、一生のうち、むねとあらまほしからんことの中(うち)に、いづれか勝(まさ)るとよく思ひ比べて、第一の事を案じ定めて、その外(ほか)は思ひ捨てて、一事(いちじ)を励むべし。一日の中、一時の中にも、あまたの事の来たらんなかに、少しも益(やく)の勝(まさ)らんことを営みて、その外(ほか)をばうち捨てて、大事を急ぐべきなり。何方(いづかた)をも捨てじと心に執(と)り持ちては、一事も成るべからず。
【現代語訳】
ある者が、子を法師にして、「学問をして因果の道理を知り、説教などをして生活の手段とせよ」と言ったので、教えのままに、説教師になるため、まず乗馬を習った。輿や車を持たない身なので、法事の主催役の僧として招かれた時に、馬で迎えによこされ、乗り方が下手で落馬しては情けないと考えたのだ。その次には、法事の後で酒など勧められたとき、法師でいながらまったく芸がないのも、施主が興ざめに思うだろうと、早歌(流行歌謡)を習った。やがて、二つのわざが熟練の境地に近づいたので、ますます上達したくなって稽古に励んでいるうちに、説教を習う暇がなくなり、ついに年を取ってしまった。
この法師に限ったことではなく、世間の人は、おしなべてこれと同じことをしている。若いうちは、あらゆる物事について一人前になり、その道を大成し、芸能も身につけ、学問もしようなどと、人生のずっと先までの遠大な計画を心に抱いているものだ。ところが一方では、先の長い人生をのんびりと構え、なすべきことを怠り、目の前のことばかりにとらわれて月日を送ってしまい、何事も成し遂げられないまま、身は老いてしまう。結局、一芸にすぐれた者にもなれず、思ったような立身出世もできず、後悔しても取返しのつく年齢ではなくなっているので、走って坂を下る車輪のようにみるみる衰えゆくのだ。
であれば、一生の間に、大事な人生目標の中で、どれが勝っているかよく思い比べて、第一のことを心に決めたら、それ以外の目標は捨てて、その一事だけを励むべきである。一日の間にも一時の間にも、為すべき事はたくさんあるが、少しでも意義のある事を行い、その外の事を捨てて、何よりもこの大事を急ぐべきである。あれもこれも捨てまいと執着していては、一つの事も成ることはなかろう。
↑ ページの先頭へ
今日は、その事をなさんと思へど~第一八九段
今日は、その事をなさんと思へど、あらぬ急ぎ、先(ま)づ出で来て紛れ暮し、待つ人は障り有りて、頼めぬ人は来(きた)り、頼みたる方(かた)の事は違(たが)ひて、思ひ寄らぬ道ばかりは叶ひぬ。煩(わづら)はしかりつる事はことなくて、易かるべき事はいと心苦し。日々に過ぎ行くさま、かねて思ひつるには似ず。一年(ひととせ)の中(うち)もかくの如し。一生の間もまたしかなり。かねてのあらまし、皆違ひ行くかと思ふに、おのづから違はぬ事もあれば、いよいよ物は定めがたし。不定(ふぢやう)と心得ぬるのみ、実(まこと)にて違はず。
【現代語訳】
今日はその事をしようと思っていても、思いがけない急用ができて、そのまま時間を費やしてしまう。待っている人は都合が悪くて来れず、当てにしていなかった人が不意に来たりする。期待通りに物事が運ばないと思っていたら、思いがけない事が成功したりする。面倒だと思っていたらすんなり済み、簡単だと思っていたことが面倒となる。日々の移ろいとは予想不可能だ。一年の間もこれと同じであり、一生もまた同じである。かねての計画が全てうまくいかないかと思えば、たまにはうまくいくこともある。ますます物事は定め難い。ならば、全てが不確かだと心得ておくことが、真実であって、間違いもない。
↑ ページの先頭へ
妻といふものこそ~第一九〇段
妻(め)といふものこそ、男(をのこ)の持つまじきものなれ。「いつも独(ひと)り住みにて」など聞くこそ、心憎けれ、「誰(たれ)がしが婿(むこ)になりぬ」とも、また、「如何(いか)なる女を取り据(す)ゑて、相(あひ)住む」など聞きつれば、無下(むげ)に心劣りせらるるわざなり。殊(こと)なることなき女を、よしと思ひ定めてこそ添ひゐたらめと、賤(いや)しくも推(お)し量(はか)られ、よき女ならば、この男をぞ、らうたくして、「あが仏」と守りゐぬらめ。たとへば、さばかりにこそと覚えぬべし。まして、家の内を行ひ治めたる女、いと口惜し。子など出(い)で来て、かしづき愛したる、心憂し。男亡くなりて後、尼になりて年寄りたるありさま、亡き跡まであさまし。
いかなる女なりとも、明け暮れ添ひ見んには、いと心づきなく、憎かりなん。女のためにも半空(なかぞら)にこそならめ。よそながら、時々通ひ住まんこそ、年月経ても絶えぬ仲らひともならめ。あからさまに来て、泊り居(ゐ)などせんは、珍しかりぬべし。
【現代語訳】
妻というものこそ、男が持ってはいけないものである。「あの人はいつまでも独身でいる」などと聞くと、奥ゆかしく感じられ、「誰それの婿になった」とか、また「これこれの女を迎え入れて同居している」など聞くと、全くがっかりさせられてしまう。大したこともない女を最高だと思いこんで一緒になったのだろうと、安っぽく下品にも思われ、万一よい女ならば、かわいがって「わが仏」とばかりに大切にしているのだろう。言ってみれば、そんな程度のものだろうと思われてしまう。まして、家の内を切りまわしている女は、実につまらない。子など生まれて、大切に可愛がっているのは、残念なものだ。男が死んで後、尼になって年を取っていくさまは、本人が死んだ後まで情けないものだ思う。
どんな女であっても、朝晩いっしょにいて顔を突き合わせていると、たいそう気に入らないことが出てきて、憎たらしくなる。女のためにも、不安定で中途半端な状態になるだろう。お互いに離れて住んだまま、時々通って泊まるのが、年月を経ても絶えない仲となるだろう。不意に訪ねて来て泊まっていくなどは、新鮮な気分がするに違いない。
【PR】
↑ ページの先頭へ
夜に入りて~第一九一段
「夜に入りて、物の映(は)えなし」と言ふ人、いと口惜し。万(よろづ)のものの綺羅(きら)、飾り、色節(いろふし)も、夜のみこそめでたけれ。昼は、ことそぎ、およすげたる姿にてもありなん。夜は、きららかに、華やかなる装束(さうぞく)、いとよし。人の気色(けしき)も、夜の火影(ほかげ)ぞ、よきはよく、物言ひたる声も、暗くて聞きたる、用意ある、心憎し。匂ひも物の音(ね)も、ただ夜ぞ一際(ひときは)めでたき。
さして殊(こと)なることなき夜(よ)、うち更(ふ)けて参れる人の、清げなるさましたる、いとよし。若きどち、心とどめて見る人は、時をも分かぬものなれば、ことにうち解けぬべき折節(をりふし)ぞ、褻(け)、晴れなく、引き繕(つくろ)はまほしき。よき男の日暮れてゆするし、女も、夜更(よふ)くるほどに滑(すべ)りつつ、鏡取りて、顔など繕(つくろ)ひて出(い)づるこそ、をかしけれ。
【現代語訳】
「夜になると、物の見映えがしない」と言う人は、たいへん残念である。あらゆる物の美しさ、装飾、色彩などは、夜が一番すばらしく見えるものだ。昼は、簡素で地味な姿をしていてもよかろう。しかし、夜は、きらびやかで華やかな衣装が大変よい。人の様子も、夜の燈火に照らされた姿が、立派な人はより立派に見え、話す声も、暗い中で聞く慎みのある声に心惹かれる。香りや楽器の音も、夜がひときわ素晴らしい。
これといった行事もない夜、遅くに参上した清楚な身なりは、大変よい。若い者同士で、お互いに関心を持って会う間柄では、時に関わらず相手に見られるものだから、とりわけ気を許してしまいそうな時こそ、日常と公式の違いなく、身なりをきちんと整えておきたいものだ。立派な男が、日が暮れて、女を訪れるために髪を濡らして整え、女もまた、夜が更けるころにそっと座を外して、鏡を手に顔などつくろってから座に戻るのは、とても情緒深い。
↑ ページの先頭へ
夜に入りて~第一九一段
「夜に入りて、物の映(は)えなし」と言ふ人、いと口惜し。万(よろづ)のものの綺羅(きら)、飾り、色節(いろふし)も、夜のみこそめでたけれ。昼は、ことそぎ、およすげたる姿にてもありなん。夜は、きららかに、華やかなる装束(さうぞく)、いとよし。人の気色(けしき)も、夜の火影(ほかげ)ぞ、よきはよく、物言ひたる声も、暗くて聞きたる、用意ある、心憎し。匂ひも物の音(ね)も、ただ夜ぞ一際(ひときは)めでたき。
さして殊(こと)なることなき夜(よ)、うち更(ふ)けて参れる人の、清げなるさましたる、いとよし。若きどち、心とどめて見る人は、時をも分かぬものなれば、ことにうち解けぬべき折節(をりふし)ぞ、褻(け)、晴れなく、引き繕(つくろ)はまほしき。よき男の日暮れてゆするし、女も、夜更(よふ)くるほどに滑(すべ)りつつ、鏡取りて、顔など繕(つくろ)ひて出(い)づるこそ、をかしけれ。
【現代語訳】
「夜になると、物の見映えがしない」と言う人は、たいへん残念である。あらゆる物の美しさ、装飾、色彩などは、夜が一番すばらしく見えるものだ。昼は、簡素で地味な姿をしていてもよかろう。しかし、夜は、きらびやかで華やかな衣装が大変よい。人の様子も、夜の燈火に照らされた姿が、立派な人はより立派に見え、話す声も、暗い中で聞く慎みのある声に心惹かれる。香りや楽器の音も、夜がひときわ素晴らしい。
これといった行事もない夜、遅くに参上した清楚な身なりは、大変よい。若い者同士で、お互いに関心を持って会う間柄では、時に関わらず相手に見られるものだから、とりわけ気を許してしまいそうな時こそ、日常と公式の違いなく、身なりをきちんと整えておきたいものだ。立派な男が、日が暮れて、女を訪れるために髪を濡らして整え、女もまた、夜が更けるころにそっと座を外して、鏡を手に顔などつくろってから座に戻るのは、とても情緒深い。
 |
古典に親しむ
万葉集・竹取物語・枕草子などの原文と現代語訳。 |
バナースペース
【PR】
兼好法師の和歌
(秋の田で稲刈りをしているが、今まで稲葉に置いていた露は、これからは一体どこに置けばよいのだろう。思えば、世の中を飽き果てた自分も、この身の置き所はどこにもない)
あらましも昨日に今日はかはるかな思ひさだめぬ世にしすまへば
(前々からの予定も昨日と今日では変わるものだな。どうも決心がつかず思い通りにならない日々を送っていると)
雲の色にわかれもゆくか逢坂の関路の花のあけぼのの空
(雲は白い色になって山から別れてゆくのか、逢坂の関路の桜が咲き満ちた、曙の空よ)
うちなびく草葉すずしく夏の日のかげろふままに風たちぬなり
(野原の草が涼しげにいっせいに靡く。夏の陽が陰ると同時に、風が起こったようだ)
しるべせよ田上(たなかみ)河のあじろもりひをへてわが身よる方もなし
(道案内を頼むよ、田上川の網代守。網代にかかる氷魚ではないが、もうずっと私は身を寄せるところがないのだ)
夜も涼し寝覚めの仮穂手枕も真袖も秋に隔てなき風
(夜も涼しい。仮穂で夜中にふと目覚めると、自分の腕枕にも左右の袖にも秋風が隔てなく吹いている)
こよろぎの磯より遠く引く潮にうかべる月は沖に出でにけり
(こよろぎの磯から遠く引いてゆく潮に乗って、水面に浮んだ月は沖へと出てしまった)
そむきてはいかなる方にながめまし秋の夕べもうき世にぞうき
(遁世したら、どんな風に眺めるのだろうか。秋の夕べも、憂き世にあって眺めるからこそ憂鬱なのだ。出家を果たした心境には、違って見えるのではないか)
住めばまた憂き世なりけりよそながら思ひしままの山里もがな
(世を逃れて住めば、ここもまた憂き世であったよ。よそから眺めて住みよいと思った、そのままの山里はないものか)
明けぬれば樗(あふち)花さく葉隠れにやめば次がるるひぐらしの声
(夜が明けると、花咲く楝の葉の繁みに隠れて蜩が鳴き、ふと鳴きやんでは、また声を継いで鳴く)
めぐりあふ秋こそいとどかなしけれ有るを見知り世は遠ざかりつつ
(あなたは遠ざかってしまったが、そのせいか巡り来る秋はいっそう悲しく思う)
ちぎりおく花とならびの岡のべにあはれいくよの春をすぐさむ
(いつまでも一緒にいようと約束した花と仲良く並んで、このならびの岡のほとりで、ああ幾年の春を過ごすことになるのだろうか)
いかにしてなぐさむ物ぞ世の中をそむかで過ぐす人に問はばや
(どのようにして気をまぎらしているのかと、世を捨てずに過ごしている人に尋ねたいものだ)
身をかくす憂き世のほかはなけれどものがれしものは心なりけり
(辛い身を隠すところといっても、この憂き世以外にはないけれども、とにかく心だけは憂き世から逃れたことだ)

語 句
気に入らない。つまらない。不似合いだ。不快である。
あさまし
驚くばかりだ。意外だ。情けない。興ざめだ。あきれるほどひどい。見苦しい。
あひしらふ
程よく受け答えをする。応対する。
あふさきるさ
ちぐはぐ。ああかこうか。あれやこれや。
いらなし
甚だしい。大げさだ。もったいぶって。
いろふ(綺ふ)
関わる。口出しする。干渉する。
うぐ(穿ぐ)
穴があく。
うるはし
端正である。整っている。壮大で美しい。色鮮やかだ。正しい。
かたくななり
頑固だ。偏屈だ。粗野で無教養なさま。
かたほなり
未熟だ。不十分だ。
かなし(愛し)
いとしい。すばらしい。しみじみとかわいい。
きら(綺羅)
美しい衣服。はなやかな美しさ。権勢。
きらめく
光り輝く。派手にふるまう。盛んにもてなす。
ぐご(供御)
(おもに天皇の)お食事。
けおさる
圧倒される。
げにげにし
実直だ。まじめだ。
けやけし
際立って目立っている。風変わりだ。きっぱりしている。
こうず(困ず)
困る。ひどく疲れる。
ごせ(後世)
来世での安楽。極楽往生。
こちたし
仰々しい。大げさだ。煩わしい。うるさい。甚だしい。
さがなし(性無し)
意地悪だ。性格が悪い。口うるさい。いたずらだ。
さらぬ
そうでない。そのほかの。大したことではない。何でもない。
すくよかなり
しっかりしている。無骨だ。険しい。無愛想だ。粗野だ。
すずろごと/そぞろごと
くだらない言葉。あてにならないこと。取るに足らないこと。
すずろなり
思いがけない。何ということもない。無関係だ。むやみやたらだ。
せうと(兄人/背人)
兄弟。兄。
そぼつ
(雨・涙などで)濡れる。びしょびしょになる。
つたなし
愚かだ。劣っている。未熟だ。下手だ。運が悪い。見苦しい。
つゆ〈副詞〉
少しも。まったく。
つれなし
素知らぬふうだ。平然としている。冷淡だ。ままならない。思うに任せない。何事もない。
なでふ
何という。どのような。なにほどの。どれほどの。どうして。なんで。
などか
どうして~か。なぜ~か。
なまめかし
優雅で気品に富んでいる。
によふ
うめく。うなる。
はかばかし
はきはきしている。しっかりしている。本格的だ。
ひさく(販く/鬻く)
売る。商う。
まさなし
よくない。不都合だ。見苦しい。予想外だ。
まばゆし
恥ずかしい。きまりが悪い。見ていられない。まぶしい。
むつかし(難し)
いやな感じだ。見苦しい。
煩わしい。うっとうしい。嫌味だ。
もだ(黙)
黙っていること。何もせずじっとしていること。
よすが
頼り。ゆかり。手掛かり。手段。
らうがはし(乱がはし)
ごたごたしている。騒々しい。無作法だ。
わびし(侘びし)
興ざめだ。つまらない。つらい。やりきれない。困ったことだ。
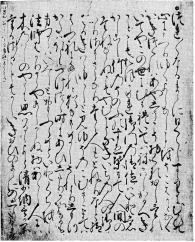
【PR】

