徒然草
十月を神無月と言ひて~第二〇二段
十月を神無月(かみなづき)と言ひて、神事(じんじ)に憚るべきよしは、記したる物なし。もと本文(もとふみ)も見えず。但し、当月、諸社の祭なきゆゑに、この名あるか。
この月、万(よろづ)の神達(かみたち)、太神宮(だいじんぐう)へ集り給ふなどいふ説あれども、その本説(ほんぜつ)なし。さる事ならば、伊勢にはことに祭月(さいげつ)とすべきに、その例もなし。十月、諸社の行幸(ぎやうがう)、その例も多し。但し、多くは不吉の例なり。
【現代語訳】
十月を神無月と言って、神事を慎むべきということを明記した書物はない。典拠となる古典の文章も見出せない。但し、この月はどの神社も祭りをしないので、この名があるのだろうか。
この月は、あらゆる神々が、伊勢大神宮へお集まりになるという説があるが、その根拠となる説はない。もしそういうことなら、伊勢では十月を特別に祭月とするはずなのに、そのような先例もない。十月にはいろいろの神社に行幸された例は多い。但し、その多くは凶例である。
(注)本文・・・拠り所となる古典の文章。
(注)不吉の例・・・具体的には未詳。
↑ ページの先頭へ
徳大寺故大臣殿~第二〇六段
徳大寺故大臣殿(とくだいじのこおほいどの)、検非違使(けんびゐし)の別当(べつたう)の時、中門(ちゆうもん)にて使庁の評定(ひやうぢやう)行はれける程に、官人(くわんにん)章兼(あきかぬ)が牛放れて、庁屋のうちへ入りて、大理の座の浜床(はまゆか)の上に登りて、にれうちかみて臥したりけり。重き怪異(けい)なりとて、牛を陰陽師(おんやうじ)のもとへつかはすべきよし、おのおの申しけるを、父の相国(しやうこく)聞き給ひて、「牛に分別なし。足あれば、いづくへか登らざらん。尩弱(わうじやく)の官人、たまたま出仕の微牛(びぎう)を取らるべきやうなし」とて、牛をば主(ぬし)に返して、臥したりける畳をば換へられにけり。あへて凶事なかりけるとなん。
「怪しみを見て怪しまざる時は、怪しみかへりて破る」と言へり。
【現代語訳】
徳大寺の故大臣殿が、検非違使庁の長官であった時、自邸の中門廊で検非違使庁の評議が行われていたところ、下級役人の章兼の牛が牛車から離れて、庁舎の中に入り、長官がお座りになる座の浜床の上に登って、食べ物を反芻しながら横になっていた。重大な異常事態であるとして、牛を陰陽師のもとに送り届けるよう各人が申し上げたのを、長官の父である太政大臣実基公がお聞きになって、「牛に分別はない。足がある以上、どこへでも行くだろう。微禄の下級役人が、たまたま出仕した時のやせ牛を、取り上げられる理由はない」といって、牛を持ち主に返して、牛が横たわった畳を取り換えられた。その後、少しも不吉なことはなかったという。
「怪しいことを見て怪しまない時は、かえって怪しさは消えてしまう」と言われている。
(注)徳大寺故大臣殿・・・藤原公孝。1267年に検非違使別当に就任。
(注)検非違使の別当・・・現在の最高検察庁長官に相当。
(注)大理・・・検非違使別当の唐名。
(注)浜床・・・寝殿内の帳台の台座。
(注)父の相国・・・公孝の父、大徳寺実基。開明的な人物だった。
↑ ページの先頭へ
亀山殿建てられんとて~第二〇七段
亀山殿(かめやまどの)建てられんとて、地を引かれけるに、大きなる蛇(くちなは)、数も知らず凝(こ)り集りたる塚ありけり。「この所の神なり」と言ひて、ことのよしを申しければ、「いかがあるべき」と勅問ありけるに、「古くよりこの地を占めたる物ならば、さうなく掘り捨てられがたし」と皆人申されけるに、この大臣(おとど)一人、「王土(わうど)にをらん虫、皇居を建てられんに、何の祟りをかなすべき。鬼神(きじん)はよこしまなし。咎(とが)むべからず。ただ皆掘り捨つべし」と申されたりければ、塚を崩して、蛇をば大井河(おほゐがは)に流してげり。さらに祟りなかりけり。
【現代語訳】
御嵯峨院の仙洞御所、亀山殿をお建てになろうとして、地ならしをされたところ、大きな蛇が、無数にかたまり集まっている塚があった。「この土地の神である」と言って、ことの次第を申し上げたところ、「どうしたものか」と御下問あった、その時に、「古くからこの地を占めていたものであるなら、むやみに捨てることはできません」と人々みな申されたところ、この大臣お一人が、「我が君が統治なさる国土に棲む虫が、皇居を建てられるのに、何の祟りをなすものか。鬼神は道理に反したことはしない。気にせずそのまま全部掘って捨てよ」と申されたので、塚を崩して、蛇を大井川に流してしまった。まったく祟りはなかった。
(注)この大臣・・・前段の太政大臣、大徳寺実基。
↑ ページの先頭へ
人の田を論ずるもの~第二〇九段
人の田を論ずるもの、訴へに負けて、ねたさに、「その田を刈りて取れ」とて、人を遣はしけるに、先づ、道すがらの田をさへ刈りもて行くを、「これは論じ給ふ所にあらず。いかにかくは」と言ひければ、刈る者ども、「その所とても、刈るべき理(ことわり)なけれども、僻事(ひがごと)せんとてまかる者なれば、いづくをか刈らざらん」とぞ言ひける。理、いとをかしかりけり。
【現代語訳】
人と田の所有権を争っていた者が、訴訟に負けて、口惜しさのあまりに、「その田の稲を刈り取って来い」と言って、人を遣わしたところ、まず、道中のよその田までもずっと刈っていくのを、「これはお前たちの主人が訴訟で争っていた田ではない。なぜこんなことをるすのか」と言ったところ、刈る者たちは、「あの問題の田だって、刈ってよい道理はないが、我らはどうせ非道を働くために参る者たちなので、どこの田であろうと刈らないことがあろうか」と言った。その屁理屈が、たいそう面白かった。
↑ ページの先頭へ
喚子鳥は~第二一〇段
「喚子鳥(よぶこどり)は春のものなり」とばかり言ひて、如何なる鳥とも、さだかに記せる物なし。ある真言書の中に、喚子鳥鳴く時、招魂(せうこん)の法をば行なふ次第あり。これは鵺(ぬえ)なり。万葉集の長歌(ながうた)に、「霞立つ長き春日(はるひ)の」など続けたり。鵺鳥(ぬえどり)も喚子鳥のことざまに通ひて聞こゆ。
【現代語訳】
「喚子鳥は春の風物である」とだけ言うだけで、どんな鳥ともはっきり記した文献はない。ある真言書の中には、喚子鳥が鳴く時に亡者の魂を招いて供養する手続きが書いてある。この時の喚子鳥とは鵺(トラツグミ)のことである。万葉集の長歌に、「霞立つ長き春日の」などと歌われている。すると、鵺鳥も喚子鳥の様子に似通っているように思える。
(注)真言書・・・何を指すか は不明。
【PR】
↑ ページの先頭へ
よろづの事は頼むべからず~第二一一段
よろづの事は頼むべからず。愚かなる人は、深く物を頼むゆゑに、恨み怒ることあり。
勢ひありとて頼むべからず。こはき者まづ滅ぶ。財(たから)多しとて頼むべからず。時の間に失ひやすし。才(ざえ)ありとて頼むべからず。孔子も時に遇(あ)はず。徳ありとて頼むべからず。顔回(がんくわい)も不幸なりき。君(きみ)の寵(ちよう)をも頼むべからず。誅(ちゆう)を受くること速かなり。奴(やつこ)従へりとて頼むべからず。背き走ることあり。人の志をも頼むべからず。必ず変ず。約をも頼むべからず。信あること少なし。
身をも人をも頼まざれば、是(ぜ)なる時は喜び、非なる時は恨みず。左右(さう)広ければ障(さは)らず、前後遠ければ塞(ふさ)がらず。狭(せば)き時はひしげくだく。心を用ゐること少しきにしてきびしき時は、物に逆(さか)ひ争ひて破る。緩(ゆる)くしてやはらかなる時は、一毛(いちまう)も損せず。
人は天地の霊なり。天地は限る所なし。人の性(せい)、何ぞ異ならん。寛大にして極まらざる時は、喜怒これに障らずして、物のために煩(わづら)はず。
【現代語訳】
何事も何かに頼ってはいけない。愚かな人は、何かを深くあてにするために、人を恨んだり怒ったりすることがある。
権勢があるからといってあてにできない。強い者が最初に滅ぶものである。財産が多いといってあてにできない。時とともに失いがちである。学才があるといってあてにできない。あの孔子ですら不遇をかこった。徳があるといってあてにできない。顔回も不幸だった。主君の寵愛もあてにできない。罪があればすぐに殺されることになる。下僕が従っているといってあてにできない。裏切って逃げることがある。人の厚意もあてにできない。人は必ず変わる。約束もあてにできない。信義が守られることは少ない。
自分の身も他人もあてにしなければ、うまくいった時は喜び、駄目であっても恨まない。左右の幅が広ければ物に遮られないし、前後が遠ければ行き詰まることはない。狭く窮屈だと、ひしゃげて壊れてしまう。心配りが少なく厳格になれば、人と衝突し、争って傷つく。ゆったりとして大らかな時は、毛の一本も損なうことはない。
人は天地の間で最も霊妙な存在である。天地は広大無辺だ。人の本性も、どうして天地のそれと異なるであろうか。寛大で窮屈でないのであれば、喜怒の情はそこに障らないから、外界によって煩わされることがない。
(注)顔回・・・中国春秋時代の人。孔子第一の高弟。
↑ ページの先頭へ
平宣時朝臣、老いののち~第二一五段
平宣時朝臣(たひらののぶときのあそん)、老いの後、昔語りに、「最明寺入道(さいみやうじのにふだう)、ある宵(よひ)の間(ま)に呼ばるることありしに、『やがて』と申しながら、直垂(ひたたれ)のなくて、とかくせしほどに、また使ひ来たりて、『直垂などの候(さうら)はぬにや。夜なれば、異様(ことやう)なりとも、疾(と)く」とありしかば、萎(な)えたる直垂、内々(うちうち)のままにて罷(まか)りたりしに、銚子(てうし)に土器(かはらけ)取り添へて持て出でて、『この酒を独りたうべんがさうざうしければ、申しつるなり。肴(さかな)こそなけれ、人は静まりぬらん。さりぬべき物やあると、いづくまでも求め給へ』とありしかば、紙燭(しそく)さして、隈々(くまぐま)を求めしほどに、台所の棚に、小土器(こかわらけ)に味噌(みそ)の少し付きたるを見出(みい)でて、『これぞ求め得て候ふ』と申ししかば、『事(こと)足りなん』とて、心よく数献(すこん)に及びて、興(きよう)に入られ侍りき。その世にはかくこそ侍りしか」と申されき。
【現代語訳】
平宣時朝臣が、年老いて後、昔語りにこのような話をした。「最明寺入道が、ある晩に私をお呼びになったので、『すぐに参ります』と申し上げたものの、しかるべき直垂がなくて、ぐずぐずしていると、また使いが来て、『直垂がおありにならないのか。夜であるので、どんな格好でも構わない。早く来てほしい』とのことなので、よれよれの直垂を着て、普段着のままで参上しました。入道殿は、銚子に素焼きの器を添えて持って現れ、『この酒を独りで飲むのは物足りないので、お呼び立てした。あいにく肴が無いのだが、人は寝静まっている。何か適当な物がないか、どこでもよいから探してくれないか」と言うので、紙燭を灯して、すみずみまで探し求めました。すると、台所の棚に、小さな素焼きの器に味噌が少しついたのを見つけて、『これを見つけ出しました』と申し上げたところ、『それで十分』と言って、気分よく何杯も酌み交わして、上機嫌になられました。あの時代は、万事こんなふうに質素でございました」と言われたのである。
(注)最明寺入道・・・鎌倉幕府の第5代執権、北条時頼。平宣時は、時頼の補佐役である連署をつとめていた。
↑ ページの先頭へ
ある大福長者~第二一七段
(一)
ある大福長者(だいふくちやうじや)の云はく、「人は万(よろづ)を差し置きて、ひたぶるに徳をつくべきなり。貧しくては生けるかひなし。富めるのみを人とす。徳をつかんと思はば、すべからくまづその心遣ひを修行(しゆぎやう)すべし。その心といふは他(た)のことにあらず。人間(にんげん)常住(じやうぢゆう)の思ひに住(ぢゆう)して、仮にも無常を観ずることなかれ。これ第一の用心なり。次に、万事の用をかなふべからず。人の世にある、自他(じた)につけて所願(しよぐわん)無量(むりやう)なり。欲に随(したが)ひて志を遂げんと思はば、百万の銭(ぜに)ありといふとも、暫くも住(ぢゆう)すべからず。所願は止(や)む時なし。財(たから)は尽くる期(ご)あり。限りある財を持ちて、限りなき願ひに従ふこと、得(う)べからず。所願、心に兆(きざ)すことあらば、我を亡(ほろ)ぼすべき悪念(あくねん)来たれりと、堅く慎み恐れて、小要(せうえう)をも為すべからず。
【現代語訳】
ある大富豪は、次のように説いた。「人は、何事にも優先して、財産を築くべきだ。貧しくては生きている甲斐がない。金持ちだけが人間らしいといえる。金持ちになろうと思えば、まず心構えを修行すべきだ。その心構えというのはほかでもない。人の世は不変だという信念を持ち、仮にも無常だなどと悟ってはいけない。これが心構えの第一である。次に、やりたいことを全部かなえようとしてはならない。生きていれば、自他ともに関して、欲望は無限に生ずる。その欲望のまま目的を遂げようとすれば、どれほど大金があっても、すぐになくなってしまう。欲望は止むことがない。財産は尽きる時がある。限りのある財産によって、無限の欲望に従うことは不可能だ。欲望が心にわいてきたら、我が身を滅ぼす邪悪な考えがやって来たと、かたく慎み恐れて、小さなことにさえ金を費やしてはならない。
(二)
次に、銭(ぜに)を奴(やつこ)の如くして使ひ用ゐる物と知らば、長く貧苦を免(まぬか)るべからず。君(きみ)の如く神の如く畏(おそ)れ尊(たふと)みて、従へ用ゐることなかれ。次に、恥に臨むといふとも、怒り怨むることなかれ。次に、正直にして、約を堅くすべし。この義を守りて利を求めん人は、富の来たること、火の乾けるにつき、水の下れるに従ふが如くなるべし。銭積もり尽きざる時は、宴飲(えんいん)、声色(せいしよく)を事(こと)とせず、居所(きよしよ)を飾らず、所願(しよぐわん)を成(じやう)ぜざれども、心とこしなへに安く楽し」と申しき。
そもそも人は、所願を成ぜんがために財(たから)を求む。銭を財とすることは、願ひをかなふるが故なり。所願あれどもかなへず、錢あれども用ゐざらんは、全く貧者と同じ。何をか楽しびとせん。この掟(おきて)は、ただ人間の望みを断ちて、貧を憂ふべからずと聞えたり。欲を成じて楽(たの)しびとせんよりは、如(し)かじ、財なからんには。癰(よう)、疽(そ)を病む者、水に洗ひて楽しびとせんよりは、病まざらんには如(し)かじ。ここに至りては、貧富(ひんぷ)分(わ)く所なし。究竟(くきやう)は理即(りそく)に等し。大欲は無欲に似たり。
【現代語訳】
次に、銭を下僕のように自由に使用できると考えていると、いつまでも貧乏から抜け出すことはできない。銭をあたかも主君や神様のように畏敬し尊重し、決して思いに任せて使ってはならない。次に、金銭のことで恥をかいても、怒り恨むことがあってはならない。次に、正直を心掛けて人との約束を堅く守らなくてはならない。以上の心構えを守って利益を求める人は、まるで火が乾いた物に燃え移り、水が低い所に流れ落ちるように、財産は集まってくるに違いない。その結果、銭が積もって尽きなくなった時は、酒や音曲、女などで遊興せず、住まいを飾らず、たとえ欲望を果たせないといっても、心はいつも安らかで楽しいものだ」と言ったのだった。
そもそも人は、欲望を成就するために財産を求める。銭を財産として尊ぶのは、欲望を叶えてくれるからだ。なのに、欲望があっても叶えず、銭があっても使わないのでは、全く貧乏人と同じである。それで何を楽しみとするのだろう。この大福長者の教えは、ただ人間の欲望を断ち切って、貧しさを嘆くな、という意味に受け取れる。それならば、欲望を成就して楽しみとするよりは、はじめから財産が無いほうがよい。たとえば悪性のできものを患う者が、患部を水で洗えば気持ちよいと感ずるであろうが、最初から病気をしないほうがいいのだ。この境地に至っては、貧富の差異は無くなる。仏教の最高の悟りの境地と、最低の迷いの境地と等しいということになる。欲望が大きいことは、無欲に似ているということだ。
【PR】
↑ ページの先頭へ
よき細工は~第二二九段
よき細工(さいく)は、少しにぶき刀を使ふといふ。
妙観(めうくわん)が刀はいたくたたず。
【現代語訳】
腕のよい細工師は、少し切れ味の悪い小刀を用いるという。
妙観(彫刻の名人)の小刀はあまりよく切れない。
↑ ページの先頭へ
万の咎あらじと思はば~第二三三段
万(よろづ)の咎(とが)あらじと思はば、何事にもまことありて、人を分かず、うやうやしく、言葉少なからんには如(し)かじ。男女老少(なんによらうせう)、皆さる人こそよけれども、ことに若くかたちよき人の、言(こと)うるはしきは、忘れがたく、思ひつかるるものなり。
万(よろづ)の咎は、馴れたるさまに上手めき、所得(ところえ)たる気色(けしき)して、人をないがしろにするにあり。
【現代語訳】
万事に間違いがないように心掛けるなら、何事にも誠実であり、人を差別せず礼儀正しくして、言葉数が少ないのが一番だ。老若男女、すべてそのような人こそよいのだが、特に若くて容姿にすぐれた人で、言葉遣い端正な人は、一度会えば忘れがたく、心引かれる思いが深くなるものだ。
あらゆるあやまちは、物馴れた様子で上手ぶり、得意げな態度で、人を軽んずることから生ずる。
↑ ページの先頭へ
主ある家には~第二三五段
主(ぬし)ある家には、すずろなる人、心のままに入り来ることなし。主(あるじ)なき所には、道行き人みだりに立ち入り、狐、梟(ふくろふ)やうの物も、人気(ひとげ)に塞(せ)かれねば、所得顔(ところえがほ)に入(い)り住み、木霊(こだま)などいふけしからぬ形も現るるものなり。
また、鏡には色、形なき故に、よろづの影(かげ)来たりて映る。鏡に色、形あらましかば、映らざらまし。
虚空(こくう)よく物を容(い)る。我らが心に、念々のほしきままに来たり浮かぶも、心といふものの無きにやあらん。心に主(ぬし)あらましかば、胸のうちに若干(そこばく)のことは入り来たらざらまし。
【現代語訳】
主人のある家には、関係のない人間が勝手に入ってくるようなことはない。主人のない家には、道行く人が勝手に立ち入ったり、狐や梟のようなものも、人の気配に妨げられないから、我が物顔に入って棲みつき、木霊などという怪奇な霊も現れるものだ。
また、鏡は、それ自体に色や形がないからこそ、あらゆる物が映る。もし鏡に色や形があったならば、それが邪魔をして何も映ることはない。
空っぽの空間は、十分に物を容れることができる。我々の心の中に、さまざまな雑念が入り込んできて浮かぶのも、心に主がいないからではなかろうか。心にも主人がいれば、そんなものは入って来ないだろう。
↑ ページの先頭へ
丹波に出雲と云ふ所あり~第二三六段
丹波(たんば)に出雲(いづも)といふ所あり。大社(おほやしろ)を移して、めでたく造れり。志田(しだ)のなにがしとかや知る所なれば、秋の頃、聖海上人(しやうかいしやうにん)その外(ほか)も、人あまた誘ひて、「いざ給へ、出雲拝みに。掻餅(かいもちひ)召させん」とて、具しもて行きたるに、おのおの拝みて、ゆゆしく信おこしたり。
御前(おまへ)なる獅子(しし)、狛犬(こまいぬ)、背(そむ)きて後(うしろ)さまに立ちたりければ、上人いみじく感じて、「あなめでたや。この獅子の立ちやう、いとめづらし。深き故あらん」と涙ぐみて、「いかに殿原(とのばら)、殊勝のことは御覧じとがめずや。無下(むげ)なり」と言へば、おのおの怪しみて、「まことに他に異なりけり。都のつとに語らん」など言ふに、上人なほゆかしがりて、おとなしく物知りぬべき顔したる神官を呼びて、「この御社(みやしろ)の獅子の立てられやう、定めて習ひあることに侍らん。ちと承らばや」と言はれければ、「その事に候ふ。さがなき童(わらはべ)どもの仕(つかまつ)りける、奇怪に候ふことなり」とて、さし寄りて、据ゑ直して往(い)にければ、上人の感涙いたづらになりにけり。
【現代語訳】
丹波の国に出雲という所がある。そこの神社は、出雲大社の御神霊を勧請して分け移して立派に造営したものだ。志田の某(なにがし)とかいう人が治めている所で、秋の頃、志田が聖海上人やその他大勢を誘って、「さあ参りましょう、出雲神社参詣に。ぼた餅をご馳走しましょう」と言って連れて行き、皆が参拝して厚い信仰心を起こしたのだった。
拝殿の前にある獅子と狛犬が、背中を向け合い後ろ向きに立っていたのを、上人がたいそう感心して、「ああ素晴らしい。この獅子の立ち方はとても珍しい。何か深いわけがあるのだろう」と涙ぐみ、「何と皆さん、こんな素晴らしいものをご覧になって、不思議に思わいのですか、全く」と言うと、皆それぞれ不思議そうに、「本当に他と違いますね。都への土産話にしよう」などと言う。上人はますますそのわけを知りたく思い、年配で物知りらしい神官を呼んで、「この御社の獅子の立てられ方は、きっと何かいわれがあるのでしょう。ちょっと承りたいものです」と言われたところ、「その事でございます。いたずらな子どもがいたしましたことで、けしからんことです」と言って、獅子と狛犬に近寄り、元通りに据え直して行ってしまったので、上人の感涙は無駄になってしまったそうだ。
↑ ページの先頭へ
八つになりし年~第二四三段
八(や)つになりし年、父に問ひて云はく、「仏(ほとけ)は如何(いか)なるものにか候(さうら)ふらん」と言ふ。父が云はく、「仏には、人の成りたるなり」と。また問ふ、「人は何として仏には成り候ふやらん」と。父また、「仏の教へによりて成るなり」と答ふ。また問ふ、「教へ候ひける仏をば、何が教へ候ひける」と。また答ふ、「それもまた、前(さき)の仏の教へによりて成り給ふなり」と。また問ふ、「その教へ始め候ひける第一の仏は、如何なる仏にか候ひける」と言ふ時、父、「空よりや降りけん。土よりや湧(わ)きけん」と言ひて、笑ふ。「問ひつめられて、え答へずなり侍(はべ)りつ」と諸人(しょにん)に語りて興(きよう)じき。
【現代語訳】
八歳になった時、父に問うたことがあった。「仏とはどんなものでしょうか」。父は、「仏とは人間がなったものだ」と答えた。私は、「では、人間はどのようにして仏になったのでしょうか」と尋ねた。父は、「仏の教えによってなったのだ」と答えた。私は、「人間を教えた仏は、何が教えて仏になったのでしょうか」と尋ねた。父は、「その仏の先輩の教えによって、仏になったのだ」と答えた。私は、「それでは、仏になる教えを始めた一番目の仏は、どんな仏なのでしょうか」と、問い詰めた。すると、父は、「空から降ってきたか、あるいは地面から湧いて出たか」と言って笑った。「問い詰められて、とうとう答えられなくなりました」と、人に語っては面白がっていた。
 |
古典に親しむ
万葉集・竹取物語・枕草子などの原文と現代語訳。 |
バナースペース
【PR】
語 句
気に入らない。つまらない。不似合いだ。不快である。
あさまし
驚くばかりだ。意外だ。情けない。興ざめだ。あきれるほどひどい。見苦しい。
あひしらふ
程よく受け答えをする。応対する。
あふさきるさ
ちぐはぐ。ああかこうか。あれやこれや。
いらなし
甚だしい。大げさだ。もったいぶって。
いろふ(綺ふ)
関わる。口出しする。干渉する。
うぐ(穿ぐ)
穴があく。
うるはし
端正である。整っている。壮大で美しい。色鮮やかだ。正しい。
かたくななり
頑固だ。偏屈だ。粗野で無教養なさま。
かたほなり
未熟だ。不十分だ。
かなし(愛し)
いとしい。すばらしい。しみじみとかわいい。
きら(綺羅)
美しい衣服。はなやかな美しさ。権勢。
きらめく
光り輝く。派手にふるまう。盛んにもてなす。
ぐご(供御)
(おもに天皇の)お食事。
けおさる
圧倒される。
げにげにし
実直だ。まじめだ。
けやけし
際立って目立っている。風変わりだ。きっぱりしている。
こうず(困ず)
困る。ひどく疲れる。
ごせ(後世)
来世での安楽。極楽往生。
こちたし
仰々しい。大げさだ。煩わしい。うるさい。甚だしい。
さがなし(性無し)
意地悪だ。性格が悪い。口うるさい。いたずらだ。
さらぬ
そうでない。そのほかの。大したことではない。何でもない。
すくよかなり
しっかりしている。無骨だ。険しい。無愛想だ。粗野だ。
すずろごと/そぞろごと
くだらない言葉。あてにならないこと。取るに足らないこと。
すずろなり
思いがけない。何ということもない。無関係だ。むやみやたらだ。
せうと(兄人/背人)
兄弟。兄。
そぼつ
(雨・涙などで)濡れる。びしょびしょになる。
つたなし
愚かだ。劣っている。未熟だ。下手だ。運が悪い。見苦しい。
つゆ〈副詞〉
少しも。まったく。
つれなし
素知らぬふうだ。平然としている。冷淡だ。ままならない。思うに任せない。何事もない。
なでふ
何という。どのような。なにほどの。どれほどの。どうして。なんで。
などか
どうして~か。なぜ~か。
なまめかし
優雅で気品に富んでいる。
によふ
うめく。うなる。
はかばかし
はきはきしている。しっかりしている。本格的だ。
ひさく(販く/鬻く)
売る。商う。
まさなし
よくない。不都合だ。見苦しい。予想外だ。
まばゆし
恥ずかしい。きまりが悪い。見ていられない。まぶしい。
むつかし(難し)
いやな感じだ。見苦しい。
煩わしい。うっとうしい。嫌味だ。
もだ(黙)
黙っていること。何もせずじっとしていること。
よすが
頼り。ゆかり。手掛かり。手段。
らうがはし(乱がはし)
ごたごたしている。騒々しい。無作法だ。
わびし(侘びし)
興ざめだ。つまらない。つらい。やりきれない。困ったことだ。
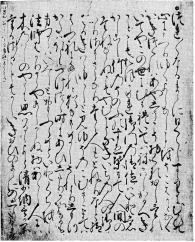
【PR】
