源氏物語
明石(あかし)
■源氏、明石に渡る
(一)
終日(ひねもす)にいりもみつる雷(かみ)の騒ぎに、さこそいへ、いたう困(こう)じ給ひにければ、心にもあらずうちまどろみ給ふ。かたじけなき御座所(おましどころ)なれば、ただ寄り居給へるに、故院ただおはしましし様(さま)ながら、立ち給ひて、「などかくあやしき所にはものするぞ」とて、御手を取りて引き立て給ふ。「住吉の神の導き給ふままに、はや舟出(ふなで)してこの浦を去りね」と宣はす。いとうれしくて、「かしこき御影に別れ奉りにしこなた、さまざま悲しき事のみ多く侍れば、今はこの渚に身をや棄て侍りなまし」と聞こえ給へば、「いとあるまじきこと。これはただいささかなる物の報いなり。我は位に在りし時、過(あやま)つことなかりしかど、おのづから犯しありければ、その罪を終(を)ふるほど暇(いとま)なくて、この世を顧(かへり)みざりつれど、いみじき愁(うれ)へに沈むを見るに、堪へ難くて、海に入り、渚に上り、いたく困(こう)じにたれど、かかるついでに内裏(だいり)に奏すべきことあるによりなむ急ぎ上りぬる」とて、立ち去り給ひぬ。
【現代語訳】
一日じゅう激しく吹き荒れた雷の騒ぎに、あのように源氏の君は気強く構えていらしたとはいっても、ひどくお疲れになったので、ついうとうととなさる。粗末なもったいない御座所なので、ただ物に寄りかかってお休みになっておられると、亡き桐壺院が、ご生前そのままのお姿でお立ちになり、「どうしてこんな見すぼらしい所にいるのだ」とおっしゃって、御手を取ってお引き立てになる。「住吉の神のお導きに従って、早々に舟出してこの浦を去りなさい」と仰せになる。あまりの嬉しさに、「父上の尊いお姿にお別れ申してからというもの、様々に悲しい事ばかり多くございますので、今はもうこの渚に身を捨ててしまいとう存じます」と申し上げると、院は「とんでもないことだ。これはほんのちょっとした事の報いなのだ。自分は位にあった時に過ちはなかったが、知らず知らずに犯した罪があったので、その罪を償う間は暇がなくてこの世を顧みなかったが、そなたが悲しみに沈んでいるのを見るに堪え難くて、海に入り渚に上がり、ひどく疲れたが、この機会に帝に申し上げたいこともあるので、これから急いで都へ上るのだ」とおっしゃって、立ち去られた。
(二)
飽かず悲しくて、「御供に参りなむ」と泣き入り給ひて、見上げ給へれば、人もなく、月の顔のみきらきらとして、夢の心地もせず、御けはひとまれる心地して、空の雲あはれにたなびけり。年ごろ夢の中(うち)にも見奉らで、恋しうおぼつかなき御様を、ほのかなれど、さだかに見奉りつるのみ面影におぼえ給ひて、「我がかく悲しびを極め、命尽きなむとしつるを、助けに翔(かけ)り給へる」とあはれに思すに、「よくぞかかる騒ぎもありける」と、なごり頼もしう、嬉しうおぼえ給ふこと限りなし。胸つと塞(ふた)がりて、なかなかなる御心まどひに、現(うつつ)の悲しき事もうち忘れ、夢にも御答(いら)へを今少し聞こえずなりぬることと、いぶせさに、「またや見え給ふ」と、ことさらに寝入り給へど、さらに御目も合はで、暁方(あかつきがた)になりにけり。
【現代語訳】
源氏の君は、あっけなくお別れすることが悲しく、「私も御供に参ります」と泣き入りながらお見上げになると、人影はなく、月の顔だけがきらきらと輝き、夢の心地もなさらない。まだそこらに御気配が残っている気がして、空の雲がしみじみとした風情でたなびいている。何年も夢の中にさえ御姿を拝せず、恋しく気がかりに存じ上げていた御姿を、ほんの少しながらもはっきりと拝見したことだけがいつまでも目の前に幻となって感じられ、「自分がこんなに悲しみに沈んで命が尽きようとしているのを、助けに天を翔っていらっしゃったのだ」と、しみじみ有難くお思いになり、「よくもこんな暴風雨もあってくれたものだ」と、夢の名残も頼もしく感じられ、嬉しくお思いになる。胸がいっぱいになり、今はかえって落ち着かず、目の前の悲しさもお忘れになり、夢の中でもっとお話し申し上げなかったことが心残りで、「またお逢いできるのではないか」と、もう一度わざと寝入ろうとなさるが、全くお眠りになれず、明け方になってしまった。
(三)
渚に小さやかなる舟寄せて、人二三人ばかり、この旅の御宿りをさして来(く)。「何人(なにびと)ならむ」と問へば、「明石の浦より、前(さき)の守(かみ)新発意(しぼち)の、御舟よそひて参れるなり。源少納言侍ひ給はば、対面(たいめ)して事の心とり申さむ」と言ふ。良清驚きて、「入道はかの国の得意にて、年ごろあひ語らひ侍りつれど、私(わたくし)にいささかあひ恨むること侍りて、ことなる消息(せうそこ)をだに通はさで、久しうなり侍りぬるを、浪の紛れに、いかなることかあらむ」とおぼめく。君の、御夢なども思し合はすることもありて、「はや会へ」と宣へば、舟に行きて会ひたり。「さばかり烈(はげ)しかりつる波風に、いつの間にか舟出しつらむ」と、心えがたく思へり。
「去(い)ぬる朔日(ついたちのひ)の夢に、さま異なる者の告げ知らすること侍りしかば、信じ難きことと思う給へしかど、『十三日にあらたなるしるし見せむ。舟、装(よそ)ひ設(まう)けて、必ず、雨風止まばこの浦にを寄せよ』と、かねて示すことの侍りしかば、こころみに舟の装ひを設けて待ち侍りしに、いかめしき雨風、雷(いかづち)の驚かし侍りつれば、他(ひと)の朝廷(みかど)にも、夢を信じて国を助くるたぐひ多う侍りけるを、『用ゐさせ給はぬまでも、このいましめの日を過ぐさず、この由を告げ申し侍らむ』とて、舟出(い)だし侍りつるに、あやしき風細う吹きて、この浦に着き侍ること、まことに神のしるべ違(たが)はずなむ。ここにも、もし知ろし召すことや侍りつらむとてなむ。いと憚(はばか)り多く侍れど、この由申し給へ」と言ふ。
【現代語訳】
岸に小さな舟を寄せて、人がニ、三人ほど、このかりそめの御宿に向かってやって来る。供人たちが「誰だろうか」と尋ねると、「明石の浦から、前の播磨国守で最近仏道に入られた方がお舟を用意して参ったのです。源少納言(良清)がおいでなら、お目にかかって事の仔細をお話しましょう」と言う。良清は驚いて「入道は播磨国で懇意にしている方で、長年親しくしておりましたが、私事で少しいさかい事がございまして、格別に手紙さえ交わさなまま長くなっておりますのに、この荒浪の中いらっしゃるとはどんな事情があるのでしょう」と不審がる。源氏の君は御夢のことなども思い合わされるふしもあって、「早く会え」とおっしゃるので、良清は舟に行って入道に会った。あれほど激しかった波風なのに、いつの間に船出したのだろうと不思議な気がする。
入道は「去る朔日の夢に、異形の者が現れて告げ知らせることがあり、信じ難い事と存じましたが、『十三日にあらたかな験(しるし)を見せよう。舟の用意をして、雨風が止んだら必ずこの浦に漕いで参れ』とのことでございましたので、ためしに舟の用意をして待っていましたら、激しい雨風、雷が起こりましたので、夢を信じて国を救う例がよその国にも多くございますから、『たとえお取り上げくださらぬまでも、お告げにあった日を見過ごさず、この由を申し上げよう』と存じて、舟を出しましたところ、不思議な風が一筋吹いてこの浦に着きましたことは、まことに神の導きに間違いはございません。もしやこちらにも何かお心当たりの事がおありかと存じ、まことに恐縮でございますが、このことを君に言上してください」と言う。
(注)新発意・・・新たに仏道に入った人。明石入道をさす。
【PR】
↑ ページの先頭へ
■入道、娘のことを語る
いたく更けゆくままに、浜風涼しうて、月も入り方になるままに澄みまさり、静かなる程に、御物語残りなく聞こえて、この浦に住み始めし程の心づかひ、後の世を勤むる様、かきくづし聞こえて、この女(むすめ)の有様、問はず語りに聞こゆ。をかしきものの、さすがにあはれと聞き給ふ節もあり。
「いと取り申し難きことなれど、わが君、かう覚えなき世界に、仮にても移ろひおはしましたるは、もし、年ごろ老法師(おいほふし)の祈り申し侍る神仏の憐(あはれ)びおはしまして、しばしのほど御心をも悩まし奉るにやとなむ思う給ふる。そのゆゑは、住吉の神を頼み始め奉りて、この十八年になり侍りぬ。女(め)の童(わらは)のいときなう侍りしより、思ふ心侍りて、年ごとの春秋ごとに必ずかの御社に参ることなむ侍る。昼夜の六時の勤めに、みづからの蓮(はちす)の上の願ひをばさるものにて、ただこの人を高き本意(ほい)かなへ給へとなむ念じ侍る。前(さき)の世の契りつたなくてこそかく口惜しき山がつとなり侍りけめ、親、大臣の位を保ち給へりき。みづからかく田舎の民となりにて侍り。次々さのみ劣りまからば、何の身にかなり侍らむと、悲しく思ひ侍るを、これは生まれし時より頼む所なむ侍る。いかにして都の貴(たか)き人に奉らむと思ふ心深きにより、ほどほどにつけて、あまたの人の嫉みを負ひ、身の為からき目を見るをりをりも多く侍れど、さらに苦しみと思ひ侍らず。命の限りはせばき衣にもはぐくみ侍りなむ。かくながら見捨て侍りなば、浪の中にも交じり失せね、となむ掟(おき)て侍る」など、すべてまねぶべくもあらぬ事どもを、うち泣きうち泣き聞こゆ。君もものをさまざま思し続くる折からは、うち涙ぐみつつ聞こし召す。
「横ざまの罪に当りて思ひかけぬ世界に漂ふも、何の罪にかとおぼつかなく思ひつるを、今宵の御物語に聞き合はすれば、げに浅からぬ前(さき)の世の契りにこそはとあはれになむ。などかは、かくさだかに思ひ知り給ひけることを今までは告げ給はざりつらむ。都離れし時より、世の常なきもあぢきなう、行ひよりほかの事なくて月日を経(ふ)るに、心も皆くづほれにけり。かかる人ものし給ふとはほの聞きながら、いたづら人をば、ゆゆしきものにこそ思ひ棄て給ふらめ、と思ひ屈(く)しつるを、さらば導き給ふべきにこそあなれ。心細き独り寝の慰めにも」など宣ふを、限りなくうれしと思へり。
【現代語訳】
夜がたいそう更け行くにつれて、浜風が涼しく吹き、月も西に傾くままにいよいよ澄み渡り、辺りが静かになってきたので、入道は頃合いを見て事情を残らず申し上げて、この浦に住み始めた頃の気づかいや、極楽往生を願ってお勤めをする様子を少しずつお話申し上げてから、自分の娘のことを問わず語りにお話になる。源氏の君は興味深くお聞きになるが、さすがに不憫にお感じなる節々もある。
「たいそう申し上げにくくはございますが、貴方さまがこうして見知らぬ土地に、たとえ一時にせよお移りあそばしたのは、もしや長年この老法師がお祈り申しておりました神仏が志を憐れんで下さって、そのためにしばらくの間、君の御心を悩まし申し上げているのではなかろうかと存じます。というのは、住吉の神に願をかけましてから十八年になります。まだあの娘が幼い頃から、思う仔細がございまして、毎年の春秋ごとに必ずあの御社へ参詣させておりました。昼夜の六時のお勤めにも、自分自身の極楽往生を願うことはさておき、ひたすらこの者を高い位にという私の望みをお叶え下さいと念じておりました。私は前世の因縁が悪くてこのように情けない山賤に落ちぶれたのでしょうが、親は大臣の位を保っておりました。私の代にこんな田舎の民になったのでございます。子孫が次々に落ちぶれていきましたら、しまいにはどんな身になりますやらと悲しく存じておりますが、この娘にだけは、生まれた時から期待をかけているところがございます。どうにかして都の貴いお方に差し上げようと心に深く決めましたので、卑しき身分ながら多くの人の嫉みを買い、私自身としましても度々辛い目にも遭いましたが、それを少しも苦には思いません。命の続く限りは、貧しい中にもあれを守り育てて参りましょう。このまま私が先立ってしまったら、海にでも身を投げてしまえ』と申しつけてあるのでございます」など、すべてそのまま書き記すこともできないような事どもを、泣く泣く申し上げる。源氏の君も様々に物を案じ続けていらっしゃる折も折なので、涙ぐみながらお聞きになる。
「言われなき罪を蒙って思いがけない土地に漂って来ましたのは、何の報いであろうかと気にかかっていたのですが、今宵のお話を伺ってみれば、なるほど浅からぬ前世の約束であったのだとしみじみ分かりました。そんなにはっきり思い当たっておられることを、なぜ今まで話して下さらなかったのです。都を離れた時から、世の無常を味気なく感じ、仏事のお勤めのほかの事もなく月日を過ごしているうちに、心もすっかり折れてしまいました。そういう人がおられるとはうすうす聞いてはいながら、私のような世に捨てられた者を、縁起でもないと相手にしても下さるまいと落胆しておりましたが、それならば引き合わせて頂けるのですね。心細い独り寝の慰めにもなることですから」などおっしゃるのを、入道はどこまでも嬉しく思う。
↑ ページの先頭へ
■源氏、明石の上と契る
(一)
造れるさま木深(こぶか)く、いたき所まさりて、見所ある住まひなり。海のつらは厳(いかめ)しう面白く、これは心細く住みたる様、「ここに居て、思ひ残すことはあらじとすらむ」と思しやらるるに、ものあはれなり。三味堂(さんまいだう)近くて、鐘の声松風に響き合ひて、もの悲しう、巌(いは)に生ひたる松の根ざしも、心ばへある様なり。前栽(せんざい)どもに虫の声を尽くしたり。ここかしこの有様など御覧ず。女(むすめ)住ませたる方は、心ことに磨きて、月入れたる真木(まき)の戸口、けしきばかりおし開けたり。
うちやすらひ何かと宣ふにも、「かうまでは見え奉らじ」と深う思ふに、もの嘆かしうて、うちとけぬ心ざまを、「こよなうも人めきたるかな。さしもあるまじき際(きは)の人だに、かばかり言ひ寄りぬれば、心強うしもあらずならひたりしを、いとかくやつれたるにあなづらはしきにや」と、妬(ねた)うさまざまに思し悩めり。
【現代語訳】
岡辺の家の作りざまは、木々が深く、数寄を凝らした見どころのある住まいである。海辺の方は堂々として興をひく建て方だったが、こちらはいかにもはかなげに住んでいる様子で、「ここで暮らしたら、あらゆる風雅を味わい尽くすだろう」と住む人の心も想像され、しみじみと胸に迫る。入道が勤行する三昧堂が近いので、鐘の音が松風と響き合って物悲しく、岩に生えた松の根の延びているのも情緒ありげである。庭の植え込みでは秋の虫がいっせいに鳴いている。源氏の君は、あちらこちらの有様をご覧になる。娘を住まわせている一棟は特に念入りに美しくこしらえてあって、月の光が差し込んだ木戸口が少しばかり押し開けてある。
源氏の君は中にお入りになり、ためらいがちにあれこれおっしゃるが、娘は「こんなに近しくお目にかかりたくはない」と固く思い決めているのでため息がちになり、打ち解けぬ気構えなのを、「たいそう一人前ぶっていることよ。近づきがたい身分の女でさえ、これほどまでに言い寄ればそう強情を張らないのが今までの例であったのに、このように落ちぶれているのを侮っているのだろうか」と、いまいましくもあり、様々に思い悩んでいらっしゃる。
(注)三昧堂・・・念仏修行をする堂。
(二)
「情なうおし立たむも、事の様に違(たが)へり。心くらべに負けむこそ人わろけれ」など、乱れ恨み給ふ様、げに物思ひ知らむ人にこそ見せまほしけれ。近き几帳(きちやう)の紐(ひも)に、箏(さう)の琴(こと)のひき鳴らされるも、けはひしどけなく、うちとけながら掻きまさぐりけるほど見えてをかしければ、「この聞きならしたる琴をさへや」など、よろづに宣ふ。
(源氏)むつごとを語りあはせむ人もがなうき世の夢もなかばさむやと
(娘)明けぬ夜にやがてまどへる心にはいづれを夢とわきて語らむ
ほのかなるけはひ、伊勢の御息所(みやすどころ)にいとよう覚えたり。何心もなくうちとけてゐたりけるを、かう物覚えぬに、いと理(わり)なくて、近かりける曹司(ざうし)の内に入りて、いかで固めけるにかいと強きを、しひてもおし立ち給はぬ様なり。されどさのみもいかでかあらむ。人ざまいとあてにそびえて、心恥づかしきけはひぞしたる。かうあながちなりける契りを思すにも、浅からずあはれなり。御心ざしの近まさりするなるべし、常は厭(いと)はしき夜の長さも、とく明けぬる心地すれば、人に知られじと思すも、心あわただしうて、こまかに語らひ置きて出で給ひぬ。
【現代語訳】
源氏の君は「そう荒々しく振舞って無理強いするのも、今の場合はふさわしくないし、かといって意地の張り合いに負けるのは体裁が悪い」など、やきもきなさっているご様子は、全く物の情けを知る人に見せたいものであった。女の近くにある几帳の紐に箏の琴が当たって音が鳴ったりする気配もしどけなく、今までここにくつろぎながら慰みに弾いていたらしい様子が偲ばれて興があるので、「いつも父君からお話に聞いている琴までも聞かせてくださらぬのか」など、言葉を尽くして思いを訴えられる。
親しい言葉を語り合う相手がほしいのです。憂き世のつらい夢も、半ば覚めるのではないかと思いまして。
長夜の闇に迷っている私の心には、何が夢で何が現か、どう分かって語ることができましょうか。
かすかに感じられる娘の気配は、伊勢におられる六条の御息所にとてもよく似ている。何も知らずにくつろいでいたところに、こうして不意の来訪を受けたことに当惑して、近くの部屋に逃げ込み、どうやって閉めたのかたいそう固く戸を閉ざしているのを、源氏の君は強いて開けようとはなさらない。しかし、そうばかりもしておられようか。この娘の人柄は実に上品で、すらりとして、こちらが引け目を感じるほどな姿である。源氏の君は、こんな無理やりの契りを思うにつけても、前世からの縁が浅からぬことにしみじみと感慨をもよおされる。お逢いになればひとしお愛しさが深く感じられるのだろう、いつもは飽き飽きなさる秋の夜長が、今夜ばかりは早く明けてしまう気がするので、人に知られまいとお思いになって気がせいて、心を込めたお言葉を残してお帰りになった。
(三)
御文いと忍びてぞ今日はある。あいなき御心の鬼なりや。ここにも、かかる事いかで漏らさじとつつみて、御使ことごとしうももてなさぬを、胸いたく思へり。かくて後は、忍びつつ時々おはす。ほどもすこし離れたるに、おのづからもの言ひさがなき海人(あま)の子もや立ちまじらんと思し憚(はばか)るほどを、さればよと思ひ嘆きたるを、げにいかならむと、入道も極楽の願ひをば忘れて、ただこの御気色を待つことにはす。今さらに心を乱るも、いといとほしげなり。
【現代語訳】
今日はたいそうこっそりと御文を届けられる。源氏の君は、わけもなく御心が咎められたのだろうか。入道の方でも昨夜の事は何とか外に漏らすまいと用心して、御使を大げさにもてなせないのを心苦しく思っている。それから後は、折々忍んで娘のもとにお通いになる。場所も少し離れているので、自然と口さがない海人の子などに行き会いはしないかとお控えになる夜が続くと、娘は早くも捨てられたと思って嘆くのを、入道も、ほんにこれはどうなることかと極楽の願いも忘れて、ひたすらご来訪を待ってばかりいる。今さら心を乱しているのがたいそう気の毒だった。
↑ ページの先頭へ
■源氏に赦免の宣旨下る
年かはりぬ。内裏(うち)に御薬のことありて、世の中さまざまにののしる。当帝(たうだい)の御子は、右大臣の女(むすめ)、承香殿の女御の御腹に男御子(をとこみこ)生まれ給へる、二つになり給へば、いといはけなし。春宮にこそは譲り聞こえたまはめ、朝廷(おほやけ)の御後見(うしろみ)をし、世をまつりごつべき人を思しめぐらすに、この源氏のかく沈み給ふ事いとあたらしうあるまじき事なれば、つひに后の御諫めを背きて、赦され給ふべき定め、出で来ぬ。去年(こぞ)より、后も御物の怪に悩み給ひ、さまざまの物のさと頻(しき)り、騒がしきを、いみじき御つつしみどもをし給ふしるしにや、よろしうおはしましける御目の悩みさへこのごろ重くならせ給ひて、もの心細く思されければ、七月(ふみづき)二十余日のほどに、また重ねて京へ帰り給ふべき宣旨下る。
つひの事と思ひしかど、世の常なきにつけても、「いかになり果つべきにか」と嘆き給ふを、かうにはかなれば、うれしきに添へても、また「この浦を今はと思ひ離れむ事」を思し嘆くに、入道、「さるべき事」と思ひながら、うち聞くより胸ふたがりて覚ゆれど、「思ひのごと栄え給はばこそは、わが思ひの叶ふにはあらめ」など思ひ直す。
その頃は夜離(よが)れなく語らひ給ふ。六月(みなづき)ばかりより心苦しき気色ありて悩みけり。かく別れ給ふべき程なれば、あやにくなるにやありけむ、ありしよりもあはれに思して、「あやしう物思ふべき身にもありけるかな」と思し乱る。女はさらにもいはず思ひ沈みたり。いと道理(ことわり)なりや。思ひの外に悲しき道に出で立ち給ひしかど、「遂には行きめぐり来なむ」と、かつは思し慰めき。この度はうれしき方の御出で立ちの、「またやは帰りみるべき」と思すに、あはれなり。
【現代語訳】
年が改まった。都では帝のご病気のことがあって、世間がさまざまに騒いでいる。今上帝の御子は、右大臣のむすめ、承香殿(じょうきょうでんの)女御の御腹に男御子がお生まれになったのがまだ二歳になられたばかりで、とても幼くていらっしゃる。将来は東宮に御位を譲り申し上げることは問題ないとしても、その場合に朝廷の御後見をして政を執り行う人をお求めになると、あの源氏の君が逆境に立たされていらっしゃるのはまことに惜しく不都合でもあるので、ついに帝は、大后(弘徽殿)のお諌めをも背いて、お許しになる評定を仰せ出される。去年から大后も御物の怪にお悩みになり、様々なお告げが多く、世の中が穏やかでなかったが、帝が厳重な物忌などをなさったおかげで、一時は少しよくなっていらした御目の病までも、最近はまた重くおなりで、もの心細く思われるので、七月二十日過ぎごろに、また重ねて京にご帰還なさるようにとの宣旨が下される。
源氏の君は、いつかはご赦免があるとは思っておられたが、世の無常につけても、最後にはどうなる運命であろうかと嘆いていらしたところ、こうまで急な仰せとなれば、嬉しいにつけても、一方ではこの明石の浦を今を限りと離れるのを悲しんでいらっしゃる。入道も当然のこととは思いながら、そう伺うと胸がつぶれる思いがするが、存分にお栄えになってこそ我が思いが叶うのであるなどと考え直す。
その頃は、夜な夜な欠かさず明石の君とお逢いになる。女君は六月あたりからただならぬ兆しがあって苦しんでいた。こんな具合にお別れせねばならない時であるので、かえって女君への執着が出てこられたのだろうか、前よりひとしお愛しくお思いになって、「不思議にも、私は物思いを尽くさねばならない身の上であることよ」と感慨深くなられる。
【PR】
↑ ページの先頭へ
澪標(みおつくし)
■明石の姫君誕生
まことや、かの明石に心苦しげなりし事は、「いかに」と思し忘るる時なければ、公私(おほやけわたくし)忙しき紛れに、え思(おぼ)すままにも訪(とぶら)ひ給はざりけるを、三月(やよひ)朔日(ついたち)の程、「この頃や」と思しやるに、人知れず、あはれにて、御使ありけり。とく帰り参りて、「十六日になむ。女にて、たひらかにものし給ふ」と告げ聞こゆ。めづらしきさまにてさへあなるを思すに、おろかならず。「などて、京に迎へてかかることをも、せさせざりけむ」と、口惜しう思さる。
宿曜(すくえう)に、「御子三人、帝、后、必ず並びて、生まれ給ふべし。中の劣りは、太政大臣(おほきおとど)にて、位を極むべし」と、勘(かむが)へ申したりしこと、さしてかなふなめり。おほかた上(かみ)なき位にのぼり、世を政(まつ)りごち給ふべきこと、さばかり賢かりしあまたの相人(さうにん)どもの聞こえ集めたるを、年頃は、世のわづらはしさにみな思し消(け)ちつるを、当帝(たうだい)の、かく位にかなひ給ひぬることを、思ひのごとうれしと思す。
自らは、もて離れ給へる筋は、「さらにあるまじき事」と思す。「あまたの御子たちの中にすぐれてらうたきものに思したりしかど、ただ人に思しおきてける御心を思ふに、宿世(すくせ)遠かりけり。内裏(うち)のかくておはしますを、「あらはに人の知る事ならねど、相人の言(こと)空しからず」と、御心の中(うち)に思しけり。今行く末のあらましごとを思すに、「住吉の神のしるべ、まことに、かの人も世になべてならぬ宿世にて、ひがひがしき親も、及びなき心をつかふにやありけむ。さるにては、かしこき筋にもなるべき人の、あやしき世界にて生まれたらむはいとほしう、かたじけなくもあるべきかな。この程過ぐして迎へてむ」と思して、東の院、急ぎ造らすべきよし、もよほし仰せ給ふ。
【現代語訳】
そういえば、あの明石でただならぬ様子になった明石の上はその後どうなったろうと、お忘れになる時がないのだが、公私ともお忙しいのに紛れて、思うままにお尋ねにもなれなかった。三月朔日ごろ、お産もこの頃かと遠く思いやると、人知れずいたたまれなくなって使者をお立てになった。じきに帰って来て、「十六日でございまして。女の御子で、ご安産でいらっしゃいます」と報告する。久しぶりの御子のご誕生である上に、珍しくも女君であるとお聞きになると、お喜びも一通りでない。「どうして、京に迎えてお産をさせなかったのか」と、残念にお思いになる。
いつぞや宿曜(占星術)の占いで、「御子は三人お生まれになります。一人は帝に、一人は后にお立ちになります。いちばん低い方は太政大臣として人臣の位を極めるでしょう」と予言されていたことが、そのまま叶うようである。大体、源氏の君が最上の位にのぼって世をお治めになるだろうとは、多くの賢かった相人たちがこぞって申していたことだが、ここ数年は世間が面倒なので心の中で打ち消していらしたのを、今上帝(冷泉帝)がこのようにご即位できたことを、源氏の君は思いが叶ったと嬉しくお思いになる。
ご自身は、帝の位につこうなどとは、決してあるまじきこととお思いである。「自分は、多くの御子たちの中でも格別に故院のご寵愛を蒙ったが、臣下の位に下すようお定めなさった叡慮を思うと、帝位には前世から縁の遠い身だったのだ。今上がこうして御位にあられることは、露わに人の知ることではないが、相人の予言は嘘ではなかったのだ」と御心の中にお思いになった。今から将来を予想してごらんになると、「住吉の神のお導きで、あの明石の人も世にまたとない宿世があり、それであの偏屈な父親も分不相応な望みを抱いたのだろうか。そうだとしたら、后の位にもつくべき人が見すぼらしい田舎で生まれたのは気の毒でもあり畏れ多いことよ。ぜひそのうちに都へお迎えしよう」とお思いになって、東の院の修繕を急ぐように仰せになる。
↑ ページの先頭へ
■紫の上の嫉妬
あやしきまで御心にかかり、ゆかしう思さる。女君には、言(こと)に表してをさをさ聞こえ給はぬを、「聞き合はせ給ふ事もこそ」と思して、「さこそあなれ。怪しうねぢけたるわざなりや。さもおはせなむと思ふあたりには心もとなくて、思ひの外(ほか)に口惜しくなむ。女にてさへあなれば、いとこそものしけれ。尋ね知らでもありぬべき事なれど、さはえ思ひ捨つまじきわざなりけり。呼びにやりて見せ奉らむ。憎み給ふなよ」と聞こえ給へば、面(おもて)うち赤みて、「怪しう、常にかやうなる筋(すぢ)宣ひつくる心の程こそ、我ながら疎ましけれ。物憎みはいつ習ふべきにか」と怨(ゑん)じ給へば、いとよくうち笑(ゑ)みて、「そよ、誰(た)が習はしにかあらむ。思はずにぞ見え給ふや。人の心より外(ほか)なる思ひやりごとして、もの怨(ゑ)じなどし給ふよ。思へば悲し」とて、果て果ては涙ぐみ給ふ。
年ごろ飽かず恋しと思ひ聞こえ給ひし御心の中(うち)ども、折々の御文の通ひなど思し出づるには、よろづの事すさびにこそあれと、思ひ消(け)たれ給ふ。「この人をかうまで思ひやり言(こと)とふは、なほ思ふやうの侍るぞ。まだきに聞こえば、またひが心得給ふべければ」と宣ひさして、「人柄のをかしかりしも、所がらにや、めづらしうおぼえきかし」など語り聞こえ給ふ。
【現代語訳】
源氏の君は、不思議なくらい小さなお姿に焦がれ給うて、早く会いたいとお思いになる。女君(紫の上)には、明石の上の件をはっきり口に出しておっしゃっていなかったので、「よそから耳に入ることがあっては」とご心配になり、「そのような次第で、妙にうまくいかないものだ。できてほしいと思う御方にはできそうもなくて、意外なところにできて、残念です。その上、女だそうだから、あまり楽しみもない。放っておいても構わないのだが、そういうわけにも行きかねます。いずれ呼び寄せてお見せしましょう。お憎みになりますな」と申されると、女君は顔をぱっと赤くして、「妙ですこと。いつもそのようなご注意をいただきます自分の性分が、我ながら嫌になります。他人を憎むということは、いつ身につくものでしょうか」と恨み言をおっしゃると、源氏の君はにっこりお笑いになり、「それ、それですよ。全く誰が教えるのだろう。あなたらしくないご様子をなさるものですよ。こちらの心にもないことを勝手に邪推なすって恨み言などおっしゃる。そう思うと悲しい」といって、最後には涙ぐまれる。
女君は、ここ数年、たまらなく恋しく思い申し上げたお互いの御心のうちや、折々のお手紙のやり取りなどを思い出されるにつけ、君の自分以外の女性とのことはすべて一時の戯れだったのだと、お恨みも自然とお消えになる。源氏の君は「あの人の身をここうまで案じて便りを送るのは、ほかに思うところがあるからなのです。今からそれをお話すれば、また誤解なさるかもしれないので」と仰せになって、「人柄がいいように思えたのも、田舎のせいで珍しく感じたのですね」などとお話しになる。
↑ ページの先頭へ
■住吉参詣
(一)
その秋、住吉に詣(まう)で給ふ。願どもはたし給ふべければ、いかめしき御歩(あり)きにて、世の中ゆすりて、上達部(かんだちめ)殿上人、我も我もと仕うまつり給ふ。
折しも、かの明石の人、年ごとの例の事にて詣づるを、去年(こぞ)今年は、さはる事ありて怠りけるかしこまり、取り重ねて思ひ立ちけり。舟にて詣でたり。岸にさし着くる程見れば、ののしりて詣で給ふ人の気配、渚に満ちて、いつくしき神宝(かむだから)を持て続けたり。楽人(がくにん)十列(とをつら)など、装束をととのへ、容貌(かたち)を選びたり。
「誰(た)が詣で給へるぞ」と問ふめれば、「内の大臣殿(おほいどの)の御願はたしに詣で給ふを、知らぬ人もありけり」とて、はかなき程の下衆(げす)だに心地よげにうち笑ふ。げにあさましう、月日もこそあれ、なかなかこの御有様をはるかに見るも、身のほど、口惜しう覚ゆ。さすがにかけ離れ奉らぬ宿世ながら、かく口惜しき際(きは)の者だに、もの思ひなげにて仕うまつるを、色節(いろふし)に思ひたるに、「何の罪深き身にて、心にかけておぼつかなう思ひ聞こえつつ、かかりける御響きをも知らで、立ち出でつらむ」など思ひつづくるに、いと悲しうて、人知れずしほたれけり。(中略)
【現代語訳】
その年の秋、源氏の大臣は住吉にご参詣になる。多くの願が叶えられなさったので、お供廻りの装いなども厳めしく、世間の大騒ぎになって、上達部や殿上人が我も我もとお供申し上げる。
そんな折も折、あの明石の人も、毎年の恒例として参詣していたのを、去年と今年は体に障ることができて怠っていたので、そのお詫びをかねて思い立ったのだった。舟でお参りするのである。岸に着いて見れば、盛んな行列の人々が渚に満ちて、立派な奉納品を捧げて続いている。楽人や十列の舞人などが装束を整えて、顔だちのすぐれたのを選んである。
「どなたがご参詣なさるのですか」と供人が尋ねると、「内大臣殿が御願を果たしにお参りになるのを、知らない人もあったのだな」と、取るに足らない下賤の者までも得意げに笑う。本当に呆れたことに、他に月日はいくらもあったのに、こんな日に来合わせて源氏の君の御有様をはるかに見るのも、身分の隔たりが実感されて残念に思われる。そうはいってもさすがに今は前世からの宿世で親しく結ばれたのだとはいっても、こういうつまらない身分の者でさえ満足そうに源氏の君にお仕え申すのを名誉に思っているのに、私はどんな因果な身で、いつも君のこと案じ申し上げていながら今日のご参詣のことをも知らずに出かけてきてしまったのだろう、などと思い続けると、たいそう悲しくなって、人知れず泣いてしまうのだった。
(二)
かの明石の舟、この響きにおされて、過ぎぬることも聞こゆれば、知らざりけるよ、とあはれに思す。神の御しるべを思し出づるもおろかならねば、「いささかなる消息をだにして心慰めばや。なかなかに思ふらむかし」と思す。
御社(みやしろ)立ち給ひて、所々に逍遥(せうえう)を尽くし給ふ。難波(なには)の御祓(はらへ)など、殊によそほしう仕(つか)まつる。堀江のわたりを御覧じて、「今はた同じ難波なる」と、御心にもあらでうち誦(ず)じ給へるを、御車のもと近き惟光(これみつ)、承りやしつらむ、「さる召しもや」と、例にならひて懐に設けたる柄(つか)短き筆など、御車とどむる所にて奉れり。「をかし」と思して、畳紙(たたうがみ)に、
みをつくし恋ふるしるしにここまでもめぐり逢ひけるえには深しな
とて賜へれば、かしこの心知れる下人(しもびと)してやりけり。駒(こま)並(な)めてうち過ぎ給ふにも、心のみ動くに、露ばかりなれど、いとあはれにかたじけなく覚えて、うち泣きぬ。
数ならでなにはのこともかひなきになどみをつくし思ひそめけむ
田蓑(たみの)の島に禊(みそぎ)仕うまつる御祓(はらへ)のものにつけて奉る。日暮れ方になりゆく。夕潮満ち来て、入江の鶴(たづ)も声惜しまぬほどのあはれなる折りからなればにや、人目もつつまずあひ見まほしくさへ思さる。
露けさのむかしに似たる旅ごろも田蓑の島の名にはかくれず
【現代語訳】
あの明石の舟が、この騒ぎに気圧されて参詣もせず立ち去ってしまったことも惟光が申し上げると、源氏の君は「少しも知らなかった」と不憫にお思いになる。この神の御導きで結ばれた契りがおろそかには思われないので、「せめて一言の便りだけも遣って心を慰めたい。なまなか行き合って、かえって悲しく思っているに違いない」とお思いになる。
住吉の御社をご出発になり、方々残らず遊覧にお立ち寄りになる。難波の御祓などは、格別立派にお勤めなさる。堀江のあたりをご覧になって「今はた同じ難波なる」と何気なくお口ずさみになるのを、御車の近くに控えている惟光が耳にしたのであろうか、このようなご用もあろうかと、いつものように懐に準備していた柄の短い筆などを、御車が停まったた所で差し上げた。惟光の気が利くのに感心なさって、畳紙に、
身を尽くして恋しく思う甲斐があって、澪標のあるこの難波まで来て巡り会った。私たち宿縁は深いのだな。
と書いてお与えになったので、明石方の事情に通じている下人に命じて届けさせた。女君は、源氏の君一行が馬を並べて通って行かれるのを拝して心が乱れるばかりだったのに、ほんの一言とはいえ、こうして文をいただけることは嬉しく勿体ないことに思えて、涙がこぼれた。
物の数にも入らない、何事もあきらめている私なのに、どうして身を尽くして君を思い始めてしまったのでしょう。
田蓑の島で禊をお勤めをし、その御祓に使うための木綿(ゆう)につけてこの歌を差し上げる。日も暮れ方になるにつれ、夕潮が満ちてきて、入江の鶴も声を惜しまず鳴き渡る景色など、情緒のある折のせいか、源氏の君は人目もはばからず逢って語りたいとさえお思いになる。
明石の海辺をさすらったあの頃のように私の旅衣は涙で濡れている、田蓑の島というのにその蓑にも隠れることができずに。
(注)「今はた同じ難波なる」・・・「わびぬれば今はた同じなるみをつくしても逢はむとぞ思ふ」(拾遺集)
【PR】
↑ ページの先頭へ
蓬生(よもぎう)
■源氏、末摘花邸を通りかかる
卯月(うづき)ばかりに、花散里(はなちるさと)を思ひ出で聞こえ給ひて、忍びて、対(たい)の上に御暇(いとま)聞こえて出で給ふ。日ごろ降りつる名残の雨少しそそきて、をかしき程に月さし出でたり。昔の御歩(あり)き思し出でられて、艶(えん)なる程の夕月夜(ゆふづくよ)に、道のほどよろづの事思し出でておはするに、形もなく荒れたる家の、木立茂く森のやうなるを過ぎ給ふ。
大きなる松に藤の咲きかかりて、月影になよびたる、風につきてさと匂ふがなつかしく、そこはかとなき香りなり。橘(たちばな)にはかはりてをかしければ、さし出で給へるに、柳もいたうしだりて、築地(ついひぢ)もさはらねば、乱れ伏したり。「見し心地する木立かな」と思すは、はやうこの宮なりけり。いとあはれにて押しとどめさせ給ふ。例の、惟光はかかる御忍び歩きに後(おく)れねば、さぶらひけり。召し寄せて、「ここは常陸(ひたち)の宮ぞかしな」「しか侍り」と聞こゆ。「ここにありし人は、まだやながむらむ。とぶらぶべきを、わざとものせむも所(ところ)狭(せ)し。かかるついでに入りて消息(せうそこ)せよ。よく尋ね寄りてを、うち出でよ。人違(たが)へしてはをこならむ」と宣ふ。
【現代語訳】
四月の頃、源氏の君は花散里のことを思い出されて、紫の上にお暇を申しあげてこっそりお出になる。ここ何日か降り続いていた名残の雨が少しぱらついて、やがて風情のある空に月が上がった。昔のお忍び歩きを思い出されて、優艶な夕月夜に、道中さまざまな回想に耽りながらたどっていらっしゃると、見るかげもなく荒れた家の周囲に木立が茂って森のようになった所をお通り過ぎになる。
大きな松に藤の花が咲きかかり、月の光になよなよと揺れている。風に吹かれて時々さっと匂ってくるのが懐かしく、ほんのりとした香りである。橘の花とは違ってまた趣があるので、御車から顔を出してご覧になると、柳の枝が長く垂れて、築地が邪魔にならないよう都合よく崩れている上に乱れかかっている。「何だか見覚えのある木立だ」とお思いになるのもそのはずで、ここは常陸宮のお邸なのであった。たいそうあわれを催しになって、御車をお停めになる。例の惟光はこのような御忍び歩きに漏れることはなかったので、今日もお付き添い申していた。お召しになり、「ここは常陸宮の邸であったな」「さようでございます」と申し上げる。源氏の君は「ここにいた人は、まだ所在なく暮していようか。訪ねてやるべきだが、わざわざ来るのも大そうであるから、この機会に入って案内を請うてみよ。よく確かめて口を聞くようにせよ。人違いをしては笑い草になろうから」とおっしゃる。
↑ ページの先頭へ
■末摘花邸に入る
「などかいと久しかりつる。いかにぞ。昔の跡も見えぬ蓬(よもぎ)の繁さかな」と宣へば、「しかじかなむたどり寄りて侍りつる。侍従が叔母の少将と言ひ侍りし老人(おいびと)なむ、変らぬ声にて侍りつる」と、有様聞こゆ。いみじうあはれに、「かかる繁き中に、何(なに)心地して過ぐし給ふらむ。今までとはざりけるよ」と、わが御心の情なさも思し知らる。「いかがすべき。かかる忍び歩(あり)きも難(かた)かるべきを。かかるついでならではえ立ち寄らじ。変はらぬ有様ならば、げにさこそはあらめと推しからるる人ざまになむ」とは宣ひながら、ふと入り給はむこと、なほつつましう思さる。
ゆゑある御消息(せうそこ)もいと聞こえまほしけれど、見給ひしほどの口遅さもまだ変はらずは、御使ひの立ちわづらはむもいとほしう、思しとどめつ。惟光も、「さらにえ分けさせ給ふまじき蓬の露けさになむ侍る。露少し払はせてなむ、入らせ給ふべき」と聞こゆれば、
たづねてもわれこそとはめ道もなく深きよもぎのもとのこころを
と独りごちて、なほ降り給へば、御さきの露を、馬(むま)の鞭(むち)して払ひつつ入れ奉る。雨(あま)そそきも、なほ秋の時雨めきてうちそそけば、「御傘(みかさ)さぶらふ。げに木の下露は、雨にまさりて」と聞こゆ。御指貫の裾は、いたうそぼちぬめり。昔だにあるかなきかなりし中門など、まして形もなくなりて、入り給ふにつけても、いと無徳(むとく)なるを、立ちまじり見る人なきぞ心安かりける。
姫君は、さりとも、と待ち過ぐし給へる心もしるく、うれしけれど、いと恥づかしき御有様にて対面せむもいとつつましく思したり。大弐の北の方の奉りおきし御衣(ぞ)どもをも、心ゆかず思されしゆかりに、見入れ給はざりけるを、この人々の香(かう)の御唐櫃(からびつ)に入れたりけるが、いとなつかしき香(か)したるを奉りければ、いかがはせむに、着換へ給ひて、かの煤(すす)けたる御几帳引き寄せておはす。
【現代語訳】
源氏の君が、「たいそう時間がかかったではないか。どうだった。昔の面影もないほどの蓬の茂りようだが」とおっしゃるので、惟光は「これこれの次第で、探って参りました。侍従の叔母で少将と言いました老女房が、昔と変わらぬ声でございました」と、その様子を申し上げる。源氏の君はたいそう不憫にお思いになって、「このような草深い中にどんな気持ちで過ごしておいでか。今まで訪れもしなかったとは」と、ご自身の薄情さを自覚なさる。「どうしたものか。このような忍び歩きも難しいだろうし、こんな機会でないと立ち寄ることはできまい。姫君が以前と変わらないならば、なるほどさもありそうなお人柄であるよ」とおっしゃりながらも、なおためらっていらっしゃる。
まず趣のある御消息でも差し上げたいが、あの頃の姫君の口重さもまだ変わっていなければ、お使いの者が待ちくたびれるのも気の毒なので、それもお止めになった。惟光も「とてもお入りになれそうにない蓬の露の多さでございます。露を少し払わせてからお入りなさいませ」と申し上げると、源氏の君は、
探り尋ねてこちらからお見舞いしよう。人の通う道もないほど深く茂った蓬の宿の、昔のままの姫君の心を。
と独り言をおっしゃって、やはり車からお降りになったので、惟光は、お足元の露を馬の鞭で払いつつご案内申し上げる。雨の雫も秋の時雨めいて木々の枝から降り注ぐので、惟光は「お傘がございます。なるほど木の下露は雨にももまさるものでございまして」と申し上げる。御指貫の裾がひどく濡れてしまったようだ。以前でさえあるかないかのように見えた中門などは、まして今は形もなくなっていて、お入りになるのに何の役にも立たないのだが、このような所を見る人のないのが気楽なことであった。
姫君は、いつかはお見えになろうと待ち過ごしていらっしゃった甲斐があったのが嬉しいものの、ひどく恥ずかしい身なりで対面するのも気がひけるとお思いになる。大弐の北の方が置いて行った多くの御召し物を、気に食わない人の進物だからと見向きもなさらずにいたのを、お側の人々が香を収める御唐櫃に入れていたのが、とても懐かしい香がしているので、取り出してお着せすると、仕方なくお召し替えになって、あのすすけた御几帳を引き寄せてお座りになる。
↑ ページの先頭へ
■末摘花の生活を援助
祭、御禊(ごけい)などの程、御いそぎどもにことつけて、人の奉りたる物いろいろに多かるを、さるべき限り御心加へ給ふ。中にもこの宮には、こまやかに思しよりて、睦まじき人々に仰せ言賜ひ、下部(しもべ)どもなど遣はして、蓬(よもぎ)払はせ、めぐりの見苦しきに、板垣といふものうち堅め繕はせ給ふ。かうたづね出で給へりと聞き伝へむにつけても、わが御ため面目なければ、渡り給ふことはなし。御文いとこまやかに書き給ひて、二条院いと近き所を造らせ給ふを、「そこになむ、渡し奉るべき。よろしき童(わらはべ)など、求めさぶらはせ給へ」など、人々の上まで思しやりつつ、とぶらひ聞こえ給へば、かくあやしき蓬のもとには置き所なきまで、女ばらも空を仰ぎてなむ、そなたに向きて喜び聞こえける。
なげの御すさびにても、おしなべたる世の常の人をば目とどめ耳たて給はず、世に少しこれはと思ほえ、心地にとまるふしあるあたりを尋ね寄り給ふものと人の知りたるに、かくひき違(たが)へ、何事もなのめにだにあらぬ御有様をものめかし出で給ふは、いかなりける御心にかありけむ。これも昔の契りなめりかし。
今は限りとあなづり果てて、さまざまに競(きほ)ひ散りあかれし上下(うへしも)の人々、我も我も参らむと争ひ出づる人もあり。心ばへなど、はた、埋(うも)れいたきまでよくおはする御有様に、心やすくならひて、殊なることなきなま受領(ずりやう)などやうの家にある人は、習はずはしたなき心地するもありて、うちつけの心みえに参り帰る。
君は、いにしへにもまさりたる御勢(いきほひ)の程にて、物の思ひやりもまして添ひ給ひにければ、こまやかに思しおきてたるに、匂ひ出でて、宮の内やうやう人目見え、木草の葉もただすごくあはれに見えなされしを、遣水(やりみづ)かき払ひ、前栽(せんざい)の本立ちも涼しうしなしなどして、ことなる覚えなき下家司(しもげいし)の、ことに仕へまほしきは、かく御心とどめて思さるることなめり、と見取りて、御気色給はりつつ、追従(ついしよう)し仕うまつる。
二年(ふたとせ)ばかりこの古宮(ふるみや)にながめ給ひて、東の院といふ所になむ、後は渡し奉り給ひける。対面し給ふことなどは、いと難けれど、近き標(しめ)のほどにて、おほかたにも渡り給ふに、さしのぞきなどし給ひつつ、いとあなづらはしげにもてなし聞こえ給はず。
【現代語訳】
賀茂祭や斎院の御禊などがある季節なので、その準備などにことよせて人々が献上した品物がいろいろと多くあり、しかるべき婦人方に御心をこめてお贈りになる。中でもこの常陸宮邸にはこまごまと御心遣いをなさって、親しい家臣たちにお命じになり、下人たちなどを遣わして蓬を払わせ、見苦しかった邸の周囲に板垣を造って修繕をおさせになる。しかし、このように常陸宮の姫君(末摘花)を探し出されたと世間が噂するのは、ご自分としても不名誉なので、お渡りになることはない。お手紙を情こまやかにお書きになり、二条院のごく近くに建物をお造らせになって「そこにお移し申しましょう。適当な童たちなどを捜してお使いなさいませ」など、召使いのことまでお心遣いなさってお世話下さるので、こんな見すぼらしい蓬の家には喜びの置きどころもない程に、女房たちも空を仰ぎ、二条院の方に向いてお礼を申し上げる。
源氏の君は、かりそめの御遊びであっても、ありふれた普通の女には見向きもなさらず、多少なりともこれはと思われ、心にとまるところがあるような女にお近づきになるものと皆は思っているのに、それとは違って、何ごとも並の人にさえ及ばない姫君を一人前のお方らしくお扱いになるのはどういう御心なのだろう、これも前世からのお約束事であろうか。
姫君のことを、もう先が見えたと見切りをつけて、先を争うように逃げ散っていった上下の召使いたちの中には、我も我もと争って戻ってこようとする者もある。姫君のご気性は底知れぬほどによくできていらっしゃるお方ゆえ、つまらぬ受領などの家に鞍替えしていた人たちは、それまで経験したことのない居心地の悪さもあって、掌を反すような態度で戻って来る。
源氏の君は以前にもまさる御威勢で、人に対する思いやりも前より深くなられ、行き届いたお指図をなさったので、常陸宮邸は活気が出て、邸内はしだいに人の出入りが多くなり、木や草の葉も荒れ放題だったのを、遣り水の流れをよくし、植込みの下草もさっぱり手入れしたりして、特に目をかけてもらえない下家司で何とかしかるべき御方にお仕えしたいと思う者は、このように源氏の君の姫君へのお心こめてのご寵愛だと見て取って、姫君のご機嫌をうかがったりお追従を述べたりしてお仕え申し上げる。
二年ほどこの古い宮邸にお住まいでいらっしゃったが、後には東の院という所へ移してお上げになった。直接お逢いになることなどは滅多になかったが、二条院に近い構えの内なので、何かの用事でお出でになる時はちょっとお覗きになったりして、そう軽んじたお取り扱いはなさらない。
【PR】
↑ ページの先頭へ
関屋(せきや)
■空蝉、源氏一行と行き合う
(一)
伊予介(いよのすけ)と言ひしは、故院かくれさせ給ひてまたの年、常陸(ひたち)になりて下りしかば、かの帚木(ははきぎ)もいざなはれにけり。須磨の御旅居もはるかに聞きて、人知れず思ひやり聞こえぬにしもあらざりしかど、伝へ聞こゆべきよすがだになくて、筑波嶺(つくばね)の山を吹き越す風も浮きたる心地して、いささかの伝へだになくて、年月重なりにけり。限れる事もなかりし御旅居なれど、京に帰り住み給ひて、またの年の秋ぞ、常陸は上りける。
関(せき)入る日しも、この殿、石山に御願(ぐわん)はたしに詣(まう)で給ひけり。京より、かの紀伊守(きのかみ)など言ひし子ども、迎へに来たる人々、「この殿かく詣で給ふべし」と告げければ、「道のほど騒がしかりなむものぞ」とて、まだ暁(あかつき)より急ぎけるを、女車多く、所せうゆるぎ来るに、日たけぬ。
打出(うちいで)の浜来るほどに、「殿は粟田山(あはたやま)越え給ひぬ」とて、御前の人々、道も避(さ)りあへず来こみぬれば、関山にみな下(お)りゐて、ここかしこの杉の下に車どもかきおろし、木隠(こがく)れに居かしこまりて過ぐし奉る。車など、かたへは後(おく)らかし、前(さき)に立てなどしたれど、なほ類(るい)ひろく見ゆ。車、十(とを)ばかりぞ、袖口、物の色あひなども漏り出でて見えたる、田舎びず由ありて、斎宮の御下り、何ぞやうの折りの物見車思し出でらる。殿もかく世に栄え出で給ふ珍しさに、数もなき御前ども、みな目とどめたり。
【現代語訳】
伊予介(空蝉の夫)であった人は、故院がお隠れになった翌年、常陸介になって任国に下ったので、あの箒木(空蝉)も伴われて一緒に下っていた。源氏の君が須磨で詫び住まいされていることも遥か遠国で聞いて、人知れずお偲び申し上げないではなかったが、心のうちをお伝え申す手立てもなく、筑波山を吹き越す風にことづてを頼むのも不確かな心地がして、全く何の音信もないまま年月が重なっていった。いつまでと限られていた侘住まいではなかったが、京にお帰りになって翌年の秋に、常陸介も帰京したのだった。
常陸介一行がちょうど逢坂の関に入ろうというその日に、源氏の君はご祈願成就のお礼に石山寺に参詣なさった。京からあの紀伊守などいう息子たちやそのほか迎えに来た人々が、源氏の君ご参詣の由を告げたので、きっと道中騒がしくなるだろうと、まだ暁のうちに急いだが、女車が多くて道をいっぱいに塞いでゆっくり進むので、昼になってしまった。
打出の浜を通る頃に、「殿は粟田山をお越えになった」と触れながら、前駆の人々が道も避けられないほど大勢入り込んできたので、関山で皆車から降りて、あちこちの杉の下に多くの車を引き入れ、木隠れに座り畏まって、源氏の君の御行列をお通し申し上げる。一行の車の一部は後ろにし、一部は先に立たせなどしているが、それでもやはり人数は多い感じである。今も十台ほどの車から女房たちの袖口や衣の色などもこぼれ出でて見えるのが、田舎びず趣きがあって、斎宮の御下向か何かの折の物見車が思い出される。源氏の君がかように世に栄えていらっしゃるので、数知れないお供が付き随っているが、先駆の者たちが皆この女車に目をとめている。
(二)
九月(ながつき)晦日(つごもり)なれば、紅葉(もみぢ)の色々こきまぜ、霜枯(しもがれ)の草むらむら、をかしう見えわたるに、関屋よりさとくづれ出でたる旅姿どもの、いろいろの襖(あを)のつきづきしき縫ひ物、括(くく)り染めのさまも、さる方にをかしう見ゆ。御車は簾(すだれ)おろし給ひて、かの昔の小君、今は右衛門佐(うゑもんのすけ)なるを召し寄せて、「今日の御関迎へは、え思ひ棄て給はじ」など宣ふ御心の中(うち)、いとあはれに思し出づる事多かれど、おほぞうにてかひなし。女も、人知れず昔のこと忘れねば、とり返してものあはれなり。
「行くと来(く)とせきとめがたき涙をや絶えぬ清水と人は見るらむ
え知りたまはじかし」と思ふに、いとかひなし。
石山より出で給ふ御迎へに、右衛門佐参れり。一日(ひとひ)まかり過ぎし畏(かしこま)りなど申す。昔、童にていと睦まじうらうたきものにし給ひしかば、かうぶりなど得しまで、この御徳に隠れたりしを、おぼえぬ世の騒ぎありし頃、物の聞こえに憚(はばか)りて常陸に下りしをぞ、少し心おきて年頃は思しけれど、色にも出(い)だし給はず。昔のやうにこそあらねど、なほ親しき家人(いへびと)の中(うち)には数へ給ひけり。
【現代語訳】
九月の末なので、紅葉がさまざまな色にまじりあい、霜枯の草が濃く薄く一面に見渡せるところに、関屋からさっと現れ出てきた源氏の行列の旅装束の色とりどりの狩衣が、それぞれにふさわしい刺繍やしぼり染めを施し、場所柄いかにも風情あるものに見える。源氏の君の御車は簾をお下ろしになって、あの昔の小君(空蝉の弟)が今は右衛門佐になっているのをお召しになり、「今日はわざわざ逢坂関までお迎えに参ったが、私のこの志をおろそかには思われますまい」などとお伝えになる。御心の中にたいそうしみじみと思い出されることが多いけれども、ありきたりの言付けしかできず、なすすべのないことである。女(空蝉)も、人知れず昔のことを忘れず思い出して、しみじみと胸を打たれる。
(空蝉)行く時も帰ってくる時も、せきとめることができない涙を、人は絶えず流れる関の清水だと見るでしょう。
心の中で詠んだだけなので、この気持を源氏の君はご存じになるはずもないと思うと、ひどく甲斐のないことである。
石山からお立ちになる折、右衛門佐がお迎えに参った。このほどお供もせずに行き過ぎてしまったお詫びなどを申し上げる。昔、童であった頃にはたいそう親しく可愛がっていらしたので、五位に叙爵するまで君のお蔭を蒙っていたのに、あの思いもせぬ世の騒ぎがあった時に、世間への聞こえを憚って常陸に下ったので、それからは少しお心に隔てがおありになっておられたが、そんなことは素振りにもお出しにならない。昔のようにとまではいかないが、それでもやはり親しい家人の中には入れていらっしゃった。
↑ ページの先頭へ
■空蝉、夫と死別、出家
かかる程に、この常陸守(ひたちのかみ)、老いの積もりにや、悩ましくのみして、もの心細かりければ、子どもに、ただこの君の御事をのみ言ひおきて、「よろづの事、ただこの御心にのみ任せて、ありつる世に変らで仕うまつれ」とのみ、明け暮れ言ひけり。女君、「心憂き宿世(すくせ)ありて、この人にさへ後れて、いかなるさまにはふれ惑ふべきにかあらむ」と思ひ嘆き給ふを見るに、命の限りあるものなれば、惜しみとどむべき方もなし。「いかでか、この人の御ために残し置く魂もがな。わが子どもの心も知らぬを」と、うしろめたう悲しきことに言ひ思へど、心にえとどめぬものにて、亡(う)せぬ。
しばしこそ、「さ宣ひしものを」など情けづくれど、うはべこそあれ、つらき事多かり。とあるもかかるも世の道理(ことわり)なれば、身一つの憂きことにて嘆き明かし暮らす。ただ、この河内守(かうちのかみ)のみぞ、昔より好き心ありて少し情けがりける。「あはれに宣ひおきし、数ならずとも、思し疎(うと)まで宣はせよ」など、追従(ついそう)し寄りて、いとあさましき心の見えければ、「憂き宿世ある身にて、かく生きとまりて、はてはては珍しき事どもを聞き添ふるかなと、人知れず思ひ知りて、人にさなむとも知らせで、尼になりにけり。
ある人々、いふかひなしと思ひ嘆く。守(かみ)もいとつらう、「おのれを厭(いと)ひ給ふほどに、残りの御齢(よはひ)は多くものし給ふらむ、いかでか過ぐし給ふべき」などぞ。「あいなのさかしらや」などぞ侍るめる。
【現代語訳】
こうした間に、常陸守は老いが重なったせいか、病気がちで心細くなってきたので、息子たちにただこの女君(空蝉)の後々ことを言い残して、「何事もこの方の好きなようにさせてあげて、私が生きていた時と変わらずお仕え申せ」とばかり、明けても暮れても言っていた。女君が「とかく苦労の多い宿世で、この夫にまで先立たれては末はどんなに落ちぶれるだろうか」と思い悩まれるのを見ながら、命には限りがあり、どんなに惜しんでもとどまる方法がなく、「何とかこの人のために我が魂を残して行けないものか、子供たちの心は将来どうなるかわからないし」と、気がかりで悲しく思っていたが、ままならないまま、ついに亡くなった。
しばらくの間こそ、息子らは「父君がああおっしゃったのだから」と、女君に対して情け深くふるまっていたが、それは表面だけで、心ない仕打ちが多かった。女君は、それもこの世の道理だとして、我が身一つの不運として嘆きながら暮していた。ただ、この河内守だけは、昔から思いをかけていて、少し親切なそぶりを見せるのだった。「父君がご遺言なさったことですから、私のような物の数でない者でも、心隔てをなさらず何でもおっしゃってください」などとへつらい寄って、浅ましい下心が見えたので、女君は「辛い宿世の身の上でこうして生き残って、最後にはとんでもないことまでも聞かされることだ」と、人知れず決心して、誰にも知らせずに尼になってしまった。
仕えていた女房たちは、情けないことなってしまったと思い嘆く。河内守もたいそう辛がって、「私をお嫌いになってのことだとしても、残りの御寿命は長くていらっしゃるのに、どうやって暮らしていかれるのだろう」などと言っていた。いらぬ世話だ、などと人々の評判であるようだ。
【PR】
↑ ページの先頭へ
絵合(えあわせ)
■帝の御前での絵合
召しありて、内大臣(うちのおとど)権中納言参り給ふ。その日、帥(そち)の宮も参り給へり。いとよしありておはするうちに、絵を好み給へば、大臣の下にすすめ給へるやうやあらむ、ことごとしき召しにはあらで、殿上におはするを、仰せ言ありて、御前に参り給ふ。この判(はん)仕うまつり給ふ。いみじうげに描きつくしたる絵どもあり。さらにえ定めやり給はず。(中略)
定めかねて夜に入りぬ。左はなほ数ひとつあるはてに、須磨の巻出で来たるに、中納言の御心騒ぎにけり。あなたにも心して、はての巻は心ことにすぐれたるを選(え)りおき給へるに、かかるいみじき物の上手の、心の限り思ひ澄まして静かに描き給へるは、たとふべき方なし。親王(みこ)よりはじめ奉りて、涙とどめ給はず。その世に、心苦し悲しと思ほしし程よりも、おはしけむありさま、御心に思しけむ事ども、ただ今のやうに見え、所のさま、おぼつかなき浦々磯の隠れなく描きあらはし給へり。草(さう)の手に仮名の所々に書きまぜて、まほのくはしき日記(にき)にはあらず、あはれなる歌などもまじれる、たぐひゆかしく、誰も他(こと)ごと思ほさず、さまざまの御絵の興、これに皆移りはてて、あはれにおもしろし。よろづ皆おしゆづりて、左勝つになりぬ。
【現代語訳】
帝のお召しがあって、内大臣(源氏)と権中納言(頭中将)が参内される。その日は帥の宮も参内なさった。趣味がお広い中でも、とくに絵を好まれるので、源氏の大臣が内々にお勧めになったのであろうか、わざわざのお召しではなく、殿上の間に居合わせらしたのを、帝からの仰せがあって御前へ参られて、この絵合の判者をお勤めになる。どれも見事で技巧の限りを尽くした絵が多く、帥の宮もまったく優劣の判定がおできにならない。(中略)
勝負が決しないまま夜になった。左方の斎宮女房方から、まだ番数がひとつ残っているという最後になって須磨の巻が出てきたので、権中納言のお心は動揺した。右の方でも心して最後の巻は格別に優秀な絵を選び残しておられたのに、こんな見事な名手が心ゆくまで思いすまして静かにお描きになったものは、たとえようもない。帥の宮をはじめ、どなたも感涙をおとどめにならない。あの当時、須磨に下向した源氏の君のことを、都の人々がお気の毒だ、悲しいとお思いになったよりも、さらに侘しいお暮らしのご様子やお気持ちなどが眼前のことのように見え、その地の景色や名も知れぬ浦々や磯の様子を漏れなく描き表していらっしゃる。草体の漢字に仮名を所々に書きまぜてあって、正式の詳しい日記(漢文)というのではなく、あわれな歌なども書き入れてあり、この残りの巻々も見たくてたまらず、もう誰も他の絵のことはお思いにならない。それまでのいろいろな絵に対する興味もこの絵日記に皆移ってしまうほどの面白さである。全部がこれに奪われて、左の勝ちになった。
(注)現代語訳は、現代文としての不自然さをなくすため、必ずしも直訳ではない箇所があります。
 |
古典に親しむ
万葉集・竹取物語・枕草子などの原文と現代語訳。 |
バナースペース
【PR】
「明石」のあらすじ
(藤壺 32~33歳)
(紫の上 19~20歳)
(明石の上 18~19歳)
風雨は一向に止まず数日を経過、源氏の閑居の一部が落雷にあって炎上した。その夜、源氏のうたたねの夢に故桐壺院があらわれ、住吉の神の導くままに早くこの浦を去れ、とお告げになった。翌朝、これもまた夢のお告げだと称して、明石から明石入道が舟を用意して迎えに来ていた。夢の内容が一致するので、不思議な縁に導かれるまま、源氏は明石の浦に移った。明石は須磨と比べ、はなやかな感じの所である。
明石入道は、かねがね一人娘(明石の上)の婿に源氏をと願っており、娘の話を切り出す。源氏は入道の人柄に好感を持ち、やがて源氏はこの娘と消息(手紙)を交わすようになった。そして8月13日の月夜、源氏を岡辺の宿に迎え、二人は結ばれた。娘は心高い性質の女であり、当初は身分差を憚り、打ち解けようとしなかったが、次第に心を開き、二人の仲は深まっていった。しかし、源氏は人目を憚り、このような時でも紫の上のことを思い出して、足繫くは通わない。明石の上は煩悶する。
あの暴風雨は都でも続いた。ある日、帝の夢に故桐壺院が現れ、帝を睨みつけながら源氏を追いやったことを叱責した。その後、帝は眼を病まれ、母の大后も病気がちになった。帝は、源氏を苦しめた報いに違いないと考え、大后の強い反対を押し切って、7月、源氏召還の宣旨を下された。源氏の家臣らはみな喜んだが、入道は涙がちに日を過ごす。源氏は、懐妊中の明石の上を残して帰京し、8月15日夜、久しぶりに参内した。そして、員外の権大納言となり政界中央に返り咲いた。
※巻名の「明石」は、源氏が須磨から 明石に移ったことによっている。
「澪標」のあらすじ
(冷泉帝 10~11歳)
(紫の上 20~21歳)
(明石の上 19~20歳)
(六条御息所 35~36歳前)
(秋好中宮 19~20歳)
帰京した源氏は、久しぶりに兄の帝としみじみ語り合って心を通わせる。そして、政権の座を固めるために様々な布石を打っていく。源氏は、故桐壺院の菩提を弔うために法華八講を営んだ。帝はご病気が重く、翌春、11歳の東宮に譲位され、冷泉帝(故桐壺院の子、実は源氏の子)が即位された。源氏は内大臣に、致仕の左大臣(葵の上の父)は太政大臣に昇進、源氏方に再び春がめぐってきた。また、頭中将は権中納言となった。
3月、明石の上は女の子(明石の姫君)を産んだ。源氏はしかるべき女を選んで乳母として明石へ遣わし、五十日の祝いにはさまざまな品を贈った。紫の上にはこのことは知らせてあったが、明石からの文を見ている源氏を、紫の上は横目に睨む。秋、明石の上は住吉明神に詣でる源氏一行と会ったが、その行列の盛大さに身分の隔たりを強く感じ、源氏に会わずに明石に帰った。このことを聞き知った源氏は、消息を送って慰め、姫君とともに上京するよう勧めた。
六条御息所は、娘の前斎宮(のちの秋好中宮:あきこのむちゅうぐう)とともに伊勢から帰京したが、重い病にかかり、娘の行く末を源氏に託して世を去った。源氏は、この婦人との過去の悲しい関係に思いを馳せ、せめて残された姫君を十分に後見しようと決心、朱雀院がこの姫君を懇望するのをしりぞけ、自分の養女とした。そして、冷泉帝に入内させようと、藤壺の女院に諮った。
※巻名の「澪標」は、源氏と明石の上との贈答歌が由来となっている。源氏「みをつくし恋ふるしるしにここまでもめぐり逢ひける縁は深しな」。明石の上「数ならで難波のこともかひなきになどみをつくし思ひそめけむ」。澪標は、船に水路を知らせるために立てた杭。

「蓬生」のあらすじ
(末摘花 年齢不明)
源氏が須磨・明石に退居していた間、援助を失った末摘花(すえつむはな)のわび住まいはますます困窮をきわめた。邸内は荒廃して狐狸の住処となり、侍女たちは次々に去り、受領の妻である叔母は、末摘花を自分の娘たちの召使いにしようと企てた。言うことを聞こうとしない末摘花に嫌味を言い、乳母子を彼女から引き離した。しかし、末摘花は苦しさに堪え、源氏との再会を信じていた。
須磨から帰京した源氏は末摘花のことは忘れていた。ある日、源氏が花散里(はなちるさと)を訪ねる途中、偶然に末摘花邸を見つけて思い出し、立ち寄って末摘花と再会した。そして、邸の荒廃や貧窮に同情するとともに、我がつれない仕打ちを悔いて、生活を援助し、邸を修理した。そして2年後、二条院に引き取った。彼女の願いは、彼女の真心によって実現した。
※巻名の「蓬生」は、末摘花の邸の荒廃を表す雑草の蓬が由来となっている。この巻と続く「関屋」の巻は 、いわゆる「横並びの巻」であり、同じ年、すなわち源氏28歳秋から29歳にかけての話である。

「関屋」のあらすじ
(空蝉 年齢不明)
(右衛門の佐 24,25歳)
9月末、源氏の一行が石山詣でに出かけた帰り、逢坂(おうさか)の関を通っていると、東(あずま)に下っていた常陸介(ひたちのすけ)が任期を終え、妻の空蝉(うつせみ)をつれて京に戻るのに出会った。源氏は空蝉のことをしみじみと思い出し、弟の右衛門佐(うもんのすけ:昔の小君)を召して空蝉にことづてをした。小君はかつて源氏に仕えていたが、源氏が須磨に下る際、それには従わず常陸国へ下っていたのだった。
源氏と出会った空蝉の心は再び揺れ動くが、その関係が進展することはなかった。その後、夫の常陸介が老病となり、子どもたちに空蝉のことを頼みおいて亡くなった。しかし、継子である子どもたちが示した彼女への情はうわべだけであり、中でも河内守(かわちのかみ)はあからさまに言い寄ってきた。空蝉は世をはかなんで出家した。周りの女房たちは、「まだ若いのに・・・」と嘆く。ただし、のちに源氏によって二条東院に引き取られることになる。
※巻名の「関屋」は、空蝉と源氏が偶然出会った逢坂の関所の館(関屋)によっている。
京都と滋賀の境にある逢坂の関は、平安時代の鈴鹿と不破とともに「三関(さんかん)」と呼ばれ、東国と畿内を隔てる三つの関の一つ。その呼称から、「逢坂」の地名と「逢ふ」をかけて出会いと別れの場所として古くから歌に詠まれてきた。
「絵合」のあらすじ
(朱雀院 34歳)
(藤壺 36歳)
(冷泉帝 13歳)
(梅壺女御 22歳)
(弘徽殿女御 14歳)
(紫の上 23歳)
亡き六条御息所の娘である前斎宮(さきのさいぐう)は、源氏の養女となり、さらに冷泉帝に入内し、梅壺に局(つぼね)を賜わった。以前から彼女を思う朱雀院は大いに落胆したが、入内の日にはさまざまな贈り物を贈った。源氏は院の胸中を思うと心を痛めた。冷泉帝は絵がお好きであった。梅壺も絵が巧みだったので、おのずから帝の愛情は、先に入内していた弘徽殿女御(頭中将の娘。朱雀帝の母・弘徽殿大后とは別人)から梅壺の方へ移っていった。そのことを知った負けず嫌いの権中納言(もとの頭中将)は、物語絵を弘徽殿に贈り、源氏もまた由緒ある絵を梅壺に贈った。
こうして後宮に絵論議の熱が高まり、3月、中宮の御前で左右に分かれての「絵合(えあわせ)」が催された。梅壺方と弘徽殿方の勝負はなかなかつかず、決着は後日の冷泉帝の御前に持ち越され、最後に源氏の「須磨の絵日記」が出るに及んで、皆が感動して梅壺方の勝ちとなった。ただしこの勝利は、源氏の苦しい日々を記した絵日記を誰も批判できないのを見越した上での作戦だった。
その夜、源氏は弟の蛍兵部卿宮(ほたるひょうぶきょうのみや:故桐壺院の息子)と、学問・絵画・書道について論じた。源氏は身の栄華につけても世の無常を思い、ひそかに出家を志し、山里に御堂を建てたいと考えた。
※巻名の「絵合」は、宮中で行われた行事「絵合」によっている。
(注)絵合・・・さまざまな者を比べ合わせ、その優劣によって勝負を競う遊戯「物合(ものあわせ)」の一つ。比べ合う物は、自然の動植物から人工の工芸品や技芸に至るまで多種多様。中でも「歌合」は、日本文学の主流である和歌の伝統を形成する上で大きく貢献した。
(注)『伊勢物語』との関係・・・『伊勢物語』という書名の、文献上の確実な初出は『源氏物語』(「絵合」の巻)であり、紫式部の『伊勢物語』に対する高い評価が反映しているとみられる。
紫式部が『伊勢物語』を強く意識していたことは容易に察せられ、「若紫」の巻の北山の垣間見は、『伊勢物語』の初段の写しであることが古くから指摘されており、巻名そのものも初段の歌に由来しているとされる。

語 句
気に入らない。不快である。つまらない。不似合いだ。「あいなく」は、わけもなく。
あえかなり
か弱い。華奢だ。繊細だ。
あくがる
心が体から離れてさまよう。うわの空にある。どこともなく出歩く。心が離れる。疎遠になる。
あさまし
驚くばかりだ。意外だ。情けない。興ざめだ。あきれるほどひどい。見苦しい。
あだあだし
浮気だ。移り気だ。うわべだけで誠意がない。
あだめく
浮気っぽく振舞う。うわつく。
あなかしこ
ああ恐れ多い。ああ慎むべきだ。
あながちなり
無理だ。身勝手だ。強引だ。ひたすらだ。ひたむきだ。
はなはだしい。ひどい。
あはあはし
いかにも軽薄だ。浮ついている。
あらましごと
予測される事柄。予想。
あらまほし
望ましい。理想的だ。
ありありて
このままでいて。生き長らえて。その果てに。
いかで
どうして。どういうわけで。どうにかして。ぜひとも。
いとど
いよいよ。いっそう。
いぶせし
気が晴れない。うっとうしい。気がかりである。不快だ。気詰まりだ。
いまいまし
慎むべきだ。縁起が悪い。不吉だ。憎らしい。癪にさわる。
今めく
現代風である。
いみじ
甚だしい。並々でない。よい。すばらしい。ひどい。恐ろしい。
うしろめたし
先が気がかりだ。どうなるか不安だ。やましい。うしろぐらい。
うしろやすし
気安い。先が安心だ。心配がない。
うたて
ますますはなはだしく。いっそうひどく。
うちつけなり
あっという間だ。軽率だ。ぶしつけだ。
うつたへに
ことさら。まったく。
うるはし
壮大で美しい。立派だ。きちんとしている。端正だ。きまじめで礼儀正しい。親密だ。誠実だ。色鮮やかだ。正しい。
うれたし
しゃくだ。いまいましい。つれない。自分には辛い。
えならず
何とも言えないほどすばらしい。
おとなぶ
大人になる。一人前になる。大人らしくなる。大人びる。
おのがじし
各自それぞれ。思い思いに。
おほとのごもる
おやすみになる。
おほやけ
朝廷。天皇。公的なこと。
かごと
言い訳。不平。恨み言。
かしこ
あそこ。かのところ。
かたはらいたし
きまりが悪い。気恥ずかしい。腹立たしい。苦々しい。みっともない。気の毒である。
形見(かたみ)
遺品。遺児。遠く別れた人の残した思い出となるもの。
くすし
神秘的だ。不思議だ。堅苦しい。窮屈だ。
くたす
腐らせる。無にする。やる気をなくさせる。非難する。
けざやかなり
はっきりしている。際立っている。
けしうはあらず
そう悪くない。まあまあだ。
げに
なるほど。いかにも。本当に、まあ。
けらし
・・・たらしい。・・・たようだ。・・・たのだなあ。
心もとなし
じれったい。待ち遠しい。不安で落ち着かない。気がかりだ。ほのかだ。かすかだ。
ことごとし
仰々しい。いかにも大げさだ。
ことわりなり
もっともだ。道理だ。
才(ざえ)
学識。教養。才能。
さかしがる
小賢しく振舞う。利口ぶる。
さはれ
えい、ままよ。どうともなれ。それはそうだが。しかし。
さぶらふ
お仕えする。参上する。(貴人のそばに)ございます。あります。
さらぬ
そうではない。そのほかの。大したことではない。
しるし
はっきり分かる。明白である。
消息(せうそこ)
手紙。便り。
そこはかとなし
どことはっきりしない。とりとめもない。何ということもない。
たいだいし
不都合だ。もってのほかだ。
たぶ
お与えになる。下さる。
つきづきし
似つかわしい。ふさわしい。調和が取れている。
つきなし
取り付くすべがない。手掛かりがない。ふさわしくない。
つとめて
早朝。翌朝。
つれなし
素知らぬふうだ。平然としている。冷淡だ。薄情だ。ままならない。
とぶらひ
訪問すること。見舞い。
長押(なげし)
柱の側面に取り付けて、柱と柱との間を横につなぐ材。鴨居に添える「上長押」、敷居に添える「下長押」がある。
なつかし
心が引かれる。親しみが持てる。昔が思い出されて慕わしい。
なづさふ
水に浮かんで漂っている。
なれ親しむ。慕い懐く。
はかなし
頼りない。むなしい。あっけない。ちょっとしたことだ。幼い。粗末だ。
ひがひがし
ひねくれている。素直でない。情緒を解さない。
ひたぶるなり
ひたすらだ。一途だ。いっこうに。まったく。
びんなし
具合が悪い。都合が悪い。不便だ。感心できない。かわいそうだ。いたわしい。
ほだし
手かせ。足かせ。妨げ。
まいて
まして。なおさら。いうまでもなく。
みづら
男性の髪型の一つで、髪を頭の中央で左右に分け、耳のあたりで束ねて結んだもの。上代には成年男子の髪型で、平安時代には少年の髪型となった。
むくつけき
異様で不気味だ。恐ろしい。ひどく無骨だ。
やむごとなし
よんどころない。格別に大切だ。この上ない。高貴だ。尊ぶべきだ。
やるかたなし
心を晴らしまぎらす方法がない。普通でない。とてつもない。
ゆゆし
恐れ多い。はばかられる。不吉だ。忌まわしい。甚だしい。とんでもない。すばらしい。立派だ。
らうたし
かわいらしい。いとおしい。世話してやりたくなる。
わりなし
仕方がない。むやみやたらだ。無理やりだ。言いようがない。ひどい。この上ない。
をこなり
間が抜けている。馬鹿げている。
をさをさ
ほとんど。あまり。めったに。なかなかどうして。
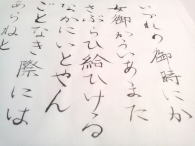
【PR】

