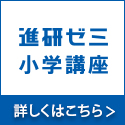���{�j�̗v�_�Əd�v���
��y�펞��`�퐶���� �^ �Õ����� �^ ���� �^ �ޗǎ��� �^ �������� �^ ���q���� �^ ��k���E�������� �^ ���y���R���� �^ �]�ˎ��� �^ �������� �^ �吳�����^���a����
��������
���������Â̑卆��
1867�N�ɑ吭��҂��s���A�V�c���������Â̑卆�������B��1868�N�A�N���������A�]�˂������Ɖ��߂āA�V�c���S�̐V���{�������߂������B
����C�푈
1868�`69�N�ɂ����ẮA���{�R�ƐV���{�̕��j�ɕs�����������{�R�̐킢�B���s�����H�E�����̐킢���礐푈���n�܂����B
�]�ˏ閳���J����������{�����C�M�ƐV���{�R����������������A�]�ˏ邪�����Ŗ����킽���ꂽ�B
��Ð푈�����Ô��𒆐S�Ƃ��铌�k�n���̏��˂��V���{�R�Ɛ�������A�s�ꂽ�
�ܗŊs�̐킢����|�{���g�����ق̌ܗŊs�ɂ��Ă������ĐV���{�R�ɒ�R�������A�~�������
���܂����̌䐾��
1868�N��V���{���V�c���S�̑̐����ł߂邽�߂ɁA�V�c���_�ɂ������`�ŁA�܂����̌䐾�������z�����B
�Ђ낭�ӌ����Đ������s���A�O������V�����m����������č��W�����Ă������Ƃ������́B
���ܞԂ̌f��
1868�N�A�܂����̌䐾���Ɠ����ɁA�����ɑ������̎��ׂ��������������
�k�}�E���i�E�L���X�g���̋֎~�ȂǤ�]�˖��{�ƕς��Ȃ�������������
���ŐЕ��
�ˎ���y�n�i�Łj���l���i�Ёj��V�c�ɕԂ����A���ˎ���m�ˎ��ɔC�������B �F���y��i�F���E���B�E�y���E��O�j�̂S�ˎ傪�܂��s������̑��̔ˎ�������ɂ���ɂȂ�����B
���p�˒u��
�ŐЕ�҂̌�����ˎ�Ɛl���Ƃ̊Ԃɂ́A�ȑO�Ɠ����悤�ȗ̎�Ɨ̖��̊W�������A���{�����ڎx�z���ł��Ȃ������B�����ŁA1871�N�A�˂�p�~���ĐV�����{�⌧�������A���{�����{�m���E�������C�����ꂽ�
�V���{�̂��ƂɑS�������ꂳ�������W�������̓y�䂪�ł����B
���l������
�m�_�H����p�~���A�m�_�H���͕����Ƃ̌����ɂ��ƂÂ��āA�V�c�̈ꑰ���c���A���ƥ�喼���ؑ��A���m���m���A�_�H���������Ƃ����B �����ɂ��c���i�݂傤���j��������A���̐g���Ƃ̌�����Z���ړ]�A�E�������R�ɂȂ����
���x������
���{�́A���{�����ėɕ����Ȃ������ߑ㍑�ƂɈ�Ă悤�ƁA�x�������ɂƂ߂��B ���̂Ȃ��ŏd�v�Ȑ���ƂȂ����̂��A�������x��n�d�����A�B�Y�����B
���������x
1873�N���������z�A20�Έȏ�̒j�q�͐g���ɊW�Ȃ����ׂĂR�N�Ԃ̕����ɂ����ƂɂȂ����B
�ߑ�I�ȌR�����x���������B
���n�d����
�x�������������߂邽�߁A�����̊�b������K�v���������B�������n�d�����ɂӂ݂���A�n���i�y�n�̂˂���j�����߁A�n�����R����n�d�i�Łj�Ƃ��������Ŕ[�߂������
�n�d�͎��n���ɊW�Ȃ��A���{�̎�������������ƍ����̊�b���ł܂����
���B�Y����
����x�܂��邽�߂ɁA���c�H��������A�z�R���J�������肵���B
�x��������������c���͂�H��Ƃ��āA�Q�n���̕x���ɐ����H�ꂪ���Ă�ꂽ��t�����X�̋@�B��Z�p���B�m���̖����������H�Ƃ��ē������
����q�g�ߒc
���{�́A�s�������̉������O���̕��j�Ƃ��A���̉����Ɖ��Ă̎���ׂ邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āA��q�������Ďg�ߒc�Ƃ��Ĕh�������B
���w��
���{�́A�ߑ㍑�Ƃ̓y��͋���ɂ���ƍl���A1872�N���w���z���A�S���ɏ��w�Z���������`�������̐��x���Ƃ肢�ꂽ�B
�i��w�Ǝ����w�Z�j
�E������w�⏊�˓�����w
�E�c���`�m�i����@�g�j
�E�������w�Z�i��G�d�M�j�˂̂��̑���c��w
�E���u�Љp�w�Z�i�V�����j�Ȃ�
�������J��
�����̎v�z��x�̂ق��A�����E�������Ƃ肢����A�������������ĕ��ɑ傫���ς�����
���z���̗̍p���1872�N�A����܂ł̑��A������߁A���z�����̗p�A�܂����j���i1�T��7���Ƃ���j���Ƃ肢���ꂽ�B
�d�M�E�S�����J�ʤ�X�����Ƃ��͂��܂�A���ɂ��l�͎����n��������A����̌������K�X�������Ă�ꂽ�B�l�X�̊Ԃɂ́A�m������H���L�܂����
�X���x����O�����̓w�͂ɂ��A1871�N������`���ԂŊJ�n���ꂽ�
������@�g
�L�O���Ô˂̎m���B�u�w��̂������v���o�ł�������I�Ȑ�������Ԃ�A�l�̎���Ɨ��Ǝ��w�̑��d���ƂȂ����B�����ɉ��Ăɗ��w����A�����c���`�m���J����l�ނ��琬�����
���m���̔���
�V���{�́A�F���E���B�˂̏o�g�҂ɂ���˔��������������߁A���{�ɎQ���ł��Ȃ������˂̎m���̑����͕s�����������B�܂��A�l����������⒥���߂Ȃǂœ��������������߁A�s���͂���ɍ��܂����
�e�n���s���m���́A���͂Ő��{�ɔ��R�������A����������s�����B����_���A�̗��A�H���̗��A���̗�
������푈
1877�N�A�������̎m�������������������Ő��{�ɔ��R�����B�����ͤ�ߑ�I�Ȑ��{�R�ɔs�ꤎ��E�
���͂ɂ�锽�R�͂��ꂪ�Ō�ƂȂ�A�s���m���̔����{�^���͌��_�𒆐S�ɍs����悤�ɂȂ����
�����R�����^��
�C�M���X��t�����X�̖����v�z�����y������R�����^�������܂����
�˔�����������{�̗v�E���A�F���E���B�ˏo�g�҂��Ɛ�
1874�N��y�����_�ޏ��́A�㓡�ۓ�Y�⍲��̍]���V���A������b��ƂƂ��ɁA���I�c�@�ݗ��̌������𐭕{�ɒ�o�����
1874�N��_�ޏ���͍��m�����u����ݗ��A������������ɔ��W�
1881�N�A�k�C���J��g���L��������������������ƁA�˔����{�ɑ�����͂������Ȃ����B
���{�ͤ�������킷���߂ɁA1881�N�10�N��i1890�N�j�ɍ�����J�����邱�Ƃ�����
�����}�̌���
���R�}���1881�N�A�_�ޏ��炪�����B�t�����X���̋}�i�I�Ȏ��R��`���咣�
�������i�}���1882�N�A��G�d�M�炪�����B�C�M���X���̂����₩�ȋc������咣�B
����������
1884�N���ʌ������R�}���Ɣ_�������������\�������B���{�͌R�������肾���Ē������A���R�}�������т���������������̌����R�����^���������ɂȂ����
���ɓ�����
1881�N������J�݂̏���10�N��ɍ���J�݂�������{�́A���N�A�ɓ����������[���b�p�ɔh�����A�e���̌��@���������B�A���㤔閧�Ō��@���Ă��������B
��v�ۗ��ʂ̎���A���{���̎��͎҂ƂȂ�A��������t������b�ɂȂ����B
������{�鍑���@
1889�N��V�c�������ɂ�������Ƃ����`�i�Ԓ茛�@�j�ŁA����{�鍑���@�����z���ꂽ�
�N�匠�̋����v���V�A�i�h�C�c�j�̌��@����{�ɂ���ꂽ�B
�V�c�匠�ŁA���̓������E���C�R�̓������ȂǁA�����������������B�����̌����Ǝ��R�́A�@���̋����͈͂ŔF�߂�ꂽ�
�A�W�A�ōŏ����������������������
���鍑�c��
���@���z�̗�1890�N��ŏ����O�c�@�c���̑��I�����s����鍑�c�����J���ꂽ�
�����̑I���őI�ꂽ�c������Ȃ��O�c�@�ƁA�c����ؑ��̑�\��V�c���C�������c������Ȃ��M���@����@���B
�O�c�@�c���̑I�����ͤ��25�Έȏ�̒j�q�ŁA���ڍ���15�~�ȏ�������߂�҂Ɍ���ꂽ�i������1���j�B
�����璺��
1890�N�ɏo���ꂽ���������̊�{���j�B�����͓V�c�ɐS��������A�ƒ�ł͕���ɍF�s�������Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ�������
�e�w�Z�ɔz���A��ǂ����B
�������@
�V�c�̑��k�ɉ�����ō��@�ւŁA���@���Ă�R�c���邽�߂ɂ���ꂽ�B���t�����قǂ̗͂��������B
�������푈�O�̊O��
�����C�D���K���1871�N����{�ƒ������Γ��̏������
���ؘ_������������炪�咣������N�͂łł��J�������悤�Ƃ����
�����C�D���K���1876�N����{�͒��N�ɕs�����ȏ����������A�J���������
�������푈
���{�����N�����ɐi�o������N���Ƃ݂Ȃ��Ă��������ƑΗ������
1894�N�A���N�ŊO�����͂̒Ǖ����߂����_�����A���w�}�Ƃ����@���c�̂ƌ���ŕ����������i���w�}�̗��j�B���{�Ɛ����o�����đΗ���[�߁A�����푈�̂��������ƂȂ����B
1894�N������푈��������A���{�R�̘A��A���ł����݁A�������~����u�a��\�����ꂽ�B
�����֏��
�����푈�ɏ����������{�́A1895�N������ōu�a�������
�@���́A���N�̓Ɨ���F�߁A���N�������������ƁB
�A���́A��p�E�ɓ������Ȃǂ���{�ɂ䂸��B
�B���́A�������Q��������{�Ɏx�����
���O������
���A�W�A�ł̓쉺������l���Ă������V�A���t�����X��h�C�c���������A�ɓ������𐴂ɕԂ��悤�v�����Ă����i�O�������j�B���{�͎O���Ƒ������͂��Ȃ����ނ������v�����������ꂽ�B
�����p����
���V�A�͖��B�E���N���͂��̂��A���{�ɂƂ��đ傫�ȋ��ЂƂȂ����1902�N����{���C�M���X�ƌR�������i���p�����j������ŁA���V�A�̐i�o�ɂ��Ȃ����B
�����I�푈
���B�ƒ��N���߂���Η�����1904�N�A���I�푈���������B
�푈�͒����嗤�̓얞�B�𒆐S�ɍs���A���{�R�͋�킵�Ȃ���������E��V�̐킢�ŏ��������
���{�C�C���ŁA���������Y�Ђ�����C�R�����V�A���o���`�b�N�͑���j�����B
�ꕔ�̍����͐푈�ɕs���������A�F���H���������ӎO�炪�푈�ɔ��A�^�Ӗ쏻�q�͏o���������S�z���鎍�����ō����̐S���Ƃ炦���B
���|�[�c�}�X���
1905�N��A�����J�����[�Y�x���g�哝���̂Ȃ������ɂ��A�A�����J���|�[�c�}�X�œ��I�푈�̍u�a����ꂽ�
�@���{���؍����w����ی삷�邱�Ƃ�F�߂�
�A�����̓씼������{�ɂ䂸��B
�B�ɓ������̓암�̑d�،�����{�ɂ䂸��B
�C�얞�B�S���̌�������{�ɂ䂸��B
���؍�����
���I�푈�㤓��{�͊؍������ĕ{���������B
���㓝���ɓ��������ÎE���ꂽ���Ƃ����������ŁA1910�N��؍��������
������
�O���������]�́A�s�����������𐬌������邽�ߤ���Ă��܂˂������������Ƃ����B
�����ɎЌ�������������āA�O���̊O�����ƕ�������J���Ȃǂ����B
���m���}���g��������
1886�N��C�M���X�̉ݕ��D�m���}���g�������a�̎R�����Œ��v����C�M���X�l�D���̓{�[�g�ŒE�o�������A���{�l��q25�l�͑S�����E���ɂ��ꂽ�
�C�M���X�̎����ٔ����s���A�D�����y���߂ɂ������Ƃ���A���O�@���p�~�����߂鐺�����܂����
���s�������̉���
���O�@���p�~���1894�N�A�O����b�����@�����C�M���X�Ƃ̌��Ő����������
�Ŏ��匠�̉����1911�N�A�O����b���������Y���A�����J�Ƃ̌��Ő����������
���Y�Ɗv��
��ꎟ�Y�Ɗv�����19���I�����납��A�����A�a�тȂǂ��y�H�������B�
��Y�Ɗv��������I�푈�O��A���S��@�B�E���D�Ȃǂ��d�H�������B�
���������S��
�����푈�̔������̈ꕔ�ł���ꂽ���c�H���B1901�N���瑀�Ƃ��͂��߂��B
�����̓S�z�𒆍�����A���A�ΒY�͒}�L�Y�c���J�����Ă��Ă��B���{�����S���̒��S�Ƃ��Ĥ�d�H���̔��W�����������B
���������R�z�Ŏ���
�Ȗ،����������R�̍z�ł��A�n�ǐ�������̏Z���ɑ傫�Ȕ�Q�����������B�O�c�@�c�����c���������A�鍑�c��ł��̖����Ƃ肠�������e������A1901�N�ɓV�c�ɒ��i�����
�yPR�z
�吳����
���鍑��`�ƍ��ۑΗ��̌���
19���I�����礒鍑��`�̐�����Ƃ鉢�Đ�i���́A�C�O�Ɍ����Ǝs������߂Đi�o��R���͂�w�i���A���n����i�߁A�h�C�c��C�M���X��t�����X�E���V�A���Η������ �h�C�c�ͤ1882�N�ɃI�[�X�g���A�E�C�^���A���O�����������сA�C�O�i�o�ɏ��o���������ɑR���āA�I�������A�p�������ɉ����A1907�N�ɉp�I�����������O�����������������
���T���G�{����
�o���J�������ͤ������e���̑Η�����A���푈���n�܂邩�킩��Ȃ��ْ�������ԂƂȂ褁u���[���b�p�̉Ζ���v�Ƃ�ꂽ�B
1914�N�A�T���G�{���Z���r�A�l�̐N���I�[�X�g���A�c���q�v�Ȃ��ÎE����Ƃ������������������B
����ꎟ���E���
1914�N���T���G�{�����̌�A�I�[�X�g���A���Z���r�A�ɐ�킵���̂�������������ꎟ���E�����������A���[���b�p�̍��̂قƂ�ǂ��A�A�����i�������j���������ɕ�����Đ�����
��ԁE�ŃK�X�E��s�@������͂Ȃǂ̐V���킪�g��ꂽ�
���{�ͤ���p�����𗝗R�ɁA�A��������ɂ��ĎQ��������̃h�C�c�̂Ȃǂ��̂����
��21�����̗v��
1915�N����{�����ؖ����ɑ��A�R���Ȃ̃h�C�c�̌�������{�ɂ䂸�邱�ƂȂǂ�21�����̗v�����o�����
�呍�����͐��M�͂��̗v�������ꂽ���A�r���^�������������B
���A�����J�̎Q��
�h�C�c�̐����͂��������̑D���U���������ƂȂǂ���A����������Ă����A�����J�ͤ1917�N�ɘA��������ɂ��ĎQ��B����ɂ���āA�A��������̏���������I�ɂȂ����
���x���T�C�����
1919�N��t�����X�̃p���ōu�a��c���J����A�x���T�C����������ꂽ�
�s�퍑�h�C�c�͐A���n�̑S���Ɩ{���̈ꕔ�������A���z�̔��������ۂ���ꂽ�
�A�����J�哝���E�B���\�����A���������A�R���k���Ȃ�14�����̌������ƂȂ����B
���{�́A�����ł̃h�C�c�̌������������A�쑾���m�̓��X�̓������܂����ꂽ�B
�����i�C
��풆�A���{�́A�A�����ւ̌R�������̋�����A�W�A�ւ̗A�o�Ȃǂ��D�i�C�ɂȂ����B
���S�ƁE���D�Ƃ��d�H���̂ق��A���D�s�������C�^�����}���ɔ��W�A��i�Ȃǂ����w�H����������ɂȂ����B
���D�A�C�^�Ƃ̂ɂ킩�̔��W�ɂƂ��Ȃ��āA�푈�����������ꂽ�B
���\�A�̐���
���V�A�łͤ�����̍c��ւ̕s����w�i�ɤ1917�N�A���[�j���̎w���ɂ�����V�A�v���������A�\�r�G�g���{���ł����B
���E�����Љ��`�����A�\�r�G�g�Љ��`���a���A�M��1922�N�ɐ��������
���r���^��
�O�E��Ɨ��^�����1919�N�ɁA���N�œƗ��^���������������A���{�ɒ������ꂽ�
�܁E�l�^�����1919�N�ɁA�����ōu�a����21�����̗v���ɔ�����^�����������B
�����V���g����c
1920�N�㤕��a��]�ސ������܂�1921�N�ɊJ���ꂽ���V���g����c�ŁA�e���̌R���k�������߂�ꂽ�
����
��풆�̍D�i�C�ŕ������オ�褃��V�A�v���ւ̃V�x���A�o����������ŁA���l���Ă��߁A�͂������Ă��l�オ�肵��� ����ɑ��1918�N�A�x�R���̋����̎�w�������Ă����߂ĕĉ��������������������A�S���ɍL������� �e�n�Ōx������R���ƏՓ˂��鎖�ԂɂȂ�A�������B���t���ӔC���Ƃ��Ď��E�����
�����}���t�̐���
�������t�����E��A���肩��̖����`�̍��܂������A�������F�������h�����t��g�D�A�{�i�I�Ȑ��}���t���������B �u�����ɑ��v�Ƃ��A��������傫�Ȋ��҂��悹��ꂽ���A���ʑI���̗v���ɔ����A�Љ�^����e�������
���吳�f���N���V�[
��ꎟ���E����A�����`�̎��������߂��吳�f���N���V�[��������ɂȂ����B
�g��쑢�́A�V�c�匠�̂��ƂŖ����`���߂������{��`���咣�����B
���Љ�^���̍L����
1920�N����{�ōŏ������[�f�[���s���A���N�A�J���g���̑S���g�D�ł������{�J�����������������ꂽ�
1922�N�A���{�_���g�����������ꂽ�
1922�N�A�퍷�ʕ����̐l�X���S�������������������
���˗������s��[�}�炪�A�w�l����^���Ɋ��₭�����B
���֓���k��
1923�N9��1���ɔ��������֓���k���ŁA��������l���傫�Ȕ�Q���A�o�ς������A�s�i�C���[���������B �����̂Ȃ��A�����̒��N�l��Љ��`�҂��E���ꂽ�
�����ʑI���@
1925�N������������t�́A���ʑI���@�𐧒肵���25�Έȏ�̂��ׂĂ̒j�q�ɑI���������������B
�������ێ��@
���ʑI���@�̐����Ɠ����ɁA�����ێ��@���������A�J���^����Љ�^������肵�܂����B
������
�O��E�O�H�E�Z�F�Ȃǂ������́A�L�x�Ȏ��{�͂����ƂɁA���{�̎Y�Ƃ̒��S�ƂȂ����
�������E�吳����̕���
���琧�x���ƂƂ̂��A���ẲȊw�E�Z�p���Ƃ肢����A���R�Ȋw�����B����� ��ʋ@�ւ̔��B�E���W�I�����̊J�n�A��y�̕��y�ȂǁA�������ߑ㉻�����
[��w]
�k���ĎO�Y�i�j�����j�E�u�ꌉ�i�ԗ��ہj�E����p���i���M�a�j
[���w]
�H�열�V���u������v�E�ΐ����E���ё�����u�I�H�D�v�E�u�꒼���i�����h�j�E���蓡���E�Ėڟ����u��y�͔L�ł���v�E�����t�E�X���O�u���P�v�E�^�Ӗ쏻�q
�yPR�z
���a����
�����E���Q
1929�N��A�����J�̃j���[���[�N�Ŋ�������\�����A�o�ϋ��Q�����������B���Q�͐��E�ɍL���褓��{���傫�ȑŌ������
�����B����
1931�N�A���{�R����V�x�O���������ŁA�얞�B�S���̐��H�j�����i�����Ύ����j�B ����𒆍��R�̍s�ׂł���Ƃ��āA���B�ɐi�������B�������������A���N�A���B�����������B
�����b�g�������c
���B�����ɂ��āA���ۘA�������b�g�����ψ����Ƃ��钲���c��h�����Ď�������s�����
���{�͖��B������̈�����������������A1933�N����ۘA����E�������
���R���̑䓪
�܁E��������1932�N5��15���A�C�R�̐N���Z�炪���{�B���ÎE�A���}�������I������
��E��Z�������1936�N2��26���A���R�̐N���Z�炪���@��x�����Ȃǂ��P���A�����Ƃ���E�l���E���A�R���̔����͂����܂����
�������푈
1937�N�A�k���x�O��ḍa���œ��{�R�ƒ����R�����傤�Ƃ��A�����푈���n�܂����B���{�R�͎�s���싞���̂����
������E���
1939�N�A�h�C�c���|�[�����h��N������C�M���X��t�����X�����B
���E�́A�������i���ƈɂȂǁj���A�����i�p���ĂȂǁj�ɕ�����Đ�����B
�����ƈɎO���R������
1940�N����{�E�h�C�c�E�C�^���A�́A�R�������Ō��т������ߤ���{�ƃA�����J�̑Η����[�܂����
�������m�푈
���{�͎������m�ۂ��邽�߂ɓ���A�W�A�ւ̐i�o���߂��������A�A�����J�͂��т����o�ϕ����̑[�u���Ƃ��ē��{��ǂ��l�߂��B
1941�N12��8���A���{���n���C�̐^��p���U�����Ĥ�����m�푈���n�܂����
�͂��߂̂����́A����A�W�A�⑾���m�̓��X�����X�ɐ�̂��A���{�R�̗D���̂����ɓW�J�����
��15�N�푈
���B�������������m�푈�܂ł�15�N�ԁA���{�͐푈�ɖ�������A���{�͍��ۓI�ɌǗ������B
�s�i�C��ŊJ���邽�߁A�R�����嗤�i�o���������A������{�����͂����
���펞�̐�
���Ƒ������@���1938�N�A�����╨�����ׂĂ�푈�ɓ����E�����ł���悤�ɂ����B
�吭���^�����1940�N�A���}�����U���Đ��{�̕��j�ɋ��͂���悤�ɂ����B
���푈���̍�������
�w���a�J�����P���͂������Ȃ�ƁA��s�s�̏��w���͏W�c���n���֑a�J�����B
�w�k��������j�q�w�������ɓ�������A���w���⏗�q�w�����ΘJ�������ꂽ�B
�z��������H�Ƃ���p�i���s�����A�āE�݂��E�ߕ��Ȃǂ��z�����ƂȂ����B
���~�b�h�E�F�[�C��
1942�N6���A���������m�̃~�h�E�F�[�C��œ��{�R����s�B�Ȍ㤓��{�͋��𑱂����
���������P
�A�����J�R���{�y��P���n�܂�1945�N3���ɤ�����ɏĈΒe�ɂ�閳���ʔ������s��ꤎ���10���l�̔�Q���o���
�������
1945�N4����A�����J�R�������ɏ㗤���A2������ɓ��{�R�͑S�ł����
����̏��q�w���i�Ђ߂�蕔���j�⒆�w�����킢�A��ʌ����̎��҂��R�W�҂̎��҂��������
�����{�̔s��
1943�N�ɃC�^���A�A1945�N5���Ƀh�C�c���~���A���[���b�p�ł̐푈���I�������B
�A�����J�R��1945�N8��6�����L���A8��9�������������q���e�𓊉������
1945�N8��6���A���{���|�c�_���錾��������ߤ�~�������
���|�c�_���錾
1945�N7���A�A�����J�E�C�M���X�E�����i�̂��Ƀ\�A���Q���j�����{�ɑ��Ĕ������錾�B
���{���������~���Ȃǂ�v�����A���{��8��15���Ɏ���\�����B
���A�����̐�̐���
���{�̔s���A�A�����J�R�𒆐S�Ƃ����A�����R�����{�ɐi�����A��̂����B
�}�b�J�[�T�[���A�������i�ߕ��i�f�g�p�j�̍ō��i�ߊ��ƂȂ�A��̐�����s�����B
���w�l�Q����
1945�N�A��20�Έȏ�̒j�����I�����āA�����̎Q���������������B
���N�̏O�c�@�c�����I���ŁA39���̏��������I�����B
�����{�����@
1946�N11��3�������{�����@�����z����A���N5��3���Ɏ{�s���ꂽ�B
�����匠�E��{�I�l���̑��d�E���a��`�̎O�����B
�V�c�́A���{������{�����̏ے��Ƃ��ꂽ�B
���_�n���v
1946�N���琔�N�ɂ킽���_�n���v���s��ꂽ�B
���{������n�������I�ɔ����グ�A����l�Ɉ����������B�����̏���l������_�ƂȂ����B
�������̉��
1945�N�A�O��E�O�H�E�Z�F�E���c�E�x�m�̑��������̂��A�����ȉ�Ђɕ������B
1947�N�A�����̑厑�{�Ƃɂ��s��̓Ɛ��h�����߁A�Ɛ�֎~�@�����肳�ꂽ�B
���J���O�@
�J���҂̌�����ی삷�邽�߁A�J���g���@�E�J����@�E�J���W�����@�̘J���O�@�����肳�ꂽ�B
�J���g���@�ɂ���āA�J���҂��c�����E�c�̌����E���c�����ۏႳ�ꂽ�B
1946�N5��1���A���[�f�[�����������B
�������{�@
1947�N�A���璺�ꂪ�p�~����A����̋@��ϓ��E�`������E�j�����w�Ȃǂ���e�Ƃ��������{�@�����肳�ꂽ�B
�`�����炪9�N�ɑ����A�Z�E�O�E�O�E�l���̊w�Z���x�ƂȂ����B
 |
����ꒆ�w���I
���w���߂������w���̂��߂̃y�[�W�ł��B |
�Љ�Ȃ̎�������W
����̎�������W
�yPR�z
�p�˒u��
���k�C�E���k�n��
�@�ٌ�
�@�O�O���E���Ό��E�l�쌧
�@���ˌ��E���ˌ��E������
�@����E�]�h���E�_��
�@��䌧�E�o�Č��E�p�c��
�@�������E�֏镽��
�@�����J���E�E�O�t��
�@�I�q���E���͌�
�@��{�����E������
�@�ᏼ���E�H�c���E��茧
�@�{�����E�T�c���E���
�@���䌧�E��E�V����
�@�V�����E�R�`���E��R��
�@�đ�
���֓��n��
�@�������E���ˌ��E���ˌ�
�@�}�Ԍ��E���ٌ��E���Ȍ�
�@�������E�Ή����E�y�Y��
�@�m�}���E���v���E��X��
�@���쌧�E���茧�E���Ì�
�@�����쌧�E������
�@���錧�E�É͌��E�֏h��
�@���q���E�������E������
�@�\��쌧�E�e�Ԍ�
�@�ߖq���E���䌧
�@�v�������E�і쌧
�@���v�ی��E���ь�
�@�������E��{��
�@�命�쌧�E�{�J��
�@�������E�Ԗ[���E�َR��
�@���m�R���E�F�s�{��
�@��c�����E���H��
�@�G�R���E�Ζ،��E�p����
�@���㌧�E���쌧�E������
�@�������E�ٗь�
�@�����s���E������
�@�������E���c���E�O����
�@���茧�E�ɐ��茧
�@��@���E��z���E�E��
�@��Ό��E�Y�a���E������
�@�����{�E�i�쌧
�@�_�ސ쌧�E�Z�Y��
�@���c�����E����R����
�������n��
�@���n���E���㌧
�@�O���s���E���쌧
�@�V���c���E������
�@���E�V�����E���茧
�@�^���E�ŒJ���E���c��
�@���茧�E�x�R���E����
�@�吹�����E�ۉ���
�@���䌧�E���R���E��쌧
�@�{�ی��E�I�]���E���l��
�@�b�{���E�⑺�c��
�@�������E��c���E���㌧
�@�{�⌧�E�юR���E���쌧
�@�ɓߌ��E�������E������
�@�ѓc���E���{���E���R��
�@�쑺���E��_���E���x��
�@�S�㌧�E�⑺���E�c�،�
�@���[���E�������E�}����
�@�B�R���E�����E�x�]��
�@�c�����E�L�����E������
�@���啽���E���茧
�@���ꌧ�E�������E���[��
�@���J���E�d����
�@�������E���R��
���ߋE�n��
�@�{�쌧�E�F�����E�R�㌧
�@�����R���E����H��
�@�������E�V�����E���
�@���s�{�E�����E�T����
�@�������E�������E�R�ƌ�
�@���m�R���E�R��
�@�������E���ߌ��E�{�Ì�
�@��R���E�v���l��
�@���쌧�E�o�Ό��E�L����
�@�������E�O�쌧�E�䌧
�@�������E�ݘa�c��
�@�g�����E���Ό��E���c��
�@���{�E���Ɍ��E��茧
�@�O�c���E�P�H���E���Ό�
�@���쌧�E�O�����E���쌧
�@�ѓc���E�ԕ䌧�E���u��
�@�R�茧�E�O������
�@�������E�S�R���E����
�@���{���E�ő���
�@�c���{���E���挧
�@�������E�ޗnj��E�ܞ���
�@�a�̎R���E�c�ӌ�
�@�V�{���E�������E�K����
�@�Ԗ쌧�E�T�R���E�_�ˌ�
�@���E�v�����E�x�
�@���H��
�������E�l���n��
�@���挧�E�ꗢ���E���]��
�@�L�����E�l�c���E�ÎR��
�@�ߓc���E�^�����E���R��
�@�q�~���E�������E���⌧
�@�됣���E���猧�E�����
�@���c���E�������E���H��
�@�V�����E���R���E�L����
�@�⍑���E�R�����E������
�@�L�Y���E�������E������
�@�ۋT���E�������E������
�@�������E���R���E��F��
�@�V�J���E�g�c��
�@�F�a�����E���m��
����B�n��
�@�������E�H�����E���쌧
�@�v�����E�O�r��
�@���Ì��E�������E���錧
�@�@�r���E���ꌧ�E���ˌ�
�@���]���E�呺���E������
�@���茧�E�������E�l�g��
�@�F�{���E�L�Ì��E�瑩��
�@�����E���o���E�{����
�@�������E�P�n���E����
�@�X���E���c���E�n�z��
�@�������E���猧�E�K�쌧
�@���y�����E��������

����{�鍑���@
�@
1885�N�A���{�͌��@�ɂ�鐭���ɔ����A���t������b�ƍ�����b�ō\���������t�̐��x���߂��B�ɓ�������������t������b�Ƃ��A�����ȑ�b�͎F���o�g�҂Ōł߂�ꂽ�B���@�̍쐬�ɂ́A�ɓ��̂ق����B�Ȃǂ��������A�����@�œ��e���������ꂽ�B
�@
1889�N�A����{�鍑���@���A�Ԓ茛�@�i�V�c�������ɂ������錛�@�j�̌`�Ŕ��z���ꂽ�B
�@
����{�鍑���@�ł́A���Ƃ̎匠�͓V�c�ɂ��邱�ƁA�V�c���R�����A�O���Ə������Ԍ����������Ƃ���߂�ꂽ�B�����ɂ͖@���͈͓̔��Ō��_��o�ť�W�樓��Х�M���̎��R�A�ٔ����錠���A���Y���Ȃǂ��F�߂�ꂽ�B�܂��A������b��c��A�ٔ����͓V�c����������̂ƈʒu�Â���ꂽ�B
�@
�����ɁA�A�W�A�ŏ��߂Č��@�Ƌc���������������Ƃ��a�������B

�i�ɓ������j
���{�����@�܂Ƃ�
��GHQ�́A�|�c�_���錾�ɉ���������{�鍑���@�̉��������߁A���{�͌��@��蒲���ψ����ݒu���āu���{�āv���쐬�����B
�@
���u���{�āv�͓V�c�匠���ێ��������߂�GHQ����������ۂ��AGHQ�ō��i�ߊ��̃}�b�J�[�T�[�ɂ��u�}�b�J�[�T�[���āv���������B
�@
�����{���{�́u�}�b�J�[�T�[���āv��@����ɂ��āA���@�������ėv�j���쐬�����B
�@
�����{�����@��1946�N11��3���Ɍ��z����A���N5��3���Ɏ{�s���ꂽ�B�O�������11��103�J������Ȃ�A��{�I�l���̑��d�E�����匠�E���a��`���O�匴���Ƃ��Ă���B
�@
�����{�����@�͑���{�鍑���@�̂悤�ȋԒ茛�@�ł͂Ȃ��A���茛�@�ł���B
�@
����{�I�l���́u�l�ނ����N�ɂ킽�鎩�R�l���̓w�͂̐��ʁv�ł���A�u�N�����Ƃ̂ł��Ȃ��i�v�̌����v�i��97���j�ł���Ƃ��č��ƌ��͂���̕s�N�����������Ă���B
�@
����{�I�l���ɂ́A���R���E�������E�Q�����E�Љ�E�������Ȃǂ�����B
�@
�����R���ɂ́A���_�̎��R�E�g�́i�l�g�j�̎��R�E�o�ϊ����̎��R��3������B
�@
���l�̑��d�i��13���j���ő�̉��l�Ƃ��A�u���ׂč����́A�l�Ƃ��đ��d�����B�����E���R����эK���Nj��ɑ��鍑���̌����ɂ��ẮA�����̕����ɔ����Ȃ�����A���@���̑��̍����̏�ŁA�ő�̑��d��K�v�Ƃ���v�ƒ�߂Ă���B
�@
�������匠�ɂ��āA�O���Łu�����Ɏ匠�������ɑ�����v�Ɛ錾���A�u�����͍����̌��l�ȐM���ɂ����́v�Ƃ��Ă���B����ɂ��V�c���́u�ے��V�c���v�ƂȂ����B
�@
�������̎O��`���Ƃ���Ă���̂́A�����������`���A�ΘJ�̋`���A�[�ł̋`���ł���B
�@
���O���Ƒ�9���ŕ��a��`�L���A�O���ł́u���a�������鏔�����̌����Ɛ��`�ɐM�����āA����̈��S�Ɛ�����ێ����悤�ƌ��ӂ����v�Ƃ��Ă���B
�@
����9���1���Ő푈�������A��2���Ő�͂̕s�ێ��ƌ�팠�̔۔F��錾���Ă���B
�@
���u���ׂč����́A�@�̉��ɕ����ł����āA�l��A�M���A���ʁA�Љ�I�g�����͖�n�ɂ��A�����I�A�o�ϓI���͎Љ�I�W�ɂ����āA���ʂ���Ȃ��v�i��14���j�B
�@
���ō��@�K�����m�ۂ��邽�߁A��99���Łu�V�c���͐ې��y�э�����b�A����c���A�ٔ������̑��̌������́A���̌��@�d���i�삷��`���Ӂv�ƒ�߂Ă���B
�@
���ʏ�̖@���������i�ȉ����葱����v����d�����@�ł���B�i�̓���@�j
�@
�����{�����@�̉����́u�e�c�@�̑��c����3����2�ȏ�̎^���ŁA�������c���A�����ɒ�Ă��Ă��̏��F���o�Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�i��96���j�Ƃ���Ă���B
�@
������ɂ���Ĕ��c���ꂽ���@�����Ă̍����ɂ�鏳�F�́A�������[�ɂ��A�L�����[�����̉ߔ����̎^�����K�v�Ƃ���Ă���B
�@
�������̋K��͂Ȃ����A����̕ω��ɔ����A���@��̐l���Ƃ��Ď咣�����悤�ɂȂ����������u�V�����l���v�Ƃ����A�����A�m�錠���A�v���C�o�V�[�̌����Ȃǂ�����B

�}�l�͗��j�Ɋw��
�yPR�z