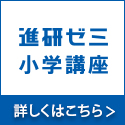日本史の要点と重要語句
先土器時代〜弥生時代 / 古墳時代 / 飛鳥時代 / 奈良時代 / 平安時代 / 鎌倉時代 / 南北朝・室町時代 / 安土桃山時代 / 江戸時代 / 明治時代 / 大正時代 / 昭和時代
鎌倉時代
●源平の争乱
平氏の貴族的な政治に反感をもつ人々が、平氏打倒の動きを強めた。
1180年に、伊豆に流されていた源頼朝が挙兵。頼朝の弟の源義経らのはたらきにより、1185年、壇の浦の戦いで平氏をほろぼした。
●源頼朝
1185年、国ごとに守護、荘園や公領に地頭を設置し、御家人(頼朝の家来)を任命した。
1192年、征夷大将軍となり鎌倉に幕府を開いた。鎌倉殿とよばれ、御家人の信望は大きかった。
●守護・地頭
守護・・・国ごとにおかれ、軍事・警察や御家人の統制にあたった。
地頭・・・荘園や公領におかれ、土地管理、年貢の取り立てなどにあたった。
地方には、国ごとに幕府が設置した守護と、朝廷が任命した国司(こくし)がいた。また荘園には、幕府が任命した地頭と、貴族や寺社が任命した荘官(しょうかん)がおり、公武による二重支配のかたちになった。
●源義仲(木曽義仲)
頼朝の従兄弟(いとこ)。木曽(長野県)で兵をあげ、平氏の軍を破って京都に入り、平氏を追放、1185年に征夷大将軍に任じられた。その後、頼朝が送った源範頼・源義経の軍にせめられ、近江国で敗死した。
●後白河上皇
保元の乱で、源義朝・平清盛を味方につけ勝利、院政を行った。平氏政権のもとでは平清盛と対立、一時的に院政は停止させられたが、清盛の死後に再開、源頼朝に平氏を打倒させた。
●源義経
頼朝の弟。頼朝挙兵に参じ、義仲討伐・平家討伐(一の谷の戦い、屋島の戦い、壇の浦の戦い)に功績を残した。 のち頼朝と不和になり、奥州藤原氏のもとにのがれたが、平泉(岩手県)で自殺した。
●鎌倉幕府のしくみ
執権・・・将軍を助けて政治を行う。
政所(まんどころ)・・・一般の政治・財政を行う。
侍所(さむらいどころ)・・・御家人の統率と軍事・警察にあたった。
問注所・・・訴訟・裁判を処理する。
●封建制度
封建制度・・・土地の給与を通じて、御恩と奉公によって結ばれた主従関係。
御恩・・・主人(将軍)が家来(御家人)の領地を認め、または領地を与えたりする。
奉公・・・主人(将軍)の命令に従い、命をかけて戦う。
●武士の生活
武士はもともと農業を行う開発領主だったから、ふだんは農村の自分の領地に住み、農業を行っていた。板ぶきで簡素な武家造とよばれる館をかまえ、へい・堀・物見やぐらなどで敵にそなえた。館のまわりには、武士が直接経営する田畑があった。戦いにそなえて、つねに犬追物・笠がけ・やぶさめなどの武芸の訓練にはげんだ。
●源氏の滅亡
2代将軍・源頼家が伊豆修善寺で暗殺され、3代将軍・源実朝が鶴岡八幡宮で暗殺され、源氏は3代でほろんだ。
●北条氏の執権政治
北条氏は伊豆(静岡県)の豪族で、源頼朝を助け、源氏再興に力をつくした。頼朝の死後は、政治の実験をにぎった。源氏の将軍が3代でたえると、名ばかりの将軍を京都からむかえ、みずからは執権として政治を行った。
●承久の乱
源氏の将軍がたえると、1221年、朝廷の勢力を回復しようとしていた後鳥羽上皇が兵をあげた。これに対して幕府側は、北条政子のよびかけで御家人の団結をかため、勝利をおさめた。乱の後、後鳥羽上皇は隠岐に流され、朝廷の勢力はおとろえた。幕府は京都に六波羅探題をおき、朝廷や西国武士を監視した。
●御成敗式目
1232年、3代執権・北条泰時が制定した、御家人に対して公平な裁判を行うための基準。51か条からなり、貞永式目ともよばれる。
最初の武家法で、戦国時代の分国法や江戸時代の武家諸法度の手本となった。
●元
1206年、チンギス=ハンがモンゴル民族を統一し、モンゴル帝国を建国した。
チンギス=ハンの孫のフビライ=ハンは、朝鮮の高麗をしたがえ、都を大都(北京)に移し、国号を元とした。
●元寇
元のフビライ=ハンが日本征服をたくらんで北九州にせめてきた、文永の役と弘安の役の2度の戦い。
執権・北条時宗の統率のもと、御家人たちがよく戦い、あらしのおかげもあって元軍をしりぞけた。
元寇の後、3度目の襲来に対する備えもあり、幕府の財政が悪化、ほうびをもらえない武士の不満が高まった。
●永仁の徳政令
1297年、御家人の生活苦を救うため徳政令を出し、売ったり質流れになったりした土地を、もとの持ち主の御家人にただで返させた。しかし、かえって経済が混乱し、幕府の信用も失われた。
●マルコ=ポーロ
イタリアの商人で、元のフビライ=ハンに17年間つかえた。
『東方見聞録』で、日本を「黄金の国ジパング」と紹介した。
●農民の生活
草や木の灰を肥料にし、牛や馬を耕作に使い、米と麦を作る二毛作がはじまった。
農民は、荘園領主と地頭から年貢や労役を課せられ、二重支配に苦しんだ。地頭の横暴に対しては、団結して反抗することもあった。
●商業の発達
寺社の門前や交通の要所などに定期市(月3回)が開かれ、売買には宋銭が流通した。
問丸や馬借などの運送業者が出現。商人や手工業業者は、座という組合をつくって利益を独占した。
●鎌倉新仏教
浄土宗・・・法然。「南無阿弥陀仏」
浄土真宗(一向宗)・・・親鸞
時宗・・・一遍。踊り念仏。
法華宗(日蓮宗)・・・日蓮。「南無妙法蓮華経」
臨済宗・・・栄西
曹洞宗・・・道元
●鎌倉文化
武士の生活や気風を反映した、素ぼくで力強い武家文化が発達した。
軍記物・・・琵琶法師が語り伝えた平家物語。
和歌・・・新古今和歌集(藤原定家)・金槐和歌集(源実朝)
随筆・・・方丈記(鴨長明)・徒然草(吉田兼好)
建築・・・東大寺南大門・円覚寺舎利殿
彫刻・・・金剛力士像(運慶・快慶)
【PR】
南北朝・室町時代
●鎌倉幕府の滅亡
後醍醐天皇が幕府をたおす計画をすすめ、楠木正成・新田義貞らが天皇方について兵をあげた。幕府は有力御家人の足利尊氏をさしむけたが、尊氏は幕府にそむき、1333年、鎌倉幕府はほろんだ。
●建武の新政
1334年、後醍醐天皇は天皇中心の政治を復活させたが、公家を重んじ武士への恩賞も不公平で、宮殿の造営費を武士に負担させたりしたため、武士の不満が高まった。
足利尊氏が建武政府にそむいて兵をあげ、天皇は吉野(奈良県)にのがれた。尊氏は京都に別の天皇をたてた。これによって、建武の新政はわずか3年ほどでくずれた。
●二条河原の落書
建武の新政を批判した落書で、京都の二条河原にかかげられた。
●南北朝時代
1336年以来、京都の朝廷(北朝)と吉野の朝廷(南朝)がならびたつことになった。この時代を南北朝時代という。 1392年、足利義満が南北朝を合一し、約60年間続いた南北朝時代は終わった。
●神皇正統記
南朝の重臣だった北畠親房が、南朝の正統性を主張するために書いた歴史書。
●太平記
後醍醐天皇の倒幕計画以後の南北朝の対立についての軍記物語。
●足利尊氏
京都に北朝をたてた足利尊氏は、1338年に征夷大将軍に任じられ、京都に室町幕府を開いた。
●新田義貞
源氏の子孫で、鎌倉幕府の有力な御家人だったが、後醍醐天皇に味方して鎌倉幕府をたおし、建武の新政に参加した。後、足利尊氏と争い敗れた。
●楠木正成
河内国(大阪府)の豪族で、後醍醐天皇に味方し、建武の新政実現のために活やくした。足利尊氏が新政府にそむいたとき、いったんは尊氏を九州に敗走させたが、後に戦死した。
●室町幕府のしくみ
鎌倉幕府のしくみにならい、執権のかわりに管領をおいた。足利氏一族の斯波・畠山・細川の3氏が交代でなった(三管領)。
中央に政所・問注所・侍所、地方に鎌倉府などをおいた。侍所の長官には、山名・一色・赤松・京極の有力守護大名がなった(四識)。
●守護大名
守護は、任地の土地や地頭などを支配して領主となり、守護大名に成長した。
●足利義満
室町幕府3代将軍。山名・大内氏などの有力守護大名をおさえて幕府の権力を確立した。
京都の室町に「花の御所」を、出家して後、北山に金閣を建てた。
南北朝の合一や、日明間の国交開始による勘合貿易を行った。
●倭寇
南北朝時代のころから、朝鮮や中国の沿岸をあらしまわった武装商人団。
前期・・・対馬、北九州の土豪、商人、漁民を中心に、朝鮮・高麗人も加わって活動。
後期・・・大部分は中国人。
●日明貿易(勘合貿易)
足利義満は、貿易による利益により、幕府財政を救おうとした。 倭寇の取りしまりを条件に、明と貿易をはじめ、国書に「日本国王臣源」と書き、明の属国の形式をとった。倭寇と区別するために、勘合符を用いた。
●永楽通宝
明でつくられた銅銭。日明貿易で輸入され、標準的な貨幣として使われた。
●正長の土一揆
1428年、借金に苦しむ近江(滋賀県)の馬借らが立ち上がり、農民も加わった。
馬借・・・馬を使った輸送業者。
幕府に徳政令の発布を要求し、酒屋・土倉や寺院をおそって借金証文をやぶりすてた。
●山城の国一揆
1485年、山城(京都府)の地侍(じざむらい)らが、守護の畠山氏を追放した。
地侍と農民が連合して、自治による政治を8年近く続けた。
●加賀の一向一揆
1488年、加賀国(石川県)の一向宗信者が守護大名の富樫氏と戦ってほろぼし、100年近く自治を続けた。
●惣(そう)
戦乱が続くと、農民たちは名主を中心にまとまっていき、惣とよばれる自治のしくみをつくった。産業の発達した近畿地方から各地に広まり、土一揆の母体となった。
●寄合
惣では、農民たちが村の神社や寺などで寄合とよばれる会合を開き、村の運営について相談したり、惣の掟(おきて)を定めたりした。
●都市の発達
城下町・門前町・港町などの都市が発達した。
堺(大阪府)・博多(福岡県)・京都では、商工業者による自治が行われた(自治都市)。
●足利義政
室町幕府の8代将軍。一揆のひん発と銀閣の造営などによる財政難で政治を乱した。
将軍のあとつぎ問題が、応仁の乱の原因の一つになった。
●室町文化
武家と公家の文化がとけあい、さらに禅宗の影響を受けた文化。民衆の文化も発達し、応仁の乱後は、都の文化が地方に広がった。
北山文化・・・足利義満が金閣を建て、能を大成した観阿弥・世阿弥を保護した。
東山文化・・・足利義政は政治から身を引き、銀閣を建てて風流な生活を楽しんだ。書院造。茶の湯。生け花。
●水墨画
中国から伝わった墨(すみ)でえがく絵。雪舟によって大成された。
●御伽草子
南北朝時代のころから多くの人々に親しまれた、文章と絵でつづった物語。「一寸法師」「浦島太郎」など。
●連歌
和歌の上の句と下の句を別の人が詠み、何人かで詠みつないでいくもの。宗祇が芸術に高めた。
●応仁の乱
守護大名の細川勝元と山名持豊(宗全)の対立に、将軍足利義政のあとつぎ問題などがからんで起こった11年間の大乱。 京都は焼け野原になり、幕府の権威はおとろえた。乱の後、戦乱は地方に広がり、約100年間の戦国時代に入った。
●戦国大名
守護大名の家臣などで、実力を強め主人をたおし(下剋上)、領国を統一して支配した大名たち。守護大名から戦国大名に変身していった者もある。
おもな戦国大名・・・上杉謙信・武田信玄・北条早雲・今川義元・毛利元就
●鉄砲の伝来
1543年、ポルトガル人を乗せた中国の船が種子島に漂着し、鉄砲を伝えた。 戦国大名の注目を集め、堺(大阪府)や近江・国友(滋賀県)などでさかんにつくられた。 鉄砲の影響・・・足軽の鉄砲隊による集団戦法にかわり、高い石垣や、鉄砲を打つ穴をあけた厚いかべの城がつくられるようになった。また、戦の勝敗が早く決まるようになり、天下統一が進んだ。
●キリスト教の伝来
1549年、イエズス会のスペイン人宣教師フランシスコ=ザビエルが鹿児島に上陸し、キリスト教を伝えた。
ザビエルは鹿児島・山口・京都などで2年あまり布教を続けた。ザビエルの後も宣教師が来日し、各地の大名の保護を受けて布教につとめた。
●キリシタン大名
キリスト教を保護し、信者となった大名。大友宗麟・大村純忠・有馬晴信など、九州に多かった。
キリスト教を保護した理由・・・ヨーロッパ人との貿易による利益に着目した。
●南蛮貿易
ポルトガルやスペインの商人が平戸や長崎などに来航するようになり、貿易をするようになった。
輸入品・・・鉄砲・火薬・生糸・絹織物・ガラス製品
輸出品・・・銀・銅・刀剣・工芸品・硫黄
●南蛮文化
南蛮貿易やキリスト教の布教を通じて伝えられたヨーロッパの文化。
活版印刷機で印刷した、ローマ字の書物(キリシタン版)、医学、天文学、航海術など。南蛮屏風。
●少年使節
九州の大村・大友・有馬の3大名がローマ法王のもとに送った4人の少年使節。
【PR】
安土桃山時代
●安土桃山時代
織田信長から豊臣秀吉にかけての約30年間。信長が築いた安土城と、秀吉が京都の桃山に築いた伏見城に由来する。
●織田信長
尾張(愛知県)の戦国大名。1560年、桶狭間の戦いで今川義元をたおし、「天下布武」の印を用いて天下統一の業をすすめた。
1573年、将軍足利義昭を京都から追放して室町幕府をほろぼし、近畿を平定した。
1575年、徳川家康と結び長篠の戦いで武田勝頼をやぶった。足軽の鉄砲隊により、武田氏の騎馬隊をやぶった。
安土城を築き、交通を整備し関所を廃止し、楽市・楽座令を出して商工業の発展をはかった。
1582年、家来の明智光秀にそむかれて本能寺の変で自害した。
●延暦寺焼き打ち
1571年、信長が浅井・朝倉氏と結んで、敵対する延暦寺を焼き打ちし、寺社勢力の最大拠点に大打撃を加えた。
●石山本願寺攻め
一向宗の信者は、しばしば一向一揆をおこして信長と敵対した。1580年、信長は、一向宗の総本山・石山本願寺を攻めてしたがえた。
●豊臣秀吉
本能寺の変後、山崎の戦いで明智光秀をたおし、織田信長の後継者となった。
大阪城を築き、関白・太政大臣となった。
1590年、北条氏(小田原)をほろぼし、東北の伊達氏をしたがえて、全国統一を完成した。
●太閤検地
秀吉が、土地と農民を支配するために全国的に行った検地。これによって荘園制がなくなった。
長さ・面積・量の単位を統一し、土地を収穫高(石高)で表し、耕作者を検地帳に登録した。
太閤・・・関白をやめたあとの尊称。
●刀狩り
秀吉は、1588年、刀狩令を出して、農民から武器を取りあげた。農民の一揆を防ぎ、耕作に専念させようとしたもの。 太閤検地と刀狩りによって、農民と武士の身分がはっきり区分された(兵農分離)。
●朝鮮出兵
秀吉は、中国の明を征服しようと、朝鮮に案内を求めたが拒否された。
1592年の文禄の役、1597年の慶長の役の2度にわたり出兵、苦戦したが、秀吉が病死したので兵を引きあげた。
●朱印船貿易
秀吉は、南蛮貿易を保護し、商人に許可証として朱印状をあたえた。
●宣教師の国外追放
はじめはキリスト教を保護していた秀吉は、九州平定のとき、長崎が教会領になっていることを知り、国内統一のさまたげになると考え、1587年に宣教師の国外追放を命じた。
●桃山文化
大名・大商人による雄大ではなやかな文化。南蛮文化の影響もあり、仏教の影響がうすれた。
建築・・・安土城・大阪城・伏見城・姫路城、天守閣
絵画・・・狩野永徳・狩野山楽らによる障壁画
茶道・・・千利休
芸能・・・出雲の阿国による歌舞伎踊り
●聚楽第
豊臣秀吉が京都に建てた城郭風の邸宅。ここに諸大名を集めて、忠誠をちかわせた。
【PR】
江戸時代
●関ヶ原の戦い
豊臣秀吉の死後、徳川家康の勢力がまし、豊臣方の石田三成は兵をあげてこれをほろぼそうとした。
1600年、全国の大名たちが豊臣方(西軍)と徳川方(東軍)に分かれて関ヶ原(岐阜県)で戦った。「天下分け目の戦い」といわれ、家康が勝った。
●徳川家康
三河(愛知県)の小さな大名だったが、織田信長の統一事業にしたがって手柄をたて、ついで豊臣秀吉にもつかえて重く用いられた。 関ヶ原の戦いに勝ち、1603年、征夷大将軍に任じられ江戸幕府を開いた。以後の約260年間を江戸時代という。
●大阪の陣
江戸幕府がはじまってからも、大阪にいる豊臣秀頼に心を寄せる大名が多く、家康は徳川政権を確立させるため、豊臣氏をほろぼそうとした。 大阪冬の陣(1614年)、大阪夏の陣(1615年)の2回にわたって大阪城を攻め、豊臣氏をほろぼした。これによって徳川氏が完全に天下を平定し、戦乱の世は終わりをつげた。
●江戸幕府のしくみと幕藩体制
中央に老中・若年寄、寺社・町・勘定の三奉行などをおき、京都に京都所司代をおいた。
全国を幕府領と大名領に分け、将軍と大名が土地と人民を支配した。幕府領は、天領(直轄領)と旗本領をあわせ、全国の4分の1をしめた。
大名は、徳川将軍家との関係から、親藩・譜代・外様の三つに区分された。将軍直属の家臣として、旗本・御家人がいた。
●参勤交代
3代将軍徳川家光のとき、武家諸法度のなかに参勤交代の制度が定められた。
全国の大名を1年おきに江戸と領地に住まわせ、その妻子を江戸に住まわせた。往復で大名行列が行われ、交通が発達し、文化が地方に広まった。
●士農工商
江戸時代初期に身分制度が整った。武士をいちばん上の身分とし、順に百姓(農民)、町人(職人・商人)とするもの。さらに低い身分の者もおかれた。
●武家諸法度
1615年に、大名を取りしまるために定めた。将軍の代替わりごとに発せられ、違反者はきびしく罰せられた。
●禁中並公家諸法度
幕府は、朝廷が大名と組んで政治力をふるうことを警戒し、1615年に禁中並公家諸法度を定め、天皇や公家の生活をこまかく制限した。
●郡代・代官
勘定奉行の下におかれ、郡代は大きな天領を、代官は小さな天領を支配した。
●朱印船貿易
徳川家康は、海外渡航を許可する朱印状を発行し、貿易を保護した。
九州の大名や角倉、茶屋、末吉などの京都・大阪の大商人が、東南アジアに朱印船を派遣した。
●日本町
朱印船の活動にともなって、東南アジアに移住する日本人がふえ、日本町ができた。
山田長政は、シャム(タイ)のアユタヤの日本町の長となり、国王にも重く用いられた。
●キリスト教の禁止
徳川家康は、貿易の利益を重くみて、はじめはキリスト教を認めたため、宣教師が多く来日し、キリシタンも増大した。 オランダが、スペインやポルトガルが布教によって領土をうばうつもりであると告げ、幕府もキリシタンが団結して反抗するのをおそれた。そして、1612年、家康は直轄地でのキリスト教の禁止を命じた。
●踏み絵
キリシタンを発見するため、キリストやマリアの像をふませた。
●海外渡航の禁止
幕府は、禁教を強めるとともに、貿易の統制をきびしくしていった。宣教師の密航や大名たちの経済力が強まることを警戒したもの。
3代将軍徳川家光のときの1635年、日本人の海外渡航と帰国を禁止した。
●島原の乱
1637年、九州の島原(長崎県)・天草(熊本県)地方の農民が、領主の圧政に対し反乱を起こした。
16歳の天草四郎を頭(かしら)とし、原城にたてこもったが、翌年、幕府軍にしずめられた。
●鎖国
幕府は島原の乱が起こったことから、ますますキリスト教を警戒し、3代将軍家光は、1639年、ポルトガル船の来航を禁止して、鎖国を完成させた。 ついで1641年、オランダ商館を平戸から長崎の出島に移し、オランダ人を出島にとじこめた。鎖国後の貿易は、オランダと中国の2国になった。
鎖国により、江戸幕府の封建支配が確立、平和が続き、独自の文化が発達したが、海外への発展が停止し、国際的視野が失われ、近代化がおくれた。
●寺受制度(宗門改め)
すべての人を、檀家(だんか)としていずれかの寺に所属させ、宗門人別改帳に登録して、キリシタンでないことを証明させた。
●慶安の御触書
1649年、3代将軍徳川家光が、農民に生活の心構えを示した法令。32か条からなり、日常生活から農業生産のことまで、細かな注意が書かれている。
●五人組
村は、だいたい数十戸からなっていたが、幕府や藩は、5戸ぐらいを1組とする五人組をつくらせ、年貢の納入や防犯、キリスト教の禁止などに共同責任をおわせた。
●年貢
検地帳に登録された農民(本百姓)は、領主に年貢を納める義務があった。 年貢は米で納めるのが原則で、収穫高の4割前後(四公六民)、5割前後(五公五民)など、藩によって、年によってちがいがあった。
●助郷役
参勤交代などで、街道の宿場の近くの村々が人足や馬を負担すること。助郷役は農民の重い負担となり、しばしば反対の一揆が起こった。
●農村のしくみと生活
農業技術の進歩・・・備中ぐわ、千歯こき、千石どおしなどの農具の発達と、油かす、ほしかなどの肥料。
農村のしくみ・・・有力な本百姓から名主(庄屋)、組頭、百姓代などの村役人を選ばせた。
本百姓と水呑百姓・・・本百姓は地主・自作農で、年貢を納めた。水呑百姓は土地を持たない小作人で、検地帳には記載されなかった。
●玉川上水・箱根用水
玉川上水・・・17世紀半ば、玉川庄右衛門・清右衛門兄弟が、多摩川の水を江戸に引いた。
箱根用水・・・17世紀後半、箱根の芦ノ湖の水を、富士山麓の深良村へトンネルで引いた。
●三都
江戸・・・「将軍のおひざもと」として発達。18世紀の中ごろの人口は100万人をこえていた(当時では世界最大)。
大阪・・・「天下の台所」とよばれ、全国の大名が蔵屋敷をたて、全国の物資が集まる経済都市としてさかえた。
京都・・・朝廷があり、古い歴史と文化、工芸(西陣織など)が発達していた。
●五街道
江戸を起点に、五つの幹線道路(五街道)がととのえられた。→東海道・中山道・甲州街道・日光街道・奥州街道
街道ぞいに、宿場・一里塚がもうけられた。
●関所
交通の要所におき、通る人を通行手形によってきびしく取りしまった。・・・「入り鉄砲に出女」
●商業の発達
幕府や藩は、年貢米を貨幣にかえて商品を買ったので、貨幣経済が発達した。
さまざまな商人が生まれ、武士や町人、農民までも貨幣なしには暮らせなくなった。
両替商・・・貨幣の交換、預金や貸しつけなど、現在の銀行のようなしごと(金融業)を行った。
大商人の台頭・・・紀伊の紀国屋文左衛門、伊勢の三井高利など。
株仲間・・・幕府や藩が許可した、大商人や手工業業者の同業組合。
●蔵屋敷
各藩が、年貢米その他の物産を売りさばくためにもうけた倉庫および取引所で、大阪に最も多かった。蔵元や掛屋が管理し、売りさばいた。
●札差
江戸の商人で、大阪の蔵元・掛屋にあたるもの。旗本・御家人の米(俸禄米)を、手数料をもらって売りさばいた。また、米を担保に、旗本・御家人に金融を行った。
●工業の発達
家内工業・・・職人や農家の副業としてすすめられた。
やがて、問屋制家内工業や工場制手工業(マニュファクチュア)の様式を取り入れるようになった。
●海上交通の発達
東北や裏日本の米を江戸や大阪に運ぶ必要から、東回り航路と西回り航路が開かれた。 江戸と大阪を結ぶ航路はとくに大切で、菱垣廻船や樽廻船などの定期船が行き来した。
●徳川綱吉
5代将軍で、学問を好み、朱子学の精神にもとづく規律ある政治(文治政治)を行った。
孔子をまつる聖堂を湯島に移した(湯島の聖堂)。のち、昌平坂学問所として幕府の学問の中心となった。
仏教への厚かったが、ゆきすぎた信仰から、生類憐れみの令を出して、きょくたんな動物愛護を人々におしつけた。
財政悪化により貨幣の質を悪くしてきりぬけようとしたが、かえって経済を混乱させた。
●新井白石
朱子学者で、6代・7代将軍につかえ、政治改革(正徳の治)を行った。
生類憐れみの令をやめ、貨幣の質をよくし、幕府の制度や儀式を簡略化、長崎貿易の貿易額を制限し金銀の海外流出をふせいだ。
●元禄文化
17世紀末〜18世紀はじめの徳川綱吉の時代、上方(大阪・京都)を中心に明るく活気にみちた町人文化がさかえた。
浮世草子・・・井原西鶴(日本永代蔵)
俳諧・・・松尾芭蕉(奥の細道)
浮世絵・・・菱川師宣(見返美人図)
浄瑠璃・・・近松門左衛門(曾根崎心中)
●朱子学
鎌倉時代に伝来した儒学の一派。林羅山が徳川家康に登用され、幕府の学問(官学)として保護された。身分秩序を重んじたので、封建体制を守るのに都合よかった。
●国学
日本の古典を研究し、日本古来の考え方を究明する学問。江戸中期以降に発達した。
本居宣長が「古事記伝」を書き、国学を大成した。
幕末の尊皇攘夷論に影響をあたえた。
●蘭学
オランダ語を通じて学ばれたヨーロッパの学問や文化。8代将軍徳川吉宗が、キリスト教に関係のない洋書の輸入を許可した。
関孝和・・・数学(和算)
杉田玄白・前野良沢・・・「解体新書」
平賀源内・・・エレキテル
伊能忠敬・・・「大日本沿海輿地全図」
●寺子屋
農民や町民の子の教育施設。僧や浪人などが、読み・書き・そろばんなどを教えた。
●大日本史
水戸藩主の徳川光圀が編集した歴史書。尊王を基本にし、幕末の尊王論に影響をあたえた。
●川柳・狂歌
川柳・・・俳句の形式で、世相や人情をこっけい、皮肉に表現したもの。
狂歌・・・和歌の形式で、世相を風刺したもの。
●享保の改革
貨幣経済がすすむと、幕府の財政が悪化し、旗本や御家人たちへの俸禄米も十分に払えないほどになっていた。8代将軍徳川吉宗は、この幕府財政のたてなおしに全力をあげ、さまざまな改革を行った(享保の改革)。
武断政治へのきりかえ・・・武芸と質素・倹約をしょうれい。
目安箱の設置・・・人々に意見を投書させた。
公事方御定書・・・裁判の公平をはかった。
上米の制・・・大名に米を献上させた。
新田開発・・・五公五民に。青木昆陽にさつまいもを研究させた。
足高の制・・・人材の登用。
(結果)財政の再建に一時的に成果を上げたが、きょくたんな増税で、民衆の不満は高まり、百姓一揆が増加した。
●百姓一揆・打ちこわし
百姓一揆・・・農民が年貢の軽減や村役人の不正などをうったえて、集団で領主に反抗した。
打ちこわし・・・都市部で、町人や農民が集団で米屋や大商人をおそい、家屋や家財を破壊した。
●田沼意次
9、10代将軍の老中となり、子の意知とともに政治の実権をにぎった(田沼時代)。
商業資本を積極的に利用し、利根川下流の干拓、蝦夷地開発、長崎貿易の新興、株仲間の奨励など、産業の発展につとめた。
わいろ政治が批判を浴び、天明のききんなどの天災があいつぎ、失脚した。
●寛政の改革
田沼意次がしりぞけられると、徳川吉宗の孫で白河藩主の松平定信が老中にむかえられた。 享保の改革にならい、質素倹約と文武を奨励した。
寛政異学の禁・・・朱子学以外を禁止。
棄捐令・・・武士の借金を帳消し。
囲い米の制・・・ききんに備え、領主に米を貯蔵させた。
(結果)あまりにきびしく急だったので、反感を買い、6年間で失職させられた。
●化政文化
元禄時代にさかえた町人文化は、11代将軍徳川家斉の時代(19世紀前半)に、江戸を中心として全盛期をむかえた。
小説・・・十返舎一九(東海道中膝栗毛)
俳諧・・・与謝蕪村、小林一茶
浮世絵・・・喜多川歌麿、葛飾北斎(富嶽三十六景)、安藤(歌川)広重(東海道五十三次)
●大塩平八郎の乱
1837年、元幕府の役人で陽明学者の大塩平八郎が、同志の人々約300人とともに、ききんで苦しむ人々を救うよう幕府にせまる乱を大阪で起こした。乱は半日で鎮圧され、大塩は自殺したが、幕府や社会にあたえた影響はひじょうに大きかった。
●天保の改革
老中水野忠邦が、享保・寛政の改革にならって、質素・倹約を奨励し改革を行った。
株仲間の解散・・・米や諸物価を下げるため。
人返し令・・・農民が都市に行くことを禁じ、すでに出かせぎにきている者を強制的に村へ返し、田畑の荒廃をふせいだ。
上知令・・・江戸・大阪周辺の大名領などを、幕府の直轄領にしようとした。
(結果)きびしすぎて猛反対にあい、2年余りで失脚した。
●外国船の接近
18世紀後半にはいると、ロシア・イギリス・アメリカの船が、通商を求めてやってくるようになった。
幕府は沿岸の警備を強め、1825年に異国船打払令を出し、清・オランダ以外の外国船を撃退するように命じた。
幕府は、外国船に備えるため、近藤重蔵に千島、間宮林蔵に樺太を探検させた。また、伊能忠敬は蝦夷地(北海道)を測量した。
●蛮社の獄
1837年、日本人の漂流民を助けたアメリカの商船モリソン号が浦賀に来航した際、幕府は砲撃して追い返した。1839年、幕府の態度を批判した渡辺崋山や高野長英らが罰せられた。
●アヘン戦争
1842年、アヘン戦争で中国(清)がイギリスに敗れた後、幕府は異国船打払令をゆるめた。
●ペリーの来航
1853年、アメリカの東インド艦隊司令長官ペリーが軍艦4せきをひきいて浦賀(神奈川県)に来航。幕府に国書を提出して、日本の開国を強く求めたが、幕府は翌年に回答することを約束して、ひとまずペリーを帰らせた。
●日米和親条約
1854年、ペリーが再び来航し、幕府に強く回答を求めた。幕府はやむなく日米和親条約を結び、下田(静岡県)・函館(北海道)を開港した。これによって、約200年間の鎖国が終わった。
●日米修好通商条約
1858年、大老の井伊直弼とアメリカ総領事ハリスが日米修好通商条約を結び、函館・神奈川・長崎・新潟・兵庫の5港を開いた(下田は閉鎖)。
アメリカの治外法権を認め、日本に関税自主権のない不平等な条約だった。
つづいて、オランダ・ロシア・イギリス・フランスとも同じような修好通商条約を結んだ(安政の5カ国条約)。
●安政の大獄と桜田門外の変
井伊直弼は、幕府の政治を批判した吉田松陰・橋本左内らを罰した(安政の大獄)。
しかし、これは反対派をますます刺激し、直弼は1860年に江戸城の桜田門外で水戸藩士によって暗殺された暗殺された(桜田門外の変)。
●尊王攘夷運動
社会不安がつづくなかで、開国した幕府や外国に対する不満が高まり、朝廷(天皇)を尊ぶ考えをもつ尊王論と、外国を追いはらおうとする攘夷論が結びついた尊王攘夷論がおこってきた。
尊王攘夷論は倒幕運動に発展し、薩摩藩(鹿児島県)と長州藩(山口県)は、元土佐藩(高知県)の坂本竜馬の仲立ちで薩長同盟を結び、倒幕の動きを強めた。
●大政奉還
1867年、15代将軍徳川慶喜が朝廷に政権返上(大政奉還)を申し出、朝廷はこれを受け入れた。265年間つづいた江戸幕府はほろび、鎌倉幕府から670年あまりにわたった武家政治も終わりをつげた。
 |
がんばれ中学受験生!
中学受験をめざす小学生のためのページです。 |
社会科の資料・問題集
【PR】
おもな軍記・歴史物語
■栄花物語
40巻。宇多天皇から堀河天皇まで15代、約200年間の歴史を編年体で記す。藤原道長の栄華を中心に、宮廷貴族の生活が仮名書きで描かれている。作者は、正編30巻を赤染衛門、続編10巻を出羽弁とする説が有力だが、不詳。
■今鏡
10巻。『大鏡』の延長線上に位置し、後一条天皇の万寿2年(1025)から高倉天皇の嘉応2年まで約150年間の歴史を紀伝体で記す。長谷寺詣での途上に出会った老女の昔語りという形式。作者未詳。
■水鏡
3巻。神武天皇から仁明天皇まで57代、約1500年間の歴史を仮名書きで編年体で記す。『大鏡』にならい、長谷寺で老尼が修行者を通じて葛城山の仙人から話を聞くという形式。作者未詳。
■増鏡
17巻。19巻、20巻の増補本もある。治承4年(1180)の後鳥羽院の誕生から、元弘3年(1333)の後醍醐天皇の隠岐島より京都への還幸まで約150年間の歴史を、編年体で記す。嵯峨の清涼寺で老尼が回想談をするという形式。「四鏡」の成立順では最後に位置する作品。作者未詳。
■保元物語
3巻。1156年に起こった保元の乱の顛末を和漢混交文で記した軍記物語。作者未詳。
■平治物語
3巻。1159年に起こった平治の乱の顛末を和漢混交文で記す。作者未詳。
■平家物語
平家一門の興亡を流麗な和漢混交文で描いた軍記物語。「徒然草」226段は作者を信濃前司行長(しなののぜんじゆきなが)としているが、成立事情は複雑で多くの諸本が伝わり、成立年次も未詳。琵琶で語られ仏教的無常観が貫流、国民的一大叙事詩として現在に生きつづけている。
■太平記
40巻。第一部は後醍醐天皇の討幕計画から北条氏滅亡まで、第二部は建武新政の失敗、足利尊氏の離反、楠木正成の戦死、後醍醐天皇の死まで。第三部は足利政権の内部抗争を経て、幼将軍義満を補佐する細川頼之の執事就任まで。50年余りにわたる全国的な戦乱を描いた軍記物語。作者未詳。
■愚管抄
7巻からなる史論書。作者は比叡山の学僧、慈円。神武天皇から第84代・順徳天皇までの歴史を記す。日本の政治の変遷を「道理」によって捉え、漢字片仮名文で述べたもの。
■吾妻鏡
47巻または52巻。1180年の源頼朝挙兵から1266年までの歴史を、和風漢文・編年体で記す。作者未詳。
■神皇正統記
3巻。北畠親房が常陸小田城で執筆。歴代天皇の事績を後村上天皇の代まで述べ、徳のある天皇を摂関家中心に貴族が補佐する政治こそ理想とする政道論を展開、南朝の正統性を論証した史論書。
■義経記
8巻。源義経の生涯を、不遇な生い立ちと悲劇的末路に重点を置き、弁慶や静御前などの活躍と合わせて、一代記風に描いた伝記物語。作者未詳。

(源義経)
室町幕府の将軍
- 足利尊氏
- 足利義詮
- 足利義満
- 足利義持
- 足利義量
- 足利義教
- 足利義勝
- 足利義政
- 足利義尚
- 足利義材
- 足利義澄
- 足利義晴
- 足利義輝
- 足利義栄
- 足利義昭

(足利義政)
おもな戦国武将
斎藤道三(1494?)
毛利元就(1497)
山本勘助(1500)
松永久秀(1510)
織田信秀(1510)
立花道雪(1513)
尼子晴久(1514)
北条氏康(1515)
武田信玄(1521)
柴田勝家(1522)
滝川一益(1525)
明智光秀(1528)
龍造寺隆信(1529)
上杉謙信(1530)
大伴宗麟(1530)
吉川元春(1530)
朝倉義景(1533)
小早川隆景(1533)
島津義久(1533)
前田利益(1533?)
織田信長(1534)
島津義弘(1535)
丹羽長秀(1535)
荒木村重(1535)
豊臣秀吉(1536)
池田恒興(1536)
佐々成政(1536)
足利義昭(1537)
北条氏政(1538)
前田利家(1538)
長宗我部元親(1539)
徳川家康(1542)
竹中重治(1544)
浅井長政(1545)
黒田孝高(1546)
武田勝頼(1546)
山内一豊(1546)
浅野長政(1547)
真田昌幸(1547)
島左近(1548?)
本田忠勝(1548)
高山右近(1552)
堀秀政(1553)
毛利輝元(1553)
小西行長(1555)
上杉景勝(1556)
蒲生氏郷(1556)
藤堂高虎(1556)
小西行長(1558?)
大谷吉継(1559)
石田三成(1560)
直江兼続(1560)
福島正則(1561)
加藤清正(1562)
細川忠興(1563)
池田輝政(1564)
伊達政宗(1567)
真田幸村(1567)
立花宗茂(1567)
黒田長政(1568)
小早川秀秋(1582)
( )内は生年です。

(織田信長)
戦国時代のおもな合戦
1555年 厳島の戦い
1556年 長良川の戦い
1560年 桶狭間の戦い
1567年 稲葉山城の戦い
1568年 観音寺城の戦い
1570年 姉川の戦い
1570年 金ヶ崎の戦い
1571年 比叡山焼き討ち
1572年 三方ヶ原の戦い
1573年 一乗谷の戦い
1573年 小谷城の戦い
1575年 長篠の戦い
1578年 三木城の戦い
1581年 鳥取城の戦い
1582年 天目山の戦い
1582年 本能寺の変
1582年 備中高松城の戦い
1582年 山崎の戦い
1583年 賤ケ岳の戦い
1584年 小牧・長久手の戦い
1585年 四国平定
1587年 九州平定
1590年 小田原征伐
1592年 文禄の役
1597年 慶長の役
1600年 関ケ原の戦い

(上杉謙信)
凡人は歴史に学ぶ
徳川将軍15代
(1603〜1605)
2代 徳川秀忠
(1605〜1623)
3代 徳川家光
(1623〜1651)
4代 徳川家綱
(1651〜1680)
5代 徳川綱吉
(1680〜1709)
6代 徳川家宣
(1709〜1712)
7代 徳川家継
(1712〜1716)
8代 徳川吉宗
(1716〜1745)
9代 徳川家重
(1745〜1760)
10代徳川家治
(1760〜1786)
11代 徳川家斉
(1786〜1837)
12代 徳川家慶
(1837〜1853)
13代 徳川家定
(1853〜1858)
14代 徳川家茂
(1858〜1866)
15代 徳川慶喜
(1866〜1867)

(徳川綱吉)
【PR】